新盆(初盆)のお供えに何を渡せば良いのか悩みを抱えている人も少なくありません。故人や遺族に喜んでもらえるようにするためには、品物として相応しいものを選択する必要があります。そこで、今回は初盆に渡すお供え物の定番や避けたいものについて詳しくご紹介していきます。
<この記事の要点>
・初盆に渡すお供え物は「消えもの」と呼ばれる消耗品がふさわしい
・初盆のお供え物は、線香やろうそく、花、果物がおすすめ
・お供え物の相場は5,000円~1万円程度、香典や御提灯代の目安は3,000円から1万円
こんな人におすすめ
新盆(初盆)のお供え物にお悩みの方
新盆(初盆)のお供え物の相場を知りたい方
お供え物の渡し方を知りたい方
新盆のお供え物の定番
お供え物は「消えもの」と呼ばれる消耗品がふさわしいですが、その中でもお菓子は定番のお供え物です。お菓子であれば遺族の方たちも食べやすいですし、比較的日持ちするものであれば受け取る側としても焦って消費する必要がありません。
お菓子の中でも羊かんやゼリーといったものであれば、季節にも相応しくおすすめと言えます。できるだけ日持ちするもので、詰め合わせとなっているものを選択するのが良い賢明です。
お菓子以外には果物や缶詰の詰め合わせ、お酒や清涼飲料といった飲み物を渡すのも問題ありません。いずれも消えものとして定番の品であり、人気があるアイテムです。基本的に渡すものを何にするか迷った場合は、消えものの中から選ぶのがおすすめです。

相手に渡しやすい新盆のお供え物
相手に喜んでもらうための品としては、お菓子をはじめとした消えものが定番と言えます。消えものを優先的に検討していく中で、その他のアイテムについても認識しておくことが大切です。そこで、ここからは相手に渡しやすい品について具体的にご紹介していきます。
線香
故人や遺族を悼むための品としては、線香が定番です。線香はこの時期に限らず、故人を供養する際に利用する品であり、数多く贈っておいても無駄にはなりません。優先的に検討したいアイテムとしておすすめです。
ロウソク
故人や遺族を悼むための品として、ロウソクも定番中の定番です。線香とロウソクをセットでお供えすると遺族にも喜んでもらうことができます。いずれも、定番の品として認識しておきたいところです。
花
このタイミングで渡す品として、お花も挙げることができます。線香やロウソクほど定番ではありませんが、お花を渡す関係者の方も少なくありません。お花を渡す際には注意点もあります。注意点として、トゲのある花や日持ちのしない花、あるいは香りが強い花などは避けることが挙げられます。
あくまでも故人を供養するために相応しいお花を選択することが求められます。しかし、近年では故人が生前に好んでいた花を渡すケースもあります。その場合は事前に遺族の方に相談をしつつ、適切な対応を取ることがポイントです。
果物
その他に果物を提供するのも有効です。消えものとしても人気のある果物ですが、なかなか日持ちしないところが弱点でもあります。そのため、できるだけ遺族の方が好きな果物を用意することで、早めに食べてもらうことも大切です。
りんごやみかん、ぶどうなどが定番の果物となります。その他、遺族の方が好んで食べられる果物を視野に入れつつ、渡す品を検討していくことがおすすめです。
日持ちする食べ物
日持ちする食べ物も相手に渡しやすい品としておすすめすることができます。特に、缶詰の詰め合わせなどはおすすめです。この時期は暑い季節でもあり、生ものはすぐに消費期限が来てしまいます。その点で、缶詰の詰め合わせであればある程度日持ちをさせた状態で楽しんでもらうことができます。季節も考慮した上で渡す品を選ぶことが重要です。
新盆に避けたいお供え物
渡しやすい品もある一方で、避けておきたい品もあります。遺族や故人の気持ちを慮ることが大切であり、マナーを適切に守ることも重要です。ここからは、避けておきたい品について具体的にご紹介していきます。
祝いの品として使われるもの
遺族に渡す品として避けておきたいものに、お祝いの品として使われるものが挙げられます。例えば、昆布やかつお節がそれらに該当します。決してお祝いの場ではないので、渡す際には注意する必要があります。
魚や肉(生もの)
魚や肉などの生ものも避けておきたいところです。特に仏教においては、殺生を禁じる風潮があるため、魚や肉は確実に避ける必要があります。時期的な視点で見ても生ものは日持ちしないので、お供え物として相応しくありません。
生前の故人が好んだ品物
生前の故人が好んだ品物についても基本的には避けておきたいところです。品物を渡す側としては良かれという気持ちで渡したとしても、受け取る側の遺族の心情が思いやられるためです。特に初盆の場合は、故人が亡くなってから日が浅いということもあります。
亡くなって間もない故人のことを思い浮かべてしまうと、遺族としては辛い心情になりかねません。大切な子供を亡くしてしまった場合も同様です。基本的に、過度に故人を思い出させるような品は避けておくのがポイントです。
神式(神道)では不要なお供え物
神式(神道)では不要なお供え物として、線香や抹香を挙げることができます。神式の供養では線香や抹香をたく慣習がないので、お菓子や飲料などの消えものを持参していけば問題ありません。

新盆のお供えの相場はいくらなのか
相手に渡す品として相応しいものやそうではないものがあることについて理解を深めることが重要です。その上で、お供えの相場についても理解することが求められます。いったいどれくらいが相場になるのかについて、具体的にご紹介していきます。
お供え物を贈る場合
品を贈る場合の相場としては、一般的に5,000円から1万円程度とされています。親戚などで故人との関係が近い場合は、1万円から3万円程度が相場になることもあります。故人や遺族との関係性を考慮しつつ、適切な金額を判断することが求められます。線香やロウソク、お菓子などの総額として目安の値段とされています。供物料として現金を包むケースも出てきています。
香典・御提灯代を包んで渡す場合
香典や御提灯代を包んで渡す場合の相場としては、3,000円から1万円程度となっています。地域によって故人と近しい親族から渡す慣習があるのが御提灯代です。不祝儀袋に「御提灯代」の表書きをして現金を包むことが一般的です。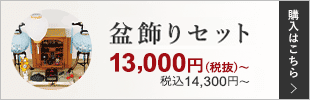
香典・御提灯代とお供え物を両方渡す場合
香典・御提灯代とお供え物を両方渡す場合については、3,000円から1万円程度が相場と考えておけば問題ありません。あまりに高い品物を渡してしまうと、遺族としても返礼品に困ってしまうことがあります。そのため、多くの品や現金を渡す場合でもあまり高額にならないように配慮することが求められます。
香典や御提灯代、お供え物は故人を供養して、遺族の精神的なケアに対する品だと考えておく必要があります。そうした品で遺族に精神的な負担を与えてしまっては本末転倒です。遺族の気持ちや喜んでもらえる品、金額を考慮していく中で渡すものを選択することがポイントです。
新盆のお供えの渡し方
新盆のお供え物について、具体的に相応しいものや相応しくないもの、相場などに関する理解を深めて行動につなげられるようにすることがポイントです。その上で、お供えの渡し方についても解説を行っていきます。遺族に失礼のないように注意を払いながら渡すことがマナーです。
新盆のお供えを渡す時期は8月15日ごろ
新盆の品を渡す時期については、一般的にお盆とされる8月15日ごろとなります。初盆は故人が家に戻ってくる期間のことで、一般的には8月13日から8月16日ごろにかけて、故人が戻ってくる時期とされています。
しかし、これはあくまでも現代の慣習のようなものであり、地域によっては7月15日ごろにお供えを渡すこともあります。東京都や神奈川県、北海道や沖縄県の一部地域では旧暦で7月13日から7月16日ごろに故人の供養を行うこともあります。遺族のところに直接訪問する際には、事前に連絡を取った上で故人の供養をすることがポイントです。
お供えは焼香の後で渡す
お供え物については、仏壇などで焼香を済ませてから渡すのがマナーです。初盆の時期には、故人が家に帰ってきているわけですが、まずは故人の魂に挨拶をすることが優先事項となります。故人への挨拶は焼香ですることになるので、それを終えてから持参してきた品物を渡すのです。そうすることで、故人にも遺族にもマナーを守った形で接することができます。
遠くの相手に新盆のお供えを送る際のマナー
距離的な問題や時間的な問題で、直接相手に渡せないケースも出てきます。そこで、遠くの相手に新盆の品を送る際のマナーについて確認していきます。直接渡す場合にもマナーがありますが、郵送する際にもマナーがあります。それを理解した中で、気持ちの良いやり取りを心がけることが求められます。
品物を送ることを相手に連絡しておく
遠くの相手に対してお供えを送る際のマナーとして、品物を送ることを事前に相手に連絡しておくことがポイントです。新盆の品物に限った話ではありませんが、相手に連絡をしておかないと、留守になっている可能性もあります。新盆の場合は家にいることが想定されますが、相手に失礼のないようにするという意味でも、事前に連絡を入れておくことが大切です。
場合によっては品物を送らなくても良いと言われる可能性もあります。その辺も含めて、事前のコミュニケーションを適切に取っておくことが求められます。
法要の前日には届くように手配する
遠方の相手に対して品物を送る場合は、法要の前日には届くように手配することもポイントです。基本的なマナーとして、お寺や斎場に送る場合は、遅くとも法要開始の1時間前までには届くようにしておく必要があります。配送業者とも連携して、スケジュール調整をすることが重要です。
相手の自宅に郵送する場合は、前日には届けることがポイントです。相手の都合も考えてゆとりある手配を心がけることが必要になります。

添え状があると相手に喜ばれる
必ずしも送らなければならないわけではありませんが、遠方の相手に対してお供え物を送る場合は添え状を入れてあげると相手に喜んでもらうことができます。
品物だけを送るとぶっきらぼうな印象を与えてしまうこともありますが、添え状があると相手に伝わる気持ちも和らいだものになります。余裕があれば、添え状に故人や遺族を悼むメッセージを書いて送ることが効果的です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
新盆(初盆)のお供えに関する情報を具体的にご紹介してきました。この時期に渡す品として適切なものもあれば、そうでないものもあることを理解しておくことが重要です。特に、故人が生前に好きだったものに関しては遺族の気持ちをネガティブなものにしてしまうリスクがあるので注意する必要があります。
その他、品物や法要の相場、渡すタイミングなども意識しつつマナーを守って行動することが大切です。本当の意味で故人の供養と遺族の悲しみを和らげるように適切な対応を心がけていきましょう。
法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


訃報は、死亡確定後、なるべく早く届けることが大切です。ホゥ。
































