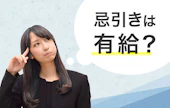家族や親族が亡くなった場合に使用する「忌引き休暇」、法律での定めがないため、公務員と一般企業では規定が異なります。そのため、公務員である場合の忌引き休暇日数が分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、公務員である場合の忌引き休暇の日数について解説をしていきます。忌引き休暇を取る際に必要な書類も併せてご紹介しますので、初めて忌引き休暇を取るという方はぜひチェックしてみてください。
<この記事の要点>
・公務員の忌引き休暇の日数は親族の続柄によって異なる
・忌引き休暇を取得する際、死亡診断書や葬儀の案内状などが必要になることもある
・子どもがいる場合は、子どもの忌引き休暇申請も忘れずに行う
こんな人におすすめ
忌引きのルールについて知りたい方
公務員で、忌引き取得について気になっている方
忌明けの対応方法について知りたい方
公務員の忌引きは「特別休暇」所属する自治体の条例によって定められる
公務員の忌引き休暇は「特別休暇」として規定されています。さらに、自分が所属している自治体の条例で定められるため、同じ公務員であっても市や県、国によって待遇が異なります。しかし、国家公務員の規定に準じていることが多く、大きく異なるということはありません。実際に休暇を取得する際は、自分の所属する自治体に確認を取りましょう。
公務員の忌引き休暇は所属する自治体によって異なる
「公務員」とひとくくりに言っても、自分が所属している自治体によって規定は異なります。
地方自治体で公務員の特別休暇の規定を定めることができますが、国家公務員の特別休暇に準じて定める自治体が多くなっています。そのため、自治体間での休暇日数の差は、それほど大きいものではありません。公務員の忌引き休暇日数は、おおよそ国家公務員の規定が参考になるでしょう。
配偶者の場合
配偶者が亡くなった場合、「7日間」または「10日間」の忌引き休暇が取得可能です。自分が喪主を務めるケースがほとんどであるため、役所への届け出を行ったり、葬儀会社で葬儀の手配を行ったりと、非常に忙しくなります。生前お世話になった方に訃報を伝えることも必要です。
また生前配偶者が会社に勤めていた場合、制服の返還や諸手続きなど、会社とのやり取りもしなければなりません。さらに、心のケアにも時間を要するでしょう。そのため最も長い休暇となっているのです。
両親・義両親の場合(1親等)
両親の場合、「7日間」の忌引き休暇となります。自分が喪主になると、役所や葬儀会社への手続きで非常に忙しくなります。精神的な負担の解消のためにも、長い休暇が必要です。
義両親の場合は「3日間」の忌引き休暇となります。血族と姻族によって休暇日数は変わりますので注意しましょう。
子供の場合(1親等)
子供の場合には、「5日間」の休暇となることが多いでしょう。一般的に、配偶者や両親よりも少ない日数となります。
しかし、自分の子供が亡くなった場合、配偶者や両親が亡くなったのと同等かそれ以上の悲しみを感じることもあるでしょう。心のケアをする期間が必要となりますから、一般企業や自治体によっては「7日間」と設定する場合もあります。
兄弟や祖父母の場合(2親等)
兄弟や姉妹、祖父母の場合は「3日間」の忌引き休暇となります。この場合自分が喪主となるケースは少ない傾向にあります。そのため関係各所への手続きなどを行う必要がなく、休暇日数も少なめに設定されているのです。
また、配偶者の祖父母や兄弟姉妹の場合は、「1日間」の特別休暇となります。1日間だけですから、基本的に葬儀のみの参列となるでしょう。葬儀両親と同様に、こちらも血族と姻族によって休暇日数は変わりますので注意してください。
叔父・叔母の場合(3親等)
叔父・叔母の場合は、最も少ない「1日間」という休暇日数です。自分が喪主となるケースはほぼないため、そこまで多忙にならないことから短い日数になっています。
また配偶者の叔父や叔母の場合だと、休暇が設定されていない場合もあります。どうしても参列したい場合、有給休暇を使用する必要があるので注意してください。
曾祖父母の場合(3親等)
曾祖父母の場合、忌引き休暇が適用されないケースがほとんどです。そのため、曾祖父母の通夜や葬儀に参列したい場合、有給休暇を使用することになります。一般企業においても曾祖父母については規定のない企業が多く、規定があったとしても「1日間」の忌引き休暇となります。自分の所属する自治体に必ず確認を取りましょう。
4親等以上の場合
4親等以上の方が亡くなった場合、基本的には特別休暇はありません。一般企業の規定でも、多くの場合は3親等以内までとしています。
しかし、4親等は「いとこ」にあたるため、親交がある方も多いのが事実です。会社の場合では、特別に忌引き休暇にすることもあります。公務員の場合、自分の所属する自治体の規定を確認しましょう。
(例)東京都の場合
東京都の場合、とても十分な日数の休暇を取ることができます。そのため、関係各所への手続きや、葬儀の準備で困ることはまずないと考えても良いでしょう。気持ちに余裕を持って葬儀を行えます。
東京都の忌引き休暇日数は下記の通りです。
| 配偶者 | 10日間 |
| 父母 | 7日間 |
| 義父母 | 3日間(生計を共にしている場合は7日間) |
| 子供 | 7日間 |
| 兄弟 | 3日間 |
| 祖父母 | 3日間 |
| 叔父・叔母 | 1日間 |
| 曾祖父母 | 0日間 |
(例)大阪府の場合
東京都とほぼ同様の規定となっています。東京都と異なる点は、配偶者の規定が「7日間」と短い点です。7日間と短くなってはいますが、世間一般的には必要十分な日数でしょう。
大阪府の忌引き休暇日数は下記の通りです。
| 配偶者 | 7日間 |
| 父母 | 7日間 |
| 義父母 | 3日間(生計を共にしている場合は7日間) |
| 子供 | 7日間 |
| 兄弟 | 3日間 |
| 祖父母 | 3日間 |
| 叔父・叔母 | 1日間 |
| 曾祖父母 | 0日間 |
(例)国家公務員の場合
大阪府とほぼ同様の規定です。異なる点は、子供の場合忌引き休暇は「5日間」と短くなっている点です。東京都と大阪府と比較すると、最も休暇日数が少ないでしょう。しかし、一般的に必要とされる日数ですので、準備のための時間は十分に取ることが可能です。
国家公務員の忌引き休暇日数は下記の通りです。
| 配偶者 | 7日間 |
| 父母 | 7日間 |
| 義父母 | 3日間(生計を共にしている場合は7日間) |
| 子供 | 5日間 |
| 兄弟 | 3日間 |
| 祖父母 | 3日間 |
| 叔父・叔母 | 1日間 |
| 曾祖父母 | 0日間 |
非常勤公務員も忌引きを申請できる
雇用形態が「非常勤」の公務員であっても、常勤の公務員と同様に前項で挙げた休暇日数を使用できます。
忌引き休暇を使用できる非常勤公務員は、「6ヵ月以上の任期や任用予定期間が定められている職員」や、「6ヵ月以上実際に勤務している職員」が対象となります。対象者となっていれば、勤務時間や日数が常勤職員より少なくても使用可能です。
6ヵ月間以上の勤務予定がない方の場合は対象外となりますので注意してください。
忌引き休暇はいつから始まりいつで終わるか
日数が分かっても、いつからいつまで休んで良いのかが分からないと、葬儀の準備や手続きの計画を立てることができません。また、遠方の葬儀に参列する場合は移動に時間がかかるため、休暇終了日を誤ってしまうと欠勤となってしまう恐れもあります。日数だけを確認するのではなく、いつ終了するのかも明確にしておくことが大事です。
土日祝などが含まれる場合
休暇の間に土日祝が含まれる場合、土日祝も休暇の日数に含まれることが多くなっています。例えば、5日間の忌引き休暇を水曜日から取る場合、日曜日が5日目と計算されるので、月曜日から出勤となります。
認識を誤ったまま休暇に入ってしまうと、本来は出勤日であるのに休んでしまい欠勤扱いになりかねません。欠勤となってしまった場合、ほかの職員にも迷惑をかけてしまうことになりますから、休暇に入る前に次回の出勤日の確認をしっかり行いましょう。
移動日数がかかる場合
葬儀を行うのは近くとは限りません。遠方での葬儀の際は、飛行機や新幹線などで半日以上かけて行くケースも考えられます。その場合、休暇日数を増やすことが可能です。
移動に日数を必要とする場合に加算される日数は、「往復にかかる日数」です。例えば、東京都の場合は下記のような規定になっています。
『遠隔の地とは、通常の交通機関を利用した場合の所要時間がおおむね片道六時間以上かかるところをいう。』
(引用:『東京都教育委員会HPより』)
葬儀場所まで何時間かかれば「遠方の地」と定義されるかは各自治体で異なるため、確認が必要です。
葬儀までに日数がかかる場合
亡くなってから葬儀を行うまでの日数に決まりはなく、各葬儀でバラバラなため、葬儀の日に合わせて忌引き休暇を取ることになります。
葬儀までに日数がかかる理由として多いのは、前項で挙げたように親族が遠方から訪れるために時間がかかるケースです。その場合は、往復にかかる日数分が休暇にプラスされるので問題ないでしょう。
その他の理由で日数を必要とする場合には、葬儀の日を明確にしてから休暇に入りましょう。
公務員の忌引きで必要な証明書
忌引き休暇の申請には、証明書類の提出が必要となることがあります。証明する書類としては、「死亡届」、「会葬礼状」、「火葬許可証」です。
自治体によって証明書となる書類も異なります。また、自分の親族であることが分かれば、上記に挙げた書類でなくても良い場合もあります。新聞の訃報欄でも良しとする場合もありますので、自分の所属する自治体に確認の上何が必要であるかを明確にすることが重要です。
忌引き休暇を取得するまで及び取得後の流れ
まずは直属の上司に報告をします。いち早く直属の上司に連絡すれば、自分がいない間の業務をどうやって行うかを計画することができます。
報告後は、必要書類を用意して申請を行いましょう。必要書類としては、前項で挙げた証明書類や自治体の休暇届けとなります。
休暇明けは、周囲の方へのお礼を行います。まずは上司にお礼をし、その後は周りの方にお礼を伝えます。自分の業務を代理で行ってくれた方へも直接感謝の気持ちを伝えましょう。お礼の際は、香典返しや菓子折りを忘れずに渡すことが大切です。
自分の忌引きを申請したら子供の忌引きも申請を忘れずに
自分の申請と同時に子供の忌引き申請も行いましょう。小、中、高校生の場合は、「忌引き」での休暇申請を行わないと通常の欠席扱いとなってしまいます。特に子供の場合、欠席となってしまうと内申点に関わり、進学に影響が出てしまう恐れも出てくるのです。
子供の将来に関わることですから、子供の学校へも忘れずに忌引き休暇申請をしましょう。
連絡する相手
連絡は担任の先生にすれば間違いありません。仮に、学校の事務員に連絡する決まりであったとしても、担任の先生に伝えることで事務員に連絡を入れてくれたり、事務員に連絡する必要がある旨を教えてくれたりします。
また、もし担任の先生と連絡がつかなかった場合は、事務員に忌引きの伝言を依頼する方法でも問題ありません。
連絡方法
一般的な連絡方法は電話です。学校によっては、規定の用紙に忌引き休暇申請をする旨を記入し、事前に子供に持たせて担任の先生に渡すという方法を取っているところもあります。
また、「連絡帳」での申請というケースもあります。どちらのケースの場合でも、いつまで休むことができるのかを明確にしておくことが必要です。
会社員の場合の忌引き
各企業によって規定が大きく異なるため、必要十分な忌引き休暇日数がないケースもあります。忌引き休暇は労働基準法で定められていないため、必ず忌引き休暇を取れる保証はありません。
休暇日数が少ない、あるいは全くないことも考えられます。中には有給休暇を使用するケースもあります。よって公務員の場合は、忌引き休暇に関して非常に恵まれているといえるでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
ここまで、公務員である場合の忌引き休暇の日数について解説をしてきました。
会社員の場合、各会社で忌引き休暇の規定は大きく異なり、中には規定自体がないこともあります。公務員の場合は比較的恵まれており、一般的に必要とされる休暇日数を規定としていることが多く、もしものときでも葬儀の準備を安心して行うことが可能です。
今回ご紹介した点を参考にして、スムーズな忌引き休暇の申請を行いましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



相続人には、被相続人の遺産を一定割合受け取れる「遺留分侵害額請求権」があります。ホゥ。