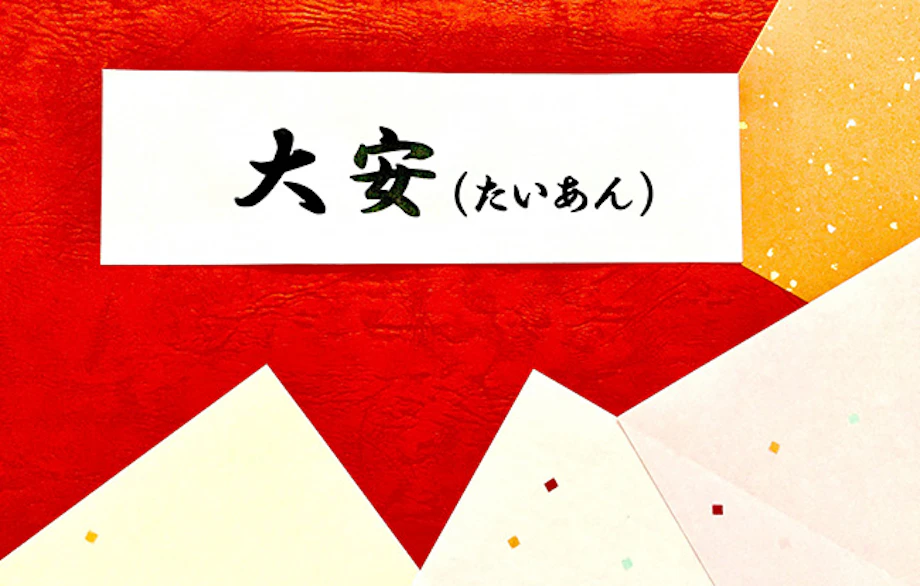「通夜や葬儀の日程の決め方を知りたい」「葬儀をしてはいけない日柄はあるのか」と疑問をお持ちの方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、六曜の日柄や通夜・葬儀との関係、葬儀の日程調整の方法を紹介します。大安に葬儀を行ってもよいかどうかについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・本来六曜と仏教には関連性がないが、友引の葬儀は避ける傾向がある
・法律により死後24時間以内の火葬は禁じられているため、亡くなった当日に葬儀を行うことはない
・葬儀の日程は僧侶の都合や火葬場の空き状況を確認してから決める
こんな人におすすめ
お通夜で六曜を気にされている方
お通夜が大安だった場合のことが知りたい方
葬儀の日程を決めようとしている方
六曜で通夜を避ける日について
本来、六曜と仏教には関連性がないので、どの日にちに葬儀を行っても問題ありません。ただし、通夜や葬儀の日取りを決めるときは、風習として友引の日を避ける傾向があります。
ここからは、六曜の意味と友引の日の通夜・葬儀を避ける理由をそれぞれ解説します。
六曜とは
六曜とは中国から伝わった暦のことで、以下の六つのことを指します。ひとつです。
・大安(たいあん)
・先勝(せんしょう・さきがち)
・先負(せんぷ・さきまけ)
・友引(ともびき)
・仏滅(ぶつめつ)
・赤口(しゃっこう・せきぐち)
六曜はその日の吉凶を占うために定められていて、その日が縁起がよいかどうかや、一日の中で物事を進めるのによい時間帯を把握するための目安として用いられてきました。
友引は避けることが多い
漢字のイメージから、友引は「友を引き連れていく」とされ、縁起がよくないと考えられています。そのため、友引の日の通夜は避けるのが一般的です。本来は「共引」という漢字で表記され、正しくは「勝敗が決まらず引き分ける日」という意味を持ちます。
「友引」という漢字が使用されるようになってからは、転じて「友を引く」という意味に捉えられるようになりました。
<関連記事>
友引にお通夜は避ける?友引と葬儀の日程との関連性
仏滅も避けることが多い
仏滅も通夜を避ける傾向にある日です。本来の意味は「仏も滅してしまうほどのよくない日」であり、何も行わずに平穏に過ごすべき日だと考えられています。慶事には特に適さない日として世間に浸透している大凶日です。
現代では、仏滅の日の通夜も避けるべきと認識されています。「仏」という漢字から「仏様の命日」と勘違いしている方が多くいるためです。
赤口は避けることが多い
赤口も縁起がよくない日柄として知られています。六曜の意味では「正午の前後1時間のみ吉」という日で、それ以外の時間帯は凶と考えられています。
「赤」という漢字を使用していることから、火や出血に関わる事故や怪我などに注意するという日でもあります。
ただし、六曜はあくまで中国の占いの一種であり、仏教とは関係がありません。喪主や参列者の間で納得できていれば、仏滅に通夜を避ける必要はないといえます。
<関連記事>
六曜とは?葬式における六曜を宗教別に解説
通夜は大安に行ってもよい?
大安に通夜を行っても問題はありませんが、大安を通夜の日取りとして選ぶ方は少ないのが実情です。ここからは、大安の概要と通夜を避ける理由をそれぞれ解説します。
大安とは
「大安(たいあん)」は、簡単に説明すると「縁起のよい日」です。「泰安」と表記されることもあります。
「大いに安し」という意味で、物事が穏やかに運ぶ日として、とても縁起がよいとされています。何を行うにも非常によい日ですが、一般的には結婚式や地鎮祭などのおめでたい行事の場合に選ばれる日柄です。
大安に通夜や葬儀をしない理由
大安に通夜や葬儀を行うことが少ないのは「大安は縁起がよい日」というイメージが根付いているためです。良日に通夜や葬儀などを行うことを不謹慎だと感じる方が多くいるため、弔事は慎む傾向にあります。
遺族側が気にしていなくても、参列者が嫌がる可能性もあります。その後の親戚付き合いや近所付き合いなども考慮して、大安の通夜や葬儀を避ける方も多いでしょう。
大安でも葬儀をしてよい
六曜と仏教には関係がないので、大安に葬儀を行っても何の問題もありません。大安を避けるのはあくまでイメージの問題です。「いかなる場合も避けなければならない」というきまりではありません。
「宗教的に不都合があるのでは」と心配する方もいますが、日本で多くの方が信仰している仏教と、六曜は関連性のないものです。仏教式の葬儀を行う際に六曜の日柄を気にする必要はありません。法律上・法令上の問題もありません。
通夜や葬式の日程の決め方
ここからは、通夜や葬儀の日程の決め方を紹介します。一般的な決め方を知っておけば、社会人のマナーとしても役立つでしょう。通夜の日程がずれるケースについても解説するので、覚えておくと安心です。
一般的な葬儀の日程の決め方
葬儀は通夜の翌日に行うのが一般的です。故人の遺体は臨終当日に自宅や喪主の家に搬送されます。命日の翌日に通夜を行い、その翌日に葬儀という流れです。つまり葬儀の日程は臨終から3日目にあたります。
直葬や一日葬など通夜を行わない葬儀の場合は、状況に合わせて日程を決めましょう。地域によっては臨終当日に通夜を行ったり、葬儀の前に火葬を行ったりする場合もあります。住んでいる土地の風習を事前によく確認しておくと安心です。
通夜を翌日に行わない時もある
故人が亡くなった時間帯や日取りによっては、通夜を翌日に執り行わないこともあります。亡くなったのが夕方以降であれば、準備の関係により、通夜や葬儀の日程を一日ずつ先送りにするのが一般的です。
年末年始など、葬儀社の営業期間外で亡くなった場合は、何日も通夜や葬儀を行えません。僧侶の都合がつかないことで日程調整を求められるケースもあるため、通夜の日程がずれてしまっても落ち着いて対処しましょう。
亡くなった当日に葬式は行わない
例外的な事情があるケースを除き、亡くなった当日に葬儀を行うことはありません。葬儀を行ったらそのまま火葬まで行うのが一般的ですが、死後24時間は火葬を行うことが法律で禁止されているためです。
直葬のように通夜や告別式が省略された形式であっても、火葬が行えるのは亡くなってから24時間以上経過した後です。法律によって定められているため、個人的な事情によって例外が認められることはないと認識しておきましょう。
<関連記事>
通夜の日程を決めるポイントは4つ!注意点を意識して準備を進めよう
通夜で六曜以外に注意したいポイント
通夜では、六曜以外にも僧侶の手配や火葬場のスケジュール確認など注意すべきポイントがあります。ここからは、通夜を行う際の注意点について解説します。
僧侶の都合を確認する
通夜や葬儀の際も、僧侶の都合を必ず確認しましょう。葬儀形式にもよりますが、どちらも読経を依頼する必要があるためです。
通夜や葬儀が重なってしまうと、僧侶のスケジュールを押さえにくいこともあります。通夜や葬儀を行うことが決まった際は、なるべく早く菩提寺に連絡しましょう。
火葬場の空きを確認する
通夜や葬儀を行う場合は、火葬場の空き状況も確認しましょう。希望の日時に火葬場が予約で埋まっていることも考えられます。日程は細かく決めすぎず、大まかな予定を組んだ段階で確認するとよいでしょう。
火葬場を予約できなかった場合は、利用可能な日時に合わせて通夜や葬儀の日程を調整する必要があります。日程を優先したい場合は、ほかの火葬場にも相談して、空きがあるところを予約しましょう。
葬儀場の空きと参列者の都合を確認する
火葬場の予約ができたら、葬儀場の空きも確認しましょう。通夜は自宅で行う場合もありますが、葬儀は葬儀会場で執り行います。アクセスはよいか、参列者の人数に見合った会場かなどもしっかりと確認します。火葬場が併設されているかどうかも葬儀日程を決める際に重要なポイントなので、あらかじめ近隣の葬儀会場を調べておくのがおすすめです。

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
本来、六曜と仏教には関連性がないので、どの日にち・日柄に葬儀を行っても問題ありません。ただし、通夜や葬儀の日取りを決めるときは、風習として友引の日を避ける傾向があります。地域によっては独自の風習に沿って葬儀を行う場合もあるため、葬儀社に相談すると安心です。
小さなお葬式では、お客様のご希望に寄り添ったプランを紹介いたします。地域の風習に合わせた葬儀のご提案もしておりますので、葬儀の日程調整にお困りの際はぜひご相談ください。急な訃報でお急ぎの方にも、迅速に対応いたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



葬儀費用は相続税から控除することが可能です。ホゥ。