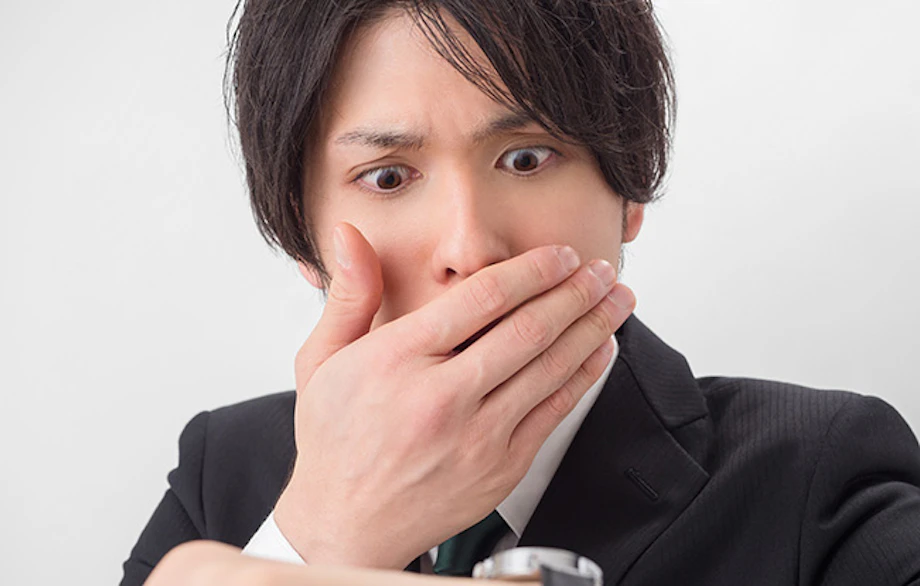みなさんは、通夜の開始時間は何時だとイメージしていますか。通夜は、いつどのようなタイミングで執り行われるかわかりません。そのため、急な連絡を受けると、仕事の都合などで「開始時間までに間に合わないかもしれないし、どのような流れで進むのか……」と不安を感じる人も多いのではないでしょうか。
この記事では通夜の基本情報や開始時間についてわかりやすく解説しているので、もしものときに備えて少しでも不安を解消させておきましょう。
<この記事の要点>
・通夜の開始時間は18時~19時が一般的で、参列者は開始時刻の30分前に着くように向かう
・20分程度の遅刻は許容されることも多いが、なるべく決められた時間までに向かう
・仮通夜は3時間程度、半通夜は3時間-6時間程度、本通夜は半日程度かかる
こんな人におすすめ
通夜の流れを知りたい方
通夜の開始時間や集合時間を知りたい方
通夜に遅刻した際の対応方法を知りたい方
通夜の意味は?
日本では、人が亡くなったときには通夜を経て葬儀が執り行われるのが一般的です。しかし、葬儀はきちんと執り行われるのに、「なぜ通夜が必要なの」と疑問を感じている人もいるのではないでしょうか。葬儀は亡くなった人を見送るために執り行われる大切な儀式ですが、通夜にも大きな意味があります。
通夜とは葬儀の前夜に遺族や親族、友人縁者が集まり、亡くなった人を見守りながら最後の夜を共に過ごす大切な時間です。従来は遺族などが夜を徹して線香とロウソクの火を絶やさないように、亡くなった人を見守り続けるのが一般的でした。
これが「通夜」という言葉の由来だといわれています。近年は防火上の観点により実際に火を使う機会が減ったので、夜のうちに終了する「半通夜」も増えています。
通夜の流れ:準備から通夜後まで
自分が参列するときだけでなく、もしものときに備えて通夜の流れを把握しておくと安心です。執り行う側になった場合には、参列者や葬儀社の対応で多忙を極める可能性が高いといえます。ここでは準備から通夜後までの流れを順に紹介していくので、突然参列することになったときや執り行う側になったときのために役立ててください。
通夜の準備
家族や親族といった大切な人が亡くなった場合、まずは葬儀社と通夜や葬儀の日取りや場所を打ち合わせします。この他には、通夜を執り行うために次のような準備が必要です。
・亡くなった人と親交があった人達へ連絡
・通夜ぶるまいの手配
・返礼品や会葬礼状の手配
亡くなった人と親交があった人達へ連絡する際には、通夜と葬儀の日時や場所だけでなく、亡くなった日時や喪主の氏名なども伝えるようにしましょう。
通夜
当日を迎えたら、次のような流れで通夜を進行していきます。
・参列者の受付
・僧侶の入場
・僧侶による読経
・喪主や遺族、参列者による焼香
・僧侶の退場
・喪主による挨拶
・通夜ぶるまい
参列者の受付は通夜の30分ほど前から開始し、記帳や香典の受け取りといった対応を行います。僧侶の到着後は控室に案内し、挨拶や進行の打ち合わせをしておきましょう。通夜が開始すると僧侶が入場し、読経の間に遺族や参列者などが焼香を済ませます。その後は僧侶が退場し、喪主の挨拶を経て通夜ぶるまいへと進行するのが一般的な流れです。
通夜後
通夜ぶるまいの後は、喪主が時間を見計らって締めの挨拶をして参列者が退出します。遺族だけになった部屋では、ロウソクと線香の火を絶やさないように亡くなった人を見守りながら最後の夜を共にする時間が訪れます。
先述したように、最近では防火上の観点から実際に火を灯さないケースが増えています。夜を徹して亡くなった人を見守る場合は、翌日に葬儀も控えているので心身を消耗している遺族ではなく、できるだけ体力が残っている遺族で行いましょう。
通夜の開始時間・集合時間
これまでに通夜に参列したことはあるものの、いざ執り行う側になった場合を想定すると「通夜の開始時間や集合時間は一体いつなの」と疑問に感じている人も多いのではないでしょうか。ここでは通夜の開始時間と集合時間を解説していくので、参列者だけでなく執り行う側になったときにあわてないように備えておきましょう。
通夜の開始時間
通夜の開始時間は18時~19時に開催されるのが一般的ですが、葬儀社の都合などで時間が前後する場合もあります。最近は時代の流れと共にライフスタイルが変化したため、通夜の開始時間を参列者の都合にあわせるケースも増えています。
また、亡くなった人が務めていた会社関係の人は、仕事の都合で葬儀に参列できないことがあります。このような場合は葬儀の代わりに通夜に参列するため、最近では葬儀よりも通夜の参列者が多い傾向にあるといわれています。
通夜の開始時間によっては遠方からの参列者は間に合わない可能性もあるため、葬儀社や参列者の都合を考慮して決めることをおすすめします。
集合時間
通夜の開始時間がわかっていても、「何時までに集合すればよいの」と疑問を持つ人もいることでしょう。通夜の集合時間は、参列者の場合は30分前ほど前、喪主や遺族の場合は1時間~1時間半ほど前が目安です。
なぜ喪主や遺族は参列者との集合時間に差があるのかというと、葬儀社などとさまざまな打ち合わせがあるからです。たとえば、通夜の手伝いをしてくれる人への挨拶や生花の配置など、喪主や遺族が通夜の開始までにしなければならないことは多岐にわたります。その場で急遽変更になる場合もあるため、特に喪主や遺族は余裕をもって集合するようにしましょう。
通夜に遅刻したときの対応は?
通夜の開始時間に仕事の都合などで間に合わない場合、「このまま参列しても失礼にあたらないのか……」と不安を感じる人もいるのではないでしょうか。通夜は、亡くなった人を見守りながら最後の夜を共に過ごす大切な時間です。そのため、できるだけ遅刻しないように心がけることが大切です。ここでは通夜に遅刻したときの対応について解説しているので、もしものときに備えましょう。
通夜へ遅れても大丈夫?
通常の場合、通夜は遺族や親族を中心に執り行われるため、参列者の遅刻がマナー違反というわけではありません。20分~30分ほどの遅刻であれば受付にも担当者がいるため、できるだけ急いで駆けつけましょう。
1時間以内の遅刻の場合は通夜が進行されているケースが多いため、担当者の案内にしたがって焼香を済ませることができます。ただ、2時間以上の大幅な遅刻が想定される場合は通夜が終了している可能性が考えられるため、あらかじめ連絡して遺族の都合を確認することが大切です。
通夜が終了した後は遺族といった亡くなった人と近しい人しか残っておらず、翌日の葬儀に備えた準備が必要です。そのため、亡くなった人とよほど親交が深くない限りは遅い時間に訪れるのは避けた方がよいでしょう。
通夜に遅れたときのマナー
決められた時間までに到着するのがマナーとして当然だといえますが、仕事の都合や遠方から駆けつけるといった理由でどうしても間に合わないケースもあることでしょう。通夜に遅れた場合には、喪主や遺族にお詫びと弔意を伝え、香典を直接喪主に渡すようにしましょう。
お詫びと弔意は長々と伝えるのではなく、遅刻した理由は排除してできるだけ簡潔に伝えることが大切です。香典を渡すタイミングを逃した場合は翌日の葬儀、または後日改めて喪主の自宅を訪れて渡します。なお、葬儀社のスタッフといった第三者に香典を預けるとトラブルに発展する可能性があるため、避けるようにしましょう。
通夜にかかる時間
通夜に参列したものの、「一体どのくらいの時間がかかるの」と疑問に感じている人も多いことでしょう。通夜には仮通夜と半通夜、本通夜の3種類があり、喪主や遺族がどの種類で通夜を執り行うかでかかる時間が異なります。ここでは、通夜にかかる時間をそれぞれ解説していくので、参列するときの参考にしてください。
仮通夜
一口に「通夜」といっても、一般的に「通夜」と呼ばれているのは「本通夜」のことです。仮通夜とは人が亡くなった当日に親族とだけで執り行われる儀式で、友人や会社関係者などは参列しません。僧侶によるお経や通夜ぶるまいもなく、亡くなった人を見守って共に過ごすことがメインとなります。時間は18時頃から開始し、21時~22時頃に終了するケースがほとんどです。
半通夜
従来は通夜ぶるまいの後に喪主や親族だけが集まり、線香とロウソクの火を絶やさないように亡くなった人を見守りながら最後の夜を共に過ごすのが一般的でした。しかし、最近では防火上の観点や夜を徹して亡くなった人を見守る習慣が少なくなっており、本来の「通夜」から「半通夜」と呼ばれるようになりました。開始から終了までの半通夜の所要時間は、3時間~6時間ほどが目安です。
本通夜
仮通夜と異なり、喪主や親族だけでなく一般の参列者と共に亡くなった人を見守る儀式が本通夜です。僧侶によるお経や焼香に加えて通夜の後には通夜ぶるまいが行われ、喪主や遺族はさまざまな準備が必要です。準備を含めた本通夜にかかる所要時間は、半日ほどが目安です。しかし、翌日には葬儀を控えているため、喪主や親族の心身の負担は大きいといえるでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
通夜は喪主や親族だけでなく参列者にとっても、亡くなった人を見守るための大切な時間です。突然の不幸で慌てないためには、通夜の信仰やマナーをきちんと理解しておくことが大切です。また、参列する際に遅れる場合は、どのくらい遅れるかによって対応を使い分けましょう。通夜に関する疑問は、24時間365日専門スタッフが在籍している「小さなお葬式」へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



葬儀費用は「葬儀一式費用・飲食接待費用・宗教者手配費用」で構成されます。ホゥ。