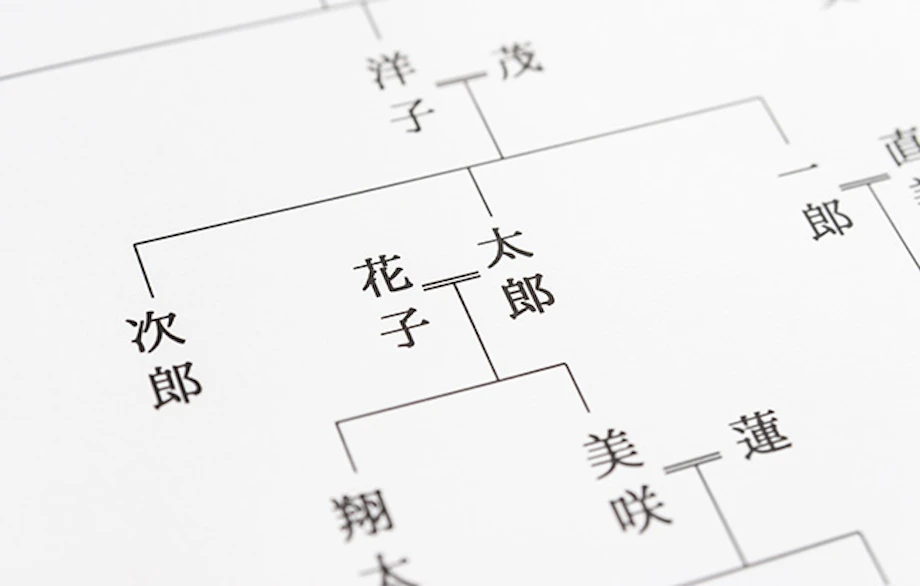香典は葬儀とは切っても切れない関係にあります。どれくらいの金額を出すのが適切なのかもポイントになる上、また誰に出すべきなのか相手との関係性も気になる点です。
亡くなった人との関係によって金額が変わるか、誰にいくらくらい渡すかなどの相場についてまとめました。
香典にはいくら以上渡してはいけないなど、明確な規定はありませんが、渡すときの指針として確認していただくことでお互いに満足のいくスマートなやりとりができるでしょう。
<この記事の要点>
・香典の金額は故人との関係性を重視して金額を決める
・会社名義で香典を出す場合は個人名義で出さないよう注意が必要
・亡くなった家族と同居している場合は香典を出す必要はない
こんな人におすすめ
香典を渡す範囲を知りたい方
故人との関係性別の金額相場を知りたい方
香典が不要になる場合について知りたい方
香典を渡す範囲に決まりはない
香典について考えるとき、どこまでの範囲に渡すかというのは大きな課題となります。葬儀に関するマナーともいえる行いであるため、具体的に法律で制定されているわけではありません。
「誰々までは確実に渡さなければならない」と決められているわけではないため、逆に混乱してしまったり相場が分からなかったりする事態もしばしば見受けられます。
香典の本来の意味
本来、香典は亡くなった人の遺族を思って送るものです。葬儀や法事など、亡くなった後の手続きにも時間とお金がかかります。特に一家の大黒柱が亡くなったときや生前も経済的に困窮している場合は葬儀も金額的負担となって重くのしかかってくるものです。
葬儀の参列者から少しずつ金品をいただくことで、この問題を参列者全員でサポートすることができます。これが香典の本来の意味になります。多ければ多いほど相手側が助かるかというと必ずしもそうではなく、相手側が恐縮してしまうこともあるでしょう。
故人を含むこれまでの関係性と遺族とのこれからの関係性、両方にまたがるかたちで香典は関わってきます。深刻に考えてしまう人がいるのも無理はありません。
見極めは「故人との関係性」
誰にいくら出すかという明確な判断基準が決められていない以上、自己判断で決めることになります。落としどころが分からない人は、故人との関係性を重視して金額を決めるとよいでしょう。
自分にとって個人がどれくらい影響力の大きい人であったか、それを考え直すことで適切な金額を決めることができます。
例えば長年会社でお世話になった上司や、自分の人生の成功に大きく関わったような人であれば、たとえ血縁関係がなかったとしても香典は出すべきだと言えます。
反対に血縁関係があったとしても全く交流がなかった、あるいは仲が悪かったという場合香典を渡さないという決断をする人もいます。
仲が悪いパターンは原因が分かりやすいですが、遠い親戚が亡くなった場合にはどこまで出すかの線引きが難しいことも関係してきます。
また自分は直接関わりがなくとも、自分の家族がお世話になった人が亡くなるということも出てくるでしょう。故人との関係性は一概に計れるものではなく、だからこそ明確なガイドラインも存在していないのが実情です。
生前の関係があったとしても、香典を受け取るのは故人の遺族になります。故人との関係だけでなく、遺族との関係も深くないと、香典をもらったときに相手も混乱してしまう可能性があります。
誰にいくらもらったかは香典返しのときにもダイレクトに関わってくる問題です。香典返しは挨拶状とともに現在郵送で行うのが主流となっており、渡した金額の3分の1から半分くらいを目安として返送する風習です。
特に大金を送ったときは送った金額の全てがなくなるというわけではないため、相手との関係性とともに香典返しのことも頭に入れておくことでより正確な金額が算出できるでしょう。
故人との関係性別の金額相場
香典の成り立ちと送る理由について一通り分かったところで、次は具体的な金額に移っていきます。このページの肝となる部分でもあり、また相場を知ることで自分も納得のいく結果にアプローチすることができるでしょう。
送る場合の金額の多寡に関わってくるものは前出の故人との関係性と血縁関係が主です。一つ一つ場合分けしてまとめました。
親族や友人への香典は自分の年齢を考慮
親族や友人に送る場合、自分の年齢を考慮に入れる必要が出てきます。例として自分が学生の場合は、基本的に香典を出すことはありません。学生といっても小学生と社会人経験をしてからまた大学に戻る場合とでは大きく年齢にも開きが見られることになります。
20歳を迎えて成人しているかどうか・学生であるかどうかが1つのポイントになります。成人して働いている、もしくは大学院生である場合は立派な大人としてみなされることが多いため香典を出した方が望ましいです。
祖父母・義祖父母
| 年齢 | 金額 |
| 20代 | 1-2万円 |
| 30代-40代 | 3-5万円 |
| 50代以降 | 5万円以上 |
最初に自分の祖父母や義祖父母が亡くなった場合を見てみましょう。上記の表を参照してみてください。1番若い20代と50代以降では大きく渡す金額に差が出ていることが分かります。自分の年齢で出る金額差は祖父母の場合おおよそこれくらいの幅です。
自分が祖父母と同居している場合、自分も遺族に含まれるため香典は不要となります。別で世帯を持っている場合は自分の祖父母であっても香典を送る方が望ましいこともあるため、家族と相談するのが大切です。
両親・義父母
| 年齢 | 金額 |
| 20代 | 5万円 |
| 30代-40代 | 5-10万円 |
| 50代以降 | 10万円以上 |
自分の両親や義父母が亡くなった場合、金額は以上の表が相場です。祖父母のときと同じくここでも例外があり、親の死によって自分が喪主を務める場合や同じ世帯に入っている場合は出す必要はありません。
しかしたとえ肉親であっても結婚して既に世帯を離れている、兄弟が喪主を務めるようであれば出した方がよいとされています。身内に渡すことになるため、本人と相談した上でお互いが納得できる方法を見つけるのがベストと言えます。
兄弟姉妹・義兄弟姉妹
| 年齢 | 金額 |
| 20代 | 3万円 |
| 30代-40代 | 3-5万円 |
| 50代以降 | 5万円以上 |
自分の兄弟姉妹、もしくは義理の兄弟姉妹が亡くなった場合の金額内訳は上記表のようになります。両親や義両親がなくなったときよりも控えめの金額になっていることが分かります。
肉親であることから、世帯はここでも関係してきます。自分と同じ世帯に住んでいる兄弟姉妹が亡くなった場合、もしくは自分が喪主を務めることになる場合は香典を出す必要はありません。
結婚して家を出ている場合、もしくは一人で生計を立てている場合は出した方がよいと言われています。出すか出さないかの判断は両親や祖父母の場合と大きく変わることはないことが分かります。
子・孫
| 年齢 | 金額 |
| 20代 | 5万円 |
| 30代-40代 | 5-10万円 |
| 50代以降 | 10万円以上 |
自分の子や孫が亡くなった場合、包むべき金額は上記の表を参照してください。親が亡くなったときと同じ金額であることが分かります。これには理由があり、法律上の血縁関係で親と子供は一番近しい続柄になることが関係しています。
そのため両親が亡くなった場合と同じく、子や孫が亡くなったときも両親のときと同じ金額が相場として算出されています。肉親が亡くなったときの金額の相場は以上が平均的な相場となっています。自分の状況をふまえて参考にしてみてください。
叔父(伯父)・叔母(伯母)
| 年齢 | 金額 |
| 20代 | 1-2万円 |
| 30代-40代 | 2-3万円 |
| 50代以降 | 3-5万円 |
叔父(伯父)や叔母(伯母)が亡くなった場合は、血縁の関係から相場とされる金額はいくぶん他の続柄と比べて少なめです。10万円近くにもなる、肉親に出す香典の相場から比べると最大でも数万円というのは大きな違いと言えます。
叔父(伯父)や叔母(伯母)などは親戚を含めると人数が多くなってしまうことがありますし、血縁上の関係でもそれほど近しい間柄でもありません。金額の相場を知らなかったとしても、何となく両親や子供よりも叔父(伯父)や叔母(伯母)の方が少なくなることは想像に難くありません。
その他の親戚
その他の親戚が亡くなった場合、いくらぐらいが適切か悩んでしまうこともあるでしょう。基本的には最初にまとめた通り、相手との関係性によりますがおおよその相場は5,000円から1万円と言われています。
しかし相手との関係が親しかったり、あるいは以前に相手側からこちら側へ香典のやりとりがあったりした場合はそれを参考にするのが妥当です。同じ金額を返すようにすれば、後々問題になることもありません。相場にこだわりすぎないようにしましょう。
友人・知人
友人や知人が亡くなったときの平均金額は3,000円から1万円と言われています。友人や知人は直接血のつながりがない相手であることから、関係性がより重視されます。プラスアルファで自分の年齢を加味した金額が出せればベストです。
何かのサークルや集まりで知り合った友人知人の場合、知り合った他の友人と連名で包むこともあります。「大勢いるときに話す間柄ではあったけど、特別親しくはなかった」という場合のように関係性が難しいときの解決法になります。
職場・会社関係の人
職場や会社を通しての付き合いがある人への金額は一見判断が複雑に見えます。上司より高い金額を出さないことや同僚と金額を揃えて出した方がよいこともあるからです。
特に会社名義で出す話が進んでいるときは個人名義で出さないよう注意が必要です。仕事での付き合いがある人が亡くなったときは、自分一人で急いで決断を出さない方がよいでしょう。
周りにいる上司や同僚、同業者など同じく香典を出す予定がある人に相談しながら決めることをおすすめします。会社名義で出す場合はいくら包んだらよいか自分以外の人に決定権をゆだねることも出てくるでしょう。
金額自体は平均で5,000円-1万円ほどと言われています。これは同僚や上司、社長など相手の立場にあまり依存しません。自分で金額を決める必要があるときは、最低5,000円を目安に相手との関係性を鑑みて金額を決定しましょう。
一点会社関係で気をつけておきたいのは、部下や同僚など会社絡みで付き合いのある人の家族が亡くなった場合です。自分との関係という面から見れば関わりのない人ではありますが、上司の家族が亡くなった場合でも包む必要があります。
ご近所の人
近所の人が亡くなったときに気をつけるべきポイントも職場のときと共通点があります。町内会やグループで金額があらかじめ決められることもあるでしょう。
同じようなかたちで以前香典をいただいたことがあるかもしれません。その場合は親戚でまとめた内容と同じように、以前いただいた金額と同じ金額を包めば失礼にはあたりません。
近所の人が亡くなったときの金額の相場は3,000円から1万円です。上記でまとめた状況プラス故人との付き合いの深さで渡す金額を決めるのがよいでしょう。
香典が不要になる場合もある
これまでの見出しでは香典のマナーについてまとめてきました。法律や条例のように決まった制度がないことから、少し複雑に感じてしまうこともあるでしょう。
相手の気持ちを考えて包むものであること、相手との関係性も金額を決める上で大切なファクターになります。
最後に送らなくてもよい場合についてまとめました。家族に送る金額の項目でも少し触れましたが、香典は不要になることもあります。
同居の親族
送らなくてもよい最初の例として、亡くなった人と同居しているケースがあげられます。同居している親族は遺族となり、葬儀をあげる側となります。葬儀をあげる側はもちろんお花代や金品を包む必要はありません。
これは同居している親族であれば、亡くなった故人との血縁上の親等によらないものです。例えば同居している祖母が亡くなった場合は送る必要はありませんし、兄弟姉妹や孫の場合でも同じことが言えます。
「家族と同居していれば香典を出す必要はない」とざっくりしたイメージをお持ちの方も多いでしょう。そのイメージは間違っておらず、自分が故人の亡き後に遺族に含まれるのであれば例外はありません。包む必要がないケースの中でも最も分かりやすいものです。
学生の子ども
自分が学生なら香典を送る必要はほとんどのケースでありません。たとえ故人との血縁関係があり、なおかつ離れて暮らしていたとしても包むことは全国的に見られません。10代の場合は香典の心配をする必要はないでしょう。
成人していてなおかつ働いている場合は、20歳などの若年層でも職場関係において香典を包む機会が出てくることもあります。しかし全体的に見れば限定的なもので、包む機会があったとしても年齢をふまえて少額に収まることがほとんどです。
香典を辞退している
最後に遺族側が香典をいただくことを辞退しているパターンが考えられます。本来であれば香典をいただくことは金銭的に助かるはずですが、いくつかの理由により辞退する可能性もあります。
一つ目に参列者に金銭的な負担をかけさせたくない場合です。葬儀に参列する以上のものを求めたくないと考える遺族の意向が反映されることがあります。
二つ目は何らかの理由によって故人と関係性の薄い人が参列者の大多数を占める場合です。故人との関係性が薄い人にいただくことをよしとせず、辞退することもありえます。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
包む側になったとき、まず気になるのは相手との関係性と金額の相場です。どれくらいの範囲にどれくらいの金額を渡すべきか、自分一人では判断しかねることもあるでしょう。
相手への思いやりに付随するかたちで送られるもののため、最終的には故人と自分の関係や信頼に委ねられる面も多分にあります。相場など必要な情報を知ることができれば、最良の決断に一歩近づくことができるはずです。
葬儀に関するマナーは複雑なものも多く、プロに聞くのが迅速かつ確実なこともあります。ぜひ小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



お通夜とは、家族や友人たちが集まり、故人と最後の夜を過ごす儀式のことです。ホゥ。