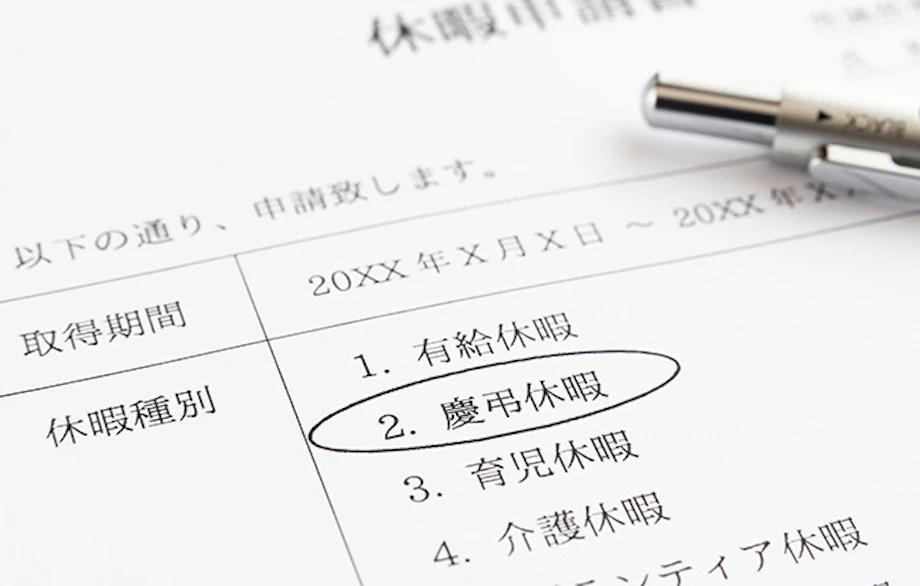「忌引き」のため、学校や会社を休んだ経験をした方もいることでしょう。家族、親族に不幸があった場合、葬儀への参列はもちろん、気持ちの整理をつけるためにも休みが必要です。そのため、忌引き休暇を取ることになります。
しかし、具体的に忌引き休暇はいつからなのか、どのくらいの日数休暇を取れるのか疑問に感じることもあるのではないでしょうか。
この記事では、忌引き休暇はいつからなのか、日数やマナーについて紹介します。忌引きに関するさまざまなことも解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・忌引き休暇は、一般的に亡くなった日またはその翌日から取得できる
・亡くなったのが両親や配偶者の場合、休暇日数は7日~10日が一般的
・忌引き休暇の取得を伝える際には、口頭でなるべく早く直接伝えるのがマナー
こんな人におすすめ
忌引き休暇の概要を知りたい方
一般的な忌引き休暇の取得日数を知りたい方
忌引き休暇を取得する際のマナーを知りたい方
忌引きについての概要
まずは、「忌引き」という言葉の意味を理解しましょう。聞いたことのある言葉であっても、意味まで詳しく知っている方はあまりいないかもしれません。
意味を理解できると、忌引きの過ごし方も変わってくるでしょう。ここでは、基本として押さえておきたい忌引きの意味や、忌引きの間にやってはいけないことを解説します。
言葉の意味
「忌引き」とは、家族や親族などの近親者が亡くなった際、喪に服すことをいいます。もともと、忌引きの期間中は喪服を着て過ごしていたとされていますが、現代では故人の冥福を祈り、慎んで過ごすことのみ受け継がれている地域が多いようです。
住んでいる地域や宗教によって忌引きの捉え方も、期間中何を行うのかも変わってくるでしょう。ただし、どの地域、宗教であっても故人を弔い、故人の安らかな眠りを心から願うことに変わりはありません。
忌中にはやってはいけないことがある
亡くなってから四十九日までを「忌中」と呼びます。忌中は慎んで生活をすることが習慣として受け継がれてきているため、派手な行動は控えたほうが賢明でしょう。
例えば、結婚式や入籍といったお祝い事は控えたほうがよいとされています。地域によって忌引きによる習わしはさまざまなので、確認しておくと安心です。
一般的に四十九日を過ぎると「忌明け」となり、それ以降は「喪中」と呼ばれ、故人との血縁の深さによって喪に服す期間が変わってきます。
忌引き休暇はいつから?実際に休める日数とは?
葬儀や通夜へ参列するため、学校や会社から取得する休暇のことを「忌引き休暇」といいます。
では、実際に忌引き休暇はいつから、どのくらいの日数で取得可能なのでしょうか。あらかじめ知っておくと、実際に忌引き休暇を取ることになった際の対応も速やかに行うことができます。一般的には、亡くなったその日、あるいは次の日から休めることが多いです。
また、休暇日数を決める際には、「誰が亡くなったのか」がポイントです。故人との関係性によって休める日数は変わってきます。ここでは、一般的な忌引きの休暇日数について解説します。亡くなった方とご自身の関係性を踏まえて参考にしてみてください。
亡くなったのが父や母、配偶者の場合
亡くなったのが父や母だった場合、休暇日数は7日~10日が一般的です。配偶者の場合は10日程度の休暇となるでしょう。亡くなった方がご自身と最も近い関係性にあたる場合、喪主を務めなくてはならないことが少なくありません。
喪主とは、遺族の代表者のことです。喪主は葬儀内容の確認や葬儀の手続き、僧侶や他の親族への対応といった重要な役目を担うため、心身ともに負担がかかります。こうした状況を考慮して一般的に長めに休めるとされています。
亡くなったのが兄弟姉妹や祖父母、息子・娘の場合
亡くなったのが兄弟姉妹や祖父母だった場合、休める日数はどちらも一般的に3日とされています。息子や娘の場合は、5日間の休みを取るのが一般的でしょう。
ただし、ご自身と近い関係にあたる点では父母や配偶者と同様なので、精神的な面を考慮して、10日程度の休みを取得可能な場合もあります。
休める日数は学校や会社によって異なる
一般的とされる日数はあるものの、実際にどのくらい休めるのかは、勤務先や通っている学校によって異なるでしょう。
会社の場合は就業規則を確認しましょう。学校の場合は生徒手帳に記載されていることが多いので確認してみるとよいでしょう。事前にどのくらい休めるのか知っておくことによって、忌引き期間の予定が組みやすくなり、各種手続きも速やかに行うことができます。
遠方へ行く場合や土日はどうなるのか
土日が忌引き休暇と重なってしまった場合はどうなるのか、気になる方もいるでしょう。一般的には土日も忌引き休暇に含まれます。例えば、金曜日から5日間の忌引き休暇を取得する場合、次に学校や会社へ行くのは土日を含めた5日後の火曜日となります。
ただし、学校や会社によって休暇日数は異なります。土日を忌引き休暇に含めるのかについても学校や会社の判断になるので、事前に確認しておきましょう。
忌引き休暇を得るときの最低限のマナー
忌引き休暇を取得する際には、休むことを伝えなければいけません。会社に勤めているなら上司に、学校に通っている場合は担任の先生に伝える必要があるでしょう。
伝え方やマナーを間違うと思わぬトラブルが起き、周りの方に迷惑をかけるかもしれません。また、休みを得る前にしておいた方がよいことや確認するべきこともあります。ここでは、忌引き休暇を得るときの最低限のマナーや確認するべきことについて紹介します。
口頭でなるべく早く伝える
忌引き休暇の取得を伝える際には、口頭でなるべく早く、直接伝えるようにしましょう。学校や会社側も、対応をしなければなりません。会社に勤めている場合は休んでいる間の引き継ぎや連絡事項があるかもしれないので、なるべく早く伝える必要があります。
口頭で伝えるのが難しい場合は、電話でも構いません。ただし、メールやSNSで伝えるのは控えましょう。また、ご自身が未成年の場合は保護者の方が担任の先生へ連絡するようにしてください。
忌引き休暇を伝える際に忘れてはいけないのが「故人との関係性」です。故人とご自身の関係性によって休める日数も変わり、その日数に応じて学校や会社も対応しなければいけません。故人との関係性を伝えることは忘れないようにしましょう。
必要な書類があるか確認する
忌引き休暇を得るためには、忌引きで休むことを証明する証明書を求められることがあります。よく使われている証明書には「会葬礼状」や「火葬許可証」といったものがあります。証明書がないと休むことができないこともあるので、事前に必要かどうか確認しておくと安心です。
忌引き明けの対応
忌引き休暇を取得し、休暇が終われば再び学校や会社に行くことになりますが、これを「忌引き明け」と呼びます。忌引き明けでは、周りへのフォローが欠かせないでしょう。休みの間、会社であれば誰かが仕事の穴埋めをし、学校でも配慮してくれた友人がいるかもしれません。
自分のために何かしてくれた人がいればこちらも何かしらの対応をしないと、今後の関係に影響を及ぼす可能性があります。ここでは、会社の同僚や学校の先生、友人と円滑に関係を進めていくためにも、忌引き明けにしておいた方がよいことを紹介します。
感謝の思いを伝える
例えば会社の場合、休んでいた間に仕事の引き継ぎをしてくれた方や仕事の穴埋めをしてくれた方が少なからずいるでしょう。まずは感謝の気持ちを伝えることが大切です。
急な休みに対応してくれたことへの感謝とともに、葬儀を滞りなく終えたことを伝えましょう。
お礼のお菓子や香典返し
忌引き明けの際に、忌引き休暇の対応をしてくれた関係者の方々に、感謝の気持ちを表す意味でお菓子などを持参するのもよいでしょう。香典返しでも、香典をいただいたお礼としてお菓子を送ることがあります。
ただし、香典返しの場合は香典返しの品を送るのが一般的ですが、忌引き明けの場合は必ず品を用意しなければならないわけではありません。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
身近な親族の方が亡くなった場合に、忌引き休暇を取得するために、どのくらい休めるのか、忌引きについて理解を深めておくことは大切です。
亡くなった人との関係性によって、休める日数は変動します。連絡をしたその日から忌引き休暇を取得することもできますが、学校や会社の対応によって違ってくるでしょう。精神的な負担もある状況ではありますが、なるべく早く連絡することを忘れないでください。
この他にも、忌引きに関して不明なことが出てくるかもしれません。また、忌引き中に執り行う葬儀について、さまざまな手続きが必要となり、負担に感じることもあるでしょう。その際には、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。専門的知識と豊富な経験を持ったスタッフが、お悩みの解決に全力で取り組ませていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



年金制度には大きく分けて公的年金制度と私的年金制度の2種類があります。ホゥ。