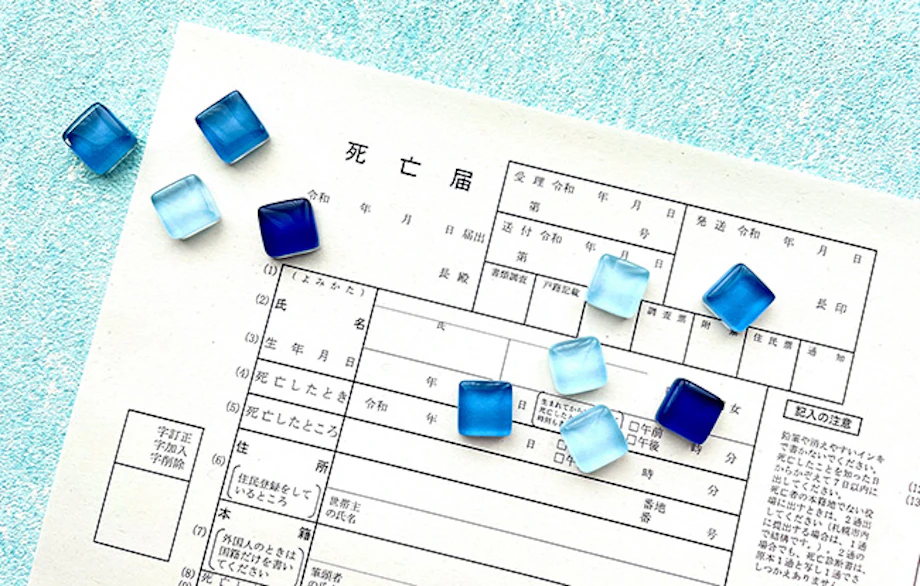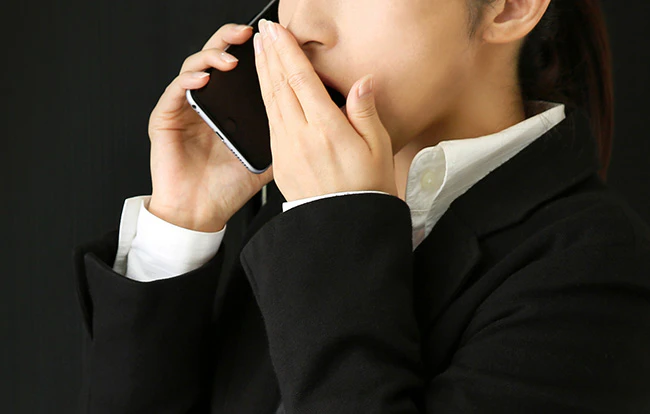葬儀を執り行う際に、何から取りかかればよいのかわからない方も多いのではないでしょうか。死亡から葬儀までの流れを把握しておけば、いざという時にも安心して進められるでしょう。
この記事では、死亡から葬儀前日までの流れ、葬儀当日の流れ、葬儀後にすべきことについて、順番に解説します。初めての人だけではなく、経験のある方も、確認のために参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・死亡後は葬儀社を手配し、日程が決まり次第、親族や知人に訃報連絡をする
・葬儀当日には故人の体を洗い清めて死装束に着替えさせ、納棺時に副葬品を入れる
・葬儀後には関係者へのお礼や香典返し、四十九日法要・納骨式などの準備を進める
こんな人におすすめ
危篤・死亡時に何をすべきか知りたい人
死亡から葬儀までの流れが不安な人
死亡後の手続きをあわせて確認したい人
死亡から葬儀前日までの流れ
家族が亡くなった際には、悲しみを感じながらも、葬儀の準備を進めなければなりません。特に、死亡から葬儀前日までは決めなければならないことが数多くあります。あらかじめ流れを把握しておくことで、スムーズに進められるでしょう。
危篤・死亡
いつ亡くなってもおかしくない「危篤」状態になった際には、家族や親族、親しい友人に連絡をしましょう。可能であれば、亡くなる前に会いたい人のリストを作っておくと漏れなく伝えられます。
付き添いをする方は、自分の職場に連絡を入れて休みを取得しましょう。
医師に死亡を告げられたら、取り急ぎ、家族や親族といった危篤を伝えていた人たちに電話などで連絡をします。
臨終後は、遺体を拭き、手術跡などの修復を行い、生前の姿に近づける「エンゼルケア」を行います。病院の看護師や葬儀社のスタッフが行うのが一般的ですが、遺族の立ち会いも可能です。
<関連記事>
危篤の意味とは?危篤時に行うべきことと葬儀までの流れ
葬儀社の手配
一般的には、速やかに葬儀社を決めて、その後の遺体搬送・安置などを進めていきます。病院から葬儀社を紹介してもらえるケースもありますが、断っても問題はありません。
葬儀社を選ぶ際のポイントは、執り行いたい葬儀に対応しているかどうかです。葬儀の規模、予算、支払い方法、宗教・宗派、葬儀会場などの希望を伝えて返答をもらいます。また、葬儀社のスタッフが信頼できる接客態度であるかどうかも含めて決めましょう。
搬送・安置
病院では一時的にしか遺体を安置できません。そのため、速やかに遺体安置場所を確保して、搬送してもらうことが必要です。
搬送先としては、自宅や斎場、葬儀社の安置室、遺体保管施設などがあります。葬儀社に希望を伝えて、寝台車で搬送してもらいましょう。
安置期間は3日~4日間が一般的ですが、1週間程度の場合もあります。安置室や遺体保管施設では心配はありませんが、自宅に安置する場合には、夏場でも室温を17度以下に保ちましょう。
葬儀社との打ち合わせ
遺体の安置を終えたら、葬儀の準備を始めます。葬儀社との打ち合わせに入る前に、家族間でどのような葬儀にしたいのかを相談しておくとよいでしょう。葬儀に関する故人の遺言があれば、踏まえた上で進めていきます。
葬儀社と確認しなければならないことは、次の通りです。
・喪主
・宗教・宗派・菩提寺の有無
・葬儀の形式・規模・予算
・通夜振る舞い・精進落とし
・斎場・火葬場
・葬儀日程
・返礼品 当日返し・香典返し
・葬祭用品(棺・祭壇・供物・供花・遺影など)
・葬儀案内(文面・部数・送り先)
・納骨先・お墓
僧侶の手配
仏式の葬儀の場合には、僧侶に戒名を授けてもらった上で、葬儀にて読経してもらいます。そのため、僧侶を手配しなければなりません。
喪家の菩提寺に依頼し、葬儀の日程を決めましょう。菩提寺がない場合は葬儀社に相談し、僧侶の手配をしてもらいましょう。葬儀日程、宗派に合わせて僧侶を紹介してもらえます。
親族や知人への訃報連絡
葬儀の日程が決まり次第、親族や知人に訃報連絡をしましょう。近しい親族には、取り急ぎ、電話やメール、LINEなどで迅速に知らせます。伝えるべき内容は、次の通りです。
・故人の氏名
・逝去した日時
・享年
・喪主の氏名
・連絡先
訃報連絡の際に、葬儀の案内もします。葬儀日時、会場、宗教・宗派、アクセス方法などを伝えましょう。
また、葬儀の案内文を作成し、電話やメールで伝えていない親族や知人、職場・学校関係者に郵送します。家族葬や直葬など、参列者を制限して身内だけで葬儀を執り行う場合には、その旨を丁寧に伝えましょう。
死亡届の提出
医師から死亡診断書を受け取り、死亡届を作成します。死亡届は、火葬許可申請書と共に、亡くなってから7日以内に役所に提出しなければなりません。提出した書類に不備がなければ、火葬許可証が発行されます。
死亡診断書は、死亡届と一体になっているため、提出してしまうと手元に残りません。後々、生命保険や銀行口座の手続きをする際に必要であるため、コピーをとっておくとよいでしょう。
葬儀当日の流れ
葬儀の準備が終わり通夜・葬儀当日を迎えた後の流れについて解説します。決めなければならないことはすでに決めてあるため、予定されたスケジュールに沿って執り行います。全体の流れを一度把握しておくと安心です。
湯灌(ゆかん)
湯灌は故人の体を洗い清め、整える儀式です。葬儀の前にきれいな外観にするとともに、この世における穢れ、悩み、苦しみを洗い流すという意味も持っています。遺族立ち合いのもとに、湯灌師や葬儀社のスタッフが行うのが一般的です。
水を入れたたらいにお湯を足し遺体を清拭する伝統的な「古式湯灌」と、簡易浴槽でシャワーを用いて遺体を洗う「新式湯灌」があります。爪を切ったり、顔を剃ったり、髪型を整えたりして、死装束に着替えさせます。
納棺
遺体を棺に納める「納棺の儀」は、故人が無事に旅立てるようにするための旅立ちの支度とされています。
死装束を着せた故人を棺に納める際に、一緒に副葬品も入れられますが、副葬品にできるものとできないものがあることに注意が必要です。代表的な副葬品としては、故人が好きだった服、花、食べ物、飲み物、故人らしい写真、手紙などが挙げられます。
また、副葬品にしてはいけないものは次の通りです。
| 燃えない素材のもの | メガネ、腕時計、指輪、ガラス製品など |
| 有害物質発生の恐れのあるもの | プラスチック製品、革製品など |
| 燃えにくいもの | 分厚い本やアルバム、水分の多い食品、大きいぬいぐるみなど |
なお、遺体の体内にペースメーカーが埋め込まれている場合は、事前に葬儀社や火葬場への報告が必要です。
通夜
通夜は18時ごろに開始されるケースが多い傾向です。遺族は開始時間の数時間前に斎場に集まり、流れや席次などを確認しておきましょう。
通夜の一般的な流れは、以下の通りです。
1.受付
2.僧侶の入場
3.僧侶による読経
4.参列者による焼香
5.僧侶による法話
6.喪主の挨拶
喪主の挨拶では、翌日の葬儀の案内も伝えましょう。通夜が終了した後には、参列者や手伝ってくれた人たちにお酒や食事を振る舞う、通夜振る舞いと呼ばれる会食の席を設けます。参列者に感謝の気持ちを伝え、故人を偲びましょう。
葬儀・告別式
通夜の翌日の午前中、または午後の早い時間帯に、葬儀・告別式が執り行われます。遺族は開始1時間前には斎場に入って葬儀社のスタッフと流れを確認し、受付の準備をしておきましょう。
1.開式
2.読経
3.弔辞
4.参列者による焼香
5.僧侶による法話
6.喪主の挨拶
なお、弔辞は、故人と親しかった人を選び、事前にお願いしておきます。
<関連記事>
お葬式をする意味とは?「葬式」「葬儀」「告別式」「通夜」それぞれの言葉の違いから見てみよう
出棺・火葬
告別式の閉式後に、出棺の準備をするのが「お別れの儀」です。遺族や参列者が、棺に花を入れ、故人と最後のお別れの挨拶をします。
故人を霊柩車に乗せて火葬場へ向かう際、故人と近しい遺族は霊柩車に同乗し、他の参列者はバスや自家用車に分乗して行くのが一般的です。
火葬場に到着したら、火葬許可証を提出しましょう。火葬炉の前で僧侶による読経、全員の焼香、合掌をした後、棺は火葬炉の中に入り火葬されます。
収骨( 骨上げ)
火葬が終わった後は、箸を使って遺骨を骨壷に入れて、故人をあの世に送る橋渡しをするための「収骨( 骨上げ)」を行います。骨を拾う順番は地方によって異なるため、火葬場の係の人に教えてもらいましょう。
東日本では全ての遺骨を骨壷に収める「全収骨」、西日本では喉仏や歯など一部の遺骨のみを収める「部分収骨」が一般的です。
初七日法要
亡くなった日から7日目に、三途の川の渡り方が決まるとされているため、無事に渡れるように祈る「初七日法要」を執り行います。
最近では、葬儀の日に初七日を行う「繰り上げ法要」を執り行うケースが増えてきました。繰り上げ法要の場合は、火葬後に僧侶に読経してもらい、参列者が焼香をし、喪主の挨拶を行います。
<関連記事>
葬儀が終わって初めての法要「初七日法要」で知っておきたい常識とマナーを紹介
精進落とし・散会
初七日法要後は、僧侶をねぎらい、故人を供養することを目的とした会食「精進落とし」が行われます。
喪主や親族代表者の挨拶で始め、お酒を故人の位牌にお供えしましょう。次に出席者の杯にお酒を注ぎ、喪主や親族代表者が「献杯」の発声をします。
会食中には、喪主や遺族は出席者の席を回り、お礼の言葉を伝えましょう。終了の挨拶を喪主や親族代表者がした後に、引き出物を渡して散会です。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
葬儀後にすべきこと
葬儀を無事に終えると、それまで張り詰めていた気持ちが緩み、急に深い悲しみを感じることがあるかもしれません。そのような中でも、葬儀後にしなければならないことがいくつもあります。ひとつずつ確認しながら、焦らずに進めていきましょう。
葬儀後のお礼
四十九日が過ぎて落ち着いたころに、葬儀後のお礼として、直接挨拶回りに伺ったりお礼状を出したりしましょう。お礼をする相手は以下の4者です。
・菩提寺
・葬儀社
・近所の方(参列者、香典・供物・供花をいただいたりした方)
・会社関係者(参列者、喪主・遺族の勤め先の関係者・故人の会社関係者)
<関連記事>
葬儀後のお礼はどうしたらいいの?知っておきたいお礼のマナーを徹底解説
さまざまな手続き
葬儀後には、さまざまな手続きが必要です。期限が定められているものもあるため、正しい知識を身に付けた上で、漏れのないように進めていきましょう。主な手続きは下記の通りです。
・葬儀費用の支払い
・勤務先への健康保険証の返却(故人が会社員であった場合)
・年金の受給停止(年金を受給していた場合)
・国民健康保険の資格喪失届(国民健康保険に加入していた場合)
・相続手続き(遺産分割・相続税の申告と納税など)
・銀行口座の名義変更
・生命保険の請求
四十九日法要
四十九日法要は、亡くなってから49日目に執り行われる法要であり、故人のあの世での行き先が決まる重要な日であるとされています。極楽浄土に行けることを祈り、遺族、親族、友人を招いて盛大に法要を営み、故人を供養するのが一般的です。
「忌明け法要」とも呼ばれ、亡くなってから喪に服してきた遺族が、この日をもって日常生活に戻る重要な節目でもあります。四十九日法要の一般的な流れは、以下の通りです。
1.開式の挨拶
2.僧侶による読経
3.焼香
4.閉式の挨拶
閉式後には「お斎(おとき)」と呼ばれる会食をします。
納骨式
納骨式は、故人の遺骨を納骨先に収める儀式です。納骨先としては、お墓、納骨堂、樹木葬、散骨、手元供養など、多様な形態があります。納骨式は四十九日法要と同時に執り行うのが一般的です。それまでに納骨先を確保しておきましょう。
新規にお墓を建てる場合など、四十九日法要までに間に合わない場合は、百箇日法要、新盆、一周忌法要などのタイミングで執り行うこともあります。納骨式の一般的な流れは、以下の通りです。
1.開式
2.僧侶よる読経
3.納骨
4.読経
5.焼香
6.会食
<関連記事>
納骨式の基礎知識|服装・香典・お布施・お供え物・挨拶・費用など
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が最大5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
家族が亡くなった際には、悲しみの中でも、さまざまな準備や手続きをしなければなりません。全体の流れを把握しておけば、いざという時にも慌てることなくスムーズに進められるでしょう。
死亡から葬儀までの流れや葬儀全般に関する疑問がある場合は、お気軽に小さなお葬式へお問い合わせください。専門知識を持つスタッフが、お悩みに寄り添い丁寧にアドバイスいたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
よくある質問
死亡から葬儀までの手順は?
死亡してから葬儀までにかけられる日数は?
身内が亡くなった時にしてはいけないことは?

お通夜とは、家族や友人たちが集まり、故人と最後の夜を過ごす儀式のことです。ホゥ。