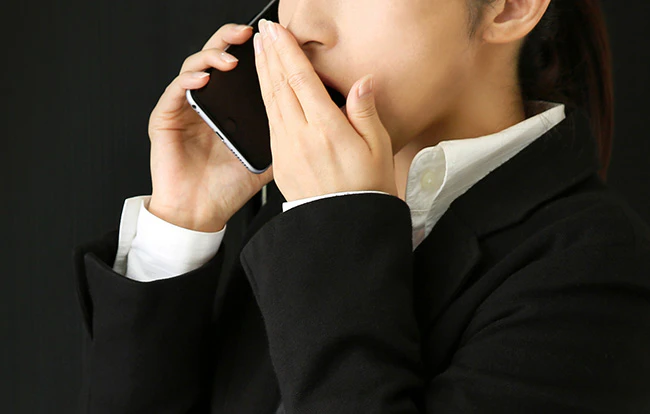治療費や葬儀費用など、万が一に備えてお金を用意しておこうと考えたとき、家族の預金を引き出してもよいのか悩む方もいるでしょう。危篤状態で本人の意思が確認できなくなる可能性もあるので、必要な書類や具体的な手続き方法を把握しておくと安心です。
この記事では、家族が知っておくべき危篤時の預金の引き出し方法について詳しく解説します。銀行口座が凍結されるタイミングや、お金を引き出す際の注意点もまとめました。
<この記事の要点>
・「代理人指名手続き」や「代理人カード」を作成しておくと、危篤時に預金を引き出せる
・預金口座の凍結は、家族の申告後に行われるのが一般的
・預金引き出しの際、領収書を保管し使用金額を記録しておくと相続トラブルを避けられる
こんな人におすすめ
危篤時の預金を引き出す方法を知りたい方
銀行口座が凍結されるタイミングを知りたい方
危篤時にお金を引き出す際の注意点を知りたい方
危篤のときに預金からお金を引き出せる?
家族が危篤になった際、本人の預金口座からお金を引き出せるのでしょうか。治療費や葬儀費用などに充てたい場合は、預金の引き出しが可能かどうかは重要な問題です。
ここからは、家族の危篤時に預金からお金を引き出せるかについて解説します。
本人(口座名義人)の意思があれば引き出せる
口座名義人の意思があれば預金の引き出しは可能です。危篤時だけでなく、体調不良や高齢で銀行に行けない場合も、家族が代理でキャッシュカードを使えます。銀行から本人が窓口に行けない理由を問われた際は、委任状や医師の診断書が必要です。
また、事前に「代理人予約サービス」で代理人指定をしておくと、危篤時でも預金を引き出せます。運用商品の売却や解約など、さまざまな金融サービスの利用も可能です。
参考:代理人予約サービスについて | みずほ銀行
各種手続きを済ませておくと、いざというときでもスムーズに預金を引き出せます。急を要する出費に対応するためにも、準備をしておきましょう。
<関連記事>
故人の銀行口座の死亡手続きに必要なことは?必要書類や預金相続の手順を紹介
勝手に引き出すとトラブルになる可能性もある
本人の意思が確認できない状況で勝手に預金を引き出すのは、後々遺産相続のトラブルに発展する可能性があります。キャッシュカードと暗証番号さえあれば誰でもお金を引き出せるため、用途が治療費だったとしても使い込みを疑われるかもしれません。
本人が亡くなったあと、預金口座に残っているお金は全額相続の対象となります。家族や親族との関係悪化を避けるためにも、勝手にお金を引き出すことは避けましょう。
銀行口座が凍結される理由
名義人が亡くなった場合、口座は相続手続きが完了するまで凍結されます。凍結されると預金の引き出しや振り込みなどの取引が一切できなくなるほか、凍結解除にも所定の手続きが必要です。
ここからは、銀行口座が凍結される理由を解説します。
相続問題に発展するのを防ぐ
預金口座が凍結される主な理由は、相続問題に発展するのを防ぐためです。本人が亡くなった時点で預金口座に残っているお金はすべて相続対象となり、金額が変わらないように金融機関は口座を凍結します。
口座が凍結されると引き落としができなくなるといったデメリットはありますが、親族間の相続トラブルを避けることができます。相続人の間で遺産分割が必ずしもスムーズに進むとは限りません。その際、口座が凍結されていないと、さらなるトラブルを招く可能性があります。遺産相続が完了するまで口座を凍結しておけば、手続きを円滑に進められるでしょう。
<関連記事>
遺産争いに発展する原因と有効的な対策方法は?未然に防ぐ手段はある?
亡くなってすぐに凍結されるわけではない
預金口座は本人が亡くなった時点で自動的に凍結されるわけではなく、家族からの申告によって凍結されるのが一般的です。しかし、新聞のお悔やみ欄や葬儀看板の情報をもとに、金融機関から家族に連絡が来るケースもあります。
凍結した口座からお金を引き出すには、相続を完了させるか「相続預金の払戻し制度」を利用しましょう。戸籍謄本など必要書類を提出することで、預金口座から最大150万円まで引き出せます。大きな出費に備えるためにも、あらかじめどのような制度があるのか確認しておくとよいでしょう。
参考:ゆうちょ銀行の相続手続き-ゆうちょ銀行
【相続】民法909条の2に基づく遺産分割前の相続預金の払戻し制度とはどんな制度ですか? | よくあるご質問 : 三井住友銀行
<関連記事>
親が死亡したら銀行口座が凍結されるって本当?
危篤時に預金を引き出す方法
名義人の預金口座からお金を引き出す方法は、本人の意思を確認できるか否かによって異なります。注意点や準備しておくものを確認して、いざというときにスムーズに対応できるようにしておきましょう。
ここからは、危篤時に預金を引き出す方法について解説していきます。
本人の意思を確認できる場合
本人の意思を確認できる場合は、ATMでの引き出しが可能です。シンプルかつ迅速に利用できる点がメリットですが、引き出せる金額に上限があることや、本人の同意を証明するのが難しいといったデメリットがあります。
銀行窓口でお金を引き出す場合に必要な持ちものは以下のとおりです。
・通帳・証書
・印鑑(届出印)
・委任状
・名義人の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
事前に代理人手続きを済ませている場合は、診断書の提出だけで引き出せます。銀行によって必要な書類が異なるので、事前に確認しておきましょう。
本人の意思を確認できない場合
意識の低下や危篤状態で本人の意思を確認できない場合は、まず利用している金融機関に相談してみましょう。その際に持参するものは以下のとおりです。
・医師による診断書
・住民票の写しや戸籍謄本
・目的となる請求書や振込用紙
医師による診断書がないと金融機関は名義人の状態を確認できないため、お金の引き出しを断られる可能性があります。また、預金の引き出しは治療費や葬儀費用など、本人のために必要な資金に限定される点に注意が必要です。支払う際も、本人の預金口座から直接支払先に振り込まれる点に留意しておきましょう。
参考:預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料|一般社団法人 全国銀行協会
<関連記事>
死亡手続き後に知っておきたい戸籍謄本が必要なケースと取り寄せ方
預金を引き出すときの注意点
家族の預金を引き出す場合は、用途を明確にしないと相続トラブルに発展する可能性があります。トラブルを未然に防ぐために、気をつけるべき点を把握しておきましょう。
ここからは、預金を引き出すときの注意点を紹介します。
用途を明確にしておく
本人の預金からお金を引き出す際は、使い道を明確にしておくことが重要です。医療費や葬儀費用などまとまった金額を使用する場合、税務署の相続税調査で問題視される可能性があります。
用途が口座名義人のためであれば問題ありませんが、それを証明するために領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。金額の大小にかかわらず、使用後には日付と金額を記録しておくと安心です。
たとえば、医療費ならどの病院にいくら支払ったのか、葬儀費用ならどの葬儀社にいくら支払ったのかを具体的に記録しておきましょう。詳細に記載しておけば、税務署や親族からの質問にも適切に対応できます。
家族や親族間で情報を共有しておく
預金口座からお金を引き出す際は、必ず家族や親族と情報を共有しておきましょう。いくら引き出して何に使うのかをしっかり伝えておくことで、お金の使用記録の信頼性も高まります。
特に、大きな金額を動かす場合は、家族や親族の理解と合意が重要です。家族関係の悪化や相続問題に発展しないように、情報共有を徹底しましょう。
万が一に備えて事前にできること
亡くなった場合に備えて、お金の準備をしておくことは非常に大切です。残された家族だけでなく、名義人本人が意識すべき課題でもあるでしょう。
ここからは、万が一に備えて事前にできることを解説します。
代理人指名手続きまたは代理人カードを作成しておく
本人に代わってお金をスムーズに引き出せるように、「代理人指名手続き」や「代理人カード」を事前に作成しておくとよいでしょう。本人と代理人が銀行窓口で手続きを済ませておけば、いざというときにお金を引き出せます。
代理人指名手続きとは、口座名義人が事前に代理人を指定し、本人が銀行やATMに行けない場合に代理人が代わりに手続きできるようにするものです。これにより、委任状がなくてもお金を引き出せるようになります。
参考:代理人指名手続 : 三井住友銀行
一方で代理人カードとは、指定された代理人が一定の金融取引をおこなえるカードのことです。カードをもつ代理人は、名義人の代わりに預金の引き出しや振り込みなどの取引ができます。ただし、名義人本人の意思がある場合にのみ使用できる点に注意が必要です。
参考:代理人カードは発行できますか?|その他手続きのよくあるご質問|りそな銀行
家族信託を組成しておく
あらかじめ家族信託を組成しておくのも有効な手段です。家族信託とは、家族に財産の管理権を託す制度で、入院中でも家族の財産を動かせるようになります。
家族信託では家族が管理する信託口座からお金を引き出すため、本人の口座からお金を引き出すわけではありません。引き出す際、委任状は不要です。本人の意思確認ができない場合でも機能が停止しない点がメリットです。
ただし、家族信託の契約には平均で1ヶ月~2ヶ月程度要します。将来を見据えて早めに組成しておくのがおすすめです。
参考:家族信託 | 阿波銀行
<関連記事>
家族信託とは一体?わかりやすく特徴や仕組みを解説します!
家族信託の特徴とは?メリットや注意点を徹底解説します!
葬儀費用に故人の預金を充てたいとき
名義人が亡くなった場合、預金口座のお金を葬儀費用に充てたいと考える方もいるでしょう。葬儀にはまとまったお金が必要になるため、急遽準備するのが困難なケースも珍しくありません。
ここからは、葬儀費用に故人の預金を充てたいときのポイントについて解説します。
葬儀費用の内訳と相場
葬儀費用は規模や内容によって大きく変わりますが、平均で約127万円※かかるといわれています。葬儀規模別の平均費用は以下のとおりです。
| 葬儀形式 | 平均葬儀費用 |
| 一般葬 | 約191万円 |
| 家族葬 | 約110万円 |
| 一日葬 | 約45万円 |
| 火葬のみ | 約36万円 |
(※対象期間:2021年2月〜2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)
一般葬とは、通夜・告別式・火葬を行うもっとも一般的な葬儀形式です。一方で、家族葬とは故人の近親者のみでおこなう小規模な葬儀です。一日葬はお通夜を省略し、告別式と火葬を一日でおこなう形式をさします。火葬のみの葬儀は、「直葬」や「火葬式」とも呼ばれ、お通夜も告別式もおこなわず、すぐに火葬をする葬儀形式です。
葬儀費用は、葬儀の規模や参列者の人数、オプションサービスによって幅があります。まとまったお金が必要になるため、故人の預金から工面することも検討しておくとよいでしょう。
<関連記事>
葬儀費用の平均は127万円!形式ごとの費用平均や安く抑える方法を解説
早めに準備しておくことが大事
葬儀費用を故人の預金で賄うには、早めの準備が肝心です。危篤になっても預金を引き出せるようにしておけば、家族の経済的・精神的な負担を軽減できます。
また、葬儀社に事前相談をしたり、見積もりを取ったりして、葬儀に必要な金額を把握しておくことも大切です。どのような葬儀にしたいのか、どの葬儀社に依頼するのかも決めておけば、いざというときにスムーズに対応できるでしょう。
急ぎの場合は、生命保険の受け取り手続きをするのもひとつの手段です。対応方法を確認して、万が一のときに備えましょう。
まとめ
口座名義人が危篤になったとき、家族が預金を引き出すには金融機関で事前手続きをしておく必要があります。「代理人指名手続き」や「代理人カード」などさまざまな制度を利用して、いざというときでも迅速にお金が用意できるようにしておきましょう。
預金口座からお金を引き出したときは、用途や金額を詳細に記載し、家族や親族間で情報を共有することが大切です。遺産相続のトラブルに発展しないように、独断でお金を引き出すことは避けましょう。
「小さなお葬式」では、危篤時の預金引き出しや葬儀に関するお問い合わせを受け付けています。お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は0120-215-618へお電話ください。

家族葬とは、家族や親族を中心に、小規模に行う葬儀形式のことです。ホゥ。