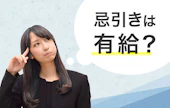家族が急に亡くなり、仕事を休むことを余儀なくされるケースがあります。不幸があったタイミングが週末だと、忌引きで休むのが土日や祝日など休日に重なることもあるでしょう。
そこでこの記事では、職場の公休である土日や祝日、長期の休日と忌引きが重なった場合はどのように処理されることが多いのかについてご紹介します。
<この記事の要点>
・弔事に伴う休みに公休は合算しないとする企業が多い
・忌引き休暇制度は雇用主が詳細なルールを決められる
・忌引き休暇の日数は故人との関係性によって異なる
こんな人におすすめ
忌引き休暇とは何かを知りたい方
土日は忌引きの日数に含まれるのかを知りたい方
忌引き休暇の日数の目安が知りたい方
土日は忌引きの日数に含まれるのか
勤め先に認定された忌引きが本来公休である土日に重なってしまうことは十分ありえます。たとえば土曜の朝に不幸があって弔事に伴う休みが3日取れるなら、土日を含んで月曜まで休みになるのでしょうか。あるいは土曜・日曜を含まず水曜までの計5日休みになるのでしょうか。これは勤め先により考え方が違います。
身内の不幸に伴う休暇は、基本的に雇用主側が独自に定めた規則に従って与えられています。労働基準法などに詳細なルールが書かれているわけではありません。このため制度のルールは勤め先によって異なっています。
また基本的には弔事に伴う休みに公休は合算しないとする職場が大半のようです。つまり、土曜から忌引きが3日付与され、月曜が祝日で3連休だったときは基本的に合計6日の休みを取れます。ただしこれはどの勤め先も同じというわけではないので、ご自身の勤め先がどのようなルールになっているのかを就業規則などで確かめてみて下さい。
長期休暇は忌引きの日数に含まれるのか
夏季や年末年始に長めの休みを取れる勤め先もあります。人員配置の問題で本来定められた時季に取得できなくても、タイミングをズラして夏季や年末年始休みの代替とできる勤務先も見られます。時には、これが忌引きと重なることもありえます。
弔事に伴う休みと重なった長期の休みを延長したり、別の日に振り替えて休んだりできるかどうかは勤め先によって違います。忌引きの制度設計は雇用主が独自におこなっているので、この辺りの細かいルールも勤め先によって異なるのです。
忌引きと被った長期休みに関する規定が明確にはないということも考えられます。この場合は休みを延長できないか、別日に振り替えて長期休暇を取りなおせないか上司や担当者に問い合わせてみて下さい。
そもそも忌引き休暇とは?
忌引き休暇とは職場が独自に定めている、身内の弔事に伴う休みが取れる制度です。労働基準法などに書かれているわけではなく、当該制度を利用できるかどうかは勤め先によりかわります。父母の逝去に伴う弔事の場合には5日、祖父母の場合は3日など、職場の決まりにより一定の期間休むことができます。
どのくらい休みを取れるかは雇用主側の決定により異なりますが、故人との関係が何親等なのかで定められていることが大半です。勤め先の福利厚生ついての説明を就業規則などで確かめて下さい。
忌引きを使って仕事を休んだ場合、給料をもらえるのか無給なのかも勤務先ごとに違います。いざというときのために、どのような扱いになっているか詳細を把握しておくべきです。
企業での忌引き休暇の扱われ方のパターン
職場での忌引きの扱われ方には違いがあります。忌引きは雇用主が詳細なルールなどの内容も自由に決めているからです。
身内の弔事に伴う休みを出勤日としてカウントした上で給料が支払われる、正当な休みとして取れても欠勤扱いになるなど、職場ごとにいくつかのパターンに分かれます。以下では、忌引きの事務上の処理方法についていくつかご紹介します。
出勤日数に含まれるうえに給料も支給される
忌引きでの休みが出勤としてカウントされる上に給料も支払われるのが最も多いです。雇われる側としては、心置きなく葬儀や気持ちの整理に時間を使えるので好ましいルールと言えます。
ただし、正社員や契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなど雇用形態によって異なることも多いようです。勤め先ではどのような決まりになっているのか、自身も対象となるのかを確認してください。
就業規則をみれば書いてあるとは思いますが、読むのが大変だという場合には先輩などに聞いてみても良いでしょう。ただいざというときにその情報が間違っていることも考えられますので、弔事のために休暇を申請する際には正確な情報がどうなっているのかをチェックしておいて下さい。
出勤日数に含まれるが給料は支給されない
忌引きは出勤としてカウントされるが給料は発生しないという職場もあります。就業規則に「忌引き休暇を無給とする」などと書いているパターンです。忌引きを取っても給料がもらえる会社は多いので、自分の勤め先もそうであろうと思っていたら、給料が支払われなかったというケースもあるので注意して下さい。
給料が支払われないなら申請する意味がないと思う方もいるかもしれません。たとえ無給でも欠勤扱いにならないのは、人事査定や年次有給休暇の付与などにおいては重要な意味をもっているのです。
忌引きは法律ではなく、職場ごとに定められる福利厚生の一つと言えます。家族や社外の友人に聞いても正しい判断はできませんので、上司や社内の担当部署で聞いて確認して下さい。
忌引き休暇の制度が設けられていない
忌引きがルールとして存在しない職場もあります。労働基準法などで決められているものではないので、制度がない職場もあるのです。忌引きがないと、身内の不幸があったからと休んでもいいのかどうかがわからないという悩みも出てきます。
無給で欠勤することを避けたいのであれば年次有給休暇を取得したい旨を伝えてください。年次有給休暇は法律で規定された制度なので、条件を満たせば誰でも取得する権利があります。与えられた有給休暇を使い切っておらず、よほどの繁忙期でもない限り休みを取れるはずです。
急な有給休暇の取得は認められない勤め先もありますが、有給休暇は労働者の権利です。上司や担当部署の方と交渉してみてください。
忌引き休暇の日数の目安
何日程度休めるのかというのは、故人との関係で違ってきます。亡くなった方がご自身から見て何親等の方にあたるのかで該当する休暇の日数が決まるのです。
夫や妻、両親、子どもなど1親等だと5日~10日間ほど休める企業が大半になります。2親等にあたるのは祖父母や兄弟姉妹、孫などで、この場合は3日間ということが多いです。おじ・おば、甥・姪、いとこなど3親等になると何とか葬儀に出れる1日の休暇か休みを取れないケースもあります。
直系か傍系かによって変わることもあるので注意して下さい。職場によっては休みを取る際には上司に了解をとったり、申請書を提出したりと手続きが必要なこともあります。上司や総務・人事部などの関係部署に、申請にあたって必要な書類と併せて正確な日数を確認して下さい。
土日に不幸があった場合にも会社への連絡は必要?
土日に不幸があり、勤め先を休むことなく済んでしまうこともあるでしょう。特に自分が葬儀の準備などに関わらない場合はお通夜や葬儀に参列して、次の日からは通常通りに業務がおこなえるということもあり得ます。
このとき職場に連絡するかどうかは、ご自身の判断によります。職場によっては忌引きが土日を含まずに取得できるので、これを利用したい際には知らせなければなりません。
上司が葬儀に参列したり、弔電や供花を送ったりするケースもあります。弔慰金がもらえる職場もあるので、確実に必要がないと判断できなければ、せめて上司には一報を入れるのがマナーと言えます。
また、上司や同僚によっては後から知らされることを不快に感じる方もいるかもしれません。これはお互いの関係性や相手の性格によっても異なります。どうすればいいのか迷った際には、同じような立場になったことがある人に確認するのが賢明な判断と言えます。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
土日や長期休暇中の忌引きの処理の仕方や給料が支払われるかどうかといった細かいルールは職場によって違います。自分の勤め先ではどのようなルールになっているかは就業規則に明記されていることが大半です。いざというときに慌てずに済むように確かめて下さい。
いずれにしても、急な休みを取ることで上司や同僚に負担があることを忘れずに、休暇後にはしっかりとあいさつなどをすることを忘れないようにしましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



年金制度には大きく分けて公的年金制度と私的年金制度の2種類があります。ホゥ。