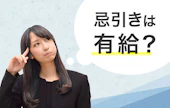社会に出て働くようになると「慶弔金」や「忌引き休暇」といった言葉を耳にする機会があるかもしれませんが、正確な意味がわからないという方も少なくないのではないでしょうか。
どちらも慶弔事に関連する事柄で、急を要する状況で触れることが多い言葉のため後々意味を知ることも少なくないでしょう。慶弔金とはどのようなときに誰に対して払うのか、忌引き休暇と有給休暇の違いは何かなど知っておきたいことはたくさんあります。
<この記事の要点>
・慶弔金は、従業員やその家族に慶弔事が発生した際に会社から支給される手当のこと
・忌引き休暇の取得が認められるかどうかは会社が定めた就業規則による
・忌引き休暇が有給になるかどうかも会社の就業規則次第となる
こんな人におすすめ
忌引き時の慶弔金について知りたい方
忌引き休暇と有給休暇の違いを知りたい方
忌引き休暇について知りたい方
忌引き時に生じる慶弔金とは
慶弔とは結婚や出産といった御祝いごとや葬儀などのおくやみごとを意味します。慶弔金はどのような状況のときにもらうものなのか、また金額相場やマナーなどは決まっているかどうかを見ていきましょう。不測の事態が起きたときに困らないようにしっかりと内容をチェックしてください。
慶弔金とは
慶弔金とは、従業員やその家族に慶弔に関わるできごとが起こった際に、勤めている会社がその社員に渡す手当てのことをいいます。あくまで会社から個人に対して渡すものですので、個人から送る香典や見舞金は慶弔金には該当しません。
慶弔金には法的な強制力がないので会社に支払いの義務もありません。ただ、社員の意欲向上や慰意のために支払いを行うケースが多いようです。
慶弔金には種類があります。ひとつ目は、結婚祝い金・出産祝い金などといったお祝いごとに対して支給される「祝賀金」です。ふたつ目は、弔慰金・傷病見舞金・災害見舞金といった不幸なできごとやおくやみごとがあったときに支給される「弔慰金」に分けられます。
慶弔金に関する規定は会社によってさまざまです。一律で定められている会社もあれば、企業のトップが一存で決める会社や特に規定を設けていない会社もあります。
慶弔金の相場
慶弔金としてもらう金額は会社によってさまざまですが、全体としての傾向は見て取ることができます。弔慰金を抜き出して見てみると、会社に勤めている本人が亡くなったときにもらう本人弔慰金と、家族が亡くなったときにもらう家族弔慰金とでは、本人弔慰金のほうが高額であるのが通例です。
社員本人が亡くなった場合でも業務内外の違いや勤続年数で金額が異なるときがあります。
家族弔意金の場合は、会社に勤めている本人が喪主かどうかという基準により増減しますが、1万円~5万円程度のケースが多くなっています。また、弔慰金は給与ではなくとも高額な場合は課税対象ですので、非課税の範囲で渡すのが慣例となっています。
忌引き休暇と有給休暇の違い
忌引き休暇と有給休暇の大きな違いは、休暇の区分が「特別休暇」か「法定休暇」か、ということです。
有給休暇や週一日の休暇は労働基準法で規定されている「法定休暇」です。会社は期間中の社員の労働義務を免除する義務があります。一方で、忌引き休暇は「特別休暇」に含まれます。
特別休暇は法律で義務づけられていないため、会社は必ずしも設定する必要がありません。忌引き休暇の取得が認められるかどうかは会社が定めた規定次第となります。
所属する会社が忌引き休暇を設けていない場合、仕事がある日に葬儀に出席するためには別の休暇を利用する必要があります。忌引き休暇が設けられている場合でも、利用できる日数や条件は各会社によって異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。
忌引き休暇は有給なのか?無給なのか?
忌引き休暇が有給か無給かについても会社は独自に制定することができるため、各会社の就業規則次第となります。規模がそれほど大きくない会社では忌引き休暇は無給とされていることが少なくないようですが、これでは忌引き休暇を申請すると給与が減ってしまうことになります。
そのため、忌引き休暇ではなく有給休暇として申請する方法もあることを覚えておくとよいでしょう。
忌引き休暇の制度がなければ、有給休暇を利用できない状況で身内に不幸があった場合は欠勤をしなければならなくなります。しかし、欠勤は給与考査や賞与などに影響を与えることもあるため、たとえ無給であったとしても忌引き休暇を利用できること自体に意味があるといえるでしょう。
忌引き休暇とはそもそもなに?
忌引き休暇の制度について紹介してきましたが、そもそも忌引き休暇とはなんなのでしょうか。どんなときのために忌引き休暇があるのか、利用できる日数の目安はどれくらいなのか、利用できるのは誰なのかなど、忌引き休暇についてさらに詳しく解説します。
忌引き休暇の意味
忌引き休暇は、該当者の家族や親族といった近親者が亡くなった場合に、葬儀の準備と参列のために勤務や登校を一時的に休止することを指します。
本来、忌引きとは近親者の死を悼んで喪に服すという意味でしたが、昨今では「仕事や学校を休んでも欠勤・欠席にカウントされない期間」といった意味合いで使われることが多くなっています。休める日数は本人と故人との関係性で決まり、関係性が近しいほど日数は増えます。
忌引き休暇の日数の目安
忌引き休暇の日数の目安としては、配偶者が亡くなった場合は10日ほど、父母の場合が7日、子の場合は5日であることが多くなっています。ほかには、祖父母、兄弟姉妹は3日、叔父、伯父、叔母、伯母が1日、孫は1日といった日数があります。
配偶者側の親族が亡くなった場合も適用されることが多く、亡くなったのが配偶者の父母の場合は3日、配偶者の祖父母は1日、配偶者の兄弟姉妹も1日であるケースが散見されます。
忌引き休暇は各社ごとに内容が異なり,休める日数は一様ではないので、正確な日数は各自で確認するようにしてください。
忌引き休暇は正社員以外でも取得できるのか?
結論から言うと、忌引き休暇が適用される雇用形態の範囲は就業規則次第です。正社員とパートタイマーでは就業規則が異なる会社もあり、正社員のみが忌引き休暇を認められて契約社員やパート・アルバイトは適用外というケースもあります。
特にパートやアルバイトの場合は忌引き休暇がない場合が少なくないようです。この場合は有給休暇を利用するか欠勤するかを選ばなければいけません。
自分が忌引き休暇を利用可能な環境であるかは就業規則で確認してください。もし忌引き休暇申請を却下された場合も、就業規則に認める旨が明記されていればしっかりと主張しましょう。
忌引き明けに行うべきこと
忌引き休暇を取るときは急を要する状況が多く、なかなか周囲への心遣いまでは気が回らないこともあるかもしれません。その分、スムーズに職場に復帰するには忌引き休暇明けの対応が重要です。社会人として覚えておきたい忌引き明けに行うべきことを解説していきますので、ぜひご確認ください。
忌引き休暇に関する書類を会社へ提出
会社によっては、忌引き休暇の不正利用を防ぐために書類の提出が必要な場合があります。死亡診断書や会葬礼状・葬儀のタイムスケジュール表などの提出が必要となるので、事前に用意しておきましょう。
もしこれらの書類が手元にない場合は、葬儀を担当していた葬儀会社に連絡するとよいでしょう。要請すれば会社に提出するための証明書を用意してもらえます。念のため多めにコピーを取っておくのもひとつの手段です。
上司や同僚へのお礼と挨拶
忌引き休暇が認められていても、実際に利用するには周囲の人の協力が必要になります。人間関係を良好に保つためにも上司や同僚へのお礼はしっかりとしておいたほうが無難です。
「おかげさまで葬儀がつつがなく終了いたしました。お忙しい中ご協力いただきありがとうございました。本日より仕事に復帰いたします。」と丁寧に伝えましょう。身内に不幸があったことを周知する意味でも忌引き明けの挨拶は重要です。
香典返し
上司や同僚から香典をいただいた場合は、しっかりとお礼を伝えたうえで一緒に香典返しを渡します。個人名義で香典をいただいた場合は、包まれていた額の半額の品物を贈る「半返し」が基本となります。
香典返しの額は15,000円を上限とするのが一般的ですので、3万円以上の香典をいただいた場合でも15,000円の香典返しをすればマナー違反とはなりません。
連名や部署名で香典をもらった場合は、1人あたりの負担額は1,000円~2,000円程度である割合が高いです。この額で半返しをすると1,000円以下の品になってしまい、あまり体裁がよくありません。こういった場合は小分けできる菓子折りなどを香典返しとしてお礼の挨拶周りのときに一緒に配るとよいでしょう。
ただし、香典を持ってきたのが上司や同僚であっても香典の名義が「社名+社長」だった場合は、香典は経費から出ているため香典返しは不要です。
参考:
香典返しの金額相場は?送る品物は?葬儀での香典返しのマナー
忌引き休暇明けの挨拶にお菓子を用意する?挨拶のマナーも合わせて解説
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
この記事では、忌引きに関する知識として弔慰金の意味と金額相場や、忌引き休暇と有給休暇の違いなどについて解説してきました。
忌引きに関連する規則は会社ごとに規定されているもので一様の決まりはありません。このことを把握したうえで事前に就業規則を下調べしておかなければ、急な事態での対応は難しくなるかもしれません。いざというときに戸惑わずに済むように、ぜひこの記事を参考に自身の環境を確認してください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



亡くなった方や仏に向けて、香を焚いて拝む行為を焼香(しょうこう)といいます。ホゥ。