銀行口座をもっている人が亡くなった後、銀行が勝手に死亡手続きをしてくれるのではないかと考えている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、故人の銀行口座について必要な手続きについてご紹介します。この記事を読むことで、故人の銀行口座に対して行う手続きの方法がわかります。また、あわせて、預金相続をするための必要書類や手順についても解説をしていますので、ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・故人名義の銀行口座は、死亡したことを銀行へ伝えてから初めて凍結される
・預金口座の相続は遺言書の有無によって手続きや必要書類が異なる
・凍結された銀行口座から遺産を相続する場合、手続き方法は金融機関によって異なる
こんな人におすすめ
銀行口座の相続手続きの流れを知りたい方
凍結された口座から預金を引き出す方法を知りたい方
相続した銀行口座に関する注意点を知りたい方
銀行口座に関する死亡手続き
故人が銀行口座をもっている場合、名義人の死亡手続きをしなければなりません。死亡手続きをしなければ、故人の銀行口座に入金されている預貯金を遺産として継承することはできないのです。
名義人の死亡手続きにあわせて遺産を相続するにはどうすればいいのか、さらに2019年7月に改正した民法の「相続税法による凍結した口座の扱い」についても紹介していきます。
名義人の死亡と口座凍結
口座名義人の死亡を銀行が確認すると口座は凍結されます。そのため、相続人だとしても遺産として口座から預金を引き出すことができません。では、各銀行はどのようにして名義人が亡くなったことを知るのでしょうか。
よくある誤解として、死亡届を受理した役所から銀行へ情報が提供されるというものがあります。役所は「亡くなった」という情報を銀行へ提供することはありません。一般的には、遺族が銀行に「亡くなった」と連絡を入れることにより、銀行は口座名義人の死亡を知るのです。
口座預金は、名義人が亡くなると相続財産となります。そのため、銀行は相続人が決まるまで、口座を凍結します。複数の相続人がいる場合、勝手に相続財産である預金を引き出すと遺産争いの原因になります。銀行は、そのトラブルを回避するために口座を凍結させます。
民法改正による凍結口座の扱い
民法改正により、相続人はほかの相続人の許可を得なくても故人の口座から預貯金を引き出すことが可能となりました。引き出し可能金額は「故人の預貯金×3分の1×その相続人の法定相続分」で求めることができます。
たとえば、相続人が3人兄弟としましょう。そして、銀行口座に1,000万円がある場合の計算式は「1,000万円×3分の1×3分の1」となり「111万円」まで引き出すことが可能です。
ただし、ひとつの銀行につき引き出し上限は150万円になります。上限額を超える額を引き出す場合、家庭裁判所へ申請をすることで引き出しの許可を簡単に得ることができます。
引き出しをする際には「亡くなった方の戸籍謄本」「亡くなった方の除籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」「引き出しをする相続人の印鑑証明書」の4点が必要になります。
ほかの相続人の許可はいりませんが、遺産争いを防ぐために事前に相談をしておくといいでしょう。さらに「どのような目的で引き出したのか」「お金の使用用途は何か」をメモに残しておくとトラブルを回避することができます。
故人の預金口座を遺族(相続人)が相続するためには
凍結された口座から預金、つまり遺産を遺族が相続するためには必要書類を集めて銀行へ提出しなければなりません。
必要書類については後述しますが、亡くなった方のすべての戸籍謄本が要求されます。出生地と現住所が違う場合は、生まれた戸籍謄本が保管されている市役所に連絡を入れて戸籍謄本を送ってもらう必要があります。
なぜ出生から死亡するまでに作成されたすべての戸籍謄本が必要かといえば、相続人の人数を確定させるためです。遺言書があれば相続人が決まっていることがありますが、遺言書がないと法定相続人の範囲で相続人を確定しなければなりません。戸籍謄本には故人とつながりのある方々が記載されていますので、隠し子や養子の有無を確認します。
口座の相続手続きに関する必要書類を銀行に提出してから初めて払戻しの手続きがなされ、代表者の口座へ入金されます。相続手続きに関する必要書類は銀行によって異なりますので、事前に銀行へ確認をとるとよいでしょう。
<関連記事>
死亡手続き後に知っておきたい戸籍謄本が必要なケースと取り寄せ方
銀行口座の相続手続きに必要な書類(遺言書があるケース)
遺言書が自筆(自筆認証遺言書)の場合には「遺言検認調書」または「検認済証明書」が必要になります。検認は家庭裁判所へ遺言書を提出することで得られるものです。公正証書遺言の場合は、遺言検認調書と検認済証明書は必要ありません。
そして、死亡したことを確認できる「亡くなった方の戸籍謄本」「遺産を相続する人の印鑑証明書」が必要です。家庭裁判所にて「遺言執行者」が選任されているときは「遺言執行者の選任審判書謄本」も提出します。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
銀行口座の相続手続きに必要な書類(遺言書がないケースA)
遺言書がない場合「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。遺言書がないケースAは「遺産分割協議書がある」ケースとします。
銀行に提出する遺産分割協議書には、法定相続人となる全員の署名押印が必要です。また「亡くなった方の除籍謄本」と「亡くなった方の戸籍謄本」を用意します。
戸籍謄本と印鑑証明書は、相続する全員分が必要です。全員分の戸籍謄本に関しては、亡くなられた方の戸籍謄本で確認できる場合は不要になることがあります。事前に銀行に確認しておくとよいでしょう。
銀行口座の相続手続きに必要な書類(遺言書がないケースB)
最後に「遺言書」と「遺産分割協議書」がともにないケースを遺言書がないケースBとします。遺言書と遺産分割協議書がない場合に必要な書類は、次のとおりです。まず「亡くなった方の除籍謄本」と「亡くなった方の戸籍謄本」は必須です。
そして、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書も用意します。相続する全員の戸籍謄本に関しては、亡くなられた方の戸籍謄本で確認できる場合は不要です。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
銀行口座の相続手続きのステップ
ここからは、凍結された銀行口座から遺産を相続するための手続きのステップを解説していきます。まず、銀行への連絡を行います。次に、必要書類の準備です。そして、書類を銀行へ提出します。最後に預金口座の相続手続きが完了となります。
手続き自体は簡単ですが、必要書類の準備にもっとも時間がかかるでしょう。それぞれのステップについて解説していきます。
金融機関への連絡
まず、人が亡くなったら故人名義の口座を凍結させ、故人の預金を守るために銀行へ連絡します。銀行へ連絡をしなければ、遺産相続の手続きを行うことがでません。
また口座が凍結されないと、口座番号とパスワードを知っていれば勝手に相続人がお金を引き出すことができます。遺産争いの原因になるため、亡くなったら早い段階で銀行へ連絡をいれて故人名義の口座の凍結を行いましょう。
必要書類の準備
銀行によって必要書類は異なります。自筆の遺言書がある場合は、家庭裁判所へ提出して検認をもらいましょう。遺言書がない場合は、遺産分割協議書の作成をおすすめします。
また亡くなったことを証明しなければならないので、故人の除籍謄本と生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を用意しましょう。出生地と現住所が違う場合は、生まれた地域の役所から戸籍謄本を取り寄せる必要があります。相続人全員の戸籍謄本とすべての相続人の印鑑証明書もあわせて用意をしましょう。
書類を金融機関に提出
集めた必要書類を銀行へ提出します。その際、書類に不備があると受理してもらえない可能性がありますので書類に不備がないようにしましょう。銀行によって書類原本を必要とするケースと書類のコピーでも大丈夫というケースがあります。
銀行によって書類の取り扱い方法は異なりますので、亡くなったという連絡を銀行へ入れる際に確認しておくとよいでしょう。また、遺産分割協議書作成から払戻完了までの手続きにかかる期間はスムーズに進んでも2か月程度はかかります。
手続き方法は金融機関の指示に従う
金融機関によって、手続き方法は異なります。たとえば、ゆうちょ銀行の場合「相続確認表」という書類を提出しなければなりません。相続確認表とは、相続手続きをする前提として相続人全体の相続関係の全体を説明する書類です。また、三井住友銀行なら「相続に関わる依頼書」の作成が必要になります。
このように手続き方法は金融機関によって異なりますので、必ず金融機関に連絡を入れて指示に従いましょう。
故人から相続した銀行口座に関する注意点
ここからは、故人から相続した銀行口座に関する注意点について解説します。特に注意しなければならないのが、相続人の間で起きる金銭トラブルです。次に公共料金の自動引き落としにも注意が必要になります。
口座が凍結されると預金があっても使用はできなくなります。そのため、故人の口座から公共料金の支払いをしている場合は料金未納でサービスが受けられなくなるケースもあるのです。故人と同居していた場合は、公共料金の名義を変更することで引き続きサービスを受けることができますので、早めに手続きしておきましょう。
ほかの相続人との間にトラブルが起こらないようにする
遺産争いでのトラブルは、大きくこじれる可能性があります。遺産争いの結果、親戚関係を切ってしまうというケースもあるほどです。
相続人との間でトラブルが起きないように対策して、回避しましょう。「遺産があまりないので遺産分割協議書は作成しない」という選択ではなく、相続人が集まり遺産分割協議書を作成したり、相続人同士でしっかり話し合ったりすることで後々のトラブルは回避できます。
故人の名義で利用していたサービスは名義変更を忘れない
故人名義の銀行口座から公共料金の支払いをしていた場合、公共料金の支払い口座を変更しなければなりません。名義変更は簡単に行えますので、必ず名義変更を行うようにしましょう。手続きしないと、料金未納でサービスが受けられなくなる可能性があります。別居だとしても遅延金がかさんでいきますので、忘れずに手続きしましょう。
借金やローンなどの支払いも相続人に移行しますので、支払い関係はしっかり把握しておく必要があります。故人名義の通帳を見直して、どのような項目でお金が引き落とされているのか確認し、ひとつひとつ名義変更や解約をしておくことをおすすめします。
相続税が発生した場合は必ず納付する
相続が発生した場合、必ず相続税が発生するわけではありません。国税庁の調査によりますと、日本全国の約8%にしか関係のない話になります。
なぜ、相続税が日本全国の約8%にしか関係がないかといえば、基礎控除によって相続税が非課税になる方が多いからです。基礎控除額を求める計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」になります。
基礎控除額を超えた場合、相続税が発生しますが相続税は必ず納付しなければなりません。相続税を隠した場合、本来の税額に40%が加算された額のペナルティが科されます。また悪質な場合は罰金刑が科される可能性もあるので、相続税は必ず納めた方がいいでしょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
銀行は口座名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して預金を保護します。ただし民法の相続税法が改正されたことにより、一定額までなら相続人は凍結された口座からお金を引き出すことが可能です。そのため、遺産争いのトラブルにならないように話し合いをしてから、相続人は故人の預金を使うようにしましょう。
故人の預金口座から相続人が遺産を相続するためには、遺言書、除籍謄本、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、そして印鑑証明書が必要になります。相続の手続き自体は簡単ですが、一般的に払戻しまで2か月程度の期間が必要です。銀行口座の凍結は経済的な問題に、遺産相続は相続人同士のトラブルに発展することもあります。
小さなお葬式では、故人様のお荷物の整理、お部屋の片づけや掃除などを行う「遺品整理」サービスをご用意しています。お見積りは完全無料で、料金にご納得いただけた場合のみのご依頼なので安心です。急いで片づけなければいけない、見積りや作業に立ち合えない、予算に余裕が無いなどのご相談も可能です。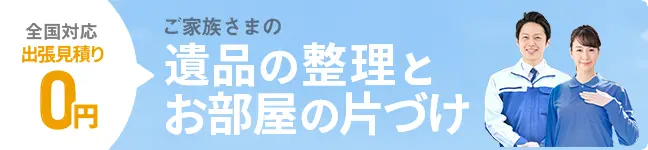
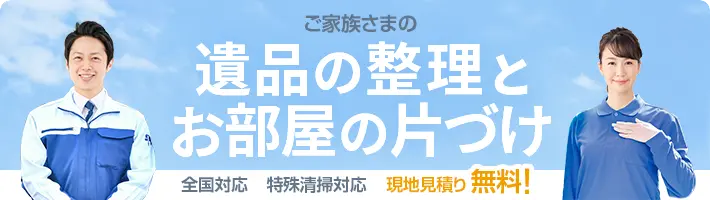
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
故人の銀行口座の死亡手続きをしないとどうなるの?
銀行口座の相続手続きに必要な書類は?
銀行口座の相続手続きはどんな流れで行われるの?
銀行への連絡は必要?
故人から相続した銀行口座に関する注意事項は?
役所から銀行に死亡の連絡はされるの?

亡くなった方や仏に向けて、香を焚いて拝む行為を焼香(しょうこう)といいます。ホゥ。




























