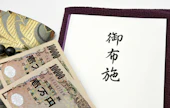身内が亡くなってから初めてお盆を迎える際、香典をいくら包めばよいのか知りたいという方もいるのではないでしょうか。お葬式と初盆の香典は同じだと思われがちですが、実は少し違いがあります。
そこでこの記事では、身内の初盆に包む香典の相場を紹介します。初盆についての知識も深められるので、ぜひ最後までお読みください。
<この記事の要点>
・香典の金額は故人との関係性や年齢、宗派によって異なる
・香典袋は一般的な不祝儀袋を選び、表書きには「御仏前」や「御佛前」と記入する
・香典袋に記入する際は、薄墨の筆や筆ペンを使用するのがマナー
こんな人におすすめ
これから初盆を迎える方
初盆の際に包む香典の金額について知りたい方
初盆の香典のマナーが気になる方
【初盆】香典の金額目安
亡くなって初めて迎えるお盆に包む香典の金額は、故人との関係性によって変わります。また、遺族の年齢によっても目安となる金額が異なります。ここからは、初盆に包む香典の金額目安を故人との関係性ごとに紹介します。
故人が親の場合
故人が親である場合は、1万円~3万円が初盆の香典の目安です。金額に幅があるのは年齢によって包む金額が変動するためです。一般的に20代や30代の方が包む金額と比べて、40代や50代の方が包む金額のほうが高くなる傾向にあります。
また、故人が親の場合は、香典とは別に「白提灯代」を兄弟姉妹と一緒に包むこともあります。白提灯代の相場は3,000円程度です。香典袋の表書きには「御提灯代」と記入します。
故人が兄弟姉妹の場合
故人が兄弟や姉妹の場合は、1万円~3万円が初盆の香典の目安です。こちらも香典を包む方の年齢が上がると金額が高くなる傾向にあります。
目安の金額が故人が親と同じなのは、実の親と同じように直接血がつながった間柄であるためです。香典は、血のつながりなど関係性の深さによって包む金額が変動します。
故人が祖父母の場合
故人が祖父や祖母の場合は1万円が初盆の香典の目安ですが、生前の親交の深さも考えて包むとよいでしょう。
祖父母の場合も年代によって目安の金額は変動します。香典を包む方の年齢が上になるほど金額が増える点に注意しましょう。
故人がおじ・おばの場合
故人がおじやおばなどの親戚の場合は、香典の金額が少なくなる傾向にあります。5,000円~1万円が目安とされていますが、生前にどれだけ親しかったのかも考えた上で、包む金額をきめるのがおすすめです。
初盆の香典の金額は、血縁関係に関係なく地域や宗派によってきめられていることもあります。自身の地域のしきたりや、宗派のマナーを事前に菩提寺などに聞いておくと安心です。
初盆の香典以外に必要な費用
初盆の際は、玄関先に提灯を飾ったり会食をしたりすることも多いでしょう。そのときに発生する費用は香典と別で用意することになります。
ここからは、香典のほかに必要になる費用を紹介します。費用ごとの金額の目安も解説するので、ぜひ参考にしてください。
会食費
法事における会食とは、施主が参列者に食事を出しておもてなしをすることです。親族や故人と親しかった方が集まって食事をしながら故人を偲び、思い出話をする場でもあります。
会食費の目安は、1人あたり5,000円ほどといわれています。会食に参加する場合は、会食費を香典に足して包むのが一般的です。会食の場が用意されているのか事前に確認して、参加すべきかどうか検討しておきましょう。
宗派や地域によっては会食の場を設けないケースもあります。自身の宗派や地域の慣習も把握しておくと安心です。
初盆用の提灯代
初盆には「白提灯」と呼ばれる提灯を飾ります。初盆のときのみに飾る提灯で、故人や先祖の霊が戻ってくるときに道に迷わないようにするために用意します。
白提灯は親族や故人と親しかった方が用意するのが一般的です。白提灯の金額目安は1万円~2万円です。自身が提灯代を出す立場であれば、香典とあわせて白提灯代も持参しましょう。
初盆の香典袋の書き方やマナー
お葬式の香典と同じように、初盆の香典にも書き方のルールやマナーが存在します。書き方を知らずに記入してしまうと失礼にあたる可能性もあるため注意が必要です。
ここからは、初盆の香典袋の書き方や不祝儀袋の選び方を紹介します。
表書きは御仏前や御佛前
仏教の場合は、四十九日を過ぎると表書きの書き方が変わります。浄土真宗以外の仏教宗派はお葬式の際の香典の表書きに「御霊前」を使用しますが、初めてお盆を迎えるときには既に故人の魂はあの世に旅立っているため、御霊前を使用しません。
初盆における香典の表書きは「御仏前」や「御佛前」です。地域によっては「御香奠(ごこうでん)」や「御供」が使われるところもあります。
自身の地域の表記の仕方を調べておくとよいでしょう。宗派などがわからない場合は「御仏前」と記載することをおすすめします。
香典袋は一般的な不祝儀袋を使う
香典袋は一般的な不祝儀袋を選ぶようにしましょう。熨斗(のし)のついていない白黒の結び切りの水引が適しています。
熨斗がついているものや水引の色が赤白になっているもの、蝶結びやあわじ結びになっているものは、結婚式や快気祝いに使う祝儀袋であるため選ばないようにしましょう。
不祝儀袋の水引の色は白黒であることが一般的ですが、地域によっては黄銀や黄白を使う場合もあります。包む金額が大きい場合は双銀や藍銀の水引を使用します。
薄墨ではなく濃墨で記入する
お葬式の際、香典袋の表書きは薄墨の筆や筆ペンで記入します。これは「涙で墨が薄まってしまった」「突然のことで墨を濃く磨れなかった」という哀惜の意を伝えるためです。
初盆の香典には「突然のことで大変だったが、無事に初盆を迎えられた」という意味も含まれているので、濃墨で記入して問題ありません。ボールペンやサインペンで表書きを記すことはマナー違反なので注意しましょう。
初盆の香典の渡し方
初盆の香典には、渡すタイミングやマナーがあります。ここからは、初盆の香典の渡し方や郵送する際の注意点について解説します。
遺族にとって初盆法要は特別な日であるため、失礼のない渡し方を覚えておきましょう。
袱紗(ふくさ)や風呂敷に包んで持参する
香典は香典袋に入れて、袱紗(ふくさ)や風呂敷に包んで持参しましょう。袱紗には香典袋が汚れたり水引が崩れたりすることを防ぐ役割があります。弔事には寒色系の袱紗が適しています。
渡し方は「喪家に直接渡す方法」「仏壇にお供えする方法」の2つ
初盆の香典を渡す方法は2つあります。1つは、喪家に挨拶する際に直接手渡す方法です。
「この度はお招きいただきありがとうございます。心ばかりですが、お仏前にお供えくださいませ」と一言添えて、袱紗から香典袋を取り出して表書きが相手に見える向きで渡しましょう。
地域によっては、仏壇に香典をお供えすることもあります。仏壇に手を合わせてからお供えしましょう。
香典を郵送する場合は現金書留封筒に入れる
法要に出席したり喪家に赴くことが難しかったりする場合は、香典を郵送してもよいでしょう。ただし、普通郵便や宅配便で現金を送ることは法律で禁止されているので、注意が必要です。郵便局の窓口で現金書留専用封筒を購入して香典袋を入れましょう。初盆法要を欠席するお詫びの手紙も入れると丁寧です。
【施主側】初盆法要の香典返し
初盆法要で香典をいただいた際は、お返しを用意するのがマナーです。しかし、香典返しの金額やどのような品物を贈ればよいかなど、わからないことが多いかもしれません。ここからは、初盆法要の香典返しについて解説します。
初盆法要の香典返しの金額目安
香典返しの金額は、いただいた香典の金額の半分~3分の1が目安とされています。香典が1万円だった場合は、3,000円~5,000円が香典返しの金額目安です。
香典の金額は故人との関係性によって異なるので、人によっては高額な場合もあるでしょう。そのような場合は4分の1程度でも問題ありません。
お返しにおすすめの品物
初盆の香典返しでは「消えもの」と呼ばれる消耗品を選ぶのが一般的です。お菓子やゼリー、そうめんなどがよく選ばれます。受け取る相手が自由に品物を選べるカタログギフトも人気です。
一方で、日持ちしない食べ物や「四つ足生臭もの」と呼ばれる肉や魚などは香典返しには不向きです。
初盆の香典に関するよくある質問
初盆の香典に関して、まだわからないことや不安なことがある方も多いのではないでしょうか。ここからは、初盆の香典に関するよくある質問を3つ紹介します。
お札の入れ方や向きはきまっている?
香典で包むお札の向きは、肖像画が裏側(下側)になるように入れるのが一般的です。複数枚入れる場合は向きをそろえましょう。
お札は新札でも問題ない?
葬儀や通夜で香典に新札を包むのは不適切とされていますが、初盆に関しては新札でも問題ありません。ただ「香典に新札を入れるのは気が引ける」という方は、新札の真ん中に折り目をつけて香典袋に入れるとよいでしょう。
香典とお供え物どちらも必要?
初盆法要は故人の魂が帰ってくる大切な日であるため、香典とともにお供え物も用意したほうが喜ばれるでしょう。明確にきめられているわけではなく、地域や家庭によって異なります。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
身内に包む香典の金額は血のつながりや故人との生前の関係性の深さによって変動します。近い関係だと金額が高く、遠くなるほど低くなるということを覚えておきましょう。故人が親や兄弟姉妹である場合は1万円~3万円、祖父母の場合は1万円が相場です。
また、初盆の際には香典以外にも会食費や初盆用の提灯代がかかります。また、香典の表書きも「御仏前」や「御佛前」に変わる点にも注意が必要です。
初盆の香典に関する疑問以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


遺産相続が発生した場合、いかなる場合でも配偶者は相続人になります。ホゥ。