故人の死を受け入れ、一段落ついた時期にやってくるのが四十九日の法要です。初めて施主になった方は何から手を付ければよいか分からないのではないでしょうか。
招待する親族を決めるのはもちろん、法要までに準備したり、手配したりすることはたくさんあります。この記事では、四十九日の法要に招待する人の一般的な範囲や施主が注意する点についてご紹介します。
<この記事の要点>
・四十九日法要には血縁関係にある親族とその家族を招待するのが一般的
・四十九日法要に呼ぶ範囲は地域の風習を優先した方がよい
・故人の意向であれば家族のみで四十九日法要をおこなってもよい
こんな人におすすめ
四十九日法要をおこなう予定のある人
四十九日法要に誰を呼べばいいのか悩んでいる人
四十九日法要の案内状について知りたい人
四十九日法要に呼ぶ人の範囲
四十九日の法要で最初に悩むのが、呼ぶ人の数や親族の範囲ではないでしょうか。漠然と招待する人を決めるのは難しいでしょう。
しかし、一般的な基準を知っておけば、スムーズに招待する人の範囲を決められます。ここでは、四十九日の法要に呼ぶ人の一般的な範囲と注意すること、参列客についてご説明します。
一般的な招待の範囲
まずは故人から見て、血縁関係のある親族とその配偶者や子どもを呼びます。葬儀の際に招待した参列者すべてではなく、血縁関係がより近い親族とその家族を招待するのが一般的です。四十九日の法要以降、一周忌まで法要はないので、すべての親族を招待するのがよいでしょう。
高齢の親族の場合
超高齢化社会の昨今、四十九日の法要に呼ぶ親族の中には90歳以上の高齢者がいる場合もあるでしょう。ただ、高齢者の方は施設に入居していたり、健康面で問題を抱えていたりして出席できない方もいます。
また、遠方に住んでいる高齢者は体力面の問題で出席が困難な方もいるでしょう。参列が難しいと分かっていても、今後の親戚付き合いに支障をきたさぬよう、招待の連絡は必須事項です。そのうえで本人の参加の意思が強い場合、断る必要はないでしょう。
小さいお子さんがいる場合
小さい子どもは大人と違い疲れやすいため、寒さの厳しい冬や夏の暑さの中では体調を崩す可能性があります。小さい子どもを招待する際には、法要を執り行う時期を考慮し、招待しない決断をすることも必要です。また、受験シーズンの冬場は流行する感染症が多く、受験生も外出を避けるため招待しないほうがよいでしょう。
故人の友人の場合
四十九日の法要は親族だけで執り行うことが一般的です。そのため、故人の友人を呼ぶことは一般的にありません。ただ、通夜や葬儀に参加できなかった故人の友人から、法要へ参列したいという打診を受ける場合があります。そのようなときは、相手の気持ちを尊重し、参列をお願いしましょう。
四十九日法要に呼ぶ範囲は地域の風習を優先すべき?
基本的に地域の風習は優先したほうがよいでしょう。その地域に脈々と受け継がれてきた風習ですから、外れた行動をすると今後の親族や近所付き合いに影響が出る可能性があります。
数名の血縁関係でこぢんまりと法要を好むところから、全ての親族と近所の方を呼んで大々的な法要を好むところもあり、地域柄は多種多様です。どこまで参列者を招待するのか判断がつかない場合は、目上の親戚や地域の相談役に相談しましょう。
家族のみだけで四十九日法要をするのはあり?
家族のみで四十九日法要をするのは「あり」です。とくに、故人が家族だけで執り行って欲しいと言明していたり、遺言が残っていたりする場合は故人の意見を尊重しましょう。また、最終的な決定権は法要を仕切る施主にあります。家族のみでこぢんまりとした法要を執り行うと決めた場合、角を立てないためにも親族には早めにその旨を報告しましょう。
四十九日法要に親族を呼ぶメリット・デメリット
故人の血縁関係を考えると、親族を無下にすることができないと考える方は多いでしょう。しかし、遺族から見ると付き合いが希薄な場合もあります。そのため、親族を呼ぶかどうか悩む方が多いのではないでしょうか。ここでは、親族を招待したときの具体的なメリットとデメリットをご紹介します。
メリット
法要には、故人の子どものころを知る親族が多く集まります。そのため、家族の知らない幼いころや、若いころの思い出話を聞きながら故人を偲ぶことができるでしょう。また、普段顔を合わせることの少ない親族と、久しぶりに再会できる機会でもあります。それがきっかけとなり、親しい親戚付き合いが始まることもあるでしょう。
そして、親族を法要に呼ぶことで「自分は招待されなかった」といったトラブルも防げます。
デメリット
デメリットの中で一番にあげられるのは費用面です。人数が多くなるほど、会場や会食の手配で費用はかさみます。親族をどの範囲まで呼ぶのかも悩むポイントです。なるべく角が立たない範囲を見極めましょう。
また、参列する親戚の中に高齢者や幼児がいる場合は、特別な配慮が必要です。事前に準備できるものであれば、手配すれば対処できます。ただ、体調不良や怪我といったイレギュラーなアクシデントが当日起こる可能性があるため、その点は念頭に入れておきましょう。
四十九日法要に必要な準備
四十九日法要に呼ぶ親族の選定が終わったら、日程や当日のための手配が必要になります。ここでは、法要までに必要な準備を分かりやすく説明します。
日時・場所の決定
四十九日法要は、故人が亡くなった日を1日目として数え、49日目に執り行います。平日の場合は日程をずらすことも可能です。ただし、49日目よりも後に法要を執り行うことはよくないとされています。49日を過ぎないよう早めに日程を決めましょう。
法要会場は一般的に「自宅」、「寺院」、「墓前」、「自宅と墓前」の4つです。参列する人数などを考慮して施主が決めましょう。場所によっては、1万円ほどの場所代がかかる場合もあります。
僧侶の手配
【お寺とお付き合いのある方】
読経してもらう僧侶に依頼をします。他の家の法要と重なる場合、早くに連絡した方が優先してもらえるので、日程が決まったらすぐに連絡することを心掛けましょう。
【お寺とお付き合いが無い方】
小さなお葬式では、お付き合いのあるお寺がない方に向けて、僧侶をお手配するサービスがございます。詳しくはこちらをご覧ください。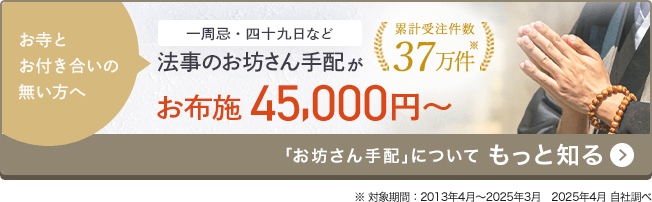
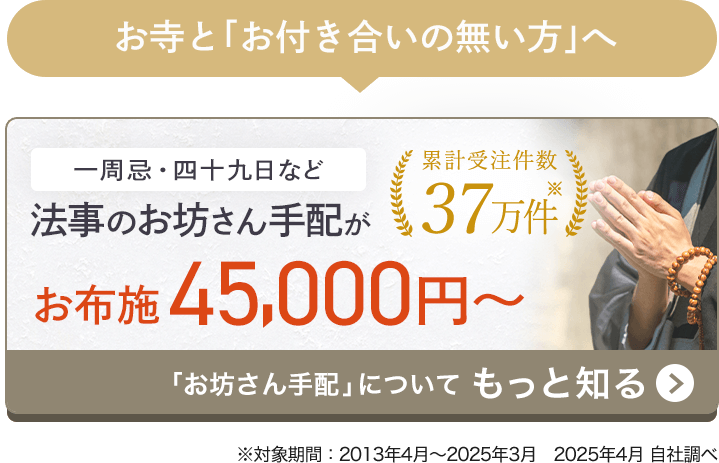
お寺の都合によっては希望日に添えない場合もあるため、1ヵ月~2週間前を目安に寺院手配の予約をすることをお勧めします。
案内状の準備
法要の日程が確定したら、すぐに案内状を手配しましょう。インターネットで簡単に手配できますし、葬儀場によっては引き受けてくれるところもあります。
特に、招待する人が多い場合は、書面で残る案内状を出したほうが確実です。会場や会食の手配のために出欠確認が必要なので、案内状に返信用のはがきを同封する必要があります。ただし、二重封筒は不幸が重なるという意味があるので使用は辞めましょう。
家族のみの場合は、電話やSNS、メールでの連絡でも問題ないでしょう。電話よりも、文面の残るSNSやメールがおすすめです。
本位牌・仏壇の準備
故人の魂は白木位牌といわれる仮の位牌に入っています。そして、僧侶の手で馴染みのある黒い本位牌へ、故人の魂を移す仏事が四十九日の法要内容です。そのため、本位牌の手配が必要になります。戒名を位牌に刻むのに時間がかかるため、早めに手配しましょう。
また、49日以降の故人の魂は仏壇に入れるようになります。家に仏壇がない方は、このタイミングで仏壇を購入するとよいでしょう。現在は、モダンなデザインのものあり、自宅のインテリアに合わせた仏壇を選ぶことが可能です。
会食・引き出物の準備
四十九日の法要を執り行った会場によって、会食の形式は異なります。施主は仕出し弁当の手配か、食事をする店の予約をしましょう。いずれも、仏事の会食には禁忌とされる食材や料理があります。法要の会食で利用することを必ず伝えましょう。会食の料理は人数分必要になりますが、引き出物は供養の御礼として一家族にひとつ用意します。
引き出物は実用性のあるタオルや、消えもののお菓子が定番です。昨今では、かさばらないカタログギフトを選ぶ方も増えています。
四十九日法要の案内状
スマートフォンが普及している現在、メールやSNSが連絡手段として普及しています。手紙を書く機会は少なく、案内状の書き方に不安がある方もいるのではないでしょうか。
案内状は、受け取った側が理解しやすいように、四十九日の法要の開催と日時や場所について分かりやすく記載してある必要があります。ここでは、四十九日法要に的を絞った案内状の書き方を分かりやすくご紹介します。
案内状の基本構成
案内状の構成は以下のとおりです。
1.時候の挨拶
手紙も案内状も、書き出しは時候の挨拶からはじまります。時候の挨拶ばかりに気が行き過ぎて、頭語(謹呈など)を忘れないようにしましょう。
時候の挨拶には明るく華やかな印象のものがあります。弔事に関する案内状なので、避けたほうが賢明です。
2.葬儀参列のお礼
忙しい中、急な葬儀に参列していただいたことに対するお礼を述べます。
3.法要の案内
ここからが本題である四十九日法要の内容です。まずは、誰のための法要なのか分かりやすくするために、故人の名前と施主との続柄を明確に書きます。故人と施主の苗字が異なる場合は、両名ともフルネームを載せましょう。
4.法要出席へのお願い
案内状の本文の文末です。法要への参列をお願いする文で締めくくります。ここでも頭語と同じく、結語(謹白など)を忘れないように注意しましょう。案内状を作成した日付は、元号と月だけで日付を入れないのが一般的です。
5.法要の日時
分かりやすくするために、日時は箇条書きで記載します。法要の開催日時を元号表記で年、月、日を入れ、時間は午前・午後表記で明記しましょう。
6.法要の場所
法要を執り行う場所を入れます。開催場所が寺院の場合は、寺院名を簡略化せずに正式名称を入れましょう。また、法要場所の住所や電話番号も書きます。
7.会食について
会食がある場合は、きちんと記載しましょう。ちなみに、法要後の会食のことを仏教用語で「お斎(おとき)」、「祖餐(そさん)」と呼びます。会食を行わない場合は、何も記載する必要はありません。
8.出欠案内と返信期限
案内状には、出欠の確認のための返信用葉書を同封します。返信期限を忘れずに記載しましょう。返信期限は一般的に法要の7~10日前です。
9.施主の指名と連絡先
最後に差出人である施主の住所、氏名、電話番号を明記しましょう。法要までの連絡や当日の急な欠席など、参列者が施主に連絡が必要となったときに便利です。
案内状の文例
ここでは、案内状の文例を紹介します。
| 謹啓 晩秋の候 皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしのことと存じ上げます さて 先般 亡母の葬儀に際しまして ご丁寧なる御芳志を賜り厚く御礼申し上げます このたび 下記日程にて 亡母 □□ 〇〇の忌明けの法要をとりおこないます ご多用のところまことに恐縮ではございますが何卒ご出席をたまわりますようご案内申し上げます 謹白 記 日時 令和〇年〇月〇日(曜日) 午前〇時より 場所 〇〇寺 住所 東京都〇〇区□□□□ ●-● 電話番号 03-XXX-XXX なお 法要のあと△△△△にて祖餐をご用意しております お手数ではございますが同封のはがきにて〇月〇日までにご返信賜りますようお願い申し上げます |
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
四十九日の法要に呼ぶ親族の範囲から、法要に必要な手配や注意点を理解できたのではないでしょうか。ただ、仕事などが忙しく手が回らない方もいるでしょう。
四十九日に関するお困りごとや葬儀全般に関する疑問がある場合は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。専門知識を持つスタッフが、お悩みに寄り添い丁寧にアドバイスいたします。


不祝儀袋は、包む金額に合わせて選ぶと丁寧です。ホゥ。


































