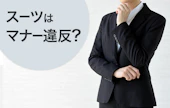故人が亡くなってから49日目に行われる四十九日法要は、身内だけで行うケースも最近では少なくありません。参列する機会が少ないと、法要や法事のマナーや知識に疎くなりがちです。
いざ法事や法要に参列するとなった際に、服装に悩むという方もいるのではないでしょうか。正しい服装や法要の流れを知っておけば、当日に慌てる必要もありません。そこでこの記事では、四十九日法要における適切な服装と法要の流れをご紹介します。
葬儀~葬儀終了後の流れについては別のページで詳しくまとめています。ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・四十九日法要では、遺族は正喪服または準喪服を着用するのがマナー
・学生の場合は、制服があれば制服を着用する
・自宅で四十九日法要を行う場合、僧侶の送迎の有無を確認しておく
こんな人におすすめ
四十九日法要を予定している人
四十九日法要に慣れていない人
四十九日法要の服装のマナーが知りたい人
四十九日法要における正しい服装とは?
遺族は、正喪服もしくは準喪服を着用します。三回忌が終わるまでは、遺族は喪服を着用するのが一般的です。親族は、三回忌までは喪服や略式喪服を着用しましょう。遺族・親族ともに、七回忌以降は略式喪服や派手ではない平服で参列して問題ありません。
そのほかの参列者は、四十九日までは略式喪服を着用します。遺族や親族よりも格式が高くならないように注意しましょう。一周忌以降は略式礼服や派手でない平服を着用します。
男性の喪服の格式とその内容とは?
葬儀や法要など故人を偲ぶ行事に参列する際は、喪服着用がマナーです。男性の喪服には、正喪服・準喪服・略式喪服があります。適切な服装で葬儀や法要に参加するために、それぞれの特徴を知っておきましょう。見た目だけでなく格式にも違いがあります。ここからは男性の喪服について詳しくご紹介します。
正喪服について
正喪服は、喪服の中で最も格式の高いものです。洋装の正喪服は、黒のモーニングコートに白のレギュラーカラーシャツ、控えめなコールズボンが基本です。ネクタイやベスト、ソックスなどは黒で統一します。
カフリンクスは不要ですが、付ける場合は黒にしましょう。モーニングコートは、通夜時は着用せず葬儀のみ着用します。
和装の正喪服は、紋付羽織袴が基本です。家紋は五つ紋、紋付と羽織は黒の羽二重のものを着用します。慶事と比べて草履の鼻緒が地味で、袴の紐と羽織紐の結び方も異なるので確認しておきましょう。
準喪服について
準喪服は、正喪服の次に格式が高い喪服です。基本はブラックスーツで、シングル・ダブルの2種類あります。一見リクルートスーツやビジネススーツに似ていますが、まったく異なるものです。弔事に、これらのスーツを着回しするのは避けましょう。
ワイシャツは白無地で、ネクタイは光沢なしの黒無地を付けましょう。靴下やハンカチも黒の無地に統一するのが基本です。
略式喪服について
略式喪服は、喪服の中では一番下の格式です。参列者の場合は、遺族や親族よりも格式の高い喪服を着るのはNGです。そのため、故人のお別れ会や仮通夜には、略式喪服での参列が賢明です。
ダークスーツが基本です。黒・紺・グレーであれば問題ありません。靴やネクタイは、地味な色であれば黒でなくてもよいでしょう。シャツは白無地、靴下は黒無地にします。
女性の喪服の格式とその内容とは?
男性同様、女性の喪服にも正喪服・準喪服・略式喪服があります。色やデザインを慎重に選びたい喪服は、どのようなものが適切なのか知った上で選択しましょう。ここからは、女性の喪服について格式と喪服の特徴を詳しくご紹介します。
正喪服について
喪服の中で最も格式の高い正喪服には、洋装と和装があります。洋装は、ワンピースやスーツ、アンサンブルが基本です。黒無地で、光沢のないものを選びましょう。
露出がなく身体のラインが強調されないものが、弔事では基本です。スーツを着るときは、白シャツは避けましょう。パンツスーツはNGです。スカート丈は、膝下かくるぶしまでのものがよいでしょう。
和装の場合、黒喪服といわれる染め抜きの五つ紋と黒無地が特徴の着物が基本です。帯や帯揚げ、帯締めも黒で統一します。草履も黒で布製のものを履きましょう。ただし、足袋と襦袢、半襟は白が基本です。髪飾りやアクセサリー、帯留めを身に着けるのは避けましょう。
準喪服について
準喪服は、正喪服の次に格式が高くなります。黒のワンピースやスーツ、アンサンブルが基本です。無地という決まりはなく、レースなどの飾りがついてもよいとされています。ただし、露出が少ないものを選びましょう。準喪服では、パンツスーツも着用できます。素材は、光沢がなく透けないものにします。パンプスは黒が基本です。
ネイルをしている場合は、飾りは落としましょう。地味なものは落とさなくても大丈夫です。落とす時間がない場合は、黒の手袋を上からするとよいでしょう。メイクはナチュラルメイク、髪飾りも付けません。髪を結ぶ場合は、黒の髪留めにしましょう。
略式喪服について
略式喪服は、喪服の中で最も格式が低い喪服です。黒や紺、グレーのワンピースやアンサンブルが基本です。パンツスーツも略式喪服として着用できます。無地でなくても、派手でなければストライプ柄などが入っていても問題ありません。
アクセサリーは、結婚指輪以外は付けるのは控えましょう。略式喪服の場合は、一連の真珠ネックスであれば付けてもよしとされています。ストッキングは、黒またはベージュのものを着用しましょう。
子どもの服装はどのようにすればよいのか?
四十九日の法要に家族で参列することもあるでしょう。その際の子どもの服装をどのようにすればよいか、迷っている方もいるかもしれません。子どもであっても、法要に適した服装をするのはマナーです。ここからは、学生や乳幼児の服装をご紹介します。
学生の場合について
制服がある場合は、制服を着ていきましょう。制服も礼服のひとつとして認められています。制服がない場合は、男の子は白か黒のワイシャツに黒か紺色のズボンを着用します。靴は地味な色にしましょう。女の子は、白か淡い色のブラウスやワイシャツに、丈が短すぎないスカートを合わせます。
靴はスニーカーやローファーを履きます。制服の一部であるネクタイやリボンは、明るい色でも取り外す必要はありません。
乳幼児の場合について
可能であれば、乳幼児は四十九日に連れて行かないほうがよいでしょう。急に泣き出して周りの方に迷惑をかけてしまう心配もあります。
しかし、どうしても連れて行かなければいけないときもあるでしょう。その際の乳幼児の服の色は、黒や紺がベターです。ベビー服のお店では取り扱いが少ない色なので持ち合わせていない人もいるでしょう。その場合は、アイボリーなど地味な色の服を着用します。
自宅で四十九日法要を行う場合の注意点とは?
四十九日法要の執り行う場所には、寺院と自宅の2種類があります。自宅で行うのであれば、僧侶に来てもらうことになります。新しく仏壇を購入する際は、自宅に設置するときにすべきこともあります。ここからは、自宅で四十九日法要を行う場合の注意点をご紹介します。
僧侶の送迎を実施する
自宅で四十九日法要を行う場合は、僧侶に家まで来てもらわなければいけません。開式前に自宅に着くように、遺族側が迎えに行くようにしましょう。特に、僧侶が遠方の場合は、移動時間も長いため早めのお迎えが安心です。
最近では、法事や法要の会場まで僧侶自らが自動車を運転して来るケースも増えました。四十九日を依頼する寺院が決まったら、送迎が必要か確認しましょう。
仏壇の開眼供養を行ってもらう
今まで家に仏壇がなかったご家庭もあることでしょう。新たに仏壇を購入した場合は、四十九日法要とあわせて開眼供養をする必要があります。四十九日法要の当日に、開眼供養を一緒に行う人も少なくありません。
開眼供養は、四十九日法要よりも前に行っても問題ありません。僧侶の予定も確認して、日時を決めて開眼供養をしてもらいましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
今回は、四十九日法要に参列する際の服装と注意点についてお伝えしました。遺族や親族、参列者と、立場によって四十九日法要に参列する際の正しい服装は違います。自宅で四十九日法要をする場合も、注意点を事前に知っておけば準備もスムーズに進むでしょう。
小さなお葬式では、寺院手配サービスも行っています。法事や法要を依頼する寺院に迷っている方はぜひご相談ください。
参考:小さなお葬式の寺院手配
法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


一日葬とは、通夜をはぶいた葬儀形式のことです。ホゥ。