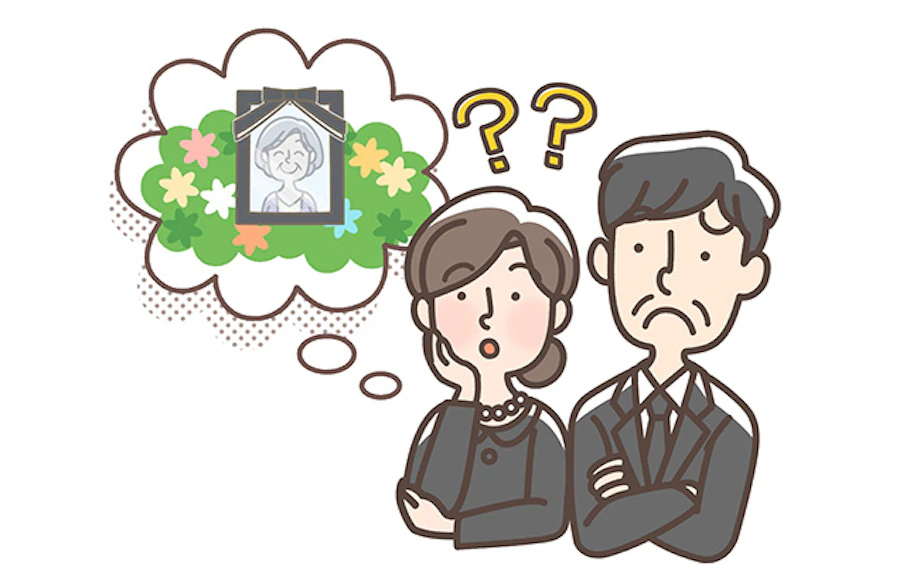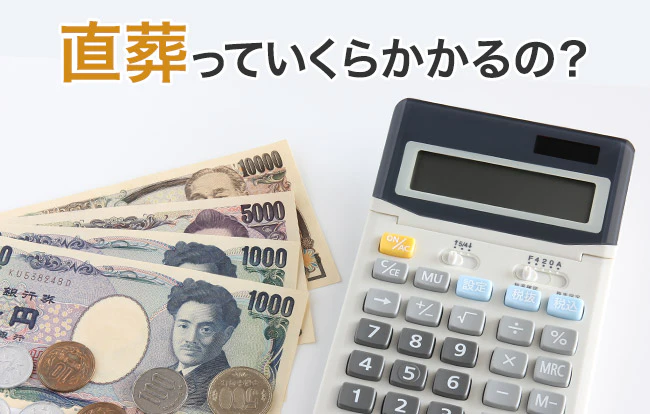「葬儀費用の平均額や内訳を知りたい」「葬儀の費用を抑える方法はないのか」と考えていませんか。
訃報は予期できないことなので、急な手配にもしっかりと対応できるように、ある程度予算について計算しておきたいものです。
そこでこの記事では、葬儀の費用の内訳や安く抑える方法を紹介しています。葬儀の費用の内訳をきちんと理解したい、安く抑えることも検討したいという方はぜひ最後までご覧ください。
<この記事の要点>
・通夜・告別式を省くなど葬儀の規模を抑えることで葬儀費用を安くできる
・自治体の葬祭費補助を利用し、葬儀費用に充てることができる
・寺院費用や飲食接待費は葬儀費用に含まれていない場合があるので注意が必要
こんな人におすすめ
葬儀費用の全国平均や内訳について知りたい方
葬儀費用を安く抑える方法を知りたい方
葬儀の費用に関する注意点を知りたい方
葬儀費用の全国平均は約127万円
小さなお葬式が行った調査では、葬儀にかかる費用の全国平均は約127万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ 火葬料金込)
【地域別・葬儀費用の合計の平均】
| 全国平均 | 約127万円※ |
| 北海道・東北 | 約146万円※ |
| 関東 | 約135万円※ |
| 中部 | 約139万円※ |
| 近畿 | 約118万円※ |
| 中国・四国 | 約114万円※ |
| 九州・沖縄 | 約116万円※ |
こちらの葬儀の費用は、葬儀にかかるすべての金額を合計したものです。具体的には、お葬式費用、会食、お布施などすべて含んでいます。
高額なことに驚かれたかもしれませんが、こちらは多くの参列者で故人を見送る比較的規模の大きい一般葬も含まれています。また、規模や形式などによって費用は大きく変動します。
葬儀費用の内訳
葬儀の費用は以下3つです。料金が高い順に並べました。
1. 葬儀費用一式
2. お布施・寺院費用
3. 飲食接待費用
葬儀の費用の内訳を把握していないと、多くのオプションをつけてしまい予算より高くなってしまうことが起こる場合があります。しっかりと相場と比較し、予算を考えましょう。
詳しくは後述しますが、飲食接待代は特に予想しづらいです。一般的な相場を紹介しますので、参考にしてください。
1. 葬儀費用一式:約86万円
葬儀にかかる費用の全国平均は約86万円※です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)こちらが全体の60%~70%を占めています。
葬儀にかかる費用とは、
・遺体の搬送費
・人件費
・祭壇費
・施設利用費
などを指します。
祭壇費は、選ぶ祭壇によって、30万円~120万円の幅で大きく変わります。祭壇をオリジナルで制作する場合はより高額になるので、葬儀社としっかり相談しましょう。
多くの場合、すべてセットでの料金で案内されます。選ぶプランに必要なものが含まれているものを選ぶことが大切です。
<関連記事>
葬儀の費用平均127万円!今すぐ用意できますか?
2. お布施・寺院費用:約26万円
寺院費用とは葬儀に協力してくれた宗教者や寺院に対して払うもので、お布施の金額も含んだ全国平均は約26万円※です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)
寺院費用の内訳は
読経料:15万円~30万円
戒名料:15万円~30万円
お車代:5,000円~1万円
御膳料:5,000円~1万円
で、それぞれ寺院によって大きくことなります。
読経料とは、葬儀で読んでもらうお経に対して払う費用のことで読経量によって変動します。
戒名とは、人が亡くなった際に、仏の弟子になった印として授かるものです。ランクによって大きく変動し、2万円のものから100万円以上のものまであります。一般的には、15万円~30万円が相場です。
お車代とは、葬儀の会場まで足を運んでくださった僧侶の方に交通費として払うものです。
御膳料とは、先ほど紹介した通夜振る舞いや精進落としに僧侶が辞退した場合にその代わりとして支払います。辞退しなかった場合は不要です。
3. 飲食接待費:約16万円
飲食接待費とは、参列者をもてなす飲食に必要な費用や、香典返しのことです。飲食接待費の全国平均は約16万円※です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)飲食接待費は参加人数によっても変動します。
費用は、1回の飲食を4,000円として見積もりをおこなうのが一般的です。
通夜ぶるまい:1人当たり4,000円程度
精進落とし:1人当たり4,000円程度
返礼品:5,000円~1万円程度
香典返し:受け取った金額の3割~5割
「通夜振る舞い」とは通夜式後の食事会、火葬後の「精進落とし」は火葬後の食事会のことです。
葬儀費用を安く抑える4つの方法
内訳でも見た通り、葬儀の内容によって葬儀費用は変動します。費用を安く抑える5つの方法を紹介します。どの方法も誰でも利用できるもので、大きく費用を抑えることも可能ですのでご確認ください。
1. 葬儀の規模を抑える
2. 葬祭費補助を利用する
3. 相続税の控除を受ける
4. 公営斎場を利用する
1. 葬儀の規模を抑える
葬儀の規模を抑えて、その分費用を安くする方法です。
以前は、多くの参列者で故人を見送る一般葬が主流でした。しかし現在では、故人や遺族に合わせた多様な葬儀があります。
| 形式 | 概要 | 費用(小さなお葬式) |
| 家族葬 | 親しい方限定の葬儀 | 450,000円(税込495,000円)※ |
| 火葬・直葬 | 通夜・告別式を省き、火葬のみ | 160,000円(税込176,000円)※ |
| 一日葬 | 通夜を省き、告別式から火葬を1日で行う | 350,000円(税込385,000円)※ |
※資料請求後の割引価格
家族葬とは、家族・親族、友人、知人などのおよそ30名以内で行われる葬儀のことです。流れは一般的な葬儀と変わらず、通夜の翌日に告別式と火葬を行います。時間はご逝去の日を含めて3日間です。葬儀の28.4%を占めるポピュラーな形式になってきています。
火葬・直葬とは、通夜・告別式の儀式を行わず、火葬のみを行います。親しい方数名で行い、一般参列者は招きません。逝去の日を含めて2日で終了します。参列者が少ない方、費用を抑えたい方に適した形式です。
一日葬とは、通夜を行わず、告別式と火葬を行います。逝去の日を含めて2日で終了します。費用を抑えたいが、告別式を行いたいという方に適した形式です。
これらの形式を使うことで、全体の費用を抑えられます。
2. 葬祭費補助を利用する
葬祭費補助とは、生活が困窮している方が葬儀を執り行う場合に、自治体がそのサポートをするものです。遺族も経済的に困窮していて葬儀の費用を賄えない、あるいは遺族以外の人が葬儀を手配するなどの場合に利用できます。
葬祭扶助で支給される金額は、最低限の葬儀を行えるだけの費用です。僧侶の読経などは基本的に行われず、直葬と呼ばれる火葬だけのお別れになるのが一般的です。
支給額は大人が20万6,000円以内、子供が16万4,800円以内とされています。
葬祭扶助は、以下の範囲内で補助されます。
1. 検案
2. 死体の運搬
3. 火葬または埋葬
4. 納骨その他葬祭のために必要なもの
葬祭扶助は、葬儀を執り行う前にしか申請できませんので気をつけましょう。葬儀社に「葬祭扶助を利用したい」と問い合わせるのが確実です。
小さなお葬式の場合、生活保護受給者の方が葬祭扶助が適用された場合に限り、葬祭扶助を利用して0円で葬儀を行うことも可能です。
参考:小さなお葬式の自己負担0円のお葬式
3. 相続税の控除を受ける
葬儀にかかった費用は、相続税の控除として利用できます。控除できる費用は、基本的には葬儀に直接必要な、
搬送費用
葬儀辞退の費用
ご遺体の搬送
葬儀に必要な物品
人件費
祭壇費
施設利用費
などが挙げられます。
一方、控除されないものは以下の通りです。
香典返し
墓石の彫刻料
位牌や仏壇などの購入費
初七日以降の法事費用
葬儀に必要な費用と考えられないものは控除対象になりません。
控除申請の際に、領収書が必要になるので必ず受け取りましょう。また相続税の申告や納税は故人の死後10か月以内です。行わないと罰則があるので注意しましょう。
<関連記事>
葬儀費用をローンで支払うための手続きと手数料(金利)について
4. 公営斎場を利用する
地方自治体が運営している公営斎場を利用すると、費用を安く抑えられます。利用料自体が低価格なのに加えて、火葬場が併設されていることが多いので、そこまでの移動料金の節約にもなります。
しかし公営斎場・火葬場の場合、予約が取りにくいというデメリットがあるので気を付けましょう。
葬儀の費用に関する注意点4つ
葬儀の費用には気をつけなければならないことを4点まとめました。葬儀を行う前に知らないとトラブルになってしまう場合があります。しっかり確認しましょう。
1. 追加料金がかかる場合がある
2. 費用は基本的に喪主が支払う
3. 支払期限のある業者が多い
4. 香典をあてにしすぎない
1. 追加料金がかかる場合がある
葬儀社の提供するプランの中に、必要な物品・サービスが含まれているか、事前に確認することが重要です。自分の希望する内容がオプション項目だった場合は、追加料金が必要になります。事前の見積書に目を通して、追加料金についてきちんと問い合わせましょう。
基本的に葬儀の見積書には「葬儀一式費用」のみが記載されます。「寺院費用」は、葬儀社が寺院を紹介した場合に記載されることが多いです。「飲食接待費」に関しては、基本的に見積書には記載されず、別途見積もりとされます。
2. 費用は基本的に喪主が支払う
葬儀の費用は、喪主が支払うのが一般的です。しかし体調がすぐれない場合や、経済的に困窮している場合は親族も負担します。また、故人が生前に葬儀社と契約し、既に費用を用意している場合もあります。支払いの前に、故人や身近な人に確認を取りましょう。
<関連記事>
葬儀費用は誰が負担するのか?費用を抑える方法も紹介
3. 支払い期限がある業者が多い
葬儀社への支払いは、葬儀終了から1週間以内という場合が多いです。ただし葬儀社によっては分割払いや生命保険の支払いを考慮してくれる場合もあります。
急に大きな額を支払う必要性が出てきますが、慌てずに準備しましょう。どうしても期日内の支払いが難しいという場合は、葬儀社に相談してみてください。
4. 香典をあてにしすぎない
香典は関係性にもよりますが、約5,000円∼1万円を包みます。参列者が多いほど香典額も増えますが、香典返しが必要になるのであまりあてにはできません。香典返しは「半返し」という、いただいた香典の半額程度の品物を送るのが一般的です。
<関連記事>
葬儀での香典返しのマナーは?金額相場・品物・香典返しなしの場合などを解説
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
葬儀の費用平均が約127万円※と聞いて驚いたかもしれません。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)しかし、葬儀は形式や規模によって費用も大きく異なります。大切なことは予算と求める葬儀の折り合いをつけることです。葬儀社にしっかり相談しましょう。
小さなお葬式では、全部で6つのお葬式プランを用意しています。不必要なものを省いた低価格で明確なお値段で、ご自身に合ったプランをお選びいただけます。費用を最小限にした「小さなお別れ葬」(税込86,900円※)から、一般的な葬儀を低価格で行う「小さな一般葬」(税込658,900円※)などをご用意しています。葬儀をお考えの際は、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。
※資料請求後の割引価格。火葬料金別。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



告別式とは、故人と最後のお別れをする社会的な式典のことです。ホゥ。