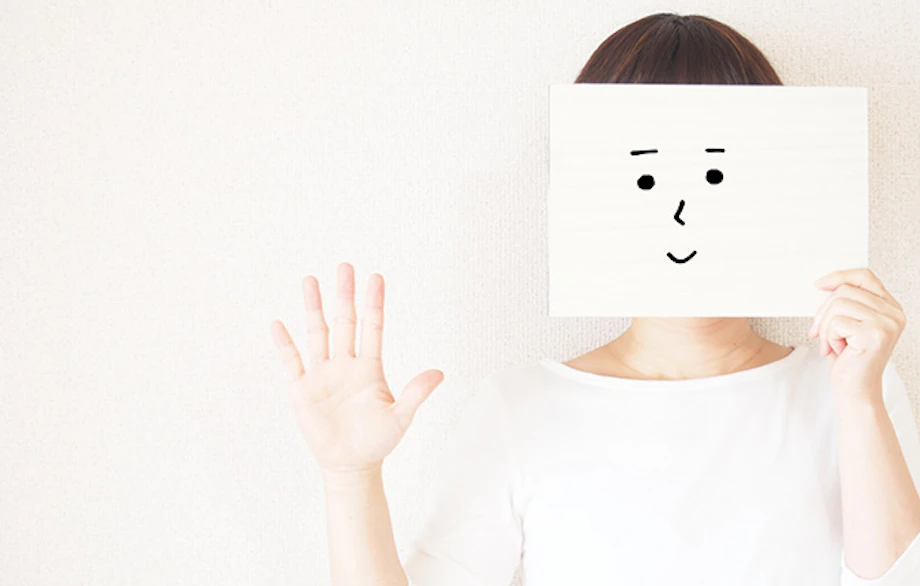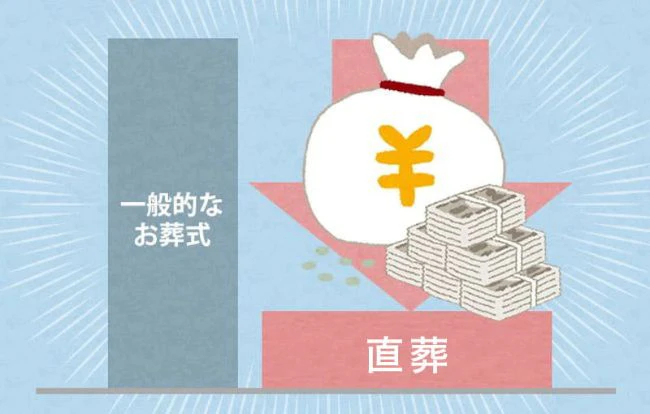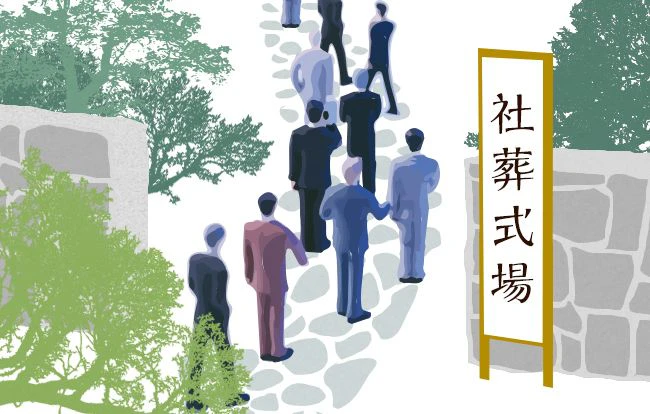「家族葬を検討しているけど、5人といった少人数でも行えるのか」「5人の場合の料金はいくらか」と疑問をお持ちではありませんか。
親族や親しい間柄の人だけで行う家族葬ですが、流石に5人では少なすぎるのではないかと不安に思う人もいると思います。結論からお伝えすると、家族葬には人数制限がないので、5人のような少人数でも執り行いが可能です。
この記事では5人で行う場合の家族葬の費用やメリット、流れを詳しく解説しています。家族葬を5人で行おうと考えている方はぜひ最後までご確認ください。
<この記事の要点>
・家族葬は最少人数や最大人数の決まりがないため、5人でも行える
・5人で行う家族葬の費用の相場は、一般的に100万円前後
・家族葬のメリットは、遺族の負担軽減・別れの時間にゆとりがある・葬儀形式を自由に決定できること
こんな人におすすめ
少人数の家族葬をお考えの方
家族葬とは何か知りたい方
家族葬と密葬の違いを知りたい方
そもそも家族葬とは?概要について解説
まずは、家族葬とはどういった葬儀なのかを改めて解説します。
故人の親族や親しい人だけを招き、少人数で行う葬儀のことを家族葬と呼びます。家族葬と呼ばれていますが、必ずしも親族だけで行うとは限りません。遺族に招かれれば、親しい友人やお世話になった人が参加することもできます。
詳しくは後述しますが、家族葬は葬儀の準備の中心となる故人の親族の負担を減らせることや、故人とのお別れにゆっくりと時間をかけられるといったメリットがあるので、家族葬のスタイルを取り入れる方は多いです。
【結論】家族葬は5人でも行える!
家族葬を行うにあたって、参列者は10〜20人程度であることが多いですが、明確な最小人数や最大人数の決まりはありません。そのため5人のような少人数でも家族葬を執り行えますし、多い場合は50人以上で行われることもあります。
少ない人数でも行えるかなと心配する必要はないので、予算や参列できそうな人数を考えた上で検討してみてください。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
5人で行う家族葬の費用
5人でも家族葬が執り行えることをお伝えしたところで、次に気になるのは費用ではないでしょうか。参列者が少なければその分、葬儀の費用も少なくなるのではないかと考える方もいると思いますが、少ないからといってその分安くなることはほとんどありません。
こちらでは、5人で家族葬を行う場合の、具体的な相場と内訳を解説します。
1. 家族葬の相場は100万円前後
小さなお葬式が実施したアンケートによると、家族葬を行う際の費用は、およそ70万円~75万円です。だたしこちらはお布施や宗教者へのお礼を除いているので、全体で100万円前後だと頭に入れておくと良いでしょう。
一般葬や直葬などの他の形式の葬儀も含んだ平均的な費用は、200万円ほどだと言われているので、半額程度で行える家族葬は比較的安い葬儀形式ではあります。
しかし、一般葬であれば参列が増えると、その分香典の金額も多くなります。家族葬は人数によって大幅に費用が変動することがあまりないので、その点は注意してください。
2. 費用の内訳
家族葬の費用の内訳は下記のようになっています。
| 葬儀基本費用 | 約38万円 |
| 式場使用料 | 約16万円 |
| 車両費用 | 約8万円 |
| 火葬 | 約2万円 |
| お布施 | 約30万円 |
| 合計 | 約94万円 |
家族葬を5人で執り行うこと自体は問題ありませんが、10人以下のような少人数専用の葬儀場はあまりないです。そのため、10名ほどの規模の家族葬と同じくらいの式場を利用することになるでしょう。
また少人数の家族葬であれば基本的に食事は用意しない場合が多いです。もし用意する場合は一人当たり1500円~3000円を飲食費の予算としておきましょう。
しかしこれはあくまで一例なので、葬儀場によって費用は変動します。一つの目安として参考にしてください。
家族葬のメリット3つ
家族葬は参列者の人数が少ないが故のメリットが3つあります。遺族の負担軽減できる、葬儀の形式を自由に決められるなど、故人や遺族の希望する葬儀に当てはまっているという方もいるでしょう。
ここでは、葬儀形式を家族葬にするメリット3つについて一つずつ解説していきます。
1. 遺族の負担が少ない
家族葬のメリットは何と言っても、遺族の負担が少ないことが挙げられるでしょう。参列者が少ないため、その分のあいさつ回りも少なく、身体的にも精神的にも負担が少なくなります。
5人程度の本当に近い親族だけであれば、あいさつ回りもほとんどないでしょう。ただでさえ葬儀前後は慌ただしいので、できるだけ負担を減らしたいと家族葬を選ぶ方も多いです。
2. 準備やお別れに時間をかけられる
また参列者が少ない分、葬儀の準備や葬儀中のお別れの時間にもゆとりが生まれます。故人との最後の時間なのに、バタバタしてきちんとお別れができないと、悔いが残ってしまうでしょう。
少ない人数の家族葬なら、家族だけで感謝の気持ちを伝えたり思い出を話したりと、ゆっくりとお別れに時間をかけられます。
3. 葬儀のスタイルを自由に決められる
葬儀の関係者や参列者が多いほど、葬儀のスタイルは希望や宗教などによって多様化します。家族葬で人数が少ない場合、故人の葬儀に対するという思いや遺族の「こんなかたちで送りたい」という意思を反映させやすくなります。
葬儀のスタイルにこだわりや希望がある人には、家族葬の少人数で行うのがおすすめです。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
家族葬の流れを紹介
ここでは、家族葬の一般的な流れを解説します。家族葬と一般葬で大きく異なるところは参列者の人数であり、流れは遺体搬送から初七日法要を行うところまでおおよそ同じです。葬儀をスムーズに進めるためにも、今一度きちんと流れを把握しておきましょう。
1. 遺体搬送
病院などで医師が死亡を確認して親族などが亡くなった場合、まずは葬儀社に連絡し、遺体を寝台車で搬送します。
搬送先は斎場や安置所、自宅などがあるので、事前に決めておくとスムーズでしょう。寝台車には1人や2人程度であれば同乗できます。
2. 遺体安置
法律上、故人が亡くなってから24時間は火葬してはいけないと定められています。そのため、遺体を安置所や自宅に搬送して1日以上は安置させる必要があります。一晩自宅で過ごした後に、安置所で安置するパターンもあります。
<関連記事>
遺体安置室の種類とは?安置の方法や注意点などを徹底解説
3. お通夜
遺体安置が終わったら、いよいよお通夜です。お通夜の名のとおり、基本的に夜に行われます。夕方18時頃からスタートするのが基本です。
家族葬は参列者が少ないので、40分程度で終わるでしょう。
4. 葬儀・告別式
お通夜の後には葬儀・告別式を行います。一般葬であれば1時間程度かかりますが、家族葬の場合は人数が少ないので、所要時間が短くて済むでしょう。5人程度の少人数であれば40分程度で終わることもあります。
<関連記事>
家族葬における通夜や告別式の流れとは?喪主の挨拶例文についても紹介
5. 火葬
葬儀・告別式が終わったら出棺し、霊柩車で火葬場に移動します。遺体の火葬が終わったら、骨壷に遺骨を納めます。火葬するには火葬許可証が必要になり、火葬後に返却されることも覚えておきましょう。
6. 初七日法要
故人が亡くなってから7日以内に初七日法要を行います。故人の極楽浄土への旅立ちを祈って供養をする儀式です。
現代では遠方の方などを考慮した「繰り上げ初七日法要」として、初七日法要は葬儀・告別式と併せて行うこともあります。
家族葬以外の葬儀の種類
葬儀形式には、家族葬の他にも直葬や一日葬といった種類があります。家族葬にすると決めている場合でも、それぞれにどのような違いがあるのかを把握しておくと良いでしょう。
場合によっては家族葬でなく、他の葬儀形式の方が希望のスタイルに近い場合もあり得ます。ここでは直葬と一日葬はどのような葬儀なのかを解説します。
1. 直葬
直葬とは火葬だけを執り行う葬儀形式で、お通夜や葬儀は行いません。火葬しか行わない分、費用や負担を抑えられるのが直葬の大きな特徴です。
参列者が少ない場合や経済的な理由で費用を減らしたい、精神的な負担を可能なだけ抑えたいといった理由で選ばれることが多いです。遺体安置は家族葬と同じように行うので、24時間以上安置後したに火葬を執り行います。
2. 一日葬
一般的な葬儀では、お通夜や葬儀・告別式を2日間にわたって行います。それを名前のとおり、1日で行うのが一日葬です。1日にまとめて儀式を行うことで、主催者も遠方から訪れる方も時間的な拘束を軽減ができるメリットがあります。
忙しい方や遠方から訪れる方にとって、時間の拘束が軽減できるのは利点が多いです。宿泊等が必要な場合も、金銭的負担の軽減にもなります。
時間的には半分になりますが、費用までもが半分になるわけではないので注意してください。
<関連記事>
一日葬の費用はいくら?相場や内訳を徹底解説!
小さなお葬式で葬儀場をさがす
家族葬と密葬との違いについて
また葬儀スタイルのひとつに「密葬」もあります。密葬は家族葬と混合して認識している方も多いです。密葬は身内だけの葬儀を終えた後、「本葬」と呼ばれる親族以外の一般の方向けの葬儀を行う形式のことを指します。
しかし近年では本葬を行わずに、身内だけの密葬だけで済ませることも多いです。このように本葬を行わない場合は、家族葬と同じ意味合いになります。
<関連記事>
密葬とは?知っておきたい葬儀の流れと注意点
家族葬の注意点について解説
故人と最後のお別れがゆっくりでき、身体的にも精神的にも負担を軽減できる家族葬はメリットが多いです。
一方で、家族葬を行うときに気をつけるべきポイントもあります。家族葬に参列する人たちはもちろんですが、不参加者の方にもしっかりと配慮をしないと、トラブルに発展してしまう可能性もあるからです。
葬儀が終わった後に誰もが良い式だったと思って終えられるように、きちんと注意点も押さえておきましょう。
1. 事前に親族に相談する
まず、家族葬を行いたいと思ったら親族に相談しましょう。家族葬と言ってもどこまでの親族を招くのか、どのように進めるのかを相談し、合意を得ておくべきです。
葬儀はたった一回だけの大切な儀式で、やり直すことができません。家族葬を行った後の報告になってしまうと、「なぜ呼んでくれなかったのか」とトラブルに発展してしまう可能性があります。
2. 葬儀に呼ぶ人には早めに連絡する
葬儀に招く人には早めに連絡しましょう。一般的には、故人が亡くなった知らせを電話でした後、葬儀の日程や場所が決まったらメール等で知らせます。
連絡する際には家族葬で行うこともきちんと伝えておきましょう。また、ご香典や供花を辞退する場合は、その旨も一緒に伝えます。仕事などの兼ね合いもあると思うので、なるべく早めに連絡するようにしましょう。
3. 葬儀の不参加者とのトラブルが起こらないように注意
参列者が限られてしまう家族葬では、葬儀の不参加者とトラブルが起きてしまう可能性があります。
負担を減らすために少人数で家族葬を行ったのに、葬儀後に対応に追われて負担が増えてしまったら意味がありません。
きちんと家族葬にした理由を説明できるようにしておき、弔問客が自宅に訪れたときの対応についても考えておくとスムーズでしょう。
4. 葬儀後の対応の準備もしておく
家族葬にお呼びしていない人や、故人が亡くなったことを通知していない方には、家族葬を行った旨をはがきで伝えます。
タイミングとしては、四十九日の法要後や納骨後に送るのが良いでしょう。年末であれば喪中はがきでもOKです。
連絡を受けて自宅に弔問に来たいと言う人もいると思うので、迎える準備をしておくと良いでしょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
家族葬は5人という少人数でも執り行うことができ、身内だけで葬儀を行いたい方や身体的・精神的な負担を減らしたい方にもぴったりな葬儀形式です。葬儀の流れや注意点などもしっかりと把握して、気持ちよく故人を送り出せるようにしましょう。
小さなお葬式でも、様々な家族葬のプランをご用意しています。希望に合った葬儀をご提案させていただきますので、家族葬をお考えの際には小さなお葬式にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



四十九日法要は、故人が亡くなってから48日目に執り行います。ホゥ。