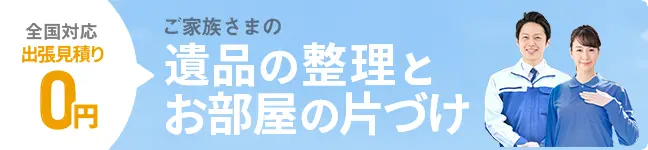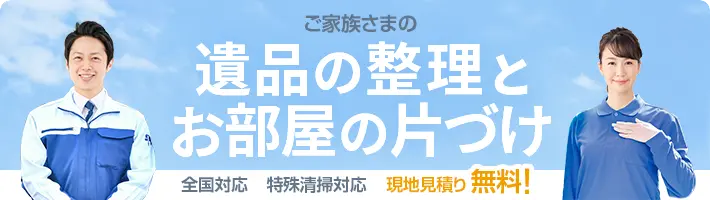相続問題は、意図せぬタイミングで訪れます。自分が相続する立場になったとしても、何から用意すればよいか分からないのではないでしょうか。相続には様々な手続きがあり、それぞれ必要な書類があります。
この記事では、相続手続きに使う書類について解説します。数多くの書類をひとつずつ確認することが可能です。そしてケース別に必要な書類も解説するとともに、手続きの相談先も紹介します。ぜひとも、最後までご覧ください。
葬儀全体の流れについては別のページで詳しくまとめています。葬儀がまだの場合は、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・相続手続きには故人と相続人の戸籍謄本・住民票、遺産分割協議書などの書類が必要
・遺言書の有無によって相続手続きに必要な書類は変わる
・相続手続きの相談先として弁護士や税理士など国家資格の専門家がある
こんな人におすすめ
相続手続きが必要になった人
必要書類をケース別に確認したい人
相続手続きの相談先が知りたい人
【一覧】相続手続きに使う書類
相続の準備で最も大変なことは、必要な書類を集めることです。相続の手続きをしたことがある方は少ないでしょうから、初めて聞くような書類もあると思います。
ここでは相続手続きに使う書類を、ひとつずつ紹介していきます。書類の数が非常に多く、全てを把握することは難しいです。必要の都度確認するようにしてください。
1. 戸籍謄本・住民票【故人・相続人】
まず用意する必要があるのは、故人と相続人の戸籍謄本と住民票です。戸籍謄本は不動産の名義変更や、相続税の申告の時にも必要となります。
ここで重要なのが、故人の戸籍謄本は出生地から亡くなった時の住所のものまで必要であることです。故人が住んでいた全ての市町村で、取得しなければなりません。
転籍が多ければ多いほど、戸籍謄本を揃えるのに労力がかかります。しかし、故人の住民票は、亡くなった時の居住地の役所で取得可能です。
また、故人だけでなく、相続人の文も同じ書類が全員分必要です。結果的に財産を相続しなかった場合でも、全員分の戸籍謄本と住民票が必要となります。
2. 遺産分割協議書
遺産分割の場面で遺言書がない場合と、遺言書の記載と異なる分割割合とするときに「遺産分割協議」が行われます。その際に作成される書類が、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と捺印をしなければなりません。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるからです。その証明となる書面にも、全員の署名と押印が必要なのです。
3. 相続関係説明図
相続関係説明図とは、相続人が誰であるのかを説明するために図式化したものです。相続人が全て確認できてから、相続関係説明図を作成します。
記載すべき内容は、以下のとおりです。
書類の名称(相続関係説明図)
被相続人(故人)の氏名
死亡日と最後の住所
配偶者及び相続人の情報
相続関係説明図に記載するのは、実際に相続をする権利のある人物だけです。そして相続権のある全員を記載しなければならず、漏れがある場合は無効となります。
4. 死亡届
死亡届は、故人の本籍地と死亡した地区の役所・役場に提出します。また死亡届は死亡診断書と死体検案書と一体となっており、死亡診断した医師に書いてもらうことが必要です。
死亡届の提出によって、戸籍に死亡と記載されて住民票が削除されます。死亡届の提出は埋葬許可申請と同時に行うことが多いため、葬儀社の方が届け出ることが多いようです。
5. 遺言書
遺言書とは、生前に自分の財産をどのように処分するのか指定する書面です。遺言書は作成方法によって、以下の種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、もっとも一般的な作成方法ですが、注意点があります。自筆というだけあり、遺言を残す人が自筆で書くことが必須です。さらに署名・捺印もしなくてはなりません。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言を残す人が自分で書くのではなく、伝えた内容を公証役場に務める公証人が作成します。メリットとしては公的な証明があるため、手続き上の不備で無効になることがないことです。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を知られたくない場合に使われる遺言書です。遺言を残す人が自分で作成した遺言書を、封入した状態で公証役場に持っていきます。そこで、日付を記載して承認2名とともに署名・捺印することで完成です。
6. 遺言執行者選任審判書
遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人です。遺言によって執行者が選任されていない場合に、家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。
家庭裁判所にて選任の審判がおりた場合に、発行されるのが遺言執行者選任審判書です。
7. 金融機関の書類
故人が金融機関の口座を持っていた場合は、残高証明書を発行してもらう必要があります。また預金通帳も必要になるので、所在を確認しておきましょう。
故人が亡くなると口座は凍結され、定期的な支払いも滞っています。相続の際には名義変更を行う必要もあるので、早めに金融機関に相談しておくことがおすすめです。
8. 不動産関係の書類
不動産関係で必要な書類は「登記事項証明書」と「固定資産評価証明書」です。「登記事項証明書」には、以下のような内容が記載されています。
・家や土地の種類
・面積
・抵当権の有無
不動産の住所を管轄する法務局で取得可能です。「固定資産評価証明書」はその名の通り不動産の評価額が記載されています。不動産の所有者に送られる固定資産税の納付書に同封されています。
9. 保険関係の書類
保険関係の書類については、以下の書類が必要です。
・生命保険支払通知書
・生命保険書
・火災保険などの保険書
・解約返戻金がわかる資料
故人が生命保険に入っていた場合は、保険金を相続できます。保険会社との連絡が必要なので、可能であれば事前に保険会社の連絡先と担当者を把握しておくことがおすすめです。
10. 葬儀に関する領収書
葬儀に関する費用は、相続税から控除することが可能です。葬儀社などから発行された領収書は全て保管しておきましょう。そして領収書が出ないような支払いであっても、控除が認められるものもあります。
控除の対象となるのは、以下のような費用です。
通夜と告別式に際して葬儀社に払った費用
通夜振る舞いや精進落としの費用
葬儀を手伝ってもらった方への心づけ
僧侶に払った戒名料や読経料などのお布施
火葬と納骨にかかった費用
遺体の安置と運搬費用
しかし「いくらでもよい」というわけではなく、世間一般において妥当な範囲とされています。心づけなど領収書がない場合は「いつ誰に支払ったのか」記録を取っておきましょう。
【ケース別】相続に必要な書類
相続で使われる書類は、多岐にわたります。各書類の用途を確認しても、実際に使う時に「どの書類が必要か」判断に迷われるのではないでしょうか。
ここでは遺言書がある場合とない場合における、必要書類を紹介します。遺言書の有無で揃えるべき書類が変わりますので、それぞれの場面を想定してご確認ください。
1. 遺言状がある場合
遺言書がある場合の相続の手続きには、以下の書類が必要です。
遺言書
検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
故人の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
相続する人及び遺言執行者の印鑑証明書
遺言執行者選任審判書
検認調書とは遺言書の内容が書き換えられないように、未開封の状態で家庭裁判所に持ち込んで「検認」を受けます。
2. 遺言状がない場合
遺言書がない場合の相続の手続きは、遺産分割協議書があるかによって必要な書類が変わります。遺産分割協議書がある場合は、以下の書類が必要です。
遺産分割協議
故人の除籍謄本と戸籍謄本または全部事項証明(出席から死亡まで)
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書がない場合は、以下の書類が必要となります。
故人の除籍謄本と戸籍謄本または全部事項証明(出席から死亡まで)
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
死亡により誰もいなくなった状態の戸籍を除籍といいます。そしてその写しを除籍謄本といいます。
相続手続きの相談先
相続手続きはやることが多く法律の知識を必要なため、難しいと感じている方が多いでしょう。そのような時に相談できる先が、知りたいのではないでしょうか。
ここでは相続手続きの相談先を「国家資格の専門家」と「葬儀社の窓口」それぞれについて解説します。相続手続きを行う際の状況を想定して、ぜひとも参考にしてください。
1. 国家資格の専門家
相続手続きの相談ができる、国家資格を持った専門家は以下のとおりです。
・弁護士
・税理士
・司法書士
・行政書士
それぞれの相談できる手続きについて、以下のとおりまとめました。
| 相談する相手 | 相談できる手続き |
| 弁護士 | 遺言書の作成と確認・保険の手続き・相続財産の確認・相続放棄と限定承認・遺産分割協議の代理・遺産分割協議書の作成・相続登記 |
| 税理士 | 相続税対策・贈与税の申告・所得税の準確定申告・相続税の申告と納付 |
| 司法書士 | 遺言書の作成・相続人の確認・相続放棄と限定承認・遺産分割協議書の作成・相続登記 |
| 行政書士 | 遺言書の作成・保険の手続き・相続人の確認・遺産分割協議書の作成 |
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
相続に関する書類は数も種類も、非常に多く存在しています。それぞれの状況によって必要な書類が異なるため、なかなか適切な書類を揃えることは難しいでしょう。そのようなときは、葬儀社などの専門業者に相談することがおすすめです。
小さなお葬式では、24時間365日対応のコールセンターがお客様からの相談に日々対応しています。相続に関する内容だけでなく、どんな些細な疑問や悩みでも結構です。お気軽にお電話ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


故人が年金受給者の場合は、すぐに年金受給停止の手続きが必要になります。ホゥ。