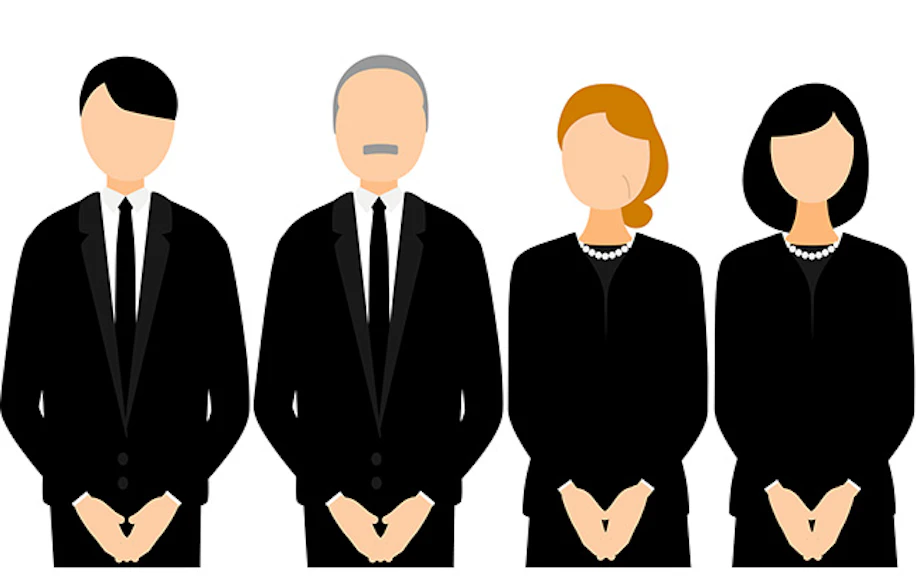通夜に参列するとき、平服を着用しても良いのか悩まれる方もいらっしゃるかと思います。「平服でお越しください」と案内があれば、平服でも問題なさそうに思いますが、そもそも平服がどういう意味なのかご存知ない方も多いのではないでしょうか。
ネットで「平服」と調べても色々な解釈があるようで、喪服とも情報が錯綜して、更に混乱を招いている状況があるようです。
本記事を読むことにより、平服の意味からはじまり通夜時の平服着用の可否などについてお解りいただけます。ぜひ最後までご覧ください。
<この記事の要点>
・通夜参列時の服装では、平服は好ましくない
・通夜式で着用する喪服は男性はブラックスーツ、女性はアンサンブルやワンピースが一般的
・葬儀告別式でも通夜式と同じ服装で参列するのが基本
こんな人におすすめ
通夜参列時の服装に悩んでいる人
「平服」がどんな服装を指すのかわからない人
通夜とは何か?平服とは何か?
通夜時の平服に関する解説をする前に、まずは通夜と平服についてそれぞれ言葉の意味を確認しておきましょう。通夜という言葉も色々な意味合いで使われていますし、平服も色々な捉え方がなされている現状があります。
平服が適切なのか不適切なのか考えるにあたって言葉の意味合いを確認しておくとは大切です。ここでは言葉の意味を整理していきます。
通夜とは何か
通夜とは、元々「故人の側に夜を通して寄り添うこと」を意味しています。しかし、たとえば職場で「通夜に伺います」という話が出たとしたら、それは元々の通夜の意味ではなく、通夜式を示していることがほとんどです。
通夜に似た言葉には仮通夜、本通夜、通夜式が挙げられます。それぞれの意味の概要は下記のとおりです。
| 仮通夜 | 本通夜を迎える前日以前の日のこと。逝去日から本通夜まで数日空けば、その数日間は毎日仮通夜となります。 |
| 本通夜 | 葬儀告別式の前日であり、通夜式を行う当日のこと。 |
| 通夜式 | 本通夜に行う僧侶による読経などを伴う儀式のこと。 (一部地域では通夜式は行わないこともあります。) |
厳密に使い分けなければならないということではありませんが、一般的に通夜と言えば、通夜式を表しているものと推測されますし、現在においてはそれで特に問題はないでしょう。ただし、通夜参列時の平服についてお伝えするうえで、言葉の意味合いを確認しておくことは重要です。
平服とは何か
平服は広辞苑によれば「日常に着る衣服。ふだんぎ」と記載されています。つまり、辞書を基に解釈すれば平服とは普段着です。
しかし、企業の採用面接や冠婚葬祭において、仮に「平服でお越しください」と案内があったとしても、それは「普段着でお越しください」という意図ではないというのが一般的な捉え方となっています。
冠婚葬祭の場にジャンバー、Tシャツ、デニムにサンダルで現れたら非難の的になることは想像に難くありません。
一般的なマナーとして時間、場所、場面に合わせた服装が求められます。したがって、平服は事実上の意味として「堅苦しい服装でなく、若干格式を下げた装い」と考えるのが相当です。
本来の意味と実際の言葉の使われ方に差があることにより、平服の考え方について混乱を招いているようですが、現実的には「平服=普段着ではない」ことに注意しておきましょう。
礼服の種類と喪服の意味
平服の対義語は礼服(式服)です。礼服は格式別に正礼装、準礼装、略礼装に分類されていて、たとえば昼はモーニングコート、夜は燕尾服(えんびふく)というように場面によって使い分けがなされます。この使い分けのルールが「ドレスコード」と呼ばれるものです。
この礼服のうち、葬祭出席時のみに使用できるもの、または冠婚葬祭以外の儀式出席時に使用できるものを、葬儀で着用する場合に喪服となります。つまり「礼服≧喪服」ということです。
礼服の一種である喪服は弔意を表し、儀式に相応しい厳粛な空間を作り出すために着用する目的があります。お洒落など自己主張をするために喪服を着用するものではないという点に注意が必要です。
通夜参列時の平服の是非
通夜参列時の平服はアリか?と問われたら、通夜式で普段着の着用を想像しているのであれば、基本的に答えは非(正しくない)です。通夜式に参列する際、普段着で行く人はまずいないことは多くの方がご存知のところです。
ただし、平服の捉え方には幅があり、若干格式を落とした服装で良いと言っても、何を基準に格式を落とすのか難しいところです。判断に迷った際は小さなお葬式にご相談ください。状況に応じた適切な服装についてもご助言させていただきます。
通夜式に参列するときの喪服マナー
では、通夜式に参列する際はどのような服装が適しているのでしょうか。「この服で葬式に行っても大丈夫かな」と不安を覚える方は少なくないでしょう。通夜式に伺う先が、自分にとって大切な相手であれば尚のことです。
男性、女性、子供とそれぞれ適した服装は異なりますので、ここでは個々に喪服マナーを紹介いたします。
男性の場合
男性は喪服としてブラックスーツの着用が基本です。ブラックスーツは礼服の種類で言えば略礼服に該当します。ただし、黒の色合いについては注意が必要で、光沢のない生地で、なるべく落ち着いた濃い黒色が無難です。
男性の正装は、本来であれば昼はモーニングコート、夜は燕尾服(えんびふく)です。しかし現在は、特別な家柄の葬儀や社葬など特別なケースでのみ喪主や葬儀委員長が着用することがあるという程度で、一般的な葬儀では使われることはありません。ブラックスーツは略礼服に該当しますが、現在における葬儀の場においては正しい服装です。
ジャケットは、シングルでもダブルでも好みで選択して差し支えありません。そのほか、白のワイシャツ、黒ネクタイ、黒靴下に黒革靴が適切です。
和装の場合には、黒羽二重の紋付羽織袴となりますが、実際の葬儀の場で見かけることは稀有なのが実状となっています。
女性の場合
女性にも正装としてモーニングドレスやアフタヌーンドレスなどがありますが、日本においては一般的ではありません。
女性の場合、通夜式の参列時には喪服としてアンサンブル、ワンピース、スーツの着用が適切です。いずれの装いでも色は黒で、男性同様に光沢のない生地を選びましょう。インナーはブラウスまたはカットソーで、ストッキング、パンプスも全て黒色です。
女性の場合、妊娠中のケースも考えられます。妊娠中でお腹が大きくなっていても、喪服以外で参列するのは避けたいところです。
妊婦用の喪服レンタルを行っているところもありますので、身体の負担にならないよう状況に応じてレンタルの利用を検討すると良いでしょう。
なお、最近では見かけることが少なくなりましたが、和装では女性の場合、黒無地染め抜き五つ紋付の着物を喪服として着用します。
子供の場合
子供の場合、幼稚園や学校の制服があれば、制服を喪服として着用できます。制服がないときには、黒や紺など落ち着いた服装で揃えます。
男子であれば、白いポロシャツに黒のニット、黒の半ズボン、黒のローファー、女児であれば白いブラウスに黒か紺のブレザー、ワンピースに黒のパンプスなどです。
靴はローファーやパンプスを所有していないこともあるかもしれませんが、小さいお子さんであれば黒に近い色合いのスニーカーを履いているケースも多く見られます。
喪服の用意が間に合わない場合
仕事中に訃報を受け、急遽職場から通夜式に参じなければならない場合は、どうしたら良いでしょうか。この場合、通夜に限り、黒、紺、グレーなど落ち着いた色合いのスーツや服装であれば、そのまま参列しても差し支えないとされています。
ただし、男性の場合、黒いネクタイはコンビニエンスストアなどで購入することが可能ですから、ネクタイだけでも付け替えて伺うのが適切な対応です。
それでも自分の服装が通夜式に相応しくないと考えられるときには、通夜式の終了直後のタイミングを見計らって、他の方に不快感をなるべく与えないよう配慮して伺うことも選択肢のひとつです。
仮通夜など通夜式以外での服装とは
仮通夜など通夜式以外のタイミングで伺う場合の服装は、どう考えたらよいでしょうか。たとえば通夜式の前日、仮通夜のお宅に弔問に訪れるようなケースです。
また、通夜式当日の午前中、弔問や打ち合わせなどで遺族宅にお邪魔するようなこともあるかもしれません。
ここでは通夜式以外の場面の服装について対応方法を紹介いたします。
喪服でなくても良い場合
たとえば、仮通夜に、親族など近しい間柄の人が故人のもとへ弔問に足を運ぶのであれば、普段着に近い平服でも差し支えないでしょう。
普段着と言ってもラフ過ぎる格好は避け、落ち着いた色合いで慎みある装いで伺いましょう。通夜式の前日に近所の方が普段着でお手伝いの打ち合わせに来られる光景も珍しくはありません。
通夜式や葬儀告別式前後で、親族など近しい間柄でない場合に弔問に伺うケースでは、「堅苦しい服装でなく、若干格式を下げた装い」という意味での平服スタイルが妥当です。
男性であれば喪服ではなく、黒、濃紺、濃灰のスーツ姿、女性であればやはり黒、濃紺、濃灰のアンサンブルなどが適しています。
葬儀告別式の適切な服装
原則的に葬儀告別式でも通夜式と同様の服装で参列します。世界的なドレスコードでは夜と昼で装いが変わりますが、日本における葬儀では、通夜式と葬儀告別式では一般的に同様の喪服を着用します。
女性に散見されますが、例外的ケースとして地域や家族の意向により、通夜は洋装で、葬儀告別式では和装をされる方もいらっしゃいます。これはこれで特に問題はありません。
一点注意が必要なのは、通夜時では職場などで訃報を受け急遽参列する場合に限り、喪服以外のビジネススーツなど仕事着も許容されますが、葬儀告別式では許されないということです。
喪章に関するマナー
葬儀会場に足を運ぶと、喪服姿に腕章やリボンを着けた方を見かけることがあります。これら腕章やリボンは「喪章(もしょう)」と言います。この喪章は何を示しているのでしょうか。葬儀時の装いの関連事項として喪章についても知っておきましょう。
ここでは喪章の目的、種類、着け方について主なポイントを紹介いたします。
喪章を着ける目的
喪章を着ける目的は大きく分けて下記の通り4つあります。
1. 遺族親族と一般参列者を見分けやすいようにするため
2. 喪主や施主、主賓や挨拶する人など特定の役割を担った人を分かりやすくするため
3. 受付係や駐車場案内などお手伝いの役割を担う人であることを示す目印とするため
4. 弔意を示すため
家族葬など限られた範囲で行う葬儀など、喪章を着けないケースもあります。
喪章の種類
喪章には、主に腕章型とリボン型があります。腕章型やリボン型には黒色一色、黒白、灰白などの色が使われ、リボン型については上部に花をモチーフとした飾りが付いているタイプもあります。
いずれの種類の喪章も、葬儀社が用意することが一般的です。ただし、地域や葬儀社によっては業者側で喪章を用意していないこともあるので、仏具店や紳士服店、斎場近隣のコンビニエンスストアや雑貨商店を探してみると良いでしょう。簡単な造りなので自作しても差し支えはありません。
喪章の着け方
男性も女性も、腕章型、リボン型どちらであっても身体の左側に着けることが基本です。腕章タイプの喪章は、左の上腕部に巻きつけて安全ピンで留めます。
肩から肘の中間に留めるイメージです。最近は安全ピンではなく、面ファスナーで装着できるタイプの腕章もあります。
リボン型の喪章は、左胸ポケット付近か、ジャケットの全面左下付近に安全ピンで留めます。目印として着けるリボンですから、目立つ位置に着けることが大切です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
通夜参列時の平服はアリか?という問いに対しては、通夜式参列時という意味合いであれば、平服は正しくありません。
平服は辞書に基づけば「日常に着る衣服。ふだんぎ」を意味しますが、一般的には「堅苦しい服装でなく、若干格式を下げた装い」と捉えるのが妥当です。
通夜式に参列するのであれば普段着は適切ではありません。通夜式参列時に適切なのは喪服です。男性であればブラックスーツ、女性であれば黒のアンサンブル、ワンピース、スーツが該当します。
弔問や葬儀での服装マナーに関して迷ったとき、どうして良いか分からないときは、小さなお葬式にご相談ください。状況に合わせて適切なアドバイスをさせていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



墓じまいとは、先祖供養の続け方を考えた際の選択肢の一つです。ホゥ。