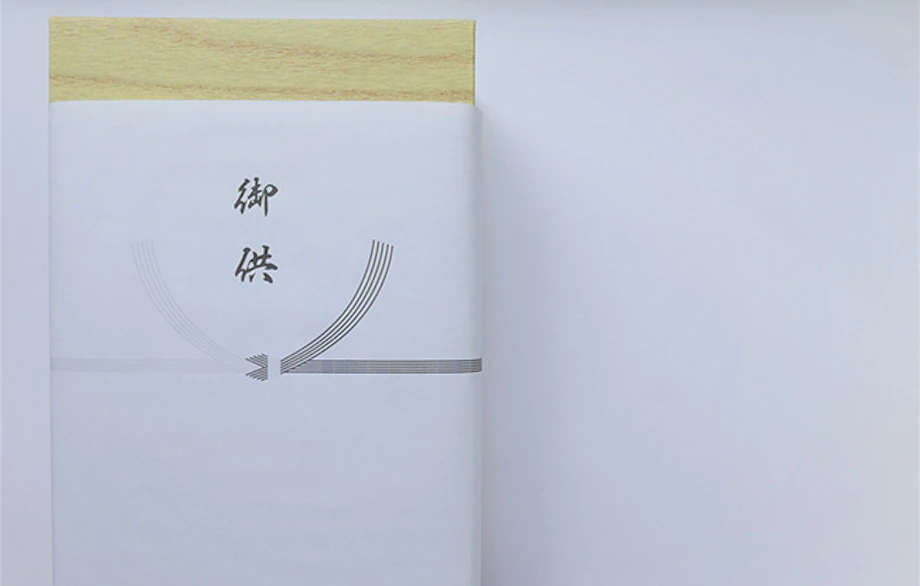一周忌を執り行うにあたり、日程、会場、持参する物など、決めることは多岐にわたります。特に会場決めは、お供えなど当日までに用意する物や参列者の人数などにも大きく関わるため、悩ましく感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、一周忌を自宅とお寺で行う際の違いや、お供えものの対応について解説します。お供え物に関するマナーについても触れている内容です。本記事を確認すれば、お寺での法要で準備すべき物が分かるようになるでしょう。
<この記事の要点>
・一周忌法要をお寺で行う場合、道具を揃えたりする必要はないなどのメリットがある
・お供え物には、食べ物や飲み物などの「消えもの」が良い
・お供え物の金額は3,000円~5,000円が一般的
こんな人におすすめ
一周忌法要をどこでやるべきか悩んでいる人
一周忌法要を自宅でやろうと考えている人
一周忌法要をお寺でやろうと考えている人
一周忌とは?
一周忌とは、故人が亡くなってから満1年の命日のことです。遺族は一周忌に合わせて法事を執り行います。ここでは、一周忌の意義を確認しましょう。意義を知れば、準備も納得のもとスムーズに進められます。
一回忌との違いは?
一周忌の法要は年忌法要の中でも特に重要とされており、家族や親族、地域の人や故人が生前に親しかった人を招いて故人をしのびます。
「一周忌」と「一回忌」は言葉が似ているので間違えられがちですが、この2つは全く意味が違います。一回忌とは命日のことで、一周忌は二回忌のことを指しますので、間違えないように気をつけましょう。
追善供養
年忌法要は、追善供養のひとつであり、故人の代わりに善行を追加することで、故人がより良い世界に行けるようにお祈りすることです。また、四十九日までの法要は、故人が極楽浄土へ行けるようにという願いから、それ以降の法要は仏様に故人をより良い世界に導いてもらうために行うとされています。
これは「輪廻転生」の考えから来ている、法要の意義です。一周忌だけでなくそれぞれの意義を知ることにより、法要に対する考え方も変わってくるかもしれません。
一周忌の場所はどこを選ぶ?
一周忌法要では、生前に故人と関わりが深かった人を招いて、読経や焼香、食事会を行います。そのため、会場の候補はひとつではありません。ここでは、一周忌法要をする際に施主がするべきことや、場所ごとのメリットをご紹介します。
お寺
菩提寺や、故人が信仰していた宗派のお寺で法要を行います。菩提寺とは、故人の家族が檀家となっているお寺のことです。菩提寺がある場合はそこに依頼します。檀家であれば、ある程度日程や状況も把握してくれていることも多く、話も進めやすいでしょう。
お寺であれば、法要に使う道具をそろえたり、会場を整えたりする必要はありません。また、お寺によっては会館を持っており、会食の手配まで請け負ってくれるところもあります。法要の相談もしやすくメリットが多いのが特徴ですが、費用が不明確なため、先に確認を取る必要がある点に注意しましょう。
自宅
一周忌法要を自宅で執り行うこともよくあることです。費用が抑えられるほか、自分たちで執り行うので参列者との距離感も近く、アットホームな雰囲気で執り行うことができるでしょう。
しかし、会場の設営や、参列者へのおもてなしは施主自身で行わなければなりません。他にも仏壇や部屋の掃除、参列者の送迎、駐車場の手配、場合によっては泊まる場所の確認といった準備をする必要があります。
準備は大変ですが、故人の思い出話をゆっくりとできるのも自宅で行うメリットのひとつです。特別な時間を過ごしたい場合は、自宅で行うとよいでしょう。
葬儀社、霊園などの法要室
お葬式を行った葬儀社や、お墓のある霊園の法要室を借りて行うこともできます。費用は少し高くなる傾向ですが、専門スタッフが会場の設営や参列者へのおもてなしまで担ってくれます。
そのため、施主の負担が少なくて済み、参列者と話す時間も多く取れるのが特徴です。会食の準備や僧侶の手配、近くのホテルの紹介などさまざまなサービスを提供してもらえます。
一周忌にはどんなお供え物を用意する?
一周忌にはお供え物を持参して参列するのが一般的です。お供え物は必ずしも必要ではなく、地域によっては不要としていることもありますので、一周忌に参列する前に一度周囲に確認をするとよいでしょう。ここでは、一周忌のお供え物として向いているものをご紹介します。
お供え物を選ぶポイント
一般的に、お供えものには食べ物や飲み物といった消費したらなくなるもの、いわゆる「消えもの」が良いとされています。
品物のジャンル以外でも、お供え物を選ぶポイントがあるので注意しましょう。法要では、お供えものを参列者で分け合うこともあります。そのため、お供えものは分けやすいものが喜ばれる傾向です。
食べ物であれば、もなかやクッキーといった、小分けにされていて持ち帰りやすいものが好まれます。
一周忌のお供え物は、法要をお寺でするにしても自宅でするにしても、仏前に供える間は常温の環境下です。要冷蔵などのものではなく、常温保存が可能なものを用意したほうがよいでしょう。
お供えものに向いている物
食べ物であれば果物や海苔、お菓子など日持ちするものが好まれ、飲み物であればお酒やお茶が挙げられます。故人が好きだったものを持っていくこともよくあります。線香やろうそくなども喜ばれます。
また、花などもお供えものとして選ばれることもありますが、お寺での一周忌法要では事前に施主が取りまとめて供花を依頼するのが一般的です。
お供えものに不向きなもの
故人が好きだったとしても肉や魚などは避けましょう。生もので日持ちしないということもありますが、仏教では否定している殺生につながるものなのでお供えものには不向きと言えます。
ニンニクやネギなど、香りが強いものも避けましょう。お寺によってはこれらの食品が心を乱すとして禁止しているところもあるからです。
その他、キャラクターやハートの柄など派手なものや、昆布などの慶事に用いるものもお供えとしては不向きなので避けるのが賢明だと言えるでしょう。
お供え物の目安金額は?
一周忌でお供え物を準備する際には、目安を考慮することが重要です。一人だけ高価すぎても安すぎても、周りとのバランスが取れずに遺族を困らせてしまいかねません。
一般的な目安としては、3,000円~5,000円と言われていますが、可能であれば他の参列者と相談して決めるとよいでしょう。
お供え物を持参する際のマナー
お供えものを持参しても、参列者が勝手に仏壇にお供えしてはいけません。挨拶の時にお供えものを持参した旨を伝え、そのまま渡すか、施主の了承を得てから仏壇に供えるのがマナーです。施主に直接渡す際は「心ばかりですが」や「御仏前にお供えください」など一言添えて渡すようにしましょう。
お寺での一周忌法要の時は?
一周忌法要をお寺で執り行う場合は、法要が始まる前の施主に挨拶をしたときにお供えものを手渡ししましょう。施主が預かってくれるか御仏前にそのまま供えてもらえるかはその時によってケースバイケースです。
御仏前に供える前には中身が見えるようにする
御仏前に供える前には、包装紙を外して中身が見えるようにする場合と、外のしの包装紙のままで供える場合とあります。自ら仏前にと促されたら、どのようにすべきか施主に指示を仰ぎましょう。
外のしは包装の上から掛け紙を掛ける包装方法です。掛け紙には贈り主の名前が入ります。仏前に供える時に誰からのものかを分かりやすくします。法要に持参する場合は外のしを選択することが一般的です。
欠席する場合は?
一周忌は年忌法要の中で特に重要な法要です。やむを得ず欠席する場合でも、お供え物や香典は送りましょう。欠席でも出席するときと同じ内容や金額を用意します。お供え物を送る際は、賞味期限に気をつけて手紙を同封するのがおすすめです。
お寺での一周忌法要で施主が用意するものとは?
お寺で一周忌法要を営むことになった場合、いくつか準備しておくものがあります。ここでは、お寺での法要に特化した準備の内容について確認しましょう。自宅や会館などで営む場合と変わらないものもあれば、お寺ならではの準備もあります。
施主はお供えとして供花を取りまとめる
お寺で法要を営む場合は、祭壇に供えるための供花を用意します。このとき、親族から供花の取りまとめ依頼をお願いされることもあることに注意しましょう。発注は、葬儀業者や生花店にします。大きさや数などはお寺と相談して決めるとよいでしょう。配送は直接お寺へと依頼します。
お寺に渡すお布施
お寺から僧侶を招いて読経を読んでもらう際、お礼として僧侶に渡すお金のことお布施と呼びます。
なぜお布施と呼ばれるのかについては諸説ありますが、粗末な衣服をきて奉仕していたお坊さんに、人々が布を施したことが始まりという説があります。このため「布施」と呼ばれるようになり、仏教の中では修行法のひとつとされています。
一周忌のお布施の目安
お布施は地域や状況によって目安は変わってきます。このため、目安としては3万円~5万円と言われています。
お寺に依頼をする前にお布施の目安を聞けるとよいのですが、お寺によっては「お気持ちで結構です」と言われることもあり、迷うこともあるでしょう。そうしたときは、地域の人に聞く、葬儀業者に相談してみるなどして、予算を決めるのもひとつの方法です。
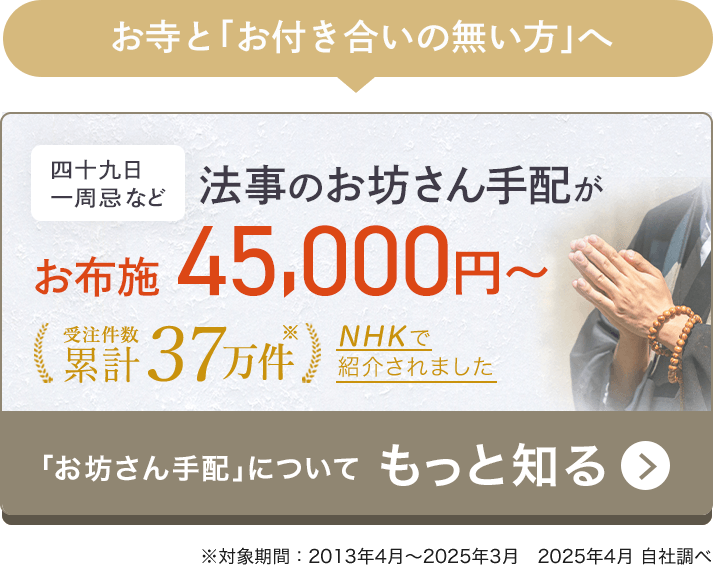
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
一周忌法要は、執り行う場所によってメリットも異なります。施主の都合や参列者の人数など、さまざまな状況に応じて相応しい場所を選択するとよいでしょう。
お寺での一周忌法要でもお供えをします。参列者のお供え物をそのまま祭壇に供えることもあれば、遺族側が用意することもあるでしょう。供えた後は、基本的に施主が持ち帰ります。
また、お供えものは故人やご遺族のことを考え、選び方にも注意しましょう。お供えものの包装紙を外すことや持ち帰りやすさを配慮することで、故人への感謝の気持ちを表せます。
このように、一周忌には注意しなければならないことも多いので、しっかり確認したうえで進めましょう。
「小さなお葬式」では、一周忌法要についてのご相談を承っております。24時間365日、法事や法要に詳しい専門スタッフが待機しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。


初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。ホゥ。