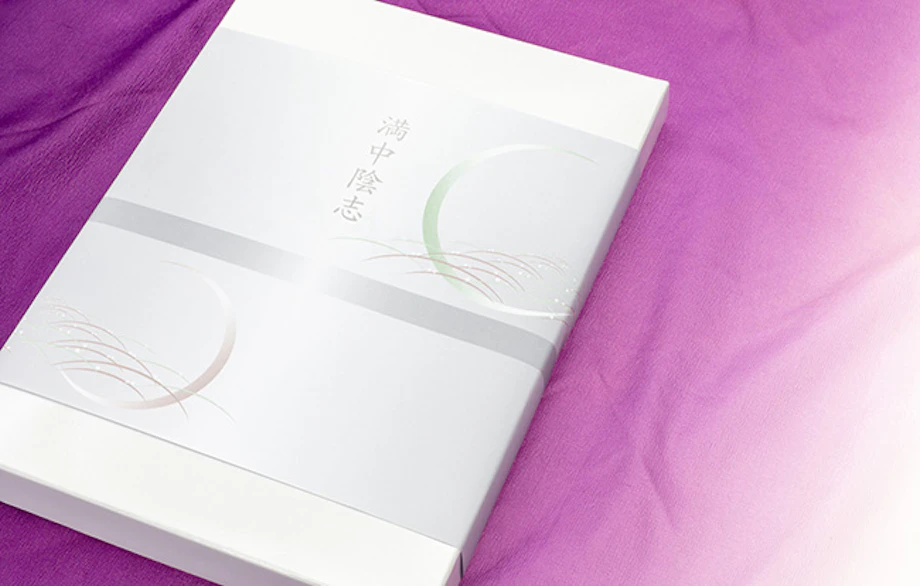満中陰志とは、四十九日法要後の香典返しのことです。しかし、西日本の一部地域を中心に使われている言葉なので、聞き慣れない方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、満中陰志の詳しい意味や、粗供養との違いといった基礎知識を解説します。満中陰志を贈るタイミングや金額の目安、品物の選び方、挨拶文のマナーなどについてもわかりやすくまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・満中陰志とは「中陰」が「満ちた」ことに対して贈る「志」で、香典返しと同じ意味を持つ
・いただいた香典の半分~3分の1程度の品を、四十九日法要が終わった後に渡す
・渡す際のマナーとして、掛け紙の表書きや水引、包み方には地域性による違いがある
こんな人におすすめ
「満中陰志」とは何か知りたい方
四十九日法要を控えている方
満中陰志を贈る際の挨拶について知りたい方
満中陰志とはどういう意味?粗供養との違いは?
「満中陰志」とはどのような意味を持つ言葉なのでしょうか。ここからは、満中陰志の基礎知識と似た意味を持つ「粗供養」について解説します。
満中陰志は香典返しと同じ意味
満中陰志とは、「中陰」が「満ちた」ことに対して贈る「志」のことです。それぞれの意味は、以下のとおりです。
中陰:命日~49日目までのこと
満ちた:中陰が終わったこと
志:感謝の気持ちを表すもの
つまり、満中陰志とは四十九日法要(満中陰法要)後に渡す「香典返し」のことです。西日本では「満中陰志」、東日本では「香典返し」、中国・四国・九州地方の一部では「茶の子」とも呼ばれますが、いずれも意味は変わりません。
満中陰志と粗供養の相違点
満中陰志と混合しやすいものに「粗供養(そくよう)」が挙げられます。
粗供養は西日本地域特有の呼び方で、会葬礼品や返礼品と同じものといえるでしょう。粗供養には、葬儀や法要にて供養していただいた方に贈るささやかな品(粗品)という意味があります。
満中陰志と粗供養の違いは下の表のとおりです。
| 満中陰志 | 粗供養 | |
| 何に対するお礼か | 葬儀・通夜などの香典 | 葬儀や法要に参列し、供養してくれたこと |
| いつ渡すか | 四十九日法要後 | 葬儀・通夜の当日または四十九日法要後 |
満中陰志と忌明志の相違点
忌明志(きめいし)は忌明けを迎えた法要に対する「志(感謝の気持ちを表すもの)」のことで、満中陰志と同じ意味があります。しかし、四十九日法要を繰り上げて実施する場合は、掛け紙の表書きに忌明志ではなく「志」と書くのが一般的です。
東日本ではいずれの場合も「志」とすることが多く、京都では満中陰志ではなく「忌明志」がよく用いられます。
中陰が3ヶ月にまたぐ「三月越え」は、「四十九(始終苦)が三月(身に付く)」の語呂合わせから縁起が悪いと考えられており、この慣習を気にする方も少なくありません。三月越えを避けたい場合には、四十九日法要を繰り上げて35日目に実施することもあります。
満中陰志を贈るタイミングと金額の目安
満中陰志を渡すタイミングや選び方がわからず、不安に感じる方も多いでしょう。相手に失礼のないように、品物の金額目安も知っておきたいところです。
宗派や地域によっても違いがある部分ですが、ここからは一般的な目安について紹介します。地域や親族の慣習に合わせて適切な方法で満中陰志を贈りましょう。
満中陰志を贈るタイミング
満中陰志は、四十九日法要が終わった後に渡します。厳密なきまりはありませんが、1ヶ月以内には参列者の元に届くようにしましょう。宗派によっては適切なタイミングが異なるため、家族や親族などに事前に確認しておくと安心です。
満中陰志は直接手渡すものとされていますが、配送してもマナー違反ではありません。また、近年では香典返しを参列当日に手渡す方も多くなりました。これは、「即日返し(即返し)」と呼ばれる方法です。
ただし、即日返しの場合は、高額の香典に対して返礼品が不相応になる可能性があります。高額な香典をいただいた方に対しては、即日返しとは別に満中陰志を贈るとよいでしょう。
満中陰志の金額の目安
満中陰志の金額の目安は香典返しと同じく、いただいた香典の半分(半返し)から3分の1程度が基本です。たとえば、1万円受け取った場合は、5,000円相当の品を返します。高額な香典に対しては、3分の1程度を目安にするとよいでしょう。
また、働き手である大黒柱を亡くした場合は、3分の1や4分の1の金額を目安にすることもあります。「即日返し」では、参列者全員に同じ品を渡すのが一般的です。2,000円~3,000円を目安に、数に余裕を持って準備しましょう。
即日返しとは別に満中陰志を贈る場合は、いただいた香典から即日返しの額を差し引いて、半返しにすることが多いです。
満中陰志として贈る品物の選び方
満中陰志として何を贈ればよいのか悩む方は少なくありません。満中陰志は何を贈ってもよいわけではなく、品物選びに関していくつかの注意点があります。ここからは、満中陰志としてふさわしい品物と不適切な品物を紹介します。
贈る品物は消えものにする
満中陰志として贈る品物は、消費してなくなる「消えもの」を選ぶのがマナーです。お菓子やお茶、海苔、調味料などの飲食料品は人気があります。また、洗剤や石鹸など消費できる日用品もおすすめです。
満中陰志の品物を選ぶ際は、食べ物なら賞味期限が長く、日用品なら劣化しにくいものを選びましょう。
消えもの以外でよく贈られるのはタオルです。故人を失った悲しみの涙をふき取ることから、タオルには「不幸を拭い去る」という意味があります。実用的で、複数あっても困らないというのも選ばれる理由のひとつです。
タオルを贈る場合は、白や落ち着いた色の無地を選ぶとよいでしょう。近年では「カタログギフト」を贈る方も増えています。
【NG】四つ足生臭ものは避ける
「四つ足生臭もの」とは、肉類や魚類のことです。たとえば、ソーセージの詰め合わせや魚の缶詰セットなどは、満中陰志としてふさわしくありません。これは、仏教に殺生を避ける考え方があるためです。
また、お祝い事を連想させるような品物も避けましょう。慶事の贈り物として選ばれるお酒、昆布、鰹節などは満中陰志として不適切です。
肉類や魚類、お酒などを選べる香典返し用のカタログギフトもありますが、カタログギフトの中から選ばれる分には問題ありません。
満中陰志を贈る際のマナー
満中陰志を贈るにあたり、知っておきたいマナーがあります。ここからは、掛け紙の選び方や挨拶文の書き方など、満中陰志に関するマナーを紹介します。
掛け紙(のし紙)に「満中陰志」と書く
満中陰志を贈る際の掛け紙、表書き、水引などの選び方は以下のとおりです。
| 東日本 | 西日本 | |
| 掛け紙 | 無地、または蓮が描かれたもの | |
| 包み方 | 外掛け | 内掛け |
| 水引 | 黒白の結びきり | 黄白色の結びきり |
| 表書き | 志 | 満中陰志 忌明志(※京都) |
| 表書きの名前 | 施主(喪主)の氏名 | |
| 墨 | 濃墨または薄墨 | |
内掛けは、掛け紙を掛けてから包装紙で包む西日本でよく用いられる包み方です。表書きや氏名は外側から見えません。外掛けは東日本でよく用いられ、包装紙で包んでから掛け紙を掛けます。満中陰志を発送する際は外掛けにするほうがよいでしょう。
濃墨または薄墨のどちらを選ぶかは、地域性による違いもありますが、基本的に遺族の一存できめて問題ありません。しかし、表書きの中で濃墨と薄墨が混ざらないように、どちらかに統一しましょう。
挨拶状を添える
満中陰志には挨拶状も添えましょう。挨拶状には、参列者へのお礼と報告の役割があります。挨拶状には以下の項目を記載するのが一般的です。
・頭語(謹啓、拝啓など)
・参列してくれたことや香典へのお礼
・四十九日法要を無事終えたことの報告
・戒名のお知らせ(戒名がある場合のみ)
・直接挨拶できないことのお詫び(配送する場合のみ)
・結語(敬白、敬具など)
・日付と喪主の名前
挨拶状には、時候の挨拶を入れません。また、「法要が滞りなく終わった」ことを伝えるために、文章を区切る句読点を使わないというしきたりもあります。
満中陰志を贈る際の挨拶状の文例
初めて満中陰志を贈る場合は、言い回しなどに不安を感じるかもしれません。
ここからは、挨拶文や直接手渡す場合の話し方の文例を紹介します。ぜひ参考にしてください。
挨拶状を添えて発送する場合の文例
謹啓
御尊家御一同様におかれましては ご清祥にお過ごしの事と存じます
さて過日 亡父○○の葬儀に関しましては 御繁忙にもかかわらずご厚志を賜り厚く御礼申し上げます
おかげをもちまして本日滞りなく
<戒名>
満中陰の法要を相済ませました
つきましては 満中陰の御印までに粗品をお届けさせていただきました
ご受納くださいます様 お願い申し上げます
早速拝趨の上御礼申し上げる筈ではございますが 略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます
敬具
令和三年八月二十四日
△△(施主の氏名)
手渡しをする場合の文例
先日の葬儀の際は、お忙しい中ご列席いただきありがとうございました。また、お心遣いに感謝いたします。おかげさまで、満中陰法要を滞りなく終えられました。○○様や皆様に見送っていただき、故人も喜んでいることと思います。ささやかですが、満中陰のしるしをお持ちしましたのでお納めください。今後ともよろしくお願いいたします。
満中陰志に関するよくある質問
満中陰志に関して、まだよく分からない部分や不安な点がある方もいるのではないでしょうか。ここからは、満中陰志に関するよくある質問を4つ紹介します。
満中陰志に商品券を贈るのは失礼?
近年、満中陰志に商品券を贈るケースも増えています。受け取った相手が自由に品物を選ぶことができて満足度も高いでしょう。ただし、商品券は金額が明確である点に注意が必要です。
満中陰志はいただいた香典の「半返し」あるいは「3分の1」が目安であるため、商品券がその目安よりも大幅に少ない場合は失礼にあたる可能性があります。
また商品券は「現金」に近いものであるため、「現金(香典)に現金で返すのはマナー違反」と捉える方もいるでしょう。目上の方や昔からの慣習を重んじる方に対しては、商品券を贈るのは避けたほうが賢明です。
満中陰志が届いたらお礼をするべき?
満中陰志はいただいた香典に対するお礼であるため、「お礼」は不要です。お礼にお礼を重ねることは失礼にあたるといわれているため、連絡をする必要はありません。
満中陰志の受け取りを辞退されたら?
満中陰志の受け取りを辞退された場合は、その意向に従いましょう。何か感謝を形で贈りたい場合は、お中元やお歳暮を贈ったり、食事をご馳走したりなど別の方法を取るとよいでしょう。
お供え物に対してお返しは必要?
お供え物をいただいた際には、「粗供養」としてお返ししましょう。香典とお供え物の両方を頂いた場合は、満中陰志と粗供養の両方を贈ります。粗供養に対しての挨拶文は不要です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
四十九日法要の後に、香典返しとして参列した方に贈るのが満中陰志です。満中陰志は、頂いた香典の半返しから3分の1を目安に選びます。法要後に、感謝の気持ちと法要を無事終えたことの報告を踏まえて、配送するか直接手渡します。配送する場合は、挨拶状を添えることを忘れないようにしましょう。
自分が施主になったときのことを考えると、細かいマナーなど不安に思うことも多いでしょう。「小さなお葬式」では満中陰志や香典返しなど、葬儀に関するさまざまな相談を専門スタッフが承ります。ささいなことでも、どうぞお気軽にお問い合わせください。



自筆証書遺言は押印がなければ無効だと判断されてしまうので注意しましょう。ホゥ。