四十九日の法要や一周忌、三回忌など仏教のセレモニーである法事には、さまざまな準備が必要です。いざという時に困らないためにも「法事の準備にかかる一般的な期間や必要な内容について、今からしっかりと押さえておきたい」という方もいるのではないでしょうか。
準備するべき内容について事前に知っておけば、スムーズに法事を執り行うことが可能です。そこでこの記事では、法事や法要の内容とともに準備するべきものなどについて詳しくご紹介します。
<この記事の要点>
・法事の準備は1か月前から始め、日時・場所・人数を決めて、僧侶や参列者の都合を確認する
・案内状には、故人の名前・法事の日時と場所・会食の有無を記載し、返信用ハガキを同封して出欠をとる
・法事のお布施は1万円~5万円程度が相場で、状況に応じて「お車代」や「御膳料」が必要
こんな人におすすめ
法事・法要について1から知りたい人
法事・法要の準備について知りたい人
法事・法要に必要なお布施の金額目安が知りたい人
主要な法事・法要を紹介!準備はいつから始める?
法要・法事について、いつから準備に取り掛かるべきか、どれくらい時間がかかるのかなど、詳しく解説していきます。
そもそも法事・法要とは?
葬儀後に執り行う法事は、故人の冥福や成仏のための仏教的なセレモニーのことです。亡くなった方は四十九日で成仏する一方、煩悩に苦しむ世界である六道のいずれかに生まれ変わることもあるというのが仏教的な考えとしてあります。そのため、故人が極楽浄土に成仏できるよう仏様にとりなす意味で行うのが法事です。
定期的に行うのが一般的な法事は、四十九日法要を始まりとして一周忌や三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌と続きます。
初七日法要
初七日は亡くなってから7日目に行う法要で、重要な追悼法要です。初七日は葬儀が終わってから期間が短いため、葬儀が終わったらすぐに参列者やご僧侶の予定を押さえるようにしましょう。
最近では、葬儀と同日に初七日法要を行う形で供養することがほとんどです。
四十九日法要
故人の魂は四十九日目に閻魔大王が裁くことで、極楽に行けるかどうかが決まります。そのため、故人・ご遺族にとって大きな意味を持つのが四十九日の法事です。また、四十九日法要にあわせて納骨も行われるのが一般的です。
万全の供養のために準備は一ヶ月前から
ご僧侶や参列者の都合も考慮して、早めに準備を整えましょう。そうすることによって、多くの方に参列していただくことが可能です。
法事・法要当日までに必要な準備
当日までの事前準備として、一ヶ月前には全て終えることを目標に予定を立てましょう。
1. 日時・場所・人数の目安を立てる
いつ、どこで、何人で行うのかを決めます。参列者やご僧侶の都合もあるので、早めに準備を開始しましょう。日時については、多くの方に集まってもらうために、法要日以前で最も近い土日に設定することが多いようです。
2. 僧侶への依頼
【お寺とお付き合いのある方】
読経してもらう僧侶に依頼をします。他の家の法要と重なる場合、早くに連絡した方が優先してもらえるので、日程が決まったらすぐに連絡することを心掛けましょう。
【お寺とお付き合いが無い方】
小さなお葬式では、お付き合いのあるお寺がない方に向けて、僧侶をお手配するサービスがございます。詳しくはこちらをご覧ください。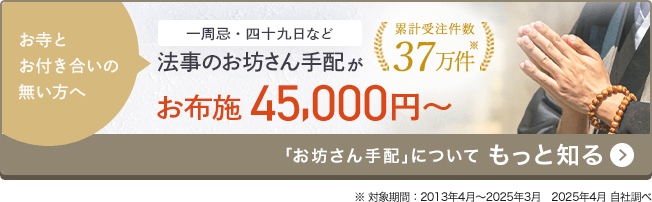
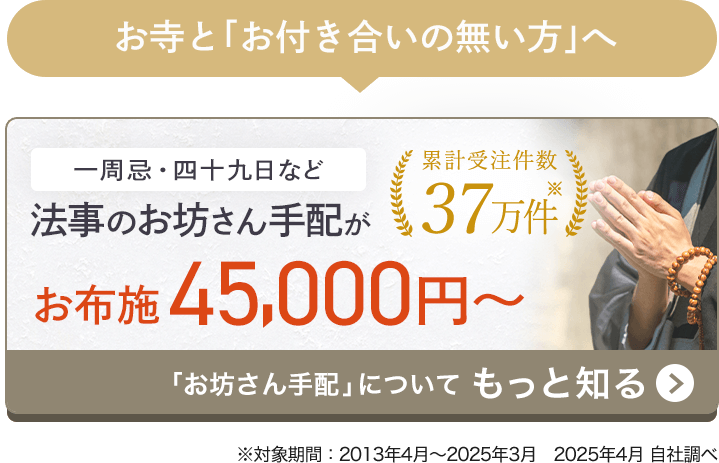
お寺の都合によっては希望日に添えない場合もあるため、1ヵ月~2週間前を目安に寺院手配の予約をすることをお勧めします。
3. 案内状を出す
法事や法要の予定が立てば、案内状を出しましょう。返信用ハガキを使用することで、出欠確認の役割も果たせます。法事や法要後に会食を予定している場合、お店の予約などもスムーズに行うことが可能です。
4. お布施の準備
ご僧侶に渡すお布施の準備をします。お布施に関しては「法事・法要のお布施金額について」の記事を参考にしてください。
法事・法要の案内状には何を書くべき?
法事や法要の日程や場所が決まったら、招待用の案内状を出す必要があります。案内状には故人の名前や法事の日程だけでなく、あいさつ文や何度目の法事なのかといったことも忘れずに記載しましょう。案内状に書くべき項目とともに、注意点や文例もまとめてご紹介します。
案内状に書くべき項目
案内状を書き始める際には、前文として、まずはあいさつ文を入れましょう。故人の名前や何度目の法事なのか、施主の名前、法事の日程・場所・内容・出欠の確認などの項目を順番に記載するのが一般的です。
案内状を書く際には上記のような項目を忘れないよう記載することはもちろん、書き方の注意点を押さえておく必要があります。縦書きにするとともに、古来の毛筆における習慣から句読点は使わずに作成しましょう。
実際に使える!案内状の文例
拝啓 皆様におかれましてはご清祥のこととお慶び申し上げます
さて 来る○月○日は○○(戒名)の三周忌法要を執り行う予定です
つきましては 亡き○○(故人名)と生前ご親交を賜りました方々にお出でいただき 左記のように三周忌法要を営みたく存じます
お忙しいところ誠に恐縮ではございますが ぜひご列席くださいますようお願い申し上げます
なお 法要の後 近くの○○で供養の粗宴をご用意しております
お手数ですが ○月○日までに同封の葉書でご出席の有無をお知らせいただければ幸いです 敬具
日時:○年○月○日 午前○時○分より
法要場所:○○寺
住所:○○
電話:○○
会食場所:○○
住所:○○
電話:○○
令和○年○月○日
○○(施主名)
住所:○○
電話:○○
お布施の費用目安
法事で読経してもらう僧侶に渡すお布施についても、相場を知っておくと良いでしょう。法事では、1万円~5万円程度のお布施が相場です。先祖代々のお墓のある菩提寺以外で法事を執り行うのであれば、僧侶への交通費として5,000円~1万円程度の御車代を用意しましょう。
また、僧侶が御斎に参加しない場合には、会食の代わりとして5,000円~1万円程度の御膳料を渡す必要があります。このように、用意するお布施の費用にはケースごとにさまざまな内訳が発生するため、しっかりと相場を押さえておくことが大切です。
遠方からの参列者がいる場合
遠方からの参列者がいる場合、駅などからお寺やお墓、会食会場までの送迎や宿泊先の手配が必要となる可能性もあります。自家用車で送迎できるのであれば、お迎え場所や時間なども双方できちんと決めておきましょう。自家用車で送迎ができない場合には、タクシーや送迎バスなどの手配が必要です。
また、日帰りでは難しく宿泊をともなう遠方からの参列者に対しては、送迎だけでなく宿泊先の手配も考慮しましょう。その際、翌日に観光もできるよう手配をしておくのもおすすめです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
故人の冥福や成仏のための仏教的なセレモニーである法事だからこそ、スムーズに執り行うためには、しっかりと準備を整えておく必要があります。いざという時に困ることのないように、法事の準備に関する具体的な内容や案内状に書くべきこと、お布施の相場などを押さえておきましょう。
法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。





































