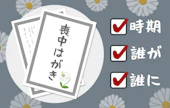忌中や喪中の期間は、故人を偲んでお祝い事を控えます。しかし、毎年年賀状を送っている方にはどのように対応したらよいのでしょうか。
そこでこの記事では、喪中の年賀状について知っておきたいマナーを紹介します。
<この記事の要点>
・忌中や喪中の間は、年賀状のやり取りを控えるのがマナー
・喪中に新年を迎える場合、年賀欠礼状(喪中はがき)を12月初旬までに届くように出す
・年賀欠礼状が届いた場合は寒中見舞いやお悔やみの手紙を出す
こんな人におすすめ
忌中と喪中の際の年賀状のやり取りについて知りたい方
「忌中」と「忌引き」の違いを知りたい方
喪中はがきが届いたときの対応を知りたい方
忌引きや喪中の場合は年賀状を出せない?
忌中や喪中とは忌服の期間を指すもので、不幸があってから四十九日までは「忌中」で、1年間は「喪中」と呼ばれます。
また、忌中と混同されやすい言葉に「忌引き」がありますが、忌引きは葬儀に出席するために会社や学校を休むことを指します。忌中とは意味がまったく異なるので注意が必要です。
忌中や喪中の間はお祝い事を控えるのが一般的ですが、年賀状は出さない方がよいのでしょうか。ここからは、忌中や喪中の際の年賀状のやりとりについて解説します。
年賀状のやり取りは控えるのがマナー
忌中や喪中の間は、年賀状のやり取りを控えるのがマナーです。また、喪中の方へ年賀状を送ることはマナー違反ではありませんが、相手に配慮して控えた方がよいとされています。
年賀状を送らない代わりに、寒中見舞いや年始状を送ります。また、仕事の取引先については、本人からではなく会社として送るため、通常通り年賀状を送れます。
喪中に年賀状を受け取っても問題ない
喪中の間は、喪に服すために新年の挨拶を控えます。ただし、年賀状を受け取る分には問題ありません。喪中の間に年賀状を受け取ったら、寒中見舞いや年始状で返事をするとよいでしょう。
忌中・喪中の場合は年賀欠礼状(喪中はがき)を出す
喪中に新年を迎える場合は、年賀欠礼状(喪中はがき)を出すとよいでしょう。年賀欠礼状とは、年賀状の辞退を事前に知らせるものです。ここからは、年賀欠礼状を出す範囲や投函時期について解説します。
年賀欠礼状を出す範囲
毎年のように年賀状のやりとりをしている方に対しては、年賀欠礼状を送ります。なお、同じく喪中である親族に対しては、お互い喪中であることを認識しているため送る必要はありません。
また、家族葬や火葬式など身内のみで葬儀を行った場合は、故人の友人や知人は亡くなったことを知らない可能性があります。故人の友人や知人に訃報を知らせたい場合も、年賀欠礼状は送ったほうがよいでしょう。
葬儀参列者に年賀欠礼状を送る場合は、参列してくれたお礼の言葉も添えましょう。
年賀欠礼状はいつまでに出すか
年賀欠礼状は、年内に届けば問題はないとされています。しかし、相手が年賀状の準備をする前に送るのが賢明です。12月中旬を過ぎると、すでに年賀状の用意をしているかもしれません。
目安としては、12月の初旬には届くようにしましょう。あまりに早すぎても、相手が喪中であることを忘れて年賀状を送ってしまう可能性があるので注意が必要です。
年末に葬儀をおこなって、年内に年賀欠礼状を送ることができない場合は、松の内が過ぎた1月8日~2月4日の間に寒中見舞いや年始状を出すとよいでしょう。
年賀欠礼状を出す際はお祝い事の報告を控える
年賀欠礼状では、「年賀」「おめでとうございます」といったお祝いの言葉は使用しません。喪中にはお祝い事を控える意味があるので、お祝いの言葉は適していません。また近況報告や個人的な報告は記載せず、必要な内容のみを伝えます。
薄墨で書く
年賀欠礼状の裏面はできる限り薄墨を使って書きましょう。
薄墨は故人を思う悲しみの感情を表しており、「涙で黒い文字が滲んでしまった」という意味があります。地域によっても考え方が異なりますが、特別な事情がない限りは薄墨で記載するのがよいでしょう。
年賀欠礼状の構成と文例
年賀欠礼状にはきまった形式はありませんが、一般的には以下のような構成と文章で記載します。
・年賀欠礼する旨:喪中につき年頭のご挨拶をご遠慮させていただきます
・いつ誰が亡くなったか:かねてより病気療養中の父○○が○月に○歳にて永眠致しました
・結びの挨拶と感謝の言葉:皆様が健やかなる新年をお迎えになりますよう心よりお祈り申し上げます
・差し出した日付:〇〇年〇〇月
年賀欠礼状が届いた場合の対応
年賀欠礼状が届いたら、基本的には年賀状は出しません。しかし、相手を気遣って「何かできないか」と思う方もいるでしょう。ここからは、年賀欠礼状が届いた場合の対応について紹介します。
お悔やみの手紙を出す
年賀状を出さない代わりに寒中見舞いや年始状を送るのもひとつの方法です。年賀欠礼状が届いて初めて不幸を知ったという方は、お悔やみの手紙を出すのもよいでしょう。
お悔やみの手紙は、故人への弔意や遺族への労いを伝えるものです。年賀欠礼状ををいただいたお礼とお悔やみの言葉を添えて手紙を出しましょう。
お供え物を送る
お悔やみの手紙だけではなく、喪中見舞いとして線香や供花などのお供え物を送るとより丁寧です。
故人との関係性にもよりますが、相手からお返しの必要があるも香典(現金)などは送らないほうがよいでしょう。お菓子やカタログギフトなども喪中見舞いとして適しています。
忌中や喪中の方への結婚式やパーティーの招待状は控える
忌中や喪中の間は、結婚式やパーティーなどに参列することは控えるのが一般的です。そのため、忌中や喪中の方にお祝い事に関する招待状を送るのは控えましょう。親しい間柄であれば、正式な招待状を送る前に電話やメールなどで事前に意見を聞いてみるのがおすすめです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
喪中の間は年賀状のやり取りを控えるのがマナーです。そして、毎年のように年賀状のやり取りをしている方には年賀欠礼状を送ります。なお、年賀欠礼状は送るタイミングにも注意が必要です。12月初旬には届くように手配しましょう。
「小さなお葬式」では、葬儀に関する知っておきたい知識やマナーについて情報を発信しています。年賀欠礼状や忌中、喪中に関する疑問にもお答えしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
メールやSNSで年賀欠礼を送ってもよい?
年賀状を出した後に年賀欠礼状が届いたらどうすればよい?
墓じまいとは、先祖供養の続け方を考えた際の選択肢の一つです。ホゥ。