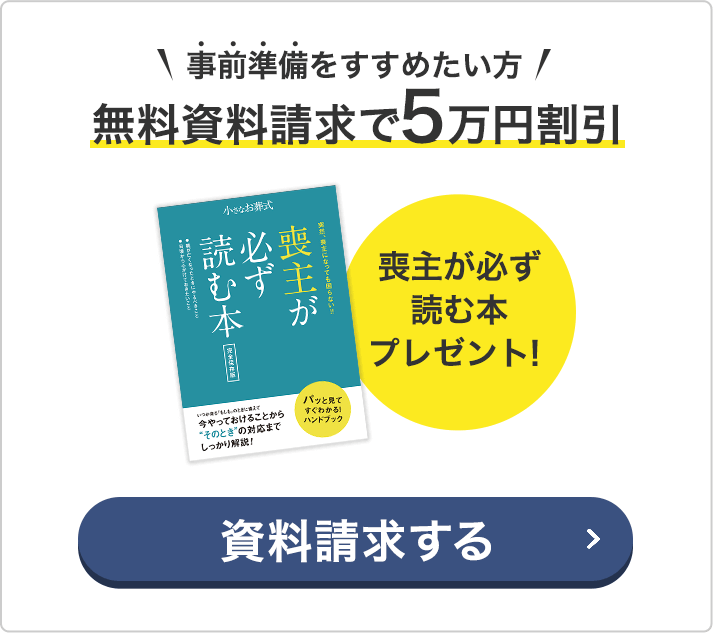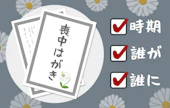日本では人が亡くなると、親族は一定期間喪に服して、日常とは異なった生活をするという風習があり、この期間を喪中と呼んでいます。現在は、官公庁の服務規程に定める忌引期間が過ぎたら、普段の生活に戻ることがほとんどですが、正月祝いを控えるという風習は残っています。
喪中(もちゅう)には新年の挨拶で「おめでとう」と言わないことや、年賀状の差し出しを控えるということは、多くの人が認識している習わしでしょう。ですが、お正月に行う風習は他にも色々あります。喪中の年はそうした一切を行わないものなのでしょうか?
この記事では、喪中時のお正月の過ごし方についてご紹介します。
<この記事の要点>
・喪中の正月には新年の挨拶を控え、年賀状の代わりに喪中はがきを送る
・喪中の正月には、正月飾りやおせち料理を控える
・喪中の場合、年賀状を受け取ることは問題ない
こんな人におすすめ
喪中のマナーについて知りたい方
喪中期間のお正月過ごし方について知りたい方
「忌中」と「喪中」の違い
「喪中」と似た言葉に「忌中(きちゅう)」というものがありますが、両者は意味が異なります。死を穢(けが)れと考え、「忌」は穢れが強い期間、「喪」は穢れが薄まり、故人の死を偲ぶ期間とみなされています。
かつては、忌中の間は外出することも控えられていました。現在でも結婚式を挙げるなど慶事は行わないことがマナーです。喪中の期間も、現在はほぼ通常の生活が行われていますが、昔は喪服を着て過ごしていました。
喪中の期間
一般的には、忌中は四十九日の法要まで、喪中はほぼ一周忌まで、と考えられています。喪中の期間は明治時代の法律を参考に、13ヶ月とされるケースもあるようです。1年ということは、この期間に必ず年越しがあるため、故人が亡くなって最初の正月は、喪中として過ごすことになります。
故人との続柄によって喪中の範囲やその期間が変わり、一般的には2親等までが喪中となることが多いようです。喪中の範囲や期間について、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
喪中の正月の過ごし方
喪中の年末年始は、正月の祝い事は控えて過ごします。具体的には何を控えて、何は行っても良いのでしょうか。ひとつずつ見ていきましょう。
年賀状・新年の挨拶
喪中の正月には、年賀状を出しません。一般的にはいわゆる「喪中はがき」と呼ばれる、年賀状を欠礼する知らせを送ります。喪中はがきには誰の喪に服しているのかを明記し、11月中旬から12月上旬に届くように発送するのがマナーです。
また、年始に人に会ったときも、「おめでとうございます」という挨拶は控え、「昨年はお世話になりました」や「今年もよろしくお願いします」などと挨拶するようにします。
正月飾り
喪中の正月には、正月飾りも控えます。門松や鏡餅、しめ縄などは神道の習慣なので、神道の忌明けとなる五十日以降は飾っても問題ないという意見もありますが、実際には行わないのが一般的です。特に家の外には正月飾りをしない方が良いでしょう。
年越しそば・おせち料理
おせち料理は正月の祝い料理なので、喪中のときは控えます。特に、めでたいことを意味する鯛や海老、紅白のかまぼこなどは避けるようにしましょう。ただ、そうしたものを除いたものであれば、普段の料理として食べても問題はありません。お雑煮も、お供え物の餅を避けて、普段の食べ物として質素に食べるのであればいいでしょう。
一方、年越しそばについては、「長寿を願う」や「1年の厄を落とす」という意味で食べられているものであり、祝い事とは関係ありません。そのため、喪中でも食べることができます。
初詣
一般的には、喪中の年は初詣を控える人が多いですが、厳密には神社とお寺で事情が異なります。
神道の忌中期間である50日間は、神社にお参りすることも、鳥居を潜ることもしてはいけないとされています。そのため、50日を過ぎていなければ初詣で神社を参拝することはできません。神社によっては喪中期間(13ヶ月)も参拝を禁じているところがあるので、やはり喪中の年は神社への初詣は控えた方がいいでしょう。
一方、お寺には死を穢れとする考えがないので、喪中に訪れても問題ありません。年始にお参りして日ごろの感謝を祈りたい場合は、お寺を訪れるようにしましょう。
お年玉
お年玉も、もともとは神様からのおくり物を意味していたので、喪中には避けた方がいいと言えます。しかし、近年は儀礼的な意味は薄れており、実家や親戚からの「お小遣い」の感覚で渡されていることが多いです。
子どもたちがお年玉を楽しみにしているので何かしてあげたいという場合は、おめでたい柄のポチ袋を避けたり、表書きを「お小遣い」や「書籍代」などにしたりして渡すのであれば良いのではないでしょうか。
喪中に年賀状が送られてきたら?
喪中であることを知らせることができなかった場合などに、年賀状が送られてくることがあります。喪中の場合でも、年賀状を受け取ることは問題ないので、受け取りを拒否する必要はありません。
ただし、その返事は正月を祝う期間である松の内の1月7日を過ぎてから、寒中見舞いという形で出すようにしましょう。また、その際には「お知らせできずに申し訳ありませんでした」と一言添えると丁寧です。
年賀欠礼状を出すのが間に合わなかった場合も同様に、1月7日過ぎに寒中見舞いを送るといいでしょう。
喪中は故人を思う気持ちが大切
決まり事やマナーも大切ですが、喪中を過ごすのにやはり何より大切なのは、故人を思う気持ちです。現代では忌明け後は普段通りに過ごすことが多いですが、年末年始に今一度故人を偲び、お墓に手を合わせてはいかがでしょうか。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
法要に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀・法要全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。


よくある質問
喪中の正月の過ごし方はどうすればいい?
喪中の範囲はどこまで?
喪中に年賀状が送られてきたらどうすればいい?
喪中見舞いとは何?
喪中はがきはいつ出せばいい?
喪中ってなんのこと?
御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。