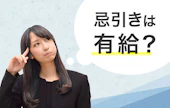身内に不幸があると忌引き休暇をとって会社を休むこともあるでしょう。忌引きが明けて次に出勤したときには周囲の方へお礼の挨拶をします。
そんなとき「メールで伝えてはいけないのだろうか」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。確かにメールの方が早く一斉に送信できます。しかし忌引き明けのお礼の方法にはマナーがあり、メールでは失礼に当たる場合があるのです。
今回は、忌引き明けの正しいお礼の伝え方とメールで連絡をするときのマナーをお伝えした上で、忌引き休暇を取得できる日数についてもご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、忌引き休暇を取るときの参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・忌引きが明けたら、まず上司に直接お礼の挨拶をして、その後同僚や部下にも挨拶をする
・お礼をする際は香典返しや菓子折りを用意しておく
・忌引き休暇の日数は故人との関係性によって異なる
こんな人におすすめ
忌引明けの挨拶の方法を知りたい方
忌引きを取る際の連絡方法について知りたい方
忌引き休暇の日数について知りたい方
忌引き明けのお礼はメールではなく直接伝えよう
忌引きが明けて最初にすべきことは周囲の方への挨拶です。忌引き休暇は多くの会社で社員に与えられている権利です。しかし急遽休んだことで他の方に迷惑を掛けている可能性もあります。
忌引き明け後の人間関係を良好に保つためにもきちんとお礼を言いましょう。まずは上司にお礼の挨拶をして、そのあと同僚や部下にも挨拶しましょう。お礼の伝え方はいくつかありますが、ご自身と相手との関係性を考えて適切な方法を選んでください。ここでは、忌引き明けのお礼の正しい方法を解説します。
忌引き明けのお礼は「直接」「手紙」「電話」が基本
忌引明けのお礼の挨拶は上司に直接言うのが望ましいでしょう。長くなりすぎないよう要点を簡潔に伝えます。そのあと同僚や部下といった周囲の方にもお礼を言いましょう。
直接伝える以外には、手紙を送るという方法もあります。メールは略式となりますので親しい関係の相手を除き会社の方へのお礼をメールで送るのは避けましょう。通夜の当日にお渡しする会葬礼状とは文面を変え、できるだけ手書きで用意します。
お礼の挨拶はできるだけ早い方がいいでしょう。そのため相手の方が休暇中の場合や出張で数日間不在の場合には電話でお礼を言うこともあります。
【例文】朝礼など大勢の前でお礼を述べる場合
勤め先によっては勤務開始前に朝礼を行うことがあると思います。朝礼では全員に向けた挨拶をします。長々と話して朝礼を長引かせないように気を付けましょう。
「この度は母〇〇の葬儀に際し皆様からたくさんの弔電と供花を賜りありがとうございました。忙しい時期に休暇を頂きご迷惑をお掛けしましたが、おかげをもちまして滞りなく葬儀が終了し、無事に母を見送ることができました」
【例文】上司や同僚に個人的にお礼を伝える場合
まずは上司に個人的にお礼を伝える場合の例文です。
「この度は母の葬儀にあたりご香典を賜りましてありがとうございました。また、急な申し出であったにもかかわらず快くお休みさせてくださり〇〇部長には大変感謝しております。本日より業務に復帰いたしますので宜しくお願いいたします」
次に、同僚に個人的にお礼を伝える場合の例文をご紹介します。
「この度は母の通夜にお越しいただきありがとうございました。また、長い間お休みを頂いたことでご心配とご迷惑をおかけしました。快く仕事を引き継いでくださり〇〇さんには大変感謝しています。本日から復帰しますので宜しくお願いします」
【例文】会葬礼状や手紙でお礼を伝える場合
一般的に会葬礼状やお礼状では句読点は使用しません。そのためこちらの例文はわかりやすいよう空白と改行で表現しています。
「亡母〇〇の葬儀におきましては ご多用中にもかかわらずご会葬いただきました上 ご弔慰を賜りまして誠に有難うございました。
混雑に取り紛れ 行き届かぬこともあったかとは存じますが何卒ご容赦くださいませ
略儀ながら書中をもちましてお礼のご挨拶を申し上げます
喪主 〇〇
外 親戚一同」
お礼の際は香典返しや菓子折りを用意しておく
忌引明けに出勤する際には香典返しや菓子折りを持参しましょう。葬儀が終わったら誰から香典を頂いたか確認しておき、香典返しを用意しておきます。郵送で送ることも可能ですが、会社で会うのであればお礼の挨拶をするときに一緒に渡したほうが良いでしょう。
弔電や供花を頂いた方には菓子折りを用意します。お菓子は個包装されていて日持ちするものがおすすめです。チョコレートは自宅に持ち帰るまでに溶けてしまう可能性があるので避けた方が無難です。
忌引きを取る際には「第一報」としてメールを使う
忌引きを取らないといけないことがわかったときは、手紙や電話よりメールの方が適切なケースがあります。勤務中や上司と連絡が取れる時間であれば口頭が一番良いですが、そうでない場合があるからです。
次に、忌引き連絡をメールで送る場合の注意点や例文をご紹介します。いざというときに慌てないようこの機会に手順を確認しておきましょう。
忌引きを連絡するのにメールが使えるのはどのような場合か
忌引き休暇を取らないといけなくなったら、できるだけ早く連絡をすることが大切です。訃報の知らせはいつ起こるかわからないので、深夜や休日に亡くなるケースもあります。また、上司が出張ですぐに電話ができないこともあります。
あなたが休むことになれば、会社は他の人に出勤を要請したり仕事の割り振りを変えたりしないといけません。会社の始業時間まで待っていたら間に合わずかえって迷惑が掛かってしまいます。そのため、電話ができなければ直属の上司にメールを送って忌引きで休むことを伝えます。
メールを送っていても最後の確認は電話にする
メールはあくまで「第一報」です。連絡が取れる時間になったら必ず上司に電話をかけて、再度忌引きで休ませてもらうことを伝えます。電話では前日にメールで送った内容に加えて、仕事の引き継ぎ事項と休ませてもらうことへのお詫びを伝えます。
特に仕事の引き継ぎは念入りに行います。前日にメールを送っているとはいえ、詳細な内容までは伝えられていません。仕事を休むことで上司や同僚は対応に追われます。できるだけスムーズに進むよう念入りに引き継ぎをしておきましょう。
忌引きの連絡をする際に必要な情報とは
忌引きの連絡をメールで送るときは「いつ、誰が亡くなったのか」「葬儀の場所と日程」「忌引きで休む日数」「緊急連絡先」の4点を記します。
メールを開いた上司がすぐに忌引き連絡であるとわかるように「忌引き」という文言は入れましょう。葬儀の日程や場を記すのは会社の方が葬儀に参列するかもしれないからです。メールを送る時点で決まっていなければ「わかり次第ご連絡します」と入れておきます。緊急連絡先は仕事の連絡が入ることも考えて、電話がつながりやすい方を選びましょう。
忌引き休暇の取得を連絡する際のポイント
本文以外にも件名に「忌引き」という文言を入れるとメールを受け取ったときにわかりやすいでしょう。書き始めは「いつ、誰が亡くなったのか」と「忌引き休暇を申請したい」という旨を簡潔に書きます。締めの挨拶は「よろしくお願いします」とまとめ、最後に自分の名前を書きます。
メールの書き方に定型文はなく、どんな文章でも構いません。しかし上司に送るからと挨拶や引き継ぎ事項を長々と書くと煩雑で内容がわかりづらいです。必要な情報のみを簡潔にまとめるのがポイントです。
【例文】忌引きを取りたいときに上司へ送るメールの件名と本文
では先ほどのポイントをふまえた上で、忌引きを取りたいときに上司に送るメールの例文をご紹介します。内容にお困りの方は以下の例文を参考にしてみてください。
件名:忌引き休暇の申請について
本文:〇〇課〇〇課長
お疲れ様です。〇〇です。
昨日〇〇が他界したため〇日間の忌引き休暇を申請させていただきます。
期間:〇〇年〇月〇日~〇〇年〇月〇日
通夜の日程:〇月〇日〇時から
住所:〇〇市〇〇区1-2-3
告別式の日程:〇月〇日〇時から
住所:〇〇市〇〇区1-2-3
緊急連絡先:080-1234-〇〇〇〇
なお、忌引き休暇中のご連絡は上記の電話番号にお願いいたします。
お手数をお掛けいたしますがよろしくお願い申し上げます。
〇〇(差出人名前)
忌引きを取る時には取引先への連絡はメールでする
上司への連絡と同様に、取引先への連絡も早いに越したことはありません。取引先との今後の関係を良好に保つためにも連絡はきちんとしておく必要があります。
電話の方が丁寧な印象を与えますが、出張で不在の可能性や休みで会社にいないことも考えられます。すぐに電話で連絡を取れるとは限らないため、忌引きで休むことになったら取引先へはメールで連絡します。
迷惑が掛かる予定がある場合は取引先にメールする
取引先と共同で打ち合わせをする予定が入っていると忌引きで休むことで迷惑を掛けてしまいます。日程変更をする場合はもちろん、代理の方に引き継ぎをお願いしていたとしてもそのことを取引先に伝えておくのがマナーです。
メールには「お詫びと日時変更のお願い」「休む理由」「今後の対応及び代理人」の3点を書きます。上司への忌引き連絡と同じく件名で用件を書き、本文は簡潔にまとめます。
【例文】取引先に予定変更を伝えるメール
取引先へのメールの例文をご紹介します。
件名:合同会議の日程変更のお願い
本文:株式会社〇〇 営業部〇〇様
いつもお世話になっております。
株式会社●●の●●です。
今週水曜日の合同会議の日程の件でご連絡いたしました。
私事で大変恐縮ですが、身内に不幸がございましたので〇日まで休暇を頂くことになりました。誠に勝手なお願いですが日程の延期をお願いできないでしょうか。
私の不在中には弊社〇〇までご連絡いただければと存じます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社●●
●●(差出人名前)
取引先へのメールで使える柔らかい表現
上司への忌引きの連絡メールでは内容を簡潔にまとめるのがマナーですが、取引先に送る場合は少し違います。挨拶のあと、本題に入る前に柔らかい表現を使って謝罪の気持ちを入れます。
先ほどの例文であった「私事で大変恐縮ですが」「まことに勝手なお願いですが」がその一例です。ほかにも「心苦しいのですが」「差し支えなければ」といったクッション言葉があります。
忌引きメールを受け取った場合には返信してもよい
ここまでは忌引きメールを送る側の視点で解説を進めてきました。しかし場合によってはメールを受け取ることもあるでしょう。忌引きメールの内容は要件のみのため、返信すべきか迷う方もいるのではないでしょうか。基本的に忌引きメールには「お悔やみメール」で返信します。以下に例文をご紹介しますので参考にしてみてください。
「件名:〇〇(差出人)よりお悔やみ申し上げます
本文:ご身内に不幸があったと伺い、心からお悔やみ申し上げます。
仕事については引き継ぎますので心配しなくて大丈夫です。
ご冥福をお祈りいたします
このように相手を気遣う内容のメールを短くまとめて送ります。顔が見えないからこそ「気にしないでください、大丈夫ですよ」という返信をしてあげると送った方も安心します。
亡くなった人との親等・親族関係によって忌引き休暇の日数が変わる
「親戚であれば誰が亡くなっても忌引きが取れる」とお思いの方もいるかもしれませんが、会社の規則によっては忌引きが取れない場合もあります。どこまで休暇を認めるかは亡くなった方とご自身の親族関係で決められています。また、休暇中の賃金についても会社によって扱いが違うことはご存知でしょうか。
ここでは忌引き休暇制度の会社ごとの違いや休暇中の賃金の扱いについて解説します。
忌引き休暇日数は勤め先によって異なる
忌引き休暇は会社によって「慶弔休暇」「特別休暇」と呼ぶこともあります。民間企業では就業規則で取得できる日数を定めています。福利厚生としての扱いなので何日休めるかはそれぞれの会社が自由に決められます。喪主を務める場合とそうでない場合で取得可能日数が違うケースもあります。
公務員の場合は条例で忌引き休暇が定められています。条例の改正によって日数が変わることもあるので取得の際には毎回確認した方が安心です。
忌引き休暇日数と親族関係の一覧表
下記に一般的な忌引き休暇日数をまとめました。血族と姻族では扱いが異なり、血縁関係がないと最高でも3日程度しか取得できないことが多いです。また、2親等内の親族でも姻族は日数を1日としている場合があります。
会社によっては3親等の親族は忌引き休暇を設けていないことがあるので、休むときは忌引き休暇ではなく「有給休暇」もしくは「欠勤」扱いとなります。上司に忌引き申請のメールをする前に会社の規定を確認しておく方が良いでしょう。
| 続柄(等身) | 日数 |
| 配偶者(1) | 10 |
| 自分の両親(1) | 7 |
| 子供(1) | 5 |
| 配偶者の両親(1) | 3 |
| 自分の兄妹(2) | 3 |
| 自分の祖父母(2) | 3 |
| 配偶者の兄妹(2) | 1 |
| 配偶者の祖父母(2) | 1 |
| 孫(2) | 1 |
| 自分の叔父・叔母(3) | 1 |
| 自分の姪・甥(3) | 1 |
| 配偶者の姪・甥(3) | 1 |
忌引き休暇日数の法律的効果
実は忌引き休暇については法律で定めがありません。忌引き休暇を設けるかどうかは会社が決められるのです。さらに言うと、休んだ期間を有給扱いにするか無給にするかも自由に判断できます。そのため忌引きで休んだ期間が無給になる可能性があることを覚えておきましょう。
現在、9割の会社では従業員に忌引き休暇を取ることを認めています。しかし、就業規則で休暇中の賃金について明示していない会社もあるので、疑問に思うことがあれば総務や上司に確認するのがおすすめです。
(参考:『平成23年版 中小企業の賃金事情』/ http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/toukei/pdf/chincho23/pdf/27.pdf )
雇用形態により忌引き休暇が変わるケースもあるので注意
ここまでは忌引き休暇の取得日数は亡くなった方との続柄や勤め先によって異なることを解説しました。そのほかにも雇用形態によって違うことがあります。
民間企業ではパートタイマーやアルバイトは「週〇時間以上、1日〇時間以上の勤務をしていれば忌引き休暇を取得可能」と一定の条件を満たすことで取得を認めるケースや、「時給制の従業員は欠勤扱いとする」と雇用形態によって扱いが違うケースもあり注意が必要です。
公務員の場合、以前は常勤の職員しか休暇を取得できませんでしたが、2009年以降は6か月以上勤務していれば勤務時間や勤務日数に関わらず取得が可能です。
(参考:『国家公務員一般労働組合』/ http://www.kokko-net.org/kokkoippan/modules/02_QandA/index.php?category_id=16 )
忌引きを取る際には「提出書類」を合わせて確認しておく
会社によっては忌引き明けに「葬儀があったことを証明する書類」を提出します。規定にもよりますが、死亡診断書のコピー・会葬礼状・火葬許可証のいずれかもしくは2点以上を提出することが多いようです。証明書の提出がないと有給として取り扱わないとする会社もありますので注意しましょう。
また、提出期限が定められていて間に合わなければ受け付けてもらえないケースもあります。お礼状や香典返しの準備に追われて忘れてしまいがちですが、会社がスムーズに手続きできるよう必要書類を確認しておきましょう。
家族葬の場合は上司と相談を
もし家族葬をすることになったら、「参列はどの範囲までか」「香典は受け取るのか」を上司に伝えておきましょう。一般葬を行うとなると会社は従業員の訃報の知らせを受けて、社内に連絡を回して香典を募ったり参列者の手配をしたりするからです。
まず上司へ第一報のメールを入れるときに「家族葬であること」をきちんと書いておきましょう。一般葬ではメールに葬儀の場所を書きますが、家族葬で参列を遠慮していただくのであれば省略して構いません。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
忌引き明けの挨拶、忌引きを申請するときの連絡には一定のマナーがあります。急に休むことで周囲の方へ心配と迷惑を掛けることになるので、きちんとした対応をする必要があります。
そうは言っても会葬礼状や香典返しを1人で準備するのは大変です。「小さなお葬式」では葬儀に関するあらゆるご相談を受け付けております。24時間365日専門スタッフが常駐し、お客様の葬儀に関するお悩みを親身になってお伺いします。
何かご不明な点やお困りのことがあればぜひお気軽にご連絡ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



包む香典の金額は、故人・遺族との関係の深さ、年齢や社会的な立場で異なります。ホゥ。