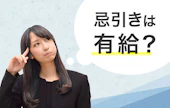アルバイトをしている時に身内が亡くなった場合、忌引き休暇を取得することはできるのでしょうか。身内の不幸は突然訪れることも多く、また初めての経験という場合もあり、「アルバイト先の職場へどのように対応し、連絡したら良いかわからない」という人もいるのではないでしょうか。
ここでは、忌引き休暇はアルバイトにも適用されるのか、身内が亡くなったときにはどのような対応をすれば良いのかを解説していきます。
<この記事の要点>
・忌引き休暇がアルバイトにも適用されるかどうかは会社の規定による
・忌引き休暇制度がない場合は有給休暇を使う
・忌引き休暇の日数は会社の就業規則によって異なる
こんな人におすすめ
アルバイトの忌引き休暇について知りたい方
アルバイトが取得できる忌引き休暇の日数を知りたい方
アルバイトが忌引き休暇を取得する際のマナーを知りたい方
アルバイトに忌引き休暇はあるのか
アルバイトに忌引き休暇があるのかについては会社によって異なるため、一概に「ある」「ない」と言うことはできません。忌引き休暇のルールを作成するのかについても会社が自由に決められるため、法律上必ず設定しなければならないものではないからです。
そのため、アルバイトだけではなく正社員や派遣社員であっても、忌引き休暇を使えるかどうかはそれぞれの会社によって違うので、まずは会社が定めているルールを確認しましょう。
まずは就業規則を確認
忌引き休暇を使えるかどうかを確認するには、就業規則をチェックしましょう。アルバイトにも忌引き休暇が適用されるのか、あるとすればどのような条件になっているのかなどが記載されています。
就業規則にアルバイトに対する忌引き休暇について記載があり、「何等親以内」などの条件を満たしている場合は、忌引き休暇を取得することができます。
忌引き休暇中の給与の扱いを調べる
忌引き休暇中の給与の有無については、会社の就業規定の内容によって変わります。
正社員の場合は「忌引き休暇を有給扱い」にしている会社も多くありますが、場合によっては無給扱いにしているところもあります。アルバイトの忌引き休暇に給料が出るかということも会社によって異なるため、就業規則を確認しましょう。
もしも無給であったとしても、忌引き休暇が無駄だというわけではありません。忌引き休暇は、身内に不幸があり急に休まなければならない場合であっても、休みを取ることができる権利です。有給無給に関わらず、不幸があった場合には忌引き休暇を利用しましょう。
アルバイトに忌引き休暇がない場合の対応
アルバイトに対する忌引き休暇の規定がない場合でも、休むためにはいくつかの方法があります。忌引き休暇がなく、急に仕事を休みにくいなどの理由でお通夜やお葬式に参列しなかった場合、後々後悔することにもなりかねません。
故人と最後のお別れをしっかりとしたいと思うのであれば、遠慮することなく休みを取りましょう。
有給を使う
アルバイトの忌引き休暇の決まりがない会社であっても、有給を利用して休みを取得することができます。忌引き休暇は法律上の義務ではないため、「アルバイトのための忌引き休暇のルール」を正式に定めていない会社も多くあります。
しかし、労働基準法では、「一定の条件を満たした労働者すべてに有給休暇を取得できる権利」を認めているため、アルバイトであっても法律上、有給休暇を申請する権利はあるのです。
もしも忌引き休暇が利用できない場合でも、有給休暇は取得できるという点を覚えておきましょう。
直属の上司に事情を説明する
アルバイトを始めてまだ日が浅く、有給休暇を取得できる状態ではない場合は、直属の上司に事情を説明しましょう。身内の不幸は悲しいことですが、人間だれしもが経験するものであるため、事情を話せば休ませてくれる場合がほとんどです。
しかし、日頃から上司が厳しく、「休む」と言いにくい場合であっても、無断欠勤は厳禁です。身内の不幸は予想できないことではありますが、突然アルバイトを休むことで職場や同僚に迷惑をかけてしまう場合もあります。
訃報を知ったら、できるだけ早くアルバイト先に連絡をして事情を説明し、休むことを伝えましょう。
シフトの確認をしておく
身内の不幸で急に休む場合、職場で働く人の負担が増えてしまうこともあるため、できればシフトの確認をするなどの気配りができるとより良いでしょう。
シフトを確認し、自分の代わりに入ってくれそうな人はいるか、それが誰かということをあらかじめ確認して伝えることが出来れば、上司もシフトの調整などがしやすくなります。
「今日休みの人はAさんとBさんで、かわりに出勤してもらえるかもしれません」と事前に調べてから連絡をすることで、上司もすぐにシフトの調整や確認ができ、あなたの職場に対する配慮も伝わります。
アルバイトが取得できる忌引き休暇の日数
アルバイトが取得できる忌引き休暇の長さは、それぞれの会社の就業規則によるため、まずはその内容を確認しましょう。
| 配偶者 | 10日 |
| 父母 | 7日 |
| 子 | 5日 |
| 兄弟姉妹 | 3日 |
| 祖父母 | 3日 |
葬儀が遠方で行われる場合は、移動にも時間がかかります。忌引き休暇よりも多くの日数が必要になる場合は事情を説明し、有給休暇を組み合わせるなど、休みをとる方法を上司と相談するようにしましょう。
アルバイトが忌引き休暇を取得する場合のマナー
アルバイトであっても、忌引き休暇を取得することで職場に迷惑をかけてしまう場合もあります。忌引き休暇を取得したいと口頭で伝えるときには、上司や同僚が不快にならないような言い方を心がけ、職場の負担をできるだけ軽くするように努めましょう。
挨拶をメールだけにしない
忌引き休暇を取りたいと申し出る場合、メールではなく、上司に直接電話で事情を伝えましょう。電話では、下記の4点を伝えます。
・誰が亡くなったのか
・通夜や葬儀の日にち
・大まかな場所(遠方かどうか)
・必要な休みの日数
特に、長めの休暇が必要な場合は早めに伝えておくと、上司もそれを見越したシフトの調整などがしやすくなります。
連絡は電話ですることが基本ですが、訃報が夜中だった場合は、「できるだけ早く知らせる」という意味でまずはメールをし、翌日になってからあらためて電話をするという方法でも良いでしょう。
余裕があれば自分でシフト調整をする
忌引き休暇を利用する場合、余裕があれば自分でシフト調整を行いましょう。数日にわたる場合、すべての調整をすることは難しいかもしれませんが、忌引き休暇の最初の日だけでも代わりに入ってくれる人を見つけておくことで、上司や同僚の負担はぐっと軽くなります。もちろん、そのような調整をする余裕がない場合は無理に行う必要はありません。
忌引き休暇を使うときに大切なことは、「代わりの人を見つけやすいように、できるだけ早く上司に伝える」ということです。その上で余裕がある場合のみ、自分でシフトの確認や調整を行いましょう。
アルバイトが忌引き休暇を申請する際に必要な書類
アルバイトが忌引き休暇を申請する際には、特に必要な書類はなく、上司に口頭で伝えれば十分です。
しかし、「忌引き」と嘘をついて休みを取る人もまれにいるため、アルバイトであっても「葬儀が行われたことを証明する書類の提出」が必要な場合があります。
ほとんどの場合は書類の提出は必要ありませんが、忌引き休暇を取る際には、必要な書類の有無についても確認をしておきましょう。
会葬礼状
葬儀が行われたことを証明できる書類として、「会葬礼状」があります。会葬礼状は、お通夜やお葬式に参列した人に渡される返礼品に添えられている礼状です。故人の名前や日付、葬儀場の名前が記されているため、証明書として説得力があります。
会葬礼状は、特別な手続きは必要なく簡単に手に入るため、葬儀会社に確認しましょう。ただし、家族葬の場合は会葬礼状を作らないため、別の証明書を検討しましょう。
訃報施行証明書または葬儀施行証明
訃報や葬儀施行証明書は葬儀社が発行するもので、葬儀が行われたことを証明してくれる書類です。決まった形式はないため、下記の点を記載して社印を押してもらうと良いでしょう。
・葬儀日時
・葬儀会場
・故人名
・喪主名
・葬儀社名
死亡診断書
死亡診断書は医師が発行する正式なものですので、忌引き休暇の証明書類としても十分です。しかし、死亡診断書は火葬許可証を取るために必要な書類のため、死亡してすぐに役所に提出する必要があります。
原本は提出すると手元に戻ってこないため、書類が必要であれば役所に提出する前にコピーをとるようにしましょう。
また、死亡診断書には本人の氏名はもちろんのこと、死因など、非常にプライベートな内容も記載されています。
会社に提出すると、上司だけではなく総務など、色々な人の目に触れる可能性があります。そのため、もしも見られたくない項目があれば、黒く塗りつぶして提出するようにしましょう。
火葬許可証
火葬許可証は、死亡診断書と同じように正式な書類になるため、忌引き休暇の証明書類と認められます。こちらも火葬場で提出しなければならない重要な書類になるため、必要な場合はコピーをとっておきましょう。
この火葬許可証は火葬場や納骨時に必要で、再発行が難しい重要な書類です。紛失しないように気を付けましょう。
忌引き明けのアルバイト初日は必ず挨拶を行う
忌引き休暇があけて最初にアルバイトに行ったときには、まずは上司のもとに行き、迷惑をかけてしまい申し訳なかったという謝罪の気持ちと、快く休ませてくれたこと、しっかりと故人とお別れができたことなどへの感謝の気持ちを伝えましょう。
また、自分の代わりにシフトに入ってくれた人や、迷惑をかけてしまった同僚にも「自分の代わりに仕事をがんばってくれた感謝」を伝えるようにしましょう。
お礼として、小分けになっていて皆で分けられるような菓子折りなどを持参すると、より感謝の気持ちを伝えることができるでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
身内に突然の不幸があると、気持ちが動転し、焦ってしまうこともあるでしょう。しかし、アルバイトを休むことで職場や同僚へ迷惑をかけてしまうことも考えられるため、配慮をしながら、適切な対応をとることが大切です。
忌引き休暇を申請した場合、協力してくれた上司や同僚への感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



御霊前は「亡くなった方の霊魂の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。