葬儀費用が相続税控除の対象になると聞いて、位牌の料金を含めるかどうか迷っている方もいるのではないでしょうか。位牌は数万円するものも多く、控除に含めることができれば控除額がかなりアップするでしょう。
結論から言うと、位牌は葬儀費用には含まれません。ただし、葬儀に使用する白木位牌のみは例外で、費用に含められます。葬儀費用と相続税の控除の関係は、複雑で線引きが難しい所です。詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
<この記事の要点>
・相続税から葬儀費用の控除は、相続財産にかかる税を下げ遺族の負担を軽くする目的がある
・葬儀費用には、葬儀に直接関わる必須のものが含まれる
・位牌の中で「白木位牌」だけは葬儀費用に含めることが可能で、相続税控除の対象
こんな人におすすめ
相続税の控除対象になる葬儀費用について知りたい方
位牌の制作費用を知りたい方
位牌が必要になるタイミングを知りたい方
葬儀費用は相続税控除の対象になる!定義や内容について紹介
そもそも「相続税から葬儀費用を控除する」とは、相続する財産にかかる税を下げる(差し引く)ということです。
相続手続き前の財産は動かすことが基本的にできなかったので、高額な葬儀費用を控除の対象として遺族の負担を軽くする目的があります。
具体的な内容は、相続税法第13条第4項と第5項に葬式費用に含まれるものと含まれないものの例として記載されていますが、原文そのままだと難解なので噛み砕いて解説していきます。
葬儀費用に含まれるもの
条文を噛み砕いて説明すると、葬儀費用に含まれるのは葬儀に直接関わる(必須の)ものです。
葬式とお通夜など「式の費用」
式中に振舞う「飲食代」(精進落とし)
読経料と戒名料を含む「お布施」
式場から火葬場までの「遺骸の回送日」
火葬や納骨などの「埋葬費」
行方不明時の「捜索費・運搬費」
具体的にはこれらが該当します。領収書を取っておければベストですが、難しい場合でも相続税の控除対象となるので、金額を必ずメモしておきましょう。
葬儀費用に含まれないもの
葬儀に必須ではないものは、葬儀費用に含まれない場合が多いです。
香典返しの費用
お墓等の仏具の料金
葬儀後の法要にかかる費用
裁判に必要な解剖費用
具体的にはこれらが該当します。どれも式を執り行うのに必須ではありませんが、殆どの場合は必要になる費用です。これらは相続税控除の対象外なので、混同しないように気をつけてください。
<関連記事>
葬儀費用で相続税から控除できる費用とできない費用とは?
位牌は葬儀費用に含まれる?
位牌は葬儀後に仏壇に供える仏具のひとつなので、基本的には葬儀費用に含まれません。お墓等と同じく、葬儀後に使用する物としてカウントされています。
しかし「白木位牌」だけは葬儀費用に含めることが可能で、相続税控除の対象です。白木位牌は葬儀自体に必須の仏具であるため、特別に控除が認められています。
両者の違いは何なのか、使用する場面と一緒に解説していきます。
白木位牌は葬儀費用に含まれる
そもそも白木位牌とは、四十九日までの間だけ故人の魂を留めておく簡素な白木の位牌のことです。葬儀中に使用し、火葬場まで持ち歩くこともあります。
予期せぬ葬儀のため、ひとまず用意した仮の位牌という意味から「仮位牌」とも呼ばれています。白木位牌は葬儀に使用するため、相続税控除の対象です。使用した金額は必ずメモしておきましょう。
本位牌は葬儀費用に含まれない
白木位牌はあくまで仮の位牌なので、四十九日の法要にてしっかりと装飾が施された位牌に魂を移されます。
これらの位牌は大きく分けて5つの種類に分かれますが、全てまとめて「本位牌」と呼ばれる白木位牌とは別の物です。本位牌は葬儀には使用しないので、相続税控除の対象にはなりません。
故人一人に対して、仮位牌と本位牌の2種類が必要になるので気をつけましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
【6種類】位牌の制作費用はいくら?
位牌には白木位牌(1種類)と本位牌(5種類)があり、制作費用は均一ではありません。
同じ種類の位牌の中でも金額には多少の差が生まれるので、まずは平均的な制作費用を解説していきます。高級な日本製位牌の場合、かなり高額になる可能性があるので、購入する前に複数見比べてみましょう。
位牌は故人を祀るための仏具なので、好みや特徴にあった物を探してみてください。
1. 白木位牌の制作費用
白木位牌は葬儀に使用する仮のものなので作りが簡素な場合が多く、制作費用は2,000円~3,000円程度が相場です。
白木位牌は葬儀に使用する都合上、場合によっては緊急で用意する必要があるかもしれません。用意する時間がない場合、通販で取り寄せることも可能なので覚えておきましょう。
2. 塗り位牌の制作費用
塗り位牌は、木材に漆を塗って作った本位牌の一つです。金粉等で装飾が施され高級感を感じさせます。
使用するものが本漆か合成漆かで大きく値段が変わりますが、1万円~3万円程度が相場です。
3. 蒔絵位牌の制作費用
蒔絵位牌は、塗り位牌に蒔絵を描いた本位牌の一つです。彩り豊かな蒔絵が華やかな印象を感じさせます。
塗り位牌同様、使用する漆によって金額に差が生まれ、蒔絵の分だけ少し値段が上がり2万円~5万円が相場です。
4. 唐木位牌の制作費用
唐木位牌は、唐木と呼ばれる高級木材(黒檀、紫檀など)を使って作られた本位牌の一つです。漆を塗らずに作られるので、木目の風合いを感じることができます。
唐木位牌に使用される高級木材は頑丈で、漆が剥がれることもないので耐久性に優れています。
木目の美しさや色の鮮やかさで大きく値段が変わりますが、2万円~5万円が相場です。
5. モダン位牌の制作費用
モダン位牌は従来の位牌のデザインに囚われない様々な位牌の総称です。素材も様々で、木ではなくガラスや金属の位牌もモダン位牌に含まれます。
故人の好みや特徴に合わせた位牌を選ぶことが可能で、洋室に溶け込こむインテリアの様に見せられます。
使用する素材や作りによって値段は上下しますが、1万円~3万円が相場です。
6. 繰出位牌の制作費用
繰出位牌は、複数人をまとめて管理するための特殊な位牌です。故人一人に対して位牌は一つが基本ですが、位牌が増えすぎて管理しきれなくなったり、位牌が古くなったりして劣化してしまうことを防ぐために繰出位牌があります。
一般的には三十三回忌や五十回忌を迎えたご先祖さまをまとめるために使用される位牌で、故人を他の本位牌から礼板(木の板)に移した後に繰出位牌に収納してひとつにまとめます。必ず利用する位牌ではありませんが、3万円~5万円が相場です。
<関連記事>
種類豊富な位牌の中から故人にぴったりのものを選ぶ方法
位牌には追加で「文字料金」が発生することがあるので注意
位牌は購入しただけでは無地の状態で、使用できません。名前を記入して初めて、故人の位牌として使用できます。
故人のために位牌を奮発して購入したとしても、名前を記入できなければ意味がありません。この時「文字料金」が発生する場合があるので気をつけましょう。
文字料金は以下の3パターンに分かれます。
・文字代込パターン
・文字代一律パターン
・文字数毎パターン
位牌の料金に文字代込みであれば良いですが、文字料金が別にかかる場合は購入先によって料金設定が変わります。
位牌を購入する前に、文字料金について必ず確認するようにしてください。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
位牌が必要なタイミングとは。ルールについて再確認
位牌は古来より故人を祀るための仏具であり、その起源は中国の「木簡」と呼ばれる木札にさかのぼります。位牌は乱雑に扱って良いものではなく、いくつかのルールに則って用意するものなので注意しましょう。
宗派によっては位牌が不要であったり、位牌を複数個作れたりする場合もあります。位牌を用意する前に知っておきたい、3つのルールをご紹介するので忘れずにチェックしてください。
浄土真宗の位牌は必須ではない
浄土真宗の教えでは、死者の魂は現世に留まることなく即座に成仏するものとされています。そのため故人を祀るための位牌は必要ありません。
しかし浄土真宗だからといって、位牌の作成を禁止しているとは限りません。細かい取り決めはお寺によって異なるため、故人を振り返るのに位牌が欲しいのであれば相談してみましょう。
<関連記事>
「どの宗派でも位牌は好みの種類を選んでよい」は本当に正しいか
本位牌は四十九日までに用意する
葬儀の段階では白木位牌を用いて、本位牌に移るのは四十九日の法要が一般的です。
そのため本位牌は四十九日に間に合うように準備しておく必要があります。位牌は購入後に文字入れをする必要があり、直前に申し込むと間に合わないかもしれないので、先に購入と文字入れを済ませておきましょう。
<関連記事>
四十九日法要までの流れと基礎知識|意味、必要な費用、服装や香典のマナー
位牌は「位牌分け」で複数個作れる
故人一人に対して位牌は一つが基本ではありますが、宗派によっては位牌を複数作る「位牌分け」をしても良い場合があります。
遠方に住む親族が、自宅でも故人に手を合わせるために位牌分けは行われることが多く、個数に制限はありません。
ただし位牌分け自体が認められない場合もあるので、事前にお寺に確認しておきましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
葬儀費用は相続税の控除対象となります。ただし式の後に使用する本位牌は葬儀費用には含まれません。葬儀に利用する白木位牌のみ費用に含めて、相続税控除を受けることが可能です。
本位牌は数万円する物ですが、今後何十年と使用する物です。故人のためにしっかりとした物を用意すると良いでしょう。
位牌は種類が豊富なので、故人を思い出せるような良い位牌をぜひ探してみてください。位牌は小さなお葬式にてお取り扱いがあります。お気軽にご相談ください。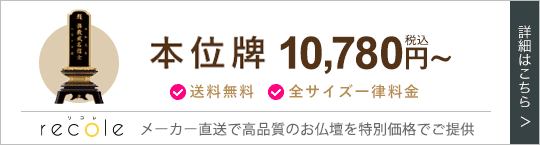
位牌に関する疑問以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


不祝儀袋は、包む金額に合わせて選ぶと丁寧です。ホゥ。





























