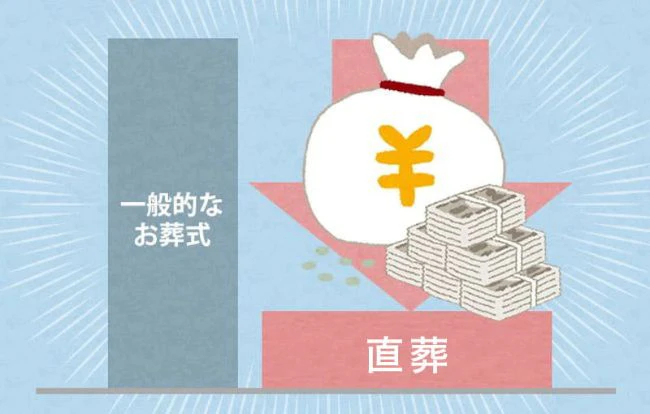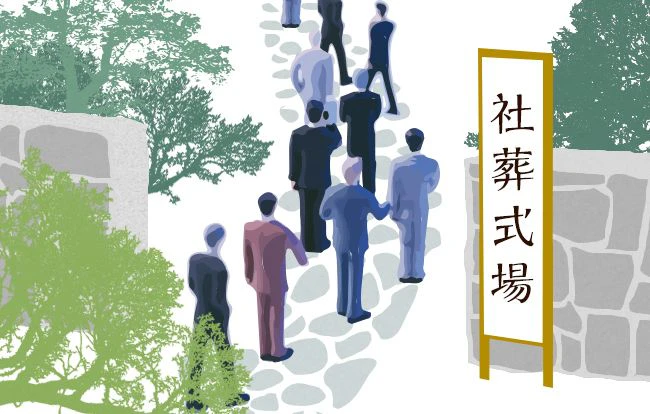葬儀のとき、喪主や遺族は悲しみに浸る余裕もないほど忙しい場合も少なくありません。特に、喪主や遺族として葬儀に関わるのは初めてという方の中には、葬儀の手順やマナーが分からずに困っている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、葬儀の中でも火葬にスポットを当てて、火葬の準備に必要な情報について解説します。火葬にかかる時間や手順、準備が分かれば、後悔することのない葬儀を執り行えるでしょう。
<この記事の要点>
・火葬にかかる時間は40分~1時間半ほどが目安
・市町村役場で申請できる火葬許可証がなければ火葬はできない
・火葬場への同行は喪主や遺族の許可が必要で、希望者全員が同行できるわけではない
こんな人におすすめ
火葬にかかる時間を知りたい方
火葬の流れについて知りたい方
火葬の待ち時間の準備とマナーを知りたい方
火葬にはどれくらいの時間がかかるの?
葬儀のタイムスケジュールを考える上で、火葬にかかる時間を知っておくことは重要です。ここでは、火葬にかかる時間の目安を紹介します。
待ち時間の使い方や次の段取りを決める参考になるでしょう。さらに、ペットの火葬についても簡単に紹介します。家族同然のペットが亡くなったときに役立つ情報です。
火葬にかかる時間の目安
火葬は40分から1時間半ほどかかります。これはお骨が冷えるまでの時間です。火葬が終わると骨上げへと続きます。タイムスケジュールを組む場合、火葬場での滞在時間として2時間ほどを見ておくとよいでしょう。
火葬の時間に幅があるのは、遺体の体格や炉の種類、副葬品の違いによるものです。遺体に脂肪が多いと温度調整が必要な場合があり、その分時間がかかります。副葬品も種類や量によっては燃えにくく、時間がかかる要因のひとつです。
ペットの火葬にかかる時間
ペットは種類によって大きさにかなりの差があるため、火葬にかかる時間も30分~3時間と幅があります。ハムスターのような小動物は30分前後、猫や小型犬は45分~1時間、中型犬は1時間~1時間半、大型犬は1時間~3時間が目安です。
ペットの火葬に関しては、火葬場によって対応が異なります。「ペットを受け入れていない」「お骨の引き取りができない」「引き受けるペットの大きさに制限を設けている」といった違いです。家族として弔いたいのであれば、事前確認は欠かせません。
<関連記事>
いま注目される最新のお葬式事情とは?犬などのペット火葬についても解説
【火葬の流れ】火葬場では待ち時間も有効に使う
葬儀が終わると出棺です。出棺以降の大まかな流れを見てみましょう。押さえておきたいポイントは待ち時間の使い方です。
ここでは、火葬場での動きと基本的なマナーを紹介します。なお、葬儀の前に火葬を行う「骨葬」を習わしとする地域もあり、全てが同じ流れではないことにご注意ください。火葬場ですることは同じです。
出棺から火葬場への移動
出棺と火葬場への移動にかかる時間は30分から1時間ほどです。同行者の人数は、事前に確認しておきましょう。後片付けや遺骨を迎える準備をするのは葬儀場に残る親族です。棺を霊柩車に移したら、喪主か親族の代表者が会葬者に出棺の挨拶をします。
霊柩車に乗るのは喪主です。霊柩車に喪主が乗らない場合には、僧侶や遺影を持った親族代表と共に他の車に乗り込み、霊柩車に続きます。その後に続くのが、他の親族や友人の車です。
火葬場に着いたら火葬許可証を提出します。分骨する場合には、必要枚数分の分骨証明書を申請しなければなりません。火葬場でも直接申請できますが、葬儀社とあらかじめ打ち合わせておくとスムーズです。
納めの式
納めの式をするのは、炉の前です。最後の別れとなりますが、出棺時にすでに別れは済ませているため、長い時間をかけることはありません。
位牌と遺影を飾り、喪主、遺族、近親者、その他の参列者の順に焼香・合掌・拝礼をします。僧侶が同伴しているときは焼香の前に読経をしてもらいますが、同伴しないケースでは読経はありません。
故人の顔を見たいのであれば、納めの式が最後のチャンスです。なお、火葬場の決まりや宗旨によっては、納めの式をしないこともあります。
火葬
納めの式が終わると、いよいよお別れです。ボタンは火葬場の職員が押すことがほとんどですが、遺族に勧める場合もあります。喪主が押すべきと思われがちですが、他の親族が押しても問題ありません。喪主の悲しみが深く心情的に難しいときには、代わりに押してあげてもよいでしょう。
なお、このときに押すボタンは点火スイッチの操作を可能にする解除ボタン、あるいは炉を操作する職員に合図をするボタンです。点火そのものを行う「点火スイッチ」ではありません。
遺族が炉の鍵を預かるケースもあります。火葬が終わったら返さなければならないため、預かった方はなくさないように注意しましょう。
<関連記事>
火葬とは?流れやマナーを徹底解説
待ち時間
火葬が始まったら、ロビーや控室で待機します。待ち時間の目安は40分~1時間半です。火葬が終わるのを待ちながら、足を運んでくれた僧侶や参列者をもてなしましょう。火葬場によって施設やルールが異なるため、事前に確認する必要があります。
火葬場に併設されているカフェやお食事処を利用するのであれば、食事を用意しなくても構いません。控室でもてなす場合、軽食やお菓子、精進落としの食事といった準備が必要です。仕出し業者の入っている火葬場もあります。
骨上げ
「骨上げ」とは、お骨を骨壺に納める儀式のことです。火葬の終了が知らされたら、骨上げのために収骨室へ向かいましょう。骨上げにかかる時間の目安は30分ほどです。
収骨室では参列者全員で遺骨を囲みます。喪主は遺骨の頭のほうに立ちましょう。心情的に骨上げがどうしてもできないという方は、見守るだけでも構いません。
拾うお骨の順番や量、拾い方といった骨上げの手順には地域差があります。火葬場の職員が教えてくれる通りにすれば問題ありません。
骨上げが終わると、職員が骨壺の蓋を閉めて包んでくれます。骨壺を収めた白木の箱には埋葬許可証が入っているため、なくさないように注意しましょう。
<関連記事>
火葬後の骨上げについて知っておきたい手順とマナー
小さなお葬式で葬儀場をさがす
【火葬の待ち時間】知っておきたい準備とマナー
火葬の待ち時間をどう使うかによって、火葬後のスケジュールや持参品が違ってきます。火葬場の設備や葬儀の規模、家族の状況はそれぞれ異なるため、自分たちに合った方法をチョイスすることが大切です。地域独特のしきたりがある場合もあります。親族や葬儀社とよく話し合っておけば、スムーズな段取りができるでしょう。
待ち時間をどう使うか決めておく
待ち時間の使い方は、飲食が可能かどうかで選択肢が分かれます。火葬場の控室が「飲食可」であれば、持ち込みのお菓子や飲み物、仕出し弁当の手配が可能です。
「飲食可」でも「アルコールは不可」というケースもあるため、注意しましょう。火葬場併設のカフェやお食事処を利用する方法もあります。
「飲食不可」の場合、火葬場の近くのカフェに移動したり、一度葬儀場に戻ったりしてもよいでしょう。
精進落としは火葬中に済ませる地域も
精進落としは、もともと四十九日の忌明けに精進料理から通常の料理に戻る区切りとして行われていた儀式です。
その儀式が時代と共に、初七日法要の際に僧侶や参列者をねぎらう宴席へと意味合いを変えました。最近は葬儀当日に繰り上げ初七日法要を執り行うケースが多いため、火葬後に精進落としをすることも多いでしょう。
火葬の後ではなく、火葬中に精進落としをするという地域もあります。時間の節約となるため、遠方に住んでいて葬儀後はゆっくりできないという近親者には、特に喜ばれるかもしれません。
精進落としの準備
火葬の待ち時間に精進落としをする場合、人数分の食事と飲み物を準備しなければなりません。飲食が禁止されている火葬場であれば、一度葬儀場に戻ります。
外食を予約してもよいでしょう。精進落としではアルコールを振る舞うのが一般的です。ただし、飲酒を禁止している火葬場もあるため、よく確認しておきましょう。
メニューは仕出し弁当や寿司、懐石料理といった選択肢があります。洋食や中華でも構いません。肉や魚は禁じられていませんが、鯛や海老といったお祝いの席でよく使われる食材は避けたほうが無難です。
<関連記事>
精進落としのマナーや流れについて解説!注意点もあわせて紹介
僧侶が会食を辞退したら
僧侶が火葬場に同伴しなかったり精進落としに同席できなかったりする場合もあります。精進落としには僧侶や参列者をねぎらうという意味があるため、残念に思うかもしれませんが、特殊なケースではありません。
僧侶が会食を辞退したときは、無理に引き止めずに「御膳料」を「お車代」と一緒にお渡ししましょう。御膳料の目安は5,000円~1万円ほど、お車代の目安は1万円程度です。金額は地域や関係性によって異なるため、迷ったときは周囲の方に相談するとよいでしょう。
火葬についての豆知識【準備編】
火葬場への同行者は限られているため、そこで行われることを目にする機会はあまりありません。喪主や遺族として葬儀の準備をする立場になると、火葬に関するさまざまな疑問を抱くこともあるでしょう。ここでは、知っておくと役立つ火葬に関する豆知識を取り上げます。
火葬許可証はどうやって手に入れるの?
火葬許可証がなければ火葬はできません。火葬許可証は市町村役場で入手します。故人の本籍地や死亡地だけでなく、届出人の住所地にある役場でも手続き可能です。
申請は死亡届の提出と同時に行います。死亡届は「死亡診断書(死体検案書)」と一体になっており、死後7日以内に提出しなければなりません。死亡届を提出できるのは、親族や同居人、家主や地主、後見人です。
委任状があれば代理人による申請もできます。葬儀社に代理申請を依頼しておけば、負担が軽くなるでしょう。なお、海外で亡くなった場合、現地大使館で手続きします。
希望日時に火葬場の予約は可能?
火葬場は1日に扱える件数が決まっています。空きがないと希望日には予約できません。特に人口が集中する大都市では混雑が顕著で、火葬まで死後1週間以上待たなければならないケースもあるほどです。
公営火葬場のほうが料金は安いですが、その分人気があり、混雑しています。できるだけ早く火葬したいのであれば、民営火葬場を当たってみましょう。
火葬まで日数がある場合、遺体を安置する場所を考えなければなりません。自宅で安置するのであれば、ドライアイスが必要です。葬儀社が所有する遺体安置所や民間の遺体保管所もあります。
希望すれば誰でも火葬場に同行できる?
火葬場は最後の別れの場となるため、親しい間柄であれば同行したいと考える方もいるでしょう。
しかし、希望者全てが火葬場に同行できるわけではありません。喪主や遺族の許可が必要です。「ごく数人の近親者のみで見送りたい」と断られる場合もあります。遺族の気持ちを優先し、無理なお願いをして困らせないようにしましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
火葬についての豆知識【礼法編】
日本でできる埋葬方法には、火葬と土葬とがあります。しかし、厳しい条件がある土葬を選ぶ方はまれです。
火葬には火葬ならではのルールやしきたりがあります。ここで紹介するのは、ルールやしきたりにまつわる豆知識です。しきたりには地域差があるため、周囲の方に尋ねたり葬儀社と相談したりしながら準備を進めましょう。
副葬品として入れてはいけないものとは?
遺体の入った棺の中には、思い出の品や花といった副葬品を一緒に納めることがあります。副葬品は遺体と一緒に焼くため、火葬に適していない物品は入れられません。
また、燃え残ったり、お骨を変色させたりする物品も入れないほうがよいでしょう。体内にある医療機器は熱で爆発する恐れがあります。ペースメーカーが入っている場合、葬儀社や火葬場の職員に伝えておかなければなりません。
| 入れてはいけないもの | 入れないほうがよいもの |
| ・ガラス製品 ・金属製品 ・プラスチック製品 ・ダイオキシンが発生するもの |
・本やアルバム ・お金 ・水分の多い果物 ・革製品 |
「骨葬」とは何?
お葬式というと、通夜、葬儀、火葬という順番をイメージする方が多いでしょう。一方、「骨葬」は少し違っていて、通夜、火葬、葬儀という順番です。葬儀会場の祭壇には、遺体ではなく骨壺や位牌が祀られます。
骨葬のメリットは、遺体の損傷を気にする必要がないことです。火葬と葬儀の日を分けられるため、混雑しない時間帯に火葬を済ませ、希望の日時に葬儀を執り行えます。
骨葬が一般的である地域もありますが、なじみのない方も少なくありません。驚かせないためにも、葬儀のお知らせの際は火葬の後に葬儀があることを明記するとよいでしょう。
<関連記事>
火葬を先に行う「骨葬」が行われるケースや特徴、費用について
骨壺にサイズがあるの?
骨壺には2寸(直径約65mm)から尺寸(直径約315mm)まで、さまざまなサイズがあります。分骨や手元供養には2寸~4寸の小さめ、一般納骨用は5寸~7寸、改葬で複数の方の納骨を合同でする場合には8寸~尺寸と使い分けるのが一般的です。男女差や体格差で区別することはありません。
また、地域差もあります。東日本で広く見られる全ての遺骨を収骨する慣習がある場合に使用する骨壺は、大きめの7寸サイズです。
一方、遺骨の一部を骨壺に納める地域では、それより小さな骨壺を使います。さらに、納骨する場所の大きさにも合わせなければなりません。骨壺を準備する際は、地元の慣習や納骨場所も確認しましょう。
感染症で亡くなると24時間以内の火葬?
通常、死後24時間以内に遺体を火葬することは法律上できません。ただし、指定感染症で亡くなった場合、特例として24時間以内の火葬が許可されています。とはいえ、必須ではありません。火葬場の状況や遺族の事情を考え併せながら決めるとよいでしょう。
葬儀社や火葬場の関係者には、指定感染症で亡くなったことをはっきりと伝えます。葬儀社や火葬場は、政府より特別な対応が指示されているためです。
医療関係者や遺族と連携して、手順や方法を調整しなければなりません。葬儀社や火葬場の指示に従うことで、スムーズなお見送りができるでしょう。
安心して火葬を執り行うポイント
火葬に関わるマナーや手順は、遺族の事情や火葬場の混雑具合、葬儀の規模といったさまざまな要因で変わります。地域ごとに慣習も異なるため、喪主の居住地と火葬する地域が違う場合、トラブルが起きる恐れもあるでしょう。
安心して火葬を執り行うには、信頼できる葬儀社を選ぶことが大切です。葬儀社は地元の慣習や特殊なケースの取り扱いに精通しています。
何でも相談しながら決めると安心です。また、火葬をはじめ、葬儀ではさまざまな手続きをしなければなりません。煩雑な手続きの多くを葬儀社に代行してもらえば、遺族の負担が軽減できます。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
火葬にかかる時間は故人の体格や炉の種類によって異なりますが、おおよそ40分~1時間半で、火葬場の滞在時間は2時間ほどです。火葬の流れや準備するものは地域差があるため、喪主の居住地と火葬地が違う場合には特に注意しましょう。
小さなお葬式では、葬儀と火葬がセットになった一般葬から火葬のみのお式まで、さまざまなプランをご用意しています。納得の価格と丁寧な対応で、気持ちのよいお見送りをサポートする小さなお葬式をぜひご利用ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



亡くなった方や仏に向けて、香を焚いて拝む行為を焼香(しょうこう)といいます。ホゥ。