亡くなった方を供養する方法といえば、お墓や納骨堂など、遺骨を保管してある場所に出向いて手を合わせる方法が一般的です。
しかし、お墓が遠方にあって出向くことが難しい方や、新しくお墓を用意することができない方もいるでしょう。そういった方にぴったりの供養方法が、手元供養(てもとくよう)です。この記事では、供養の選択肢のひとつとして手元供養を始めるために知っておきたいことをご紹介します。
<この記事の要点>
・手元供養には、遺骨や遺灰を自宅で保管する方法と、一部を納骨して一部を自宅で保管する方法がある
・手元供養することで、常に故人を身近に感じることができる
・手元供養は新しい供養方法であるため、家族の理解を得られない場合がある
こんな人におすすめ
手元供養をご検討中の方
手元供養の種類について知りたい方
手元供養のメリットとデメリットを知りたい方
手元供養の方法には2種類ある
手元供養は、遺骨・遺灰を自宅で管理するという方法のことで、自宅供養(じたくくよう)とも呼ばれます。その保管方法は2種類あります。
1.遺骨や遺灰の全てを自宅で保管する
2.墓地や寺院へ納骨した上で、一部だけ自宅で保管する
どちらを選ぶかは、人それぞれの供養に対する意識によりますが、ひとつの選択の基準として、信仰心の深さで寺院での供養を選ぶこともあります。また、成仏できないのではと遺骨を分けることへ不安を持つ方も少なくありません。しかし、仏教では昔から「分骨」が一般的に行われているため問題ないといえるでしょう。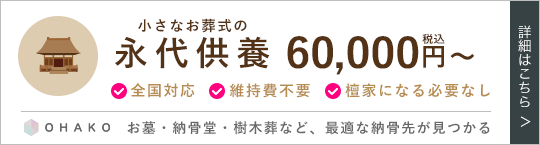
手元供養をするメリット
手元供養には、お墓での供養にはないメリットがあります。
故人を身近に感じられる
遺骨や遺灰を自宅で保管することで、常に故人をそばに感じることができます。手元供養を選択された方の中には、「暗いお墓の中ではかわいそう」といった意見もあり、故人とのこれまでの関係性を大切にされる方にとって大きなメリットとなります。
遠方へ出向かずに供養ができる
引っ越しや、体調が優れない場合などに、お墓や寺院などに納骨している場合は出向くことが難しくなることもあります。距離や時間を気にすることなく供養ができます。
費用を抑えられる
新しくお墓を建てるのであれば、最低でも100万円程度の費用がかかります。それに対して、手元供養は必ず必要となる物品はないため、供養の仕方によってはほとんど費用をかけずに供養することが可能です。
保管場所に困らない
遺骨を納める骨壺やアクセサリー類はコンパクトなものが主流であり、保管場所に困らないこともメリットです。例えば、ミニ骨壺と呼ばれる骨壺は、棚やテーブルの狭いスペースにも置けるでしょう。また、ペンダントのように身に付けられるものや、一般的な住宅のインテリアになじみやすいプレート型のものもあります。
保管場所に困らないことは、将来的に引っ越しをしたり高齢者向けの施設などに移ったりすることを考えたときにも安心です。
手元供養をする際の注意点
手元供養をする際には、お墓や仏壇にはない注意点があります。特に、周囲の理解を得ることや保管に気を使うことは大切です。ここでは、トラブルにならないために知っておきたいポイントをまとめました。
家族や親族の理解を得られない場合がある
手元供養が選ばれるようになったのはここ10年ほどのことで、比較的新しい供養の形であるといえます。そのため、反対する家族や親族は少なくありません。特に、日本では「遺骨はお墓に納めるもの」というイメージが強く、年配の方ほど手元供養に抵抗を感じる傾向です。
こうしたことを踏まえると、家族や親族の理解を得られないケースがあることを想定したほうがよいでしょう。その時は強引に進めず、ご自身や遺族の気持ちを丁寧に伝え、しっかりと話し合いをした上で決めることが大切です。
紛失するリスクがある
身に着けるタイプの手元供養品は、紛失リスクが高くなります。例えば、携帯できるミニ骨壺を入れたバッグを置き忘れたり、遺骨を入れたペンダントの鎖が切れて知らない間に紛失してしまったりすることもあるでしょう。
また自宅保管のタイプでも、洪水や地震などの災害で失ってしまう可能性はゼロではありません。こうしたリスクがあることを知った上で、責任を持って大切に保管し続けることが必要です。
骨壺のカビなどに注意するため保管場所に気を付ける
遺骨にカビが生えるトラブルは多く、保管場所には注意が必要です。カビは高温多湿の環境を好むため、お風呂場やキッチンの近くやクローゼットの中などを避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所を選びます。
また保管容器の内と外で温度差が生じると、結露が発生してカビの原因になるでしょう。エアコンの風が直接当たる位置などは、冷房を稼働させた際に温度差が生じて結露しやすくなるので注意します。
保管場所以外の対策として、しっかり密閉できる容器を選ぶのがおすすめです。空気が遮断されて結露が生じにくくなる上、カビの胞子の侵入も防げるでしょう。その他にも、真空パックや乾燥剤を用いる方法があります。
手元供養の種類と費用
手元供養の種類は大きく分けると、骨壺、アクセサリー、プレートの3つです。このうち、小型の骨壺やアクセサリーの一種である遺骨ペンダントは認知度が高く、手元供養品の中でも人気があります。また近年では、遺骨を加工したプレートタイプを選ぶ方も増えてきました。ここでは、それぞれの種類の特徴を紹介し、あわせて費用の目安を解説します。
骨壺
遺骨や遺灰をそのまま保管する場合、保管用の骨壺が必要です。特に規定などはないため、手元供養の利用者が増えていることからさまざまなデザイン・素材・大きさの骨壺が販売されています。
片手に乗る程度のミニ骨壺と呼ばれるタイプは、数千円から購入できます。それよりサイズが大きいものは、5,000円~数万円程度が目安です。また、色柄やデザインが凝ったものや、貴金属、大理石、漆などが使われた数十万円の高級品も販売されています。

OHAKO-おはこ-の手元供養:モダンスタイルミニ骨壷
アクセサリー
加工品の中でも人気が高いのが、アクセサリーにする方法です。アクセサリーにもいくつか種類があり、遺骨や遺灰でダイヤモンドを作ってそれをアクセサリーにするものや、遺骨や遺灰を入れておけるペンダントなどがあります。
アクセサリーの費用の目安は、数千円~数十万円と幅があり、価格は主に素材と装飾によって変動します。例えば、ステンレス製やガラス製のペンダントは比較的安価です。一方、指輪やネックレスなどのタイプは、貴金属性でパールやダイヤモンドなどの装飾を施されているものもあり、価格が高い傾向にあります。

OHAKO-おはこ-の手元供養:カプセルタイプのペンダント
プレート
プレート型の手元供養は、「遺骨プレート」や「エターナルプレート」とも呼ばれます。遺骨の一部を粉状にして金属に混ぜ、プレート状に加工したものです。大きさはさまざまですが、一般的には写真立てに収まるくらいのものが多く、故人の名前や生没年などを刻印します。
加工に手間がかかる遺骨プレートは値段が高く、おおよそ10万円~30万円が費用の目安です。プレートの材質や硬度、デザイン、写真の刻印の有無などによって、価格が変わります。
手元供養をする流れ
手元供養をすると決めたら、準備が必要です。しかし、手元供養は比較的新しい方法のため、どのように手配をすればよいか分からない方もいるでしょう。ここからは手元供養の流れについて、具体的な方法とポイントを解説します。
1.親族の理解を得る
手元供養に抵抗を感じる方は一定割合います。後のトラブルを避けるためにも、まず親族の理解を得ておきましょう。
理解を得るのに適切な方法は、相手によって異なります。宗教上の理由から手元供養を好まない方、地域の慣習にそぐわないと考える方、対面上の理由からお墓を持ってほしいと頼む方もいます。また、故人の遺骨を手元に置かれることに対して、気持ちの整理が付かない親族もいるかもしれません。
いずれにしても、相手の立場に配慮しながら理解を求めましょう。手元供養について知識が全くない方も多いので、丁寧な説明が大切です。
2.手元供養の方法を選ぶ
手元供養には遺骨の全てを自宅で保管する方法と、墓地・寺院と手元供養で分骨する2つの方法があります。どちらの方法を選ぶか、この段階でしっかり決めておきましょう。
分骨するタイミングで一般的なのは、火葬が終わった後に自宅に親族が集まるときです。また、火葬のお骨上げのときに分骨する遺族もいます。なお、納骨してからの分骨も可能ですが、墓地管理者に了承を取る必要があります。
3.手元供養品を決める
手元供養の方法が決まったら、手元供養品を具体的に決めます。中でも骨壺を選ぶ方が多いでしょう。骨壺にはさまざまな種類があり、遺骨をどのくらい納めるかによって適したサイズが異なります。関東では全ての遺骨を納める傾向にあるため7寸~8寸のものを、関西では一部を納める傾向にあるため5寸~6寸のものを選ぶのが一般的です。
また、分骨の場合は、リングやペンダントなどのアクセサリーや、遺骨を加工したプレートを選ぶ方法もあります。それぞれ納めやすい遺骨の量が決まっているため、分骨を選択した段階で、手元供養品の種類を決めたほうがよいでしょう。
4.業者に依頼する
手元供養品の種類が決まったら、依頼する業者を選んで発注します。購入先としては、仏壇・位牌・仏具を扱う業者や、一部の葬儀サービス業者があります。また、現在では、オンラインショッピングでも簡単に手元供養品を購入できるようになりました。
手元供養品は一般的な商品と同じように価格が明確に決まっており、すぐに取り寄せが可能です。ただし、特注品の場合は予算や製作期間の見積もりが必要になることもあります。
手元供養のための分骨方法
火葬時に分骨する場合と納骨済みのお墓や納骨堂などから分骨する場合では、それぞれ手続きが必要です。ここでは、具体的な内容と分骨までの流れを解説します。
ちなみに、全ての遺骨を手元供養する場合は、特別な手続きはありません。ただし、後からお墓へ分骨する際には、管轄の自治体または納骨先に「分骨証明書」を発行してもらいます。
火葬時に分骨する場合
火葬時に分骨する場合は、以下の連絡・手続きが必要です。
| 手続き内容 | 手続き先 |
| お骨上げの際に分骨を希望する旨の連絡 | 火葬業者 |
| 分骨する数の骨壺の発注 | 販売業者または火葬業者 |
| 分骨証明書の発行 | 火葬業者 |
火葬場所が決まったら、お骨上げの際に分骨したい旨を直接または葬儀サービス業者経由で連絡しましょう。当日までに、分骨する数に応じた骨壺を用意します。少量を分骨したい場合は、小さなサイズを選びましょう。なお、骨壺を販売している火葬業者もあります。
分骨が終わったら、遺骨を複数に分けたことを証明する「分骨証明書」を、火葬業者に発行してもらいます。分骨証明書は、分骨をした数だけ必要です。
納骨済みのお墓や納骨堂から分骨する場合
納骨済みのお墓や納骨堂から分骨する場合は、以下の手続きを行います。
| 手続き内容 | 手続き先 |
| 遺骨をお墓から取り出したい旨とスケジュールの調整 | 寺院や霊園 |
| 分骨証明書の発行 | 寺院や霊園 |
| 閉眼供養・開眼供養などの宗教的な儀式の手配 | 寺院や霊園、僧侶など |
まず、お墓を管理している寺院や霊園に分骨したい旨を連絡し、あわせて遺骨を取り出す日程や段取りを決めます。樹木葬や合祀(合葬)の場合は、基本的に分骨できません。
分骨が終わったら、寺院や霊園に分骨証明書を発行してもらいましょう。また、仏教では分骨時に閉眼供養・開眼供養など、宗教的な儀式を行うことも一般的です。宗派やご自身、親族の考え方にあわせて、儀式の依頼先に連絡しておきましょう。
残った遺骨を供養する方法は?
少量を手元供養のために分骨した場合や、手元供養をしていた方が亡くなった場合などは遺骨が残ります。故人や家族、親族などの気持ちを考えながら、その後の供養について考えましょう。ここでは、お墓や永代供養墓などの4つの方法を解説します。
お墓への納骨
最も一般的なのが、遺骨の一部を手元供養にして、残った遺骨をお墓に入れる方法です。この方法は、お墓が遠方にあり、なかなかお墓参りに行けない方にも向いています。正式なお墓もあるため、家族や親族の理解を得やすい面もあるでしょう。ただし、新たにお墓を建てる場合は、費用の面でも手続きの面でも負担が大きくなるため注意が必要です。
永代供養墓や納骨堂への納骨
お墓よりも負担の少ない方法が、永代供養墓や納骨堂です。永代供養墓にはさまざまなタイプがありますが、合祀型では遺骨を共同の場所に埋葬します。合祀型は比較的安価な料金で納骨できるのが特徴です。集合安置型は納める場所は同じですが、骨壺が分けられているため、後から他の場所への納骨・分骨ができます。
近年は、マンション型の納骨堂を利用する方も増えてきました。ロッカールームのようにコンパクトなお墓が並ぶタイプや、遺骨が参拝場所に自動搬送される機械式の納骨堂などがあります。一般的なお墓よりも料金が安く、交通アクセスがよい場所にあるのが特徴です。
樹木葬
樹木葬は樹木を故人のシンボルとして偲べることから、人気が高まっている方法です。樹木葬は大きく分けると、以下の3タイプがあります。
| 種類 | 特徴 |
| 個別型 | ・墓石の代わりに樹木を植える ・故人にあわせて桜・紅葉・バラなどの樹木を自由に選べる ・お墓を建てるより安いが、樹木葬の中で最も料金が高い |
| 合祀型 | ・シンボルとなる樹木は共同で1本 ・埋葬スペースは他の故人と共通 ・樹木葬の中で最も料金が安い |
| 集合型 | ・個別型と合祀型の中間 ・シンボルとなる樹木は共同で1本だが、遺骨を納めるスペースが分かれている |
散骨
散骨は遺骨を粉状にして、海や山などの自然に帰す方法です。手元供養の際も粉末状にすることもあり、手元供養と散骨を組み合わせる方も少なくありません。
散骨をするために特別な手続きはないですが、散骨の場所には注意が必要です。公園など多くの方が利用する公共の場で散骨すると、嫌な気持ちになる方もいるでしょう。散骨を規制する条例を持つ自治体もあるため、事前に確認します。
散骨場所としてメジャーなのは海ですが、岸に近い場所では漁業権なども問題も発生するでしょう。トラブルを避けるためにも、散骨は専門業者への依頼がおすすめです。
新しい供養方法のひとつとして
お墓離れが進んでいる今、手元供養は選択肢のひとつとなります。
小さなお葬式では、手元供養などの納骨方法はもちろん、永代供養・海洋散骨・樹木葬など、納骨先探しをお手伝いするサービス「OHAKO-おはこ-」をご用意しております。 納骨先をご検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。
納骨先探しのお手伝いをするサービス「OHAKO-おはこ-」
・土地、墓石など必要な費用を全て含んだ明瞭価格
・お墓、納骨堂、樹木葬、永代供養、海洋散骨、手元供養など様々な納骨方法から簡単に比較、検索できる
・全国の霊園、寺院、墓地の豊富な情報を集約
あなたに最適な納骨先が見つかる「OHAKO」詳しくはこちら
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
手元供養とは、遺骨を骨壺やアクセサリーなどに保管して供養する方法です。故人を身近で供養できることや費用が抑えられるなどのメリットがあります。一方、家族の理解が得られない場合や、他の供養方法と組み合わせたほうがよい場合もあるので、慎重に検討しましょう。
供養の方法にお悩みなら、小さなお葬式にご相談ください。小さなお葬式は、手元供養を含めたさまざまな納骨プランにも対応しており、ライフスタイルにあった方法をご提案いたします。
供養の方法に関する疑問以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


相続人には、被相続人の遺産を一定割合受け取れる「遺留分侵害額請求権」があります。ホゥ。































