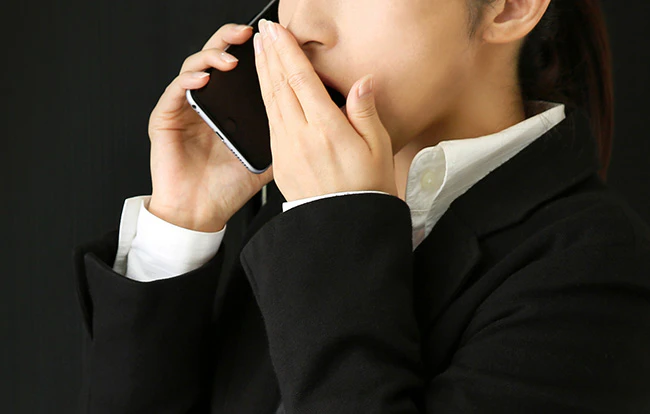「人は臨終が近づくと表情に変化が生じる」と聞いたことがある方もいるかもしれません。目や肌の色が変化するのは、臨終が近いサインのひとつです。
この記事では、臨終が近いことを知らせる表情について解説します。大切な方との最期の時間をどのように過ごすか考えたい方の参考になる内容です。
<この記事の要点>
・死の3つの兆候は、「呼吸の停止」「心臓の停止」「瞳孔が散大」
・食事や水分を摂れなくなり、呼吸に変化がある、寝る時間が多くなるなどの症状も死の兆候
・死亡診断書と死亡届は合わせて1枚の用紙になっている
こんな人におすすめ
死期を前にした兆候について知りたい方
死の3兆候(3徴候)について知りたい方
亡くなってからの流れが知りたい人
死の3兆候(3徴候)とは
死亡判定や、死亡診断書・死体検案書を発行できるのは医師のみです。医師が死亡を判定する際の基準に「死の3兆候(3徴候)」があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
・呼吸が完全に停止している
・心臓が完全に停止している
・瞳孔が散大・対光反射が見られない
3つの項目すべてに当てはまったとき、人は死亡していると判定されます。一方で、「脳死」は3兆候(3徴候)には含まれないため、注意しましょう。
<関連記事>
死亡宣告とは? 医師のやり方や蘇生の有無、その後の手続について
臨終が近いことを知らせる表情
臨終が近づいていることを、表情から見て取れる場合があります。目や肌の色が判断の基準になります。ここでは臨終の近さを知らせる表情について紹介します。
目の色が濁る
亡くなる兆候のひとつとして、目の色の変化があります。栄養が摂れなくなると全身や顔の筋肉、目の周りなど、さまざまな箇所に影響が及びます。目の色から光が消えて濁りはじめることは臨終が近づいている兆候のため、見送る側は心の準備を整えておきましょう。
肌の色が青白くなる
臨終が近づくと、肌の色が青白く変化することがあります。この現象は、心臓や呼吸器官の機能が低下し、体内の酸素不足が進むことが原因です。
家族や介護スタッフは変化に気づき次第、患者の体調を見守ります。血行をよくするために、優しくさすってあげることもあるでしょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
死亡前に見られる兆候
ここからは、表情以外の死亡前に見られる兆候について解説します。すべての方に当てはまるわけではありませんが、心の準備をするための目安にしてください。
食事や水分が摂れず体重が減る
気づきやすい兆候には、「食事や水分が摂れなくなる」「体重が減っていく」という現象があります。それに合わせて目が落ちくぼむといった変化も出てきます。
亡くなる直前は、体の機能も衰えて体内で水分をうまく処理できなくなります。そのため、食事や水分が摂れなくなります。お茶やお水だけではなく食事から水分を摂取することも難しくなります。
その結果、体重が減ったり目元が落ちくぼんで見えたりします。水分を体内で処理できない状態なので、無理やり食事や水分を摂らせることは避けましょう。かえって苦しい思いをさせる恐れがあるので、迷ったときは医師に相談しましょう。
寝ている時間が増える
体の代謝が悪くなり、寝て過ごす時間が増えてきます。「このまま亡くなってしまうのではないか」と不安になって、つい起こしたくなりますが寝かせてあげましょう。
せん妄などの症状が出る
急に奇声をあげたり、理解できないようなことを口走ったり、意識障害が出ることもあります。亡くなる直前は体の機能が衰えていきますが、それは脳も同じです。脳の動きが正常でなくなると、幻覚や幻聴などの症状が出てくることがあります。
気をつけたいのが、死亡前に見られる兆候ではない場合もあることです。薬の副作用や、ほかの病気の可能性もあるため、気になる場合は医師に相談しましょう。
呼吸の変化がある
呼吸の変化も死亡前の兆候の一つです。死期が近いときの呼吸の仕方は、大きく分けて2つあります。「下顎呼吸(かがくこきゅう)」と「死前喘鳴(しぜんぜんめい)」です。
下顎呼吸は、顎を上下に動かすように呼吸をすることです。体の機能の衰えにより酸素が足りなくなり、体が酸素を取り入れようとするため、あえぎ苦しんでいるように見えます。しかし、脳内の二酸化炭素の濃度が上がり「エンドルフィン」という脳内麻薬が出ている状態になるので、本人は苦しく感じていません。
「苦しそうだから」と酸素吸入をしてしまうと、二酸化炭素の濃度が下がりエンドルフィンが出なくなり苦しませてしまうので注意しましょう。
死前喘鳴は、意識がない状態で、呼吸をするたびにゴロゴロと喉奥で音がなる呼吸です。これは痰が絡まっているわけではなく、唾液が喉奥で溜まっている音なので吸入しても音は消えません。
下顎呼吸と同じく苦しそうに聞こえますが、本人は苦しくない呼吸です。どうしても苦しそうに見える場合は、口の中の唾液を拭き取ってあげる程度にしてあげましょう。死前喘鳴が始まると、おおよそ48時間以内に亡くなるといわれています。
臨終に立ち会う際に意識したいこと
臨終に立ち会う際は、安心して最期を迎えられるように支援するのが重要です。ここからは、臨終に立ち会う際に意識したいことを紹介します。
親族全員で看取る
臨終に立ち会う際は、できる限り親族全員で看取りましょう。長く過ごしてきた家族が見守ることで、心安らかな最期を迎えられます。また、看取りの場を家族で共有すると、悲しみや喪失感をより分かちあえるでしょう。
後悔のないように別れを告げる
後悔のないように別れを告げることも大切です。最期を迎える前に、大切な言葉や感謝の気持ちを伝えます。言葉をかけるだけでなく、手を握ったり撫でたりすることも励ましや安心感につながるでしょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
家族が亡くなってから埋葬までの流れ
家族が亡くなり埋葬をするためには、いいくつか必要な手続きがあります。それぞれ事前に確認しておき、いざというときに慌てないようにしましょう。ここからは、家族が亡くなってから埋葬までの流れを解説します。
死亡診断書の取得
家族が亡くなった際、最初にすべきことは死亡診断書の取得です。死亡診断書は、医師が患者の死因を正確に診断した証明書のことです。
病院で亡くなった場合は、医師が死亡診断をして死亡診断書が発行されます。死亡診断書と死亡届はあわせて1枚の用紙になっているため、受け取ったら必要事項を記入して市区町村役場に提出しましょう。死亡届には患者の氏名や生年月日、住所、死因などの情報が必要です。
<関連記事>
死亡診断書とは?発行や提出の手続き方法・費用など
葬儀社の手配
亡くなった後は、葬儀社に連絡して葬儀の手配を進めましょう。家族や近親者と相談しながら日程を調整して、葬儀社に希望の葬儀形式やプランを伝えます。
葬儀社は遺体を適切に管理し、葬儀の手配や司会進行、花輪や弔電の手配なども担当します。家族が亡くなってから埋葬までの流れには、葬儀社の協力が不可欠です。
お通夜・葬儀
お通夜は故人を偲び、最後の別れを告げる時間です。これまでのさまざまな思い出を語り合いましょう。
葬儀は仏式や神式、キリスト教式など、それぞれの宗派の形式で進められます。仏式の場合は、僧侶による読経や遺族・参列者による焼香などが行われた後に、出棺という流れが一般的です。
火葬・埋葬
通夜・葬儀を終えた後は、火葬が執り行われます。遺族が弔いの花を棺の中に入れて、最後のお別れをしたあとに火葬をします。
火葬が終わると収骨(骨拾い・骨上げ)の儀式を行い、骨壺に納めます。地域によって収骨方法が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。遺骨は、四十九日法要を終えた後に霊園や寺院などに埋葬するのが一般的ですが、近年は樹木葬や散骨を選ぶ方も増えています。
<関連記事>
埋葬許可証とは?いつ必要?火葬許可証との違いとは
本人は苦しくないケースがほとんど
ほとんどの人は、死の間際の姿を見て「苦しそう」と不安になるものです。しかし実際は、死期が近づいてきて体が衰えると同時に脳の機能も衰えていくため、苦しいという感覚は鈍くなっています。
とはいえ、様子を見ていて不安に思う場合は遠慮せずに医師や看護師に相談しましょう。また意識がないように見えても、声は聞こえている可能性が高いといわれています。最期まで声をかけて、送り出してあげましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
死の3兆候(徴候)とは、「呼吸の停止」「心臓の停止」「瞳孔が散大」です。この兆候(徴候)以外にも、食事や水分を摂れなくなったり、呼吸に変化があったりすると臨終が近い可能性があります。
身近な方が亡くなるのは非常につらく、葬儀の手続きまで手が回らないことも多いでしょう。そんなときには、小さなお葬式にご相談ください。小さなお葬式では、専門スタッフがどんなお悩みにも24時間365日体制でお答えいたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



初盆(はつぼん)とは、亡くなった方の忌明け後、最初に迎えるお盆のことです。ホゥ。