海外にはない日本特有の行事のひとつに「お彼岸」があります。逝去した方の供養を目的として、年に2回春と秋に行われます。名前は聞いたことがあっても、お彼岸の意味やその際に行われる法要についてわからない方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、お彼岸や執り行う法要について詳しく解説します。お布施や供花などどうしたらよいのか迷うポイントにもしっかり触れています。故人を手厚く供養するためにも、ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・複数の家の法要を一度に行う「合同法要」か、個別で行う「自宅法要」の2種類がある
・お布施の金額は、合同法要は3,000円∼1万円、自宅法要は3万円∼5万円が目安
・命日から四十九日が経過して初めて訪れるお彼岸を「初彼岸」と呼ぶ
こんな人におすすめ
お彼岸とは何か知りたい方
お彼岸にお墓参りをする理由を知りたい方
お彼岸に必要な準備物を知りたい方
お彼岸とは?
お彼岸は、仏教の行事のひとつです。ご先祖様に感謝の意を伝えて供養をしたり、豊作を祈ったりさまざまな目的があります。ここでは、お彼岸の時期やルーツ、お盆との違いについて紹介します。
お彼岸の時期
お彼岸は3月と9月の年2回あり、「春彼岸」「秋彼岸」と呼ばれています。春分の日と秋分の日をそれぞれを中日(ちゅうにち)として前後にそれぞれ3日間、合計7日間がお彼岸の期間です。初日を「彼岸の入り」、最終日を「彼岸の明け」、折り返しに当たる祝日を「中日」と呼びます。
お彼岸の起源
約1200年前に全国に点在する国分寺の僧侶が、春と秋にそれぞれ7日間かけて読経したのがお彼岸の起源とされています。かつては僧侶に限定された行事でしたが、時代が進むとともに一般の市民にも浸透し恒例行事として定着しました。
インドや中国は仏教徒が多いですが、お彼岸は日本発祥の仏教行事であるため、他国にはお彼岸の文化はありません。
お彼岸の歴史
806年に仏教の法会である「彼岸会(ひがんえ)」が開催された記録が残っていることから、お彼岸は平安時代の初期から始まった文化であることがわかります。
お彼岸の時期に参拝に出向く慣習が生まれたのは、江戸時代の中頃です。参拝のほかにも、全国に6ヶ所点在している阿弥陀仏にお参りをする「六阿弥陀参り」も普及しました。
お盆との違い
お彼岸と似た慣習に「お盆」があります。いずれもご先祖様を供養するという目的がありますが、お彼岸とお盆はまったくの別物です。お盆はご先祖様の霊を迎え入れて供養しますが、お彼岸にご先祖様の霊は戻ってきません。
お彼岸は、此岸(この世)と彼岸(あの世)がもっとも近くなる日とされています。その期間に、こちらから出向きお墓参りをすることでご先祖様を供養します。
お彼岸に法要やお墓参りをする理由
お彼岸にお墓参りをすることが習慣づいている方は、その目的や意義をあまり意識したことがないかもしれません。お墓参りをする理由がわかると、より気持ちを込めてご先祖様を供養できるでしょう。ここでは、お彼岸にお墓参りや法要をする理由について解説します。
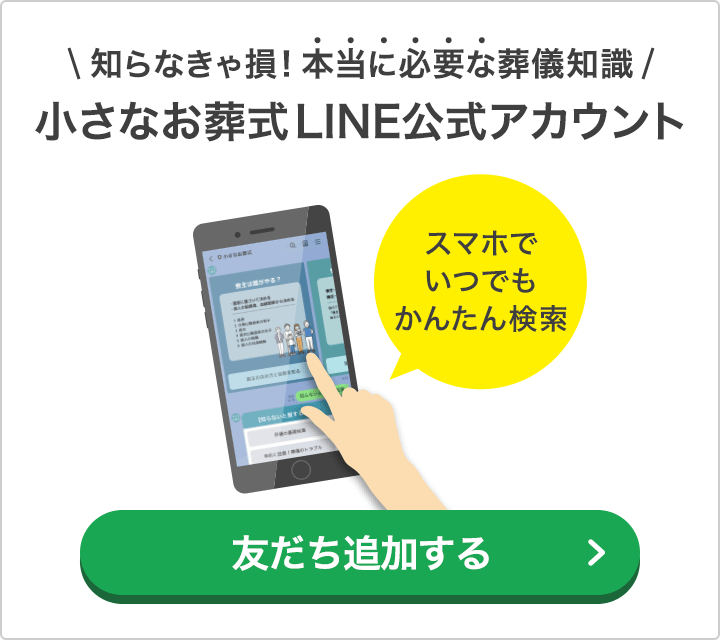
中道思想に沿っているから
お墓参りをする理由のひとつは、仏教の教えである「中道(ちゅうどう)」を大切にしているからです。中道は「何事にも偏見を持たず、正しい判断をする」という考え方です。春分と秋分は日照時間がほぼ同じであることから、この特徴が中道の思想に沿っているとされています。そのため、春彼岸と秋彼岸はお墓参りをするのに適した時期として認知されています。
八王日だから
お彼岸が「八王日(はちおうにち)」であることから、お墓参りをするともいわれています。八王日とは「立春」「春分」「立夏」「夏至」「立秋」「秋分」「立冬」「冬至」の8日を指す言葉で、人間のことを治める天地の諸神・陰陽が交代する日です。地獄の大王である閻魔は、この8日間を選んで日本中を巡回して人々の行いを観察・記録します。そのため、八王日に善行を積むとよいとされています。
太陽が真西に沈むから
日本では、阿弥陀如来の極楽浄土は真西にあるとされていました。お彼岸の日は、太陽が真西に沈むため極楽浄土の場所がはっきりとわかります。このことから、西にある浄土に向かって拝むことで徳を積めるとされています。
豊穣を祈るのに適しているから
お彼岸の時期は、季節の変わり目にあたります。豊穣を祈るのに最適な時期に仏教的な考えが加わり、「お彼岸は逝去した方を供養する時期」という意識が生まれました。
お彼岸に営む法要の種類
お彼岸には法要を執り行うのが一般的です。ご先祖様を手厚く供養することが目的ですが、規模や会場によって行われる法要が異なります。ここでは、お彼岸に営む2種類の法要について解説します。
合同法要
お彼岸の時期に営む法要には「合同法要」と呼ばれるものがあります。複数の家の法要を一度に行う法要で、「お彼岸法要」や「彼岸会」とも呼ばれています。お寺の境内にお墓を所有している方や、檀家である方が出席します。会場はお寺の本堂であることがほとんどですが、霊園が中心となって執り仕切ることもあります。
自宅法要
亡くなってから1年~2年の間は、自宅で法要が執り行われるケースもあります。参列者の範囲や人数に制限はないため、家族や親族であらかじめ法要の規模をきめておきましょう。自宅法要と合同法要どちらにすべきか迷った場合は、僧侶に相談することをおすすめします。
お彼岸の法要で準備するもの
お彼岸にはお墓参りをするのが習わしですが、自宅に仏壇がある方は仏壇にもお供えをするとよいでしょう。お彼岸のお供え物としてふさわしいのは、果物やお菓子、そうめんです。また、餅米を小豆で包んだお菓子をお供えする場合は、春はこしあんの「ぼた餅」、秋は粒あんの「おはぎ」という違いがあるので注意しましょう。
お彼岸の法要のお布施
法要では、僧侶にお布施を渡す必要があります。菩提寺との関係で金額は変動しますが、合同法要の場合の目安は3,000円∼1万円と少額でも構いません。一方で、個別法要の場合は3万円∼5万円が目安です。お布施を渡す際は白い無地の封筒に包み、裏に施主の住所と氏名を記載しましょう。
香典袋に入れないといけないと思われる方もいますが、お彼岸のお布施は香典袋に入れる必要はありません。ただし、手渡しはマナーに反するため切手盆や袱紗の上に置いて渡します。渡す際には、読経に対する感謝の意を述べましょう。
お彼岸の供花
仏壇やお墓にお供えする花は、葬儀とは異なり特に制限はありません。ただし、とげや毒、強い香りのある花は避けたほうがよいでしょう。
よく使用される花は菊やカーネーションですが、黄色や赤色の花でも構いません。常識の範囲内であれば、亡くなった方が好んでいた花を選ぶのもおすすめです。花屋をはじめインターネットショップからも買えるため、自身が買いやすい方法で購入しましょう。
初彼岸とは?
命日から四十九日が経過して初めて訪れるお彼岸を「初彼岸」といいます。初彼岸には団子をお供えし、お墓参りをするのがしきたりです。服装の制限はありませんが、法要があればフォーマルな服装を心がけましょう。男性は黒のスーツに白いワイシャツ、女性は黒色のアンサンブルやワンピースが賢明です。
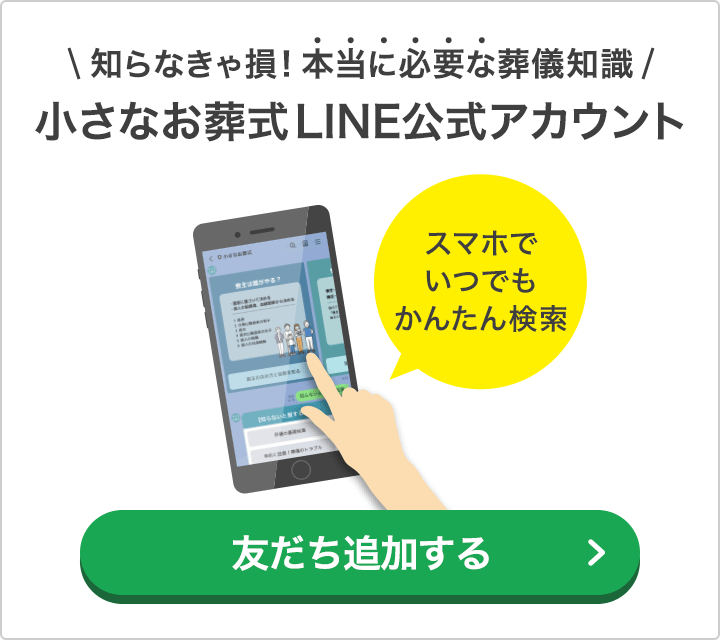
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
お彼岸とは、年に2回春分と秋分を中日とした7日間で、逝去した方を供養する期間です。お盆には故人の魂が戻ってくるのに対し、お彼岸には戻ってこないという違いがあります。
また、お彼岸には法要を営む場合があります。いくつかの檀家が同時に出席する「合同法要」と自宅で個別に営む「自宅法要」があり、どちらを選んでも構いません。自宅法要は僧侶を自宅に呼ぶため、あらかじめ準備が必要です。
お彼岸の法要について分からないことがあれば、小さなお葬式にお気軽にご相談ください。専門知識が豊富なスタッフがお客さまのお悩みや疑問に合わせて親身にアドバイスします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


遺言者の意思や希望を書面に反映し、公文書として承認された遺言書が「公正証書遺言」です。ホゥ。


































