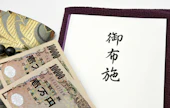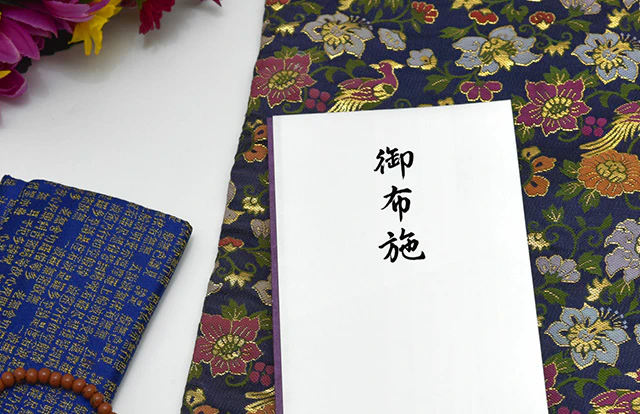葬儀や法要で読経などを依頼した場合、僧侶に「お布施」を手渡します。参列者のように直接コミュニケーションを取る機会が少ないため、「いつ渡すかが分からない」と不安に感じることもあるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、お布施を渡すタイミングや、事前に押さえておきたいマナーについて詳しく解説します。お布施に包む相場もピックアップしているため、実際に依頼する際の参考にできるでしょう。表書きの適切な書き方もご紹介します。
<この記事の要点>
・お布施は葬儀・法事・納骨の際に僧侶に渡す金銭のこと
・お布施は「切手盆」と呼ばれるお盆にのせて渡すのが正式な作法
・お布施の相場や表書きの書き方は宗派や地域によって異なる
こんな人におすすめ
お布施を渡す際のマナーを知りたい方
お布施の金額の相場を知りたい方
お布施の表書きの書き方を知りたい方
お布施はいつ渡すべき?
お布施をいつ渡すかは、葬儀会社と契約するときのように厳密な決まりがあるわけではありません。葬儀・法要など儀式の種類によっては時間が限られているため、渡し忘れがないよう大まかなタイミングを把握しておきましょう。僧侶にかける言葉も適切に選べると安心です。3つのパターンに分けて、それぞれ適切な渡し方を解説します。
葬儀でお布施を渡す場合
葬儀に僧侶を招く際、お布施を渡すタイミングで多いのは儀式前の段階です。儀式が始まるまでに、喪主や遺族と僧侶が顔を合わせる時間があります。葬儀をお願いする声掛けのタイミングでもあるため、お布施も同時に渡すと良いでしょう。
葬儀社を介して依頼する場合は、あいさつのために時間を設けてくれるケースがほとんどです。足を運んでもらった行為に対し、あいさつの言葉と共に感謝の気持ちを込めお布施も手渡します。
開始前のタイミングで渡す余裕がなかった場合は、一連の儀式を終えてから渡しても問題ありません。僧侶が式場を離れると手渡しが困難になるため、儀式が終わってから帰宅されるまでの間に時間を設けましょう。
法事・法要でお布施を渡す場合
四十九日や一周忌など、亡くなってから一定期間が経過した時期に法事・法要を執り行います。儀式が始まる前にあいさつをする時間がある場合は、このときにお布施を手渡しましょう。
複数の故人に対して合同で儀式を行う場合、あいさつの時間が十分に設けられない可能性が高くなります。このようなケースでは、儀式を行う前の受付口で渡す流れが一般的です。僧侶に直接渡せないため、受付の担当者に受け取ってもらいましょう。
儀式前に渡せるような場所・時間がない場合は、終了後に直接手渡します。多くの参列者が入り乱れる可能性もあるため、状況が落ち着いてからお渡しすると良いでしょう。お礼の言葉も忘れずに添えるよう意識します。
納骨でお布施を渡す場合
納骨の際には、僧侶へ依頼して適切な儀式を行う必要があります。納骨場所まで足を運んでもらったことや、読経に対するお布施を用意しておきましょう。手渡すのは、儀式前にあいさつを交わすタイミングが一般的です。
菩提寺で納骨式を行う場合も、儀式が始まる前のタイミングであいさつと共に手渡します。お布施を渡せないまま納骨式が始まってしまったときは、終了後にお礼を兼ねて渡しても問題ありません。
当日中に時間を作れなかった場合は、後日僧侶へ直接渡しに行きましょう。明確な期限はありませんが、可能な限り早く手渡した方が賢明です。納骨式と別の日に渡すのであれば、依頼を受けてもらったことに対するお礼もしっかり伝えましょう。
お布施を渡す際のマナーは?
葬儀や法要といった儀式と同様、お布施にも複数のマナーがあります。感謝の気持ちを伝える大切な要素でもあるため、失礼にあたらないよう理解を深めておきましょう。
お布施に包むお札の向きや、袱紗(ふくさ)に関する取り扱いを把握しておくと安心です。手渡しする際の適切なマナーも押さえておきましょう。お布施において、一般的なマナーを3つご紹介します。
お札の向きを揃えておく
僧侶が気持ちよく受け取れるよう、お金を包むときに気を付けたいのが「お札の向き」です。普段意識しない方もいるかもしれませんが、お布施においては特に重要なポイントともいえます。
正しい向きの基準となるのは、お札を入れる封筒の表面です。表面側にお札の肖像が接するよう、全ての向きを揃えます。お金を取り出したときに肖像を認識するようなイメージで、封筒の口側(フラップ)に肖像を揃えましょう。お布施としてのマナーだけでなく、受け取った方が金額を把握しやすくなるメリットもあります。
また、お布施には新札が適切です。使われた形跡がある物や、折り目が付いているお札は避けましょう。香典とはマナーが異なる点に注意が必要です。
袱紗(ふくさ)にお布施を包んでおく
封筒に入れたお金をそのまま持参するのは適切といえません。袱紗(ふくさ)を用意し、お布施に適した作法で包んでおきましょう。以下のような手順で包みます。
・ダイヤ型になるよう袱紗を広げる
・中央よりやや右側の位置に封筒を置く
・右側から封筒へ被せるように折る
・下、上、左の順に折る
・左から折って余った部分は、表側へさらに折る
あらかじめ包んだ状態で備え、渡す際に取り出すのがマナーです。袱紗から出した封筒は、そのまま袱紗の上へ乗せましょう。
葬儀や法要においては、紺色や深い青色のように暗い色の袱紗を選びます。派手なデザインの物を使わないよう注意しましょう。適切な袱紗を所有していない方は、慶弔どちらでも利用できる物を購入しておくのがおすすめです。
切手盆に乗せて渡す
本来の正式なマナーで渡すのであれば、お布施を切手盆(きってぼん)に乗せた状態で受け取ってもらいます。葬儀や法要の他、慶弔を問わずさまざまなシーンで用いる道具です。ひとつあると幅広く使えるため、事前に用意しておくと良いでしょう。
葬儀社によっては、お布施を渡すために切手盆を貸し出しているケースもあります。用意できない方は、切手盆の有無をチェックしておくと安心です。袱紗と組み合わせ、スムーズな流れで渡しましょう。
切手盆が使えない場合は、袱紗のみで渡しても問題ありません。切手盆の代用品として袱紗の利用が可能なためです。封筒のみで渡すのは失礼にあたるため、最低限度のマナーとして袱紗は用意できるよう配慮しましょう。
お布施の相場は?
葬儀社に依頼する費用とは異なり、お布施の明確な相場は決まっていません。あくまでも依頼した方の気持ちを表すものであるため、無理のない範囲で金額を決定しましょう。
葬儀や納骨など、儀式の種類によって異なる傾向を知ると決めやすくなります。地域によっても差が見られるため、大まかな目安として相場をチェックしておくのがおすすめです。
葬儀のお布施の相場
規模が大きくなりやすい葬儀では、地域によって金額の差も目立ちます。お布施の内訳として、以下の項目と概要を理解しておきましょう。
・読経料:読経に対するお礼
・戒名料:戒名を授けてもらったことに対するお礼
・交通費(お車代):僧侶に移動が必要な場合の交通費や宿泊費
・食事代(お膳料):僧侶が会食を辞退した場合の食事代
戒名に対して包むお布施の金額は、授けられた戒名の位や文字数にも左右されます。また、僧侶の食事も用意する場合のお膳料は不要です。目安になる相場は45万円~50万円(全国平均)で、各地域では以下のような傾向が見られます。
| 地域 | 金額(相場) |
| 北海道 | 30万円~35万円 |
| 東北地方 | 60万円前後 |
| 関東地方 | 50万円~55万円 |
| 中部地方 | 40万円~65万円 |
| 近畿地方 | 45万円前後 |
| 四国地方 | 40万円前後 |
| 九州地方 | 30万円前後 |
法事・法要のお布施の相場
四十九日や三回忌といった法要の場合、葬儀のように高額なお布施を包まないケースがほとんどです。一般的な相場である3万円~5万円の価格帯を基準に決めると良いでしょう。葬儀に比べて儀式の工程が少なく、僧侶の拘束時間を抑えやすい点が理由といえます。
僧侶が移動を必要とする場合は、お布施とは別にお車代を用意しておきましょう。金額は距離によって変動しますが、単体で渡すのが適切といわれています。
また、僧侶や菩提寺との関係性で金額が変わる可能性にも注意が必要です。古くからお世話になっている菩提寺へ依頼するのであれば、相場よりも高い金額を包んだ方が良いでしょう。故人と僧侶との関係も踏まえた上で、遺族と相談しながら決められると安心です。
納骨のお布施の相場
納骨へのお布施は、読経に対するお礼が重点的な目的となります。儀式の内容や宗派によって変動しやすいため、大まかな目安として1万円~5万円を想定しておきましょう。仏式で儀式を行う場合は、3万円~5万円が相場とされています。
新しい墓石を建てたり法要もあわせて行ったりする場合は、納骨とは別でお布施を用意しましょう。日数や時間に対するお礼ではなく、ひとつひとつの儀式に対してお礼の気持ちを伝えることが大切です。
菩提寺とどのような関係にあるかを問わず、宗派によって相場が変動するケースもあります。適切な金額が分からず悩む方は、依頼する菩提寺や葬儀社に相談してみると良いでしょう。親族に経験者がいる場合はアドバイスを求めるのもおすすめです。
お布施の表書きの書き方は?
お金を入れた封筒には、お布施であることが認識しやすいよう表書きを記載します。中央上部に「お布施」などの言葉、下部に自分の名前を書くのが一般的です。個人名ではなく、「〇〇家」とで記載しても問題ありません。表書きに適した言葉は宗派によって異なるため、以下の代表例を参考に反映しましょう。
・仏教:御礼、御回向料
・浄土真宗:お布施、御布施
・神道:御玉串料、御祈祷料、御祭祀料
・カトリック:謝礼
・プロテスタント:記念献金
仏式を例に挙げると、濃い色の墨を用いるのが原則的なマナーです。毛筆が用意できない場合は、筆ペンを購入して正しく記入しましょう。
お布施のことでお悩みなら小さなお葬式へ!
これまで葬儀や法事の喪主になった経験がない方は、お布施に関するマナーが分からず迷うかもしれません。特に葬儀は当日までの日数が限られやすいため、焦りを感じてうまく進められないこともあるでしょう。
お布施で悩んだ場合は、ぜひ「小さなお葬式」のスタッフへご相談ください。お布施の相談のほか、葬儀のプラン設計や、事前準備のサポートなども実施しています。葬儀に必要な物品やサービスをそろえることで、安心性を高める取り組みです。
価格の安さも強みなため、「葬儀の出費が気になる」という方にもご満足いただけることでしょう。一般葬や家族葬の他、火葬のみで送り出すセットプランも展開しています。お布施に関して不安がある場合は、寺院の手配も可能です。ご希望に合わせて最適なプランを提案しますので、ぜひ「小さなお葬式」にご相談ください。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
お布施は、僧侶へ感謝の気持ちを表明するためにも重要なお金です。いつ渡すかは明確に決まっていないため、儀式の前後で適切な時間を設けましょう。袱紗の包み方やお札の方向など、細かいマナーにも気を配れると安心です。
適切な金額は、僧侶との関係性や儀式の内容によって変動します。「どのように決めれば良いか分からない」と不安を抱えている方は、幅広いサービスをご提供する「小さなお葬式」までお問い合わせください。
また法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


葬儀の喪主を選ぶとき、もっとも影響力を持つのは故人の遺言です。ホゥ。