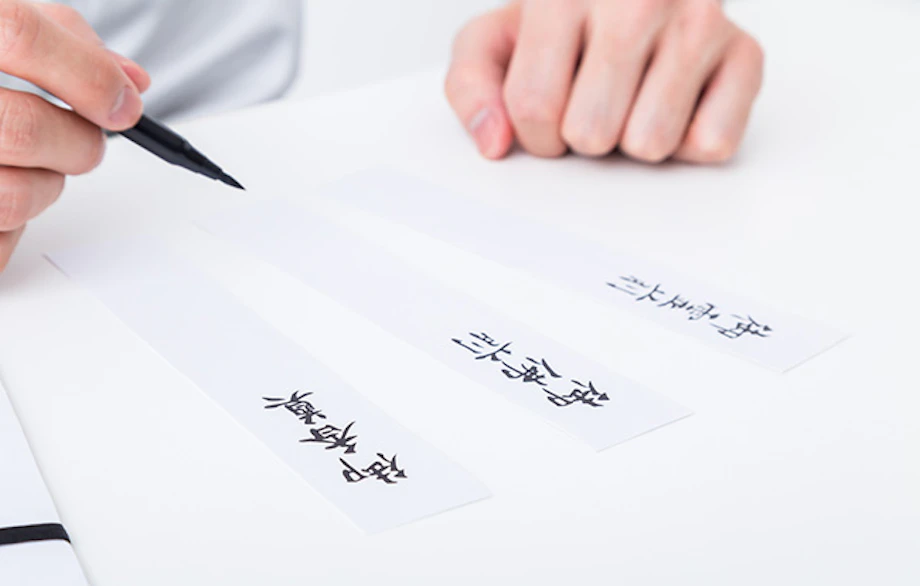短冊といって思い出すのは「七夕」の星に願いを書く用紙かと思いますが、香典と短冊にもつながりがあります。もしかするとこの紙のことを短冊というのか、と思った方もいらっしゃるでしょう。
この短冊どのように書くのか分からない、書く際にどのような点に気をつけたらよいのだろうか、と困った経験はありませんか。今回は用途別に合わせた使い方や書き方について解説していますので、ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・香典袋の短冊は表書きとして使用する
・浄土真宗の場合、四十九日前でも「御仏前」を使用する
・香典袋には水引の上に表書きを書き、水引より下に名前を書く
こんな人におすすめ
香典の短冊の使い方を知りたい方
短冊の書き方とマナーについて知りたい方
香典袋の種類について知りたい方
香典の短冊の使い方
短冊は、香典袋を購入した際に一緒についてくる縦長の白い用紙のことを言います。よく不祝儀袋や祝儀袋についてくるものですが、どのように使うのかご存知でしょうか。ここでは短冊の使い方について紹介しますので、以下から確認しましょう。
短冊は表書きに使う
短冊は、外袋の表面の中央に差し込んで使うもので、用紙の上には御霊前や御仏前といった表書きを書き、水引より下にはご自身の名前を書きます。
記入後は、そのまま差し込んで問題ないのですが、落ちてしまうのではないかと心配になる方もいらっしゃるでしょう。メーカーによって両面テープをあらかじめ付けているところもありますので、取れないように貼り付けてください。
短冊のサイズは、香典袋の大きさによって変わってきます。基本的に香典袋と一緒に同封されている短冊を使用しても良いですし、短冊が入っていない場合、ご自身で作成することもできますので、今後のために覚えておきましょう。
短冊が入っていない場合、または短冊が入っていても直接外袋へ記入しても良いのでしょうか。中にはそのまま書いている方もいらっしゃいますが、特に問題ありません。
ただし、書き間違いがあると、新しい外袋に書き直す必要があります。そういった手間や無駄を省くためにも、短冊の使用をおすすめします。
用途に合わせて選ぶ
短冊にはあらかじめ御霊前や御仏前、御花料と言った表書きが書かれているものや、表書きを自分で記入する真っ白なタイプがあります。
何も記載がされていないタイプであれば、故人の宗教や宗派に従い記入してかまいません。表書きがすでに印刷されているものであれば、故人の宗教に応じで適切なものを選ぶ必要があります。
ここで注意すべき点は、仏教の中でも浄土真宗や禅宗は四十九日前でも「御仏前」を表書きに記入するということです。他の宗派であれば「御霊前」を用いてもかまいませんが、浄土真宗に限っては死後、すぐに仏様になると考えられています。
つまり、浄土真宗の方に「御霊前」と書いた香典を渡してしまうとトラブルが生じてしまいますので、気をつけるようにしましょう。もし宗教があいまいな場合は、あらかじめ確認しておいた方が良いです。
ほかにも、キリスト教の中でもカトリックやプロテスタントの宗派によって書き方が異なりますので、後ほど個別に紹介します。
短冊のみ購入することもできる
短冊が付属でついていなかった場合や、ご自身で書くことにためらう方もいらっしゃるでしょう。その場合は、短冊のみ大手通販サイトや文房具店などで購入することをおすすめします。
中身は同じ表書きの10枚セットや、宗教別、用途別、無地タイプ、香典袋の種類別に分かれており、様々なものが取りそろえてあるようです。
それぞれ表書きがすでに書いてあると名前のみになるので楽ですが、無地タイプであれば汎用性が高いというメリットがあります。ご自身の用途によって使い方が変わりますので、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
自分で作ることも可能
先ほど短冊を購入する方法をお伝えしましたが、ご自身で作成することも可能です。いくつか方法があるのですが、インターネット上で「香典袋 短冊 テンプレート」などと検索してみると候補が上がってきます。
他にWordやExcelを使ってパソコンで作成することもできます。この場合、なるべく毛筆に近いフォントを選ぶことを忘れないようにしましょう。
また年賀状を作成する際に使用することが多い、筆まめや筆ぐるめといったはがき作成ソフトでも作ることができますが、専用ソフトかつ有料です。
もともとパソコンに内蔵されているのであれば問題ありませんが、今回のみの使用であれば別途購入する必要が出てきますので、他の方法をおすすめします。
自身で作成する際に気をつけていただきたいことは、表書きとご自身の名前を全て印刷で済ませてしまう方もいらっしゃいます。その方が、字が整っているため見栄えは良いかもしれません。
ですが、ご遺族側からすると温かみを感じないと思う場合もありますので、できれば名前は薄墨の筆を使い手書きで書いてみることをおすすめします。
字がきれいではないからと敬遠してしまうかもしれませんが、丁寧に書くことによってご遺族にあなたの誠意が伝わりやすく、印象も良いです。
短冊の書き方とマナー
表書きは一般的に「御霊前」や「御仏前」と書いても問題ないのでしょうか。仏教や神式、キリスト教の宗教に応じて表書きの書き方は変わってきます。
宗教によって表書きを間違えると失礼に当たるので、気をつけるべきマナーや書き方について、宗教ごとに確認してみましょう。
仏教の場合
仏教の場合、一つの境目として四十九日前か後かによって書き方が変わってきます。四十九日前のお通夜や葬儀では、御霊前、御香典、四十九日後は御仏前です。
御香典は故人やご遺族に対して「急な不幸事で大変でしょうから、お線香やお供物に使ってください」という相手を思いやる意味もありますので、宗派に限らず使用できる表書きとなっています。
反対に、御霊前は浄土真宗や禅宗では使ってはいけない表書きです。これらの宗派には故人が霊になるという考えがなく、極楽浄土から仏様へ生まれ変わるとされています。そのため、御霊前を使わず御仏前を使うようにしましょう。
禅宗の場合も浄土真宗と同じような書き方で問題ありません。
禅宗は臨済宗、曹洞宗、黄檗宗(おうばくしゅう)が含まれており、ここでは詳しい説明は割愛させていただきますが、故人をお釈迦様の弟子である「仏弟子」にするため御仏前の表書きを使用します。
神式の場合
神道(神式)にも宗派がいくつかありますが、それによって表書きが変わるということはありません。神式の場合、仏式の法事にあたる死後100日までを「霊祭」と言い、1年以降を「式年祭」と言います。
一般的に葬儀や霊祭、式年祭で使われる表書きは「御神前」「御玉串料」「御榊料」です。ここで気をつけるべきポイントは、香典袋の中には蓮の花が描かれているものがありますが、仏式のものであり神式では使用することはできませんので覚えておきましょう
キリスト教の場合
キリスト教の場合、プロテスタントやカトリックといった宗派によって、表書きの書き方は変わってきます。葬儀ではプロテスタントでは「御花料」を使い、カトリックでは「御花料」「御ミサ料」を使います。
どちらの宗派でも御霊前の書くことも可能ですが、プロテスタントの中でも福音派と呼ばれる宗派では、霊と言う考えを持たないため使用することはできません。よってどちらの宗派でも対応できる書き方として「御花料」を使うと良いでしょう。
またキリスト教の場合、仏教でいう法事の概念がなく「追悼ミサ」と呼ばれる儀式があり、教会にご遺族ならびに関係者が集まり、故人へ祈りを捧げお茶会をする会を開くようです。
故人の宗教が不明な場合
故人の宗教が分からない場合は、どのように表書きを書くべきなのでしょうか。一緒に参列する方がいらっしゃるのであれば、まずはその方々に確認を取ってみましょう。それでも分からない場合は「御霊前」と書くと良いでしょう。
先ほど御仏前やキリスト教の一部の宗派では使用できないとお話しましたが、故人の宗教が不明な場合に限っては、御霊前を使っても良いとされているので覚えておいた方が良いです。
名前の書き方
外袋には表書きとご自身の名前を記入します。(代理の場合は香典を包んだ方の名前)水引よりも上に御霊前や御香典といった表書きを書き、水引より下に名前を書くようにしましょう。
短冊にあらかじめ表書きが記載されている場合は、名前のみを書きます。宗教や宗派によって表書きが変わってきますので、名前を書く際にも一度確認するようにしましょう。
複数人の名前を書く場合は短冊に十分なスペースがありませんので、直接外袋に記載するか、団体名(会社の所属やグループ名)と外一同と左下に書くと良いです。また代理でお渡しする場合は、お金を包んだ方の名前の左下に、代理の「代」を記入しましょう。
夫婦連名の場合、故人とどのように関わっていたかにもよって書き方が変わってきます。基本的には夫のみの名前で良いとされていますが、夫婦どちらも親交があった場合は中央に夫の名前、左下に妻の名前のみを書くようにしましょう。
短冊はのり付けする?
外袋へ短冊を差し込んだものの、ふとした瞬間に落ちてしまわないか心配になります。
通常であれば差し込んだだけでも良いのですが、短冊が落ちないように貼っておくとご遺族側の負担も減ります。外袋と付ける際は、両端と真ん中にのりがはみ出ないように貼ります。
あまりつけすぎてしまうと短冊のまわりが汚れてしまいますし、とはいえ少量すぎるとはがれてしまうこともありますので、適度な量で貼り付けるようにしましょう。
メーカーによって短冊の後ろに両面テープを貼っているところもあります。そのような場合は両面テープで外袋と短冊を固定しておくと良いです。
表書きは「薄墨」で書く
ご自身の名前と表書きを書く際には、薄墨の筆を使って書くようにしましょう。薄墨には「故人を亡くしたため、涙で墨がにじんだ」「急いで故人の元へ駆けつけたので、十分に墨をする時間がなかった」と言う意味があります。
本来であれば硯(すずり)を使って墨をすることが望ましいですが、薄墨の筆ペンはコンビニや文具店でもあり、簡単に購入することができます。黒色のサインペンでも問題はありませんが、表書きをボールペンで書くことは失礼ですので控えるようにしましょう。
外袋はボールペンを使うことはできませんが、内袋で住所や名前、金額を記入する際には使っても良いです。
こちらも本来筆で書くことが推奨されていますが、外袋に比べると内袋へ記入する文字は小さいため、にじんで読みにくい文字になってしまうことも考えられます。ボールペンで記入する際も、きれいには書けなくとも丁寧に書くように意識して取り組みましょう。
香典袋の種類
香典袋は様々な種類があり、包む金額によって装飾や大きさ、水引の本数なども変わってきます。ここでは金額に合わせた袋の種類や水引の結び方の意味、本数について解説していますので、参考にしてみてください。
香典袋は包む金額で分かれている
一般的に香典袋は、3,000円~5,000円、1~2万円、3~5万円以上、10万円以上と金額に応じて使用するものも変わってきます。
種類も封筒と奉書紙の2種類あり、封筒は奉書紙と比較すると金額も少額です。反対に、奉書紙は高額を包むということもあり、和紙で作られており中袋を包むように使うタイプです。
包む金額で3,000円~5,000円は最もランクが低いもので、すでに水引が印刷されている簡素な封筒を使い、1~2万円は水引金封を用意しましょう。地域によって差もありますが3〜5万円以上の場合、中金封と短冊を使用しより質の高いものを使用します。
親が亡くなった場合などに使用する大金封は、10万円以上を包む際に使われることが多いです。中金封よりも袋が大きく、高級和紙を使い装飾も立派なものを選びます。
特大金封という10万円以上100万円程度の額を包むものもあるのですが、さらに袋のサイズが大きく、装飾も豪華で厚みがあるのが特徴です。
水引の本数と結び方の違い
香典袋にも種類があるのと同じように、水引の本数や結び方にも違いがあります。葬儀や法事で使用する水引には、どのようなものがあるのでしょうか。
香典で使われる結び方には、結び切りとあわじ結びという2種類あります。結び切りは、ほどけて結び直すことができないよう固結びにされているもので、二度と繰り返さないようにという意味です。
一方のあわじ結びは、2色の水引を横から見て8の字になるように、交差させて結びます。こちらも結び切り同様に、同じ意味を持っておりどちらも不祝儀の他にご祝儀でも使われている結び方なので覚えておくとよいでしょう。
最後に水引の本数は、基本的には5本で束ねたものを使います。金額や格式によって本数が7本、10本となりますが、5本は7本の丁寧結び、10本は基本の5本を二重、つまり握手をしている形を表しているため、弔いごとのほかお祝いごとでも使われる結び方です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
香典の短冊の使い方、用途に合わせた書き方についてご紹介しました。表書きは宗教や宗派によっても書き方が変わり、短冊の作り方や薄墨の筆を使った方が良いなど、気をつけるマナーがいくつもあります。
短冊の使い方や書き方で何かお困り事や疑問に思った点があれば、小さなお葬式へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



自筆証書遺言は押印がなければ無効だと判断されてしまうので注意しましょう。ホゥ。