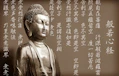「葬儀費用が高すぎて払えない」「格安の葬儀社を探している」「今より安く済ませるコツはないのか」とお考えではありませんか。
葬儀費用は高額かつ、突発的に発生する場合もあります。急な支払いに困っている方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、葬儀費用は工夫次第で大きく減額できます。しかし、葬儀社や周囲に言われるままに契約を進めてしまうと、支払いが困難な額まで膨らんでしまうかもしれません。
そこで今回は、葬儀費用を格安で済ませる方法を6つご紹介します。安くしすぎて起こるトラブルについても解説するので、この記事を読めば事前に親族と話し合って解決できるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
<この記事の要点>
・葬儀費用を抑えるためには、事前に複数の葬儀社から相見積もりをとっておく
・公営の火葬場であれば葬儀費用の控除を受けられる
・僧侶による読経がない直葬の場合、お寺によっては納骨を受け付けない場合がある
こんな人におすすめ
葬儀費用を格安で抑えたい方
費用が安い葬儀形式を知りたい方
葬儀費用を支払えない場合の対応方法を知りたい方
葬儀費用の全国平均は約127万円
小さなお葬式が行った調査では、葬儀にかかる費用の全国平均は約127万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)ここでいう「葬儀費用」とは、葬儀社に支払う式の料金だけではなく、僧侶へのお布施や火葬費用なども合わせた費用を指します。
控除や香典を考慮すると全額負担ではないとはいえ、葬儀費用は突発的に発生する場合もあり、これほどの大金を即座に用意するのは困難かもしれません。
葬儀費用は地域や式の規模によって大きく増減するので、平均以下に抑えることも可能です。まずは一番効果的な、式の費用を抑えるところから始めましょう。
葬儀費用の中には式以外にも様々な費用が含まれますが、式を変更することで他の費用も一緒に安くなります。
<関連記事>
【第1回調査】一般葬にかかる費用相場(全国編)
【第1回調査】家族葬にかかる費用相場(全国編)
【第1回調査】直葬にかかる費用相場(全国編)
葬儀費用が格安の式を紹介
葬儀費用の中で大きなものの一つが、葬儀社に支払う式の費用です。多くの方が、親族だけでなく故人の知人を集めて行う「一般葬」を行っていますが、参列する人数が多くなり費用が膨らむ傾向があります。
葬儀費用を格安で済ませたい場合は、一般葬ではなくもっと小規模な式を行うと良いでしょう。
小規模な式には3つのパターンがあるので、順に解説していきます。
1. 家族葬:約110万円
家族葬は、限られた親族のみで行う葬儀です。小さなお葬式が行った調査では、家族葬にかかる費用総額の全国平均は約110万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)人数が少ないので、会場にかかる費用が一般葬と比べて大きく抑えられます。
また、人数が少ないと、通夜振る舞いや精進落としなどの参列者に振る舞う食事の数も少なくなります。当然かかる費用も少なくなるのも見逃せないポイントです。僧侶を呼んでお通夜も行うため、人数以外は一般葬との違いはありません。
2. 一日葬:約45万円
一日葬は、お通夜を省略した葬儀です。名前の通り一日で終了するので、会場費をはじめとする様々な費用が半額になります。小さなお葬式が行った調査では、一日葬にかかる費用の全国平均は約45万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年2月 2022年3月 自社調べ。火葬料金を含む)
費用の他に、お通夜がないため遠方の方でも都合を合わせやすいのも一日葬のメリットの一つです。
僧侶へのお布施も一日で済む関係上、安く済ませることができます。明確な料金が定められているものではないので、相談しつつ金額を設定するとよいでしょう。
<関連記事>
一日葬の費用はいくら?相場や内訳を徹底解説!
3. 直葬:約36万円
直葬は、式を行わずに直接火葬に進む葬儀です。別名「火葬式」「荼毘式」とも呼ばれています。
式がないので、葬儀社に支払う費用は最小限で済むのが特徴です。小さなお葬式が行った調査では、直葬にかかる費用総額の全国平均は約36万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ。火葬料金を含む)
式を行わないため、僧侶の読経もありません。そのため、お布施を支払わなくてもよいのが大きなメリットになります。ただし、火葬にかかる費用は他の葬儀と同様に発生するので注意しましょう。
僧侶の読経がない関係上、宗派によっては一族のお墓に納骨できない場合があるので注意してください。
葬儀費用を抑えるコツ
式自体を変更する以外にも、葬儀費用を抑えるコツは沢山あります。今回紹介する方法の多くは、できるだけ早く準備することが重要なので、早めに動き出すようにしてください。生前にできる限りの準備ができていれば万全です。
全部で6つのコツをお伝えするので、格安で葬儀を済ませたい場合は、予定をしっかり組めるように気をつけましょう。
1. 格安の式場を探す
葬儀にかかる費用は葬儀社によって変わります。建物の大きさによっても一般葬向けか家族葬向けかが大きく変わるので、近隣の葬儀社に問い合わせて相見積りを取っておきましょう。
式場探しには時間がかかるので、生前に決定しておくと開式までスムーズに進みます。間に合わなかった場合は、親族で手分けして探してください。
もちろん安ければ良いわけではなく、式場の立地や開式にかかる時間なども考慮する必要があるので注意が必要です。
2. 火葬場付近の式場を選ぶ
式場と火葬場が離れすぎていると、遺体の搬送費用が高額になってしまうので注意してください。また、参列者のアクセスも考慮した立地を選ぶように心がけましょう。
数が少ない火葬場の方が混雑する傾向にあるので、先に火葬場の予約を取ってから式場を選んだ方が無難です。
式場と火葬場が離れすぎていると、参列者をマイクロバスで運ぶのも一苦労なので、運転手に支払う心付けにも気を使う必要が出てきます。
3. できるだけ早く開式する
遺体は自宅で管理してもかまいませんが、腐敗を防ぐための処理や死化粧を素人が行うのは困難です。多くの方が葬儀社に遺体を預け、開式までの保管を任せています。
ただし、遺体の保管は有料なので、費用を抑えるためにはできるだけ早く開式すると良いでしょう。葬儀の日付は親戚一同に通知して調整する必要がある他、火葬場を事前に予約しておかなくてはならないので注意してください。
また、死亡確認から24時間以内の火葬は法律で禁じられているので、あまり急ぎすぎるのも禁物です。
<関連記事>
遺体安置の期間は?ご逝去からの流れと安置する場所や費用について解説
4. 公営の火葬場を選ぶ
故人が戸籍を置いていた自治体が運営している火葬場であれば、葬儀費用の控除を受けられます。控除額は自治体によって異なるので、詳しくは役所で確認してください。無料になる場合もあります。
公営の火葬場は人気があり、すぐに予約が埋まってしまうので、できるだけ早く予約をしてください。しかし、骨壺などの仏具は控除の対象外であり、通常通りの料金になるので気をつけましょう。
5. お布施や心付けを最小限にする
葬儀に僧侶を呼んだ場合、読経の謝礼としてお布施を渡すのがマナーです。しかし、お布施は具体的な金額が定められていないので、事情を説明して最小限に収めましょう。
葬儀社職員や運転手への心付けも同様に、金額が決まっていないので限界まで抑えてください。
しかし、一族の付き合いがある場合は、あまり値切りすぎると関係が悪化する危険があるので注意しましょう。
6. 食事や返礼品を小規模にする
葬儀を開式する際、喪主は必ず「通夜振る舞い」と「精進落とし」を用意して参列者に振る舞います。食事の価格に決まりはないので、できるだけ安く済ませましょう。
また、通夜に参列した方には「通夜参列品」、葬儀に参列した方には「会葬御礼品」を用意します。どちらもハンカチや缶コーヒー程度に済ませて価格を抑えてください。
参列者に渡すものは「香典返し」がもっとも高額になりがちです。しかし、いただいた香典の3分の1程度までならマナー違反にはなりません。
<関連記事>
葬儀での香典返しのマナーは?金額相場・品物・香典返しなしの場合などを解説
葬儀費用が支払えない場合
葬儀費用を抑える方法はいくつかありますが、それでも葬儀費用は元々が高額なので支払うのが難しいかもしれません。
どうしても支払いが困難な場合は、他からお金を工面して支払いにあてましょう。お金を用意する3つの方法を紹介するので、どれかを活用して支払いを済ませてください。順に解説していきます。
1. 親族で分担して支払う
葬儀費用は基本的に喪主が支払いますが、高額すぎて困難な場合は親族で分担しても構いません。
葬儀費用の支払いは相続税控除の対象になるので、できるだけ法定相続人の間で済ませた方が無難です。相続争いに発展しかねないので十分注意してください。
また、いただいた香典も葬儀費用を支払った人の間で分担しましょう。喪主の総取りになると良くないので、親族間で話し合って決めてください。
2. 故人の遺産を葬儀費用にあてる
相続前の遺産を動かすことは基本的にはできません。しかし、葬儀費用は高額なので特例として使用を認められています。
ただし、故人の口座は死亡が確認されると凍結されてしまうので、法定相続人が銀行で特別な手続きをしなくてはなりません。全員で書類を作れば口座の解凍ができますが、一人でも一部を引き出せるので緊急の際は掛け合ってみてください。
また、相続前の遺産は相続人全員のものなので、許可なく動かすと相続争いに発展しかねません。使用する際は事前に話し合って全員の許可を取りましょう。
<関連記事>
遺産から葬儀費用を払える?凍結口座からお金を引き出す方法や控除をまとめて解説
3. 控除や保険金を使う
葬儀費用は、国や自治体から控除が受けられます。受け取りに期限があるものも多いので、忘れずに申請してください。
受け取り先は大きく分けると年金と保険の二つです。遺族宛に送られる給付金の他、葬祭費用として送られるお金もあります。
基本的に役所で申請して受け取りますが、社会保険のみ故人の職場で手続きする必要があるので注意しましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
格安の葬儀はトラブルの火種になるので注意
葬儀は故人を弔う大切な儀式です。費用を抑えたい気持ちも分かりますが、あまりに規模を縮小しすぎると故人も浮かばれず、様々なトラブルの火種となります。
経済状況的に高額な葬儀は難しいかもしれませんが、せめてトラブルが起こらないよう、親族間でしっかりと話し合いをした上で葬儀を進行してください。
想定されるトラブルについて、順に解説していきます。
1. 親戚の反対を受けるリスクがある
葬儀の規模を縮小するという考え方は比較的新しく、一般葬という名前の通り、今までは故人の知人を集めて式を行うのが一般的でした。
人数が極端に少なかったり、お通夜が無かったりするとご年配の方は不自然に思い、反対される可能性があります。この先やってくる自分の葬儀のことも考えると、より苛烈な反対を受けるかもしれません。
故人に対する思いは人それぞれなので、特に付き合いの長かった方は盛大な葬儀を望むはずです。しっかりと話し合った上で、全員が納得できる葬儀を行いましょう。
2. 一族の墓に入れない可能性がある
葬儀費用を限界まで抑えようとすると、直葬を選ぶことになります。直葬は式を行わないので、僧侶による読経や供養が行われません。
そのためお寺によっては、直葬を正式な葬儀を認めておらず、納骨を受け付けない場合があります。
埋葬する方法は自由です。しかし、一族のお墓に入りたい場合はお寺が直葬を認めているか事前に確認が必要です。直葬を選ぶ場合は十分注意しましょう。
3. 葬儀後に高額な費用を請求される
格安の葬儀社を選んだと思っても、実際の請求額が見積りと大きく異なる場合があります。
一見良心的なプランに見えても、式の費用以外で水増しをして法外な請求を突きつける悪徳な葬儀業者もいるので、費用の見落としがないように全て書面に落として確認しましょう。
状況によってはゆっくり相見積りを取っている余裕がないかもしれませんが、焦りが一番の敵です。落ち着いて葬儀社を選んでください。
特に遺体の保管費用や、お花の料金は見落としがちなので注意してください。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が最大5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
葬儀費用は高額かつ予期せず発生するので、支払いが困難な場合も十分に考えられます。葬儀は故人を弔う大切な儀式なので、削りすぎないように気をつけつつ、無理のない範囲で進行できるように調整してください。
大切な方が亡くなった直後で、大変な時期かもしれませんが、冷静にお金と向き合って格安で済ませるコツを押さえるようにしましょう。
葬儀費用の詳細な金額が知りたい方は「小さなお葬式」までお問い合わせください。専門のオペレーターがヒアリングを行い、具体的なプランを提案させていただきます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



遺言書には、誰の遺言かを明確にするために署名が必要です。ホゥ。