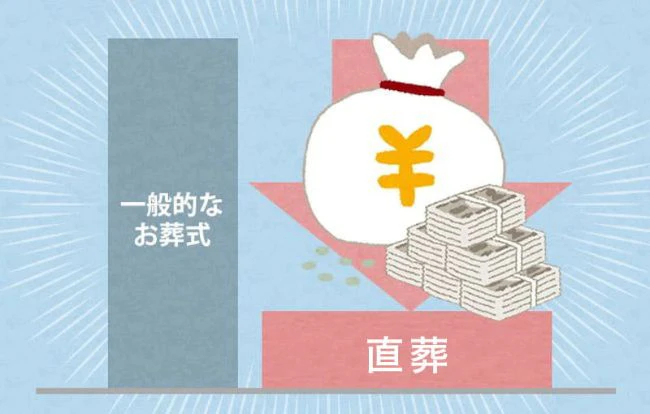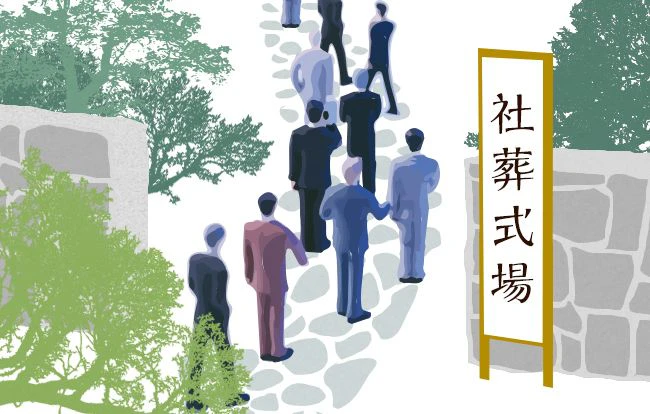身近な方が亡くなって告別式から火葬まで参列した際、その後の会食に参加した経験がある方もいらっしゃるでしょう。葬儀に参列する際は会食の時間まで考えて、予定を調整する必要があります。
この記事では「精進落としにかかる時間」について解説します。精進落としは、葬儀全体の中で最後の行事です。精進落とし自体の意味やマナーの解説とともに、告別式当日の全ての行事の流れも紹介します。ぜひとも最後までご覧ください。葬儀全体の流れについてあわせてご確認することもおすすめです。
<この記事の要点>
・精進落としの時間は1時間~2時間程度が目安
・精進落としとは初七日法要の後に行われる食事のことで、動物性の食材を使わないのが特徴
・精進落としでは喪主が下座、上座は僧侶の席とするのがマナー
こんな人におすすめ
精進落としにかかる時間が知りたい人
精進落としに参加予定の人
精進落としの流れを把握しておきたい人
精進落としにかかる時間は【1時間~2時間程度】
精進落としの時間は1時間~2時間程度を目安にしましょう。全体的な雰囲気は、一般的な会食と変わりありません。喪主の挨拶と献杯(けんぱい)があり、その後食事となります。
喪主や遺族がお酒を継ぎながら、故人に対する思い出などを語り合います。終了時間を明確に決めていないケースもありますが、会場の利用時間に応じてお開きとなることがほとんどです。良きタイミングで、喪主の方が締めの挨拶を行い終了となります。
精進落としの内容を解説
「葬儀の後に行われる食事」ということは、知っている方は多いと思います。しかし、「具体的に何をする行事なのか」「通常の会食とは何が違うのか」わからない方も多いでしょう。
ここでは、精進落とし自体の内容について解説します。全体の流れやマナーについても紹介しますので、ご自身が参加する際の参考になるようしっかりと確認してください。
1. 精進落としの意味
精進落としとは、「初七日法要の後に行われる食事」です。そのため、必ずしも告別式当日の行われる行事ではありません。近年では初七日法要が告別式当日に行われることが多いため、併せて同日に行われることが一般的になっているのです。
精進料理は中国で生まれた「仏教の教えにもとづき殺生や煩悩への刺激を避けること」を目的とした料理です。動物性の食材を使わないという特徴があります。
かつては故人の逝去から四十九日が過ぎるまでの間、遺族が肉類や魚類を避けた食生活を送るという慣習がありました。四十九日の経過後を「忌明け」といって、このときに通常の生活に戻る儀式として精進落としが行われていました。
2. 精進落としに参加する人
参加者は当日の流れによって異なります。火葬や初七日法要など直前の儀式に参列していた方は、そのまま参加することがほとんどです。一方で告別式から出棺までの一般の参列客が、参加することはありません。
通夜の後に行われる「通夜振る舞い」と比較すると、参列者の範囲に大きな違いがあります。通夜振る舞いは、通夜が行われる会場に席が設けられていることがほとんどです。そのため、通夜に参列した方は、そのまま通夜振る舞いの会場に移動することになります。
本来は告別式後ではなく、火葬や初七日法要の後に行われる行事です。そのため、参加者が限定されているのが特徴です。
3. 精進落としの準備
料理などの準備は、喪主を中心とした遺族が行います。特に決まったメニューなどはありませんが、以下の要素などを考慮して手配する必要があります。
・人数と年齢構成
・予算
・火葬場や斎場からのアクセス
・飲み放題などのプラン
あまり神経質になる必要はありませんが、余裕があれば、アレルギーなども確認しておきましょう。
料理は和食となりますが、寿司や会席料理などが一般的です。注意点としては、お祝いの席で出されることの多い「鯛」や「伊勢海老」などは避けるのがマナーです。お店に相談すれば「専用のメニュー」を用意しているケースもあります。
準備においては、参加人数の把握も重要です。火葬に参列するのは近親者に限られるため、全員の出席の有無を確認しておきましょう。また、僧侶に参加をお願いすることを忘れないでください。
4. 精進落としのマナー
精進落としが行われる趣旨は、以下の通りです。
・葬儀や法要が滞りなく終わったことの報告
・参列者や関係者へのねぎらいの気持ち
・読経をしていただいた僧侶への感謝
精進落としには「喪主が僧侶や関係者をもてなす」といった性質があるのです。そのため、席順は喪主が入り口付近の下座となります。そして、親族から友人、会社関係者と座っていき、もっとも上座は僧侶の席です。
会食中は故人への思い出を語り合うことになりますが、死に関するような話題は禁物です。火葬の後に行われる会食のため、どうしても気持ちが暗い方に向いてしまいます。楽しいエピソードを話すなど、参加者全員で明るい気持ちになるよう心がけましょう。
5. 精進落としの流れ
精進落としは、以下のような流れで行われるのが一般的です。
1. 喪主の挨拶
2. 親族代表者の献杯
3. 会食・歓談
4. 締めの挨拶(喪主か親族代表)
全員が席についてことを確認したら、最初に挨拶が行われます。そしてそのままの流れで献杯が行われ、歓談となります。
献杯の際に最初にお酒を注ぐのは、故人の位牌の前の杯です。続いて全員の杯にもお酒が注がれ、献杯の発声が行われます。
参加者は代表者の発生に合わせて自身も唱和し、杯は軽く持ち上げるのみです。一般的な乾杯のように隣の人の杯に自分の杯を当ててはいけません。献杯後の拍手も不要なので、注意しましょう。
開始の挨拶では「葬儀が滞り無く終わった報告」と「関係者への感謝」が伝えられます。最後の挨拶でも感謝の意を伝えますが「その後の法要スケジュールなどの連絡事項」は、この時に伝えておきましょう。僧侶が出席している場合は、お布施を渡すのを忘れないように注意してください。
告別式当日の流れと所要時間を解説
告別式の当日には、精進落としが行われるまでにも様々な儀式があります。全ての儀式の内容を把握している方は少ないのではないでしょうか。
ここでは、告別式当日の流れと、各所要時間を解説します。当日の全体のスケジュールが理解できるような内容になっているので、ぜひとも確認してください。
1. 受付(準備含む)【45分】
受付の開始時間は、告別式開始の30分前に設定するのが一般的です。準備も含めて15分程余裕を持って、受付場所にいることをおすすめします。
実際に、案内している時間より早めに来る方は多いです。会場には案内できなくても、その場にいることでお声がけ等することができます。それまでは遺族用の控室が用意されているので、そこで待機しましょう。
2. 各関係者の入場【15分】
入場する順番についてですが、一般的には以下のとおりです。
1. 遺族と親族
2. 一般の参列者
3. 僧侶
席順は祭壇に向かって右側が親族席で、左側が一般参列者の席となります。親族席も喪主が最前列の通路側で、血縁の深い順番に座っていくのがしきたりです。一般参列者についても決まりがあり、故人との関係が深い順番に座っていきます。
3. 開式から読経まで【30分~40分】
僧侶が入場したら開式となります。司会の方が「ただいまより故○○○○の葬儀ならびに告別式を執り行います」といったように簡潔に開式の辞を述べます。その後、僧侶による読経が始まるのが一般的です。
読経とは声に出してお経を読むことですが、告別式における読経は「参列している親族や近しい人に説法する」という意味もあります。また一口に「読経」といっても、仏教の中の宗派ごとに形式は異なります。
4. 各関係者の焼香【20分】
各関係者が焼香を行いますが、ここでも順番があります。親族から血縁の濃い順番に行うのがしきたりです。
入場の際にその順番で着席していますので、祭壇に近い席の方から順番に焼香をあげていけば問題ありません。
一般的な焼香の手順は、以下のとおりです。
1. 祭壇に進んで遺族に一礼
2. 焼香台の手前で祭壇に一礼
3. 抹香(まっこう)をつまんで香炉に落とす
4. 宗派ごとの作法で1回~3回繰り返す
5. 遺影に向かって合掌・一礼
6. 遺影を向いたまま下がって遺族に一礼
5. 喪主の挨拶【2分~3分】
喪主の挨拶は2~3分程度で、簡潔に行います。挨拶の内容は以下のとおりです。
・参列者への御礼
・故人の趣味など人柄がわかるエピソード
・自身の心境
・故人がお世話になったことへの感謝
故人のために集まっていただいた参列者に対して、喪主が自身の言葉で感謝の想いを伝えます。
6. 出棺の儀【30分】
出棺の儀は、以下のような流れで行われます。
1. 別れ花
2. 釘打ち
3. 出棺・お見送り
4. 火葬場への搬送
まずはお棺の蓋を開けて、ご遺体の周りを「別れ花」という生花で飾ります。花だけでなく、故人の思い出の品なども入れることが一般的です。
次に「釘打ち」ですが、小槌や小石で釘を2回打ち込んでお棺に蓋をします。物理的に蓋を固定する意味合いと、死者の蘇りを防ぐ宗教的な意味合いがある儀式です。
その後は参列者全員で棺を見送って、火葬場へ搬送されます。
7. 火葬【1時間】
火葬場へは喪主と近しい親族が移動し、一般の参列者は同行しません。火葬場に到着すると、火葬炉の前に棺が置かれた状態で「納めの式」が行われます。この場が故人との最後の別れとなり、ここで僧侶による読経が行われます。
この後に棺が火葬炉に入れられ、火葬の開始です。火葬の所要時間は1時間程度が一般的で、その間は控室で待機します。なお、控室には遺族側で軽食などを用意しておくことが一般的です。
8. 骨上げ【30分】
骨上げとは、火葬されて残った骨を二人で箸を使って、一つずつ骨壷に納める儀式です。最初に担当者が最後に納める頭蓋骨や、喉仏の骨をよけておいてくれます。
担当者による準備が完了したら、喪主などの故人の近しい親類から、二人ずつ順番に行います。最後は火葬場の担当者が、骨壷に納まるように整えてくれるので安心してください。
9. 初七日法要【30分】
初七日法要とは、正式には故人が亡くなってから七日目に行う法要です。しかし、近年では繰り上げて告別式当日に行うのが一般的となっています。葬儀が終わった直後に遺族が再び集まることは、負担が大きいというのが大きな理由です。
内容としては僧侶に読経していただき、遺族が祈りを捧げて焼香をあげます。故人が無事に浄土へ行けるよう供養を行う儀式です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
社会に出れば葬儀に参列する機会が増えていくものですが、精進落としまで参加する機会は多くはないでしょう。
精進落としに招待されるということは、故人は自身にとって近しい存在であったと考えられます。そのようなケースでは失礼のないよう、葬儀全体の流れを把握しておくことが重要です。
「小さなお葬式」では葬儀に関するあらゆるご相談に対応するべく、24時間365日対応のコールセンターを用意しております。ぜひともお気軽にお電話ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



お彼岸の時期は年に2回で、春分の日、秋分の日の頃だと覚えておくとよいでしょう。ホゥ。