初七日法要は、葬儀後に初めて執り行う追善供養のひとつです。初めて喪主を務める場合、初七日法要について概要を理解できていない方もいるのではないでしょうか。日程や必要な準備など一連の流れを知っておけば、当日も慌てることなく喪主を務められるでしょう。
そこでこの記事では、初七日法要について詳しく解説します。当日までに必要な準備や挨拶の参考になる例文についても紹介していますので、喪主を務める可能性がある方はぜひ参考にしてください。
葬儀全体の流れについては別のページで詳しくまとめています。振り返りとしてぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・初七日法要には遺族が故人の冥福を祈る意味があり、故人が亡くなってから7日目に行われる
・初七日法要の日取りは、行う場所などと一緒に葬儀の段階で決める
・日程が決まったら菩提寺に連絡して、読経の依頼を行う
こんな人におすすめ
初七日法要の日程を考えている方
初七日法要について知りたい方
初七日法要の事前準備をしておきたい方
初七日法要にはどのような意味がある?
初七日法要の「初七日」の読み方は、「しょなのか」または「しょなぬか」です。初七日法要には、遺族が故人の冥福を祈る意味があります。故人が無事に極楽浄土に行くためには、遺族が追善供養しなければいけません。
また、区切りとなる四十九日までに執り行う追善供養の回数は計七回です。初七日法要は初回であり、最終回の四十九日には故人が極楽浄土に行けるかどうかが分かります。
初七日法要が行われる日はいつ?
初七日法要を執り行う際は、初七日までの数え方に注意します。初七日とは、故人が亡くなった日である命日から数えて7日目です。
ただし、地域によっては亡くなる前日から数える場合もあります。最近は同居ではなく離れて暮らすご家族も増えてきたことから、初七日法要を葬儀の日にまとめて執り行うケースも増えてきました。
しかし、同じ仏教でも宗派が浄土真宗の場合は、初七日法要を執り行う意味合いが異なるため注意しましょう。浄土真宗では、故人は亡くなったら時間をかけることなく極楽浄土に行けるとされています。そのため、初七日法要は遺族が故人を想う意味合いで執り行われるのが一般的です。
葬儀と同じ日に行う・葬儀とは別日に行う
初七日法要のタイミングは、遺族の事情に合わせて決めましょう。パターンとしては2つあり、葬儀の日に行う場合と、葬儀とは別日に行う場合があります。それぞれの違いを遺族や参列者が事前に知っておけば、当日に戸惑うことも少なくなるでしょう。
葬儀と同じ日に初七日を行う
以前は、葬儀と初七日を別日に行うパターンが一般的でした。しかし近年は参列者への負担を考えて、葬儀と同じ日に行うことが多くあります。
これが「繰り上げ初七日」または「繰り込み初七日」です。繰り上げ初七日は、火葬を終えてから斎場に戻り、初七日を行います。また繰り込み初七日とは、葬儀の中に初七日を取り入れて行う法要です。
最大のメリットは、参加者が別日の予定を確保しなくてよいことでしょう。別日に行うと、参列者の都合で参列できない場合があります。
慣例通りに初七日に行う
正式な形で命日から数えた7日目に初七日を行う場合は、近しい親族に声を掛けて自宅やお寺などに集まるのが一般的です。声を掛ける人数が多い場合は案内状を出しますが、少ない場合は直接伝えたり、電話でその旨を伝えたりするとよいでしょう。
当日は僧侶が読経を上げたら参列者は焼香を行い、精進落としで故人を偲びながら会食する流れです。また、地域によってはお墓がある場所で焼香を行うこともあります。
初七日に行う場合は僧侶への心付けを準備
葬儀と別の日に初七日法要を行う場合は、僧侶への心付け(お布施)の準備が必要です。相場はお車代として5,000円~1万円前後、御膳料は3千円~5千円前後となっています。
渡す際は、奉書紙または白封筒(無地のものに限る)に入れましょう。見た目にこだわりたい場合は、双銀または白黒の水引を付けます。地域によっては白と黄色の水引を付けても問題ありません。
初七日法要までの4つの準備
初めて喪主を務める場合、初七日法要に向けて何をすればよいのか分からない方もいるのではないでしょうか。故人が無事に極楽浄土に行くためにも、喪主としてしっかりと役割を果たす必要があります。ここでは、初七日法要までにしておくとよい準備について確認しましょう。
1. 初七日法要の日程を決める
初七日法要の日取りは、行う場所や誰を招くのかなどと一緒に葬儀の段階で決めます。行う場所として選ばれることが多いのは自宅、お寺、斎場です。また初七日法要を月日に行う場合は命日から数えて7日目のため、葬儀から日が経っていません。そのため、声をかける人は故人や遺族にとって近しい人のみになることが多い傾向です。
2. お寺・葬儀社に依頼
日程が決まったらお寺や葬儀社に依頼しましょう。
お寺とお付き合いのある方
菩提寺(ぼだいじ)とは、先祖代々のお墓のあるお寺のことです。菩提寺がある場合には、菩提寺に連絡をして、読経の依頼を行いましょう。本家との付き合いがある分家の場合は、本家のお寺へ依頼してみるとよいでしょう。
お寺とお付き合いが無い方
菩提寺が無い場合には、知人縁故からお寺を紹介してもらう方法や、葬儀の際にお世話になったお寺に相談する方法があります。
その他最近では、インターネット上でお坊さん手配サービスを利用される方も増えています。
自宅や斎場はもちろん、手配したお坊さんのお寺での法要も行えるので、菩提寺がない方には便利です。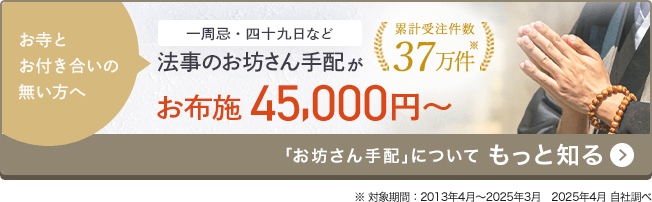
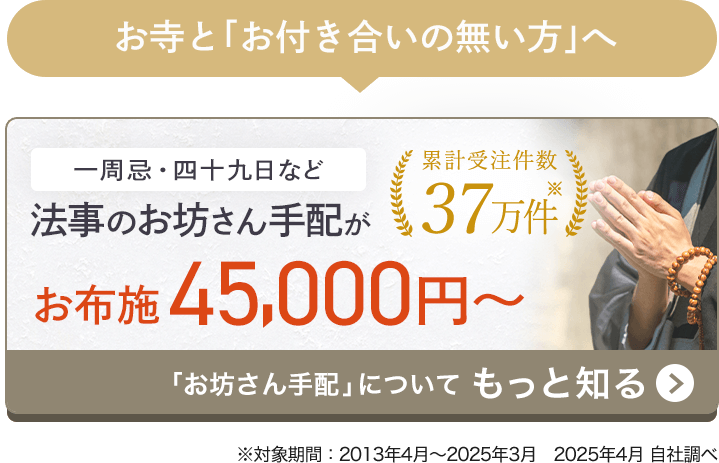
3. 精進落しを注文
お寺や葬儀社への依頼が済んだら、精進落としの準備に取りかかります。精進落としとは、遺族が僧侶や法要の参列者に向けて感謝の気持ちを伝える会食です。近年は、仕出し弁当を注文する遺族も増えてきました。
精進落としにかけられる費用は各家庭で変わってきます。事前にメニューや値段を確認した上で、参列する方の人数分を注文しておくとよいでしょう。
4. 香典返しを準備
初七日法要では、葬儀と同様に香典返しを準備します。弔事の返礼品は「消え物」を選ぶのがマナーです。飲食することで形に残らないものを選ぶとよいでしょう。ただし、いただいた香典に対してふさわしい金額の返礼品をそれぞれ選ぶため、数が多くなればなるほど遺族の負担になります。
近年は参列者が好きなものを選べる観点から、カタログギフトを選ぶ遺族も増えてきました。
初七日法要の挨拶には型がある
喪主は初七日法要の際に、参列者に対して挨拶をしなければいけません。どのようなポイントを踏まえて挨拶するのが正解なのか、分からない方もいるのではないでしょうか。挨拶のポイントを以下にまとめましたので、参考にしてください。
【挨拶序盤】
・初七日法要の参列者に対して感謝の気持ちを伝える
【挨拶中盤】
・遺族視点で故人が亡くなってからの気持ちの変化を伝える
・葬儀への参列に対して感謝の気持ちを伝える
【挨拶終盤】
・再度、初七日法要の参列者に対して感謝の気持ちを伝える
以下に例文を紹介しますので、挨拶の言葉が思い浮かばない場合は参考にするとよいでしょう。
本日はご多忙の中にもかかわらず、母○○の初七日に参列いただきましてありがとうございました。この通り、無事に初七日法要を済ませられそうです。誠にありがとうござしました。
葬儀の際はここに居る皆様をはじめ、さまざまな方に良くしていただいたことを心より感謝しております。
多くの心配をおかけしたとは思いますが、母の死後から7日目となった本日はすっかり気持ちも落ち着きました。突然のことで正直なところまだ信じられないのですが、少しずつ気持ちを整理しながら前向きに生きていければと思っております。
本日は皆様への感謝の気持ちを込めて、簡単ではありますが会食の場を設けました。母も喜ぶかと思いますので、時間が許す限りごゆっくりとおくつろぎください。本日はご多忙の中、参列いただきまして誠にありがとうございました。
仏壇店に位牌を依頼
位牌には、白木の位牌と本位牌があります。白木の位牌は四十九日法要まで位牌の代わりとして、本祭壇に祀るものです。四十九日法要時には菩提寺に納めます。それと引き換えに、住職が魂を入れた本位牌を仏壇に祀る決まりです。
本位牌は戒名の文字を入れる関係で、出来上がるまでに2週間程度要します。四十九日法要に間に合わない事態を避けるためには、できるだけ早く仏壇店に依頼したほうがよいでしょう。
初七日・四十九日までの心得
遺族は四十九日を迎えるまでは忌中(きちゅう)となり、故人の死を悼みながら過ごします。そのため、生活するうえで行動をセーブしなければいけないこともあるでしょう。
例えば、お祝いごとは四十九日を迎えるまでは避けます。他にもさまざまなことに注意しながら、生活することになるでしょう。ここでは、初七日・四十九日までの過ごし方を解説します。
忌中・喪中の意味とは?
忌中・喪中とは、遺族が故人の死を偲びながら身を慎む期間のことです。仏式の場合は四十九日を迎えたことを忌明けといいます。忌明け後はお祝いごとへの出席を控える必要はありません。遺族は香典を送る時期です。
忌中の期間は宗教によって異なります。キリスト教では1ヶ月後の召天記念日または五十日祭まで、仏式では四十九日、神式では五十日祭までが一般的です。喪中は宗教に関係なく1ヶ月となっています。
初七日・四十九日の祭壇の意味は?
四十九日を迎えるまでは、自宅に「後飾り」と呼ばれる祭壇を設置して、遺骨と位碑を祀りましょう。後飾りを中陰壇と呼ぶ地域もあります。祭壇には五供(ごく)であるお香、お花、お灯明、お仏飯、お水(浄水)を供えるのが基本です。
葬儀社に依頼すれば、祭壇の飾りを含めた設置を全て済ませてもらえます。初七日までの仮の祭壇ではありますが、四十九日の法要まではそのままにしておきましょう。
供養の方法は?
初七日・四十九日までは、法要のときだけと限定することなく、日常的に供養するのがベストです。祭壇にお供え物を用意して手を合わせ、故人を偲ぶことが供養に繋がります。四十九日までは線香の火を絶やさないほうがよいと考える家庭もあるため、分からない場合は周りの人に確認するとよいでしょう。
また祭壇がある家を生活拠点としていない方の場合は、忌中といえども遺族の生活もありますので線香の火を絶やすのは難しいかもしれません。
その場合は故人を偲んだり、ご飯やお花などを供えたりするときに線香の火を焚きます。故人の知人や友人がお参りに来るときも線香を焚くようにしましょう。
お祝いごとは自粛する?
忌中・喪中の間はお祝いごとを主催することは避け、参加することもできるだけ控えます。お祝いごとの代表になりやすいのが、年賀状のやりとりや結婚式です。
正月が喪中と重なる場合は全ての恒例行事を取り止めましょう。また喪中はがきを出せば、相手に年賀状が出せないことや新年の挨拶を遠慮する旨が伝わります。
挙式予定があったり、知人の結婚式に参列する予定があったりした場合はできるだけ控えたほうがよいでしょう。参列できない旨を伝える場合は、忌中や喪中であることを伝えるのはふさわしくありません。
お中元・お歳暮は贈らない?
お中元・お歳暮は、相手に感謝の気持ちを伝える習慣のひとつです。年賀状や結婚式などのお祝いごとではないため、喪中に贈っても問題ありません。
ただし、忌中の場合は控えたほうがベターです。気にしない方も増えてきましたが、忌中にお中元・お歳暮を贈ると穢れを広めてしまうと考える方もいます。
また故人が亡くなった時期によっては、お中元・お歳暮の時期と香典返しの時期が重なることもあるでしょう。日ごろからやりとりしている相手には、忌中であることを事前に伝えておくと安心です。
初七日法要における参列者のマナー
初七日法要に参列する場合は基本的なマナーを守った上で、故人が無事に極楽浄土に行けるよう祈ることが大切です。初めて参列する場合は、香典は持参したほうがよいのか、挨拶はどうすればよいのかなど分からないことも多くあるでしょう。ここでは、初七日法要に参列する際に参考になるマナーを解説します。
香典を持参する
初七日法要を葬儀と分けて執り行う場合、参列者は香典を持参しましょう。葬儀で香典を渡した場合は、包む金額は半額にします。香典の相場は故人と参列者の関係性によって異なるため、それぞれが判断し適切な金額を包むことが大切です。以下に香典の相場をまとめました。香典の金額に迷った時は、目安にするとよいでしょう。
| 両親・義理の両親 | 3万円~5万円 |
| 兄弟・姉妹 | 3万円 |
| 祖父母 | 5,000円~1万円 |
| 友人・知人 | 3,000円~5,000円 |
また参加者の年齢が若い場合は、相場よりも低い金額で香典を包んでもマナー違反にはなりません。地域によって相場が異なることもあるため、事前に確認するとよいでしょう。
お悔やみの挨拶を述べる
香典はのし袋に入れ、袱紗(ふくさ)に入れて持参します。会場に到着したら、受付の方に渡すのが一般的です。渡す際はお悔やみの挨拶を述べましょう。
「心からご冥福をお祈りいたします」「この度はご愁傷様でございます」など、短く済ませるのがベストです。また受付の方と簡単に会話する場合は、忌み言葉を使用しないように注意しましょう。
服装のマナー
葬儀と分けて初七日法要を執り行う場合、参列者は簡易喪服で参列します。葬儀と同日の場合は喪服です。男性はスーツとネクタイは共に黒無地のものを、シャツは白を着用します。女性は露出しないワンピースやスーツを選び、控えめで暗い色の服を着用しましょう。
また、初七日法要では派手な服装はふさわしくありません。故人が無事に極楽浄土に行くためにも、マナーを守った服装で参列することが大切です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
初七日法要や四十九日法要を遺族がしっかり行えば、故人が極楽浄土に行きやすくなります。忌中・喪中の間は故人を偲んで、遺族としてふさわしい過ごし方を心掛けましょう。
遺族にかかる負担を和らげるには、小さなお葬式がおすすめです。葬儀にかかる費用を抑えながら、無理のない範囲で葬儀や法要ができます。費用面とサービス面のどちらも重視した葬儀社をお探しであれば、小さなお葬式にお任せください。


墓じまいとは、先祖供養の続け方を考えた際の選択肢の一つです。ホゥ。






































