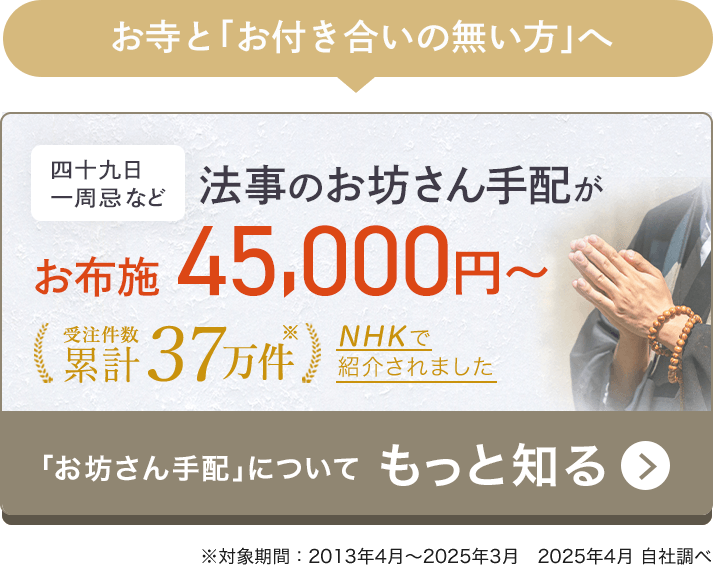法事に出席した際、仏壇の前にお供え物が置かれているのを目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。仏飯やお餅などのお供え物は遺族が用意しますが、お菓子や果物などは、法事の出席者が持参する場合もあります。
そこで今回は、法事に出席する際のお供え物の必要性やお供え物の選び方を紹介します。
<この記事の要点>
・法事のお供え物は必須ではないが、事前の断りがない限りは持っていく方がよい
・法事のお供え物の金額は3,000円~5,000円が相場
・お供え物ののし紙には四十九日までは「御霊前」、四十九日以降は「御仏前」と書く
こんな人におすすめ
法事に参列予定の方
法事に持参するお供え物にお悩みの方
お供え物の選び方や目安の金額を知りたい方
法事とは?法要との違いは
「法事」と「法要」は仏事の際によく聞く言葉ですが、違いがよく分からないという方も少なくありません。ここからは、法事の意味と法要との違いを解説します。
法事と法要は違う?
「法事」は仏教行事全般のことで、法要から会食までを含めた一連の行事を指す言葉です。「法要」は忌日法要や年忌法要など、故人の供養に関する行事を指します。
法要以外のさまざまな仏教行事も「法事」と呼ばれます。仏教的に正しい表現を用いるのであれば、法事と法要の細かい意味の違いを理解しておきましょう。
故人が亡くなってからの1年は法事が多い
故人を供養する行事には「○○法要」という名前がついています。故人を供養する法要は定期的に執り行われますが、亡くなってから1年間は特に法要が多くあります。一周忌までに行われる法要は以下のとおりです。
| 法要名 | 亡くなってからの日数 | 法要実施の有無 |
| 初七日 | 7日目 | 葬儀・告別式と同日に実施することも多い |
| 二七日 | 14日目 | 省略される場合あり |
| 三七日 | 21日目 | |
| 四七日 | 28日目 | |
| 五七日 | 35日目 | |
| 六七日 | 42日目 | |
| 七七日(四十九日) | 49日目 | 実施するのが一般的 |
| 百箇日 | 100日目 | 省略される場合あり |
| 一周忌 | 1年目 | 実施するのが一般的 |
四十九日までは7日ごとに忌日法要がありますが、昨今は省略されることも多いです。初七日・四十九日・一周忌のみ行うケースも増えています。
一周忌以降の法事は
一周忌以降の法事(年忌法要)は、以下のとおりです。
| 法要名 | 亡くなってからの年数 | 法要実施の有無 |
| 三回忌 | 2年後の命日 | 多くの参列者を招き実施するのが一般的 |
| 七回忌 | 没後6年 | 小規模で実施する家庭もある |
| 十三回忌 | 没後12年 | 小規模で実施する家庭もある |
| 十七回忌 | 没後16年 | 実施する場合は家族だけが多い |
| 二十三回忌 | 没後22年 | 実施しない家庭も多い |
| 二十七回忌 | 没後26年 | 実施しない家庭も多い |
| 三十三回忌 | 没後32年 | 弔い上げとして実施することも多い |
| 三十七回忌 | 没後36年 | 実施しない家庭も多い |
| 四十三回忌 | 没後42年 | 実施しない家庭も多い |
| 四十七回忌 | 没後46年 | ほとんどの家庭では実施しない |
| 五十回忌 | 没後49年 | 正式な弔い上げとして実施することも多い |
| 百回忌 | 没後99年 | ほとんどの家庭では実施しない |
三回忌を行ってからは、遺族や近しい親族のみで小規模で法要を行う、もしくは法要そのものを行わないというケースも増えています。
また、正式には五十回忌が「弔い上げ」と呼ばれ、最後の法要として盛大に行われますが、昨今は三十三回忌を弔い上げとして、それ以降の法要はしないという家庭も多いです。
法事にはお供え物が必要?
親族が亡くなると、定期的に法事に呼ばれることもあるでしょう。また、年齢を重ねると、親しい友人や職場の方などの忌日法要や年忌法要に出席する機会も増えます。ここからは、法事に参列する際のお供え物の必要性について解説します。
法事のお供え物は「必須」ではない
法事に出席する際、必ずしもお供え物を持参する必要はありません。とはいえ、お供え物を持っていくと故人や遺族への心遣いの気持ちが伝わるでしょう。
持参したお供え物は、親族への手土産や法事の際のお茶請けに使用されることもあります。
持っていったほうがよいケース
お供え物を持参しなくても、マナー違反にはなりません。しかし、親戚の法事など「お供え物はお互いなしで」といったきまりがない場合は持参するのが一般的です。
親戚以外の法事であってもお供え物を準備する方が多いので、事前の断りがない限り「持っていくもの」という認識でいましょう。
学生の場合は持参しなくても問題ありませんが、家族と相談しながら品物をきめてもよいでしょう。
お供え物はすべての法事に必要?
お供え物はすべての法事に必要なわけではありません。一般的にお供え物が必要なのは、初七日と四十九日です。
年忌法要の場合は地域によって異なりますが、七回忌までは持参してそれ以降のお供え物は不要とすることが多いでしょう。参列者同士で事前に話し合って足並みをそろえるとよいでしょう。
【法事のお供え物】金額の目安や一般的な品物は
法事に参列する際はお供え物を持参しますが、いくらくらいの品物を選べばよいかわからない方もいるかもしれません。ここからは、お供え物の金額の目安やふさわしい品物を紹介します。
お供え物の金額の目安
地域差もありますが、法事のお供え物の金額は3,000円~5,000円が目安です。あまりにも高額なお供え物は、遺族が恐縮してしまう可能性があるため避けましょう。遺族に気を遣わせない範囲の予算で選ぶのが理想的です。
どのようなものを選べばよい?
お供え物にするなら、お茶請けや手土産などになるお菓子が最適です。お菓子以外にも、お供え物にふさわしい品物があります。
・線香
「心身を浄化する」という意味があり、お供え物として喜ばれます。
・ろうそく
「故人がいる場所を明るく照らす」という意味があります。
・花
お供え物の定番で、故人に喜んでもらうために持参します。
・飲み物や食べ物
故人への食事や飲み物として供えます。
お供え物は消費してなくなるものを選びましょう。食べ物や飲み物の場合は、衛生面にも配慮したお供え物を選びましょう。
缶詰がお供え物の定番になっている地域もありますが、食べにくく持ち運びにくいため、選ばない地域も増えています。餅や海苔などの食べ物は缶詰と同じく日持ちするので、お菓子以外の食べ物を選びたいときに便利です。
お供え物のお菓子の選び方
一口にお菓子といっても、和菓子や洋菓子などさまざまな種類があります。お供え物は、後から参列者で分けることがあるため、小分けになっているものが理想です。個別包装されていれば、衛生的で手を汚さずに食べられます。
数日お供え物として仏壇に置いておくことも想定して、常温保存が可能な日持ちするものを選ぶことも大切です。
お供え物を食べ物にする場合は、子どもから高齢者まで食べやすいものを選びましょう。また、ニンニク風味やカレー風味など、においが強いお菓子はお供え物としてふさわしくありません。パッケージが華やかなお菓子も法要には不向きです。
お供え物におすすめのお菓子は
ここからは、お供え物におすすめのお菓子を紹介します。
・洋菓子
マドレーヌやクッキーなど、誰でも一度は口にしたことのあるようなものを選ぶとよいでしょう。賞味期限が短く、冷蔵保存が必要なケーキなどは選ばないようにしましょう。
・和菓子
羊羹やもなか、団子、まんじゅうなどがお供え物として人気です。ただし、和菓子のなかにはのどに詰まりやすいものもあるので注意が必要です。せんべいもおすすめですが、硬すぎるものは避けましょう。故人が好きだった和菓子があれば、それを持参してもよいでしょう。
・地域の特産品
遠方から法事に参列する場合は、地元の名産品を選ぶのもおすすめです。地域の銘菓は、遺族からも喜ばれるでしょう。
銘菓であっても、日持ちのしないものや個包装になっていないものは避けましょう。
【法事のお供え物】包み方や渡し方のマナーを確認しよう
法事に持参するお供え物を選んだら、包み方や渡し方を確認しましょう。ここからは、正しいのし紙の選び方や表書きの書き方、施主への渡し方を紹介します。
お供え物の包み方
お供え物には法事用ののし紙をかけて、表書きを記入します。のし紙には、包装紙の下にかける「内のし」と包装紙の上にかける「外のし」があります。お供え物の場合は、誰からのものか一目で分かる外のしが適しています。
のし紙には水引が印刷されていますが、四十九日までは白黒、四十九日以降は双銀、三回忌以降は黄白のものを選ぶのが一般的です。ただし、地域によって異なる場合もあるので、親族や親しい方に確認しておくと安心です。
表書きには四十九日までは「御霊前」、四十九日以降は「御仏前」と書きます。水引の下には贈る方の名前を書きましょう。宗派によって表書きが異なる場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。宗派がわからないときには「御供」「粗供養」と記入します。
お供え物はいつ渡す?
準備したお供え物は、施主に挨拶をするときに渡しましょう。香典とお供え物を一緒に渡して「御仏前にお供えください」など一言添えると丁寧です。
施主以外の方に渡したり、勝手に仏壇に供えたりするのはマナー違反になるため、注意しましょう。
お供え物を渡す際のポイント
お供え物にはのし紙をかけて、持参する際は紙袋などに入れましょう。渡す際は、紙袋から出して中身だけを施主に渡して紙袋は持ち帰ります。紙袋がない場合は、風呂敷に包むと丁寧です。風呂敷の場合も、中身だけを渡しましょう。
【法事のお供え物】さまざまな疑問を解決しよう
法事に参列できない場合、お供え物はどうしたらよいのでしょうか。品物ではなく現金で用意しても問題ないのでしょうか。
ここからは、法事のお供え物に関するよくある質問と回答を紹介します。お供え物選びの際の参考にしてみてください。
法事を欠席する場合、お供え物はどうする?
法事をやむを得ず欠席しなければならないこともあるでしょう。その場合は、香典とお供え物をそれぞれ送ります。送る場合の注意点は以下のとおりです。
・欠席連絡は早めに
法事を欠席する場合は、施主に電話などで直接事情を説明しましょう。出席できないとわかった時点で連絡をしてお詫びをすると丁寧です。
香典とお供え物は、法事が行われる日の前日までに現地に届くように手配しましょう。欠席連絡をする際に「○月○日にお供えが届くよう手配しました。よろしければ御仏前にお供えください」と伝えましょう。
・配送におすすめのお供え物は?
法事を欠席する場合も、お供え物や香典は出席するときと同様の予算で用意します。お菓子は配送手配するお供え物としてもおすすめです。常温保存で日持ちするもの、そして破損しづらいものを選びましょう。
・手紙を添える
お供え物を配送するときは、手紙を添えるとより丁寧です。「心ばかりのものをお送りします。御仏前にお供えください」という言葉とともに、欠席についてのお詫びの言葉を添えるとよいでしょう。
香典はお供え物に同封できません。別途現金書留で郵送しましょう。法事の前に遺族を訪ねる時間がある場合は、遺族と相談して前もって渡すのもおすすめです。
品物ではなく金銭でもよい?
地域によっては、お供えを品物ではなく「御供物料」として用意するところもあります。この場合は、香典とは別に金銭を包みます。表書きの上段には「御供物料」、下段には送り主の氏名を書きます。
葬儀とは異なり、四十九日より後の法事でお渡しする現金は新札でも問題ありません。新札を用意できない場合は、できるだけきれいなお札を包みましょう。
お札は葬儀と同様に、肖像画のあるほうを裏に向けて包みます。ただし、包み方も地域によってマナーが異なるので、不安な方は詳しい方に聞いておくと安心です。
お供え物としてふさわしくないものは?
お供え物として肉や魚を選ぶことは避けましょう。これらは「四つ足生臭もの」と呼ばれ、殺傷を連想させるのでマナー違反にあたります。加工品のハムやベーコンなども同様ですので注意しましょう。
また、お菓子などは個包装だと分けやすく親切ですが、4個や9個入りは「死」「苦」を想起させ縁起が悪いとされています。お供え物を用意するときは、個数にも注意をするようにしましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
法事に出席する場合は、香典と別にお供え物を準備して持参します。お供え物には、常温保存が可能な日持ちする個包装のお菓子がおすすめです。3,000円~5,000円を目安に選びましょう。
法事に参列できない場合は、お供え物と香典を配送しましょう。香典は普通郵便では送れないため、別途現金書留で送ります。お供え物を配送する際は、手紙を添えるとより丁寧です。
法事の準備や葬儀についてお困りのことがございましたら、「小さなお葬式」にご相談ください。専門知識を持つスタッフが、24時間365日、通話料無料でお客様のお悩みに寄り添い丁寧にアドバイスいたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


遺言者の意思や希望を書面に反映し、公文書として承認された遺言書が「公正証書遺言」です。ホゥ。