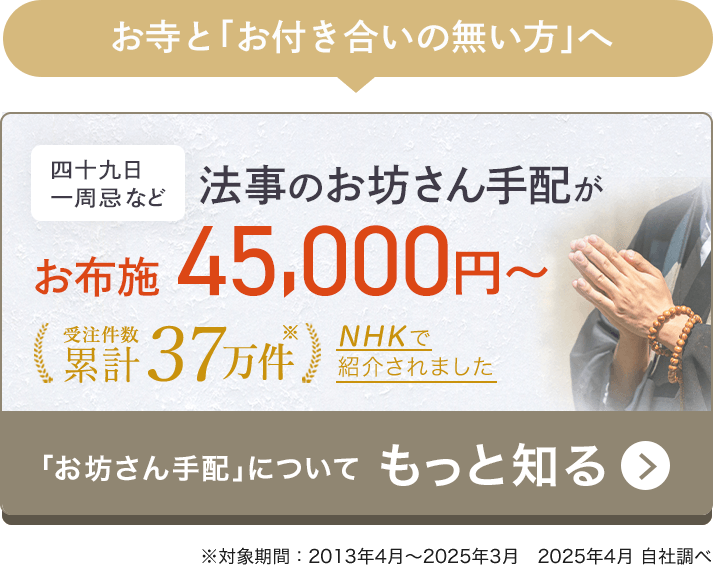一周忌や三回忌の案内状が届いた際、あるいは実際に法要を営む際に、回忌法要とは何か疑問に思った方もいるでしょう。回忌とは亡くなった方の命日に合わせて営む法要で、まだ亡くなってから年数が浅い場合は葬儀と同様に人を集めて執り行うことが一般的です。
今回は回忌の基本や間違えやすい一回忌と一周忌の違い、さらに回忌法要をどこまで続けるかの目安について解説します。日々の供養を大切にしつつも、悔いのない供養ができるよう、知識を深められる内容です。
<この記事の要点>
・回忌とは、亡くなった方の祥月命日に執り行う年忌法要を営む日
・一回忌とは亡くなった当日のことで、一周忌は命日から1年経った祥月命日を指す
・回数は命日(一回忌)から起算するため、三回忌は亡くなってから2年目にあたる
こんな人におすすめ
回忌について知りたい方
一回忌と一周忌の違いについて知りたい方
回忌法要をどこまで続けるのかお悩みの方
回忌とは年忌法要を営む日
故人の祥月命日が近くなると、三回忌・七回忌などの年忌法要について関心が高まるでしょう。回忌は仏式の供養において故人を偲ぶ重要な意味を持ちます。以下では年忌法要の基本や開催する時期についてまとめました。また、間違われやすい法事・法要の違いも合わせてチェックしましょう。
年忌法要とは
年忌法要とは、亡くなった同じ月・同じ日(祥月命日)に執り行う供養の儀式です。親族が一堂に会し、僧侶による読経やお墓参りによって故人を偲びます。三回忌や七回忌など、決まった年数で開催することが一般的です。
年忌法要の規模や意味合いは地方やご家庭、寺院側の考えによって異なります。七回忌を一区切りとして以降は規模を小さくすることもあれば、三十三回忌の弔い上げまで各年忌法要をきちんと行うこともあるでしょう。
祥月命日に営むべき?
祥月命日は亡くなった月日を指します。ある年の8月31日に亡くなった方がいるなら、翌年以降の8月31日がその方の祥月命日に当たります。年忌法要は祥月命日に営むことを推奨されますが、平日や長期休み開けなど参列者を呼びにくい場合は別の日取りでも問題ありません。
法要の日取りを調整する場合は、原則としてその日より前に執り行います。なお七回忌以降に他の方と合同で法要を行う(併修する、あるいは合斎する)場合は、日程は祥月命日が早い方に合わせ、式の順番は亡くなってから年数の浅いほうから始めるのが通例です。
法事と法要の違いは?
法要は故人の供養のための仏教儀式で、僧侶からの読経や焼香を行います。一方で法事は法要に加え、その後の食事会(お斎)を含めた一連の行事のことです。つまり法要は、法事に含まれるひとつの儀式と言えます。最近は新型コロナウイルスの感染拡大により、法事の規模を小さくしたり、法要のみ行ったりするケースも少なくありません。
一回忌と一周忌の違いは?
一回忌と一周忌は同じ「1」がつくことから、混同されることも多いものです。しかし一回忌と一周忌は、明確に違う日を指します。ここでは、一回忌と一周忌の違いに加え、それぞれの儀式の意味合いを見てみましょう。
一回忌とは
一回忌は「1回目の命日」の意味で、亡くなった当日のことです。つまり一回忌の法要は葬式のことですが、葬式を一回忌と呼ぶことはあまりありません。
また、一回忌(命日)から数えて49日間を中陰(ちゅういん)と呼びます。地域によって期間や考え方は異なりますが、この期間中は亡くなった方の霊がまだ現世に留まっているため、追善供養を行うことで死後の裁きがよりよいものになるよう祈ります。
一周忌とは
一周忌は「命日から1年経った祥月命日」を指します。伝統的に一周忌までは喪中と考えられており、一周忌法要は喪明けの区切りとなる重要な儀式です。親族や僧侶を呼び、葬儀と同等の規模で法事・法要を開く方が多いでしょう。
なお、年忌法要としては一回忌ではなく一周忌が正確な呼び方です。それぞれが混合してしまわないよう、しっかりと意味を理解しておきましょう。
回忌の数え方
回忌の数え方は特徴的なため、混乱する方もいるでしょう。特に一周忌と三回忌は数字が離れているにも関わらず、亡くなった翌年・翌々年と続けて営むため、難しく感じるかもしれません。ここでは回忌の数え方の仕組みと、迷った際の計算方法について解説します。
○回忌とは○回目の祥月命日
○回忌とは「○回目の祥月命日」という意味です。回数は命日(一回忌)から起算するため、三回忌であれば亡くなってから2年目、七回忌なら6年目に行います。なお、亡くなった翌年に開く法事は二回忌とも考えられますが、「一周忌」と呼ぶのが通例です。命日の当日を基準とする考え方は、日本古来の数え年の考え方とも共通しています。
何年後か迷ったら「回忌-1」
回忌を開く時期に迷ったら「回忌-1」の式で計算します。例えば三回忌なら「3-1=亡くなってから2年後」、三十三回忌であれば「33-1=亡くなってから32年後」です。
一周忌・三回忌は立て続けに開きますが、七回忌以降は4~6年ごとの開催になるため時期が判別しにくくなります。回忌のだいたい半年前には法要を営むかどうか決める必要があるため、上記の式を利用して開催する年を忘れないようにしましょう。
年忌法要早見表
ここでは、主な年忌法要を「命日から何年後に執り行うか」「亡くなってから何年目に執り行うか」に分けて早見表を作成しました。年忌法要を行う際の参考にしてみてください。
| 法要名 | 命日から何年後 | 亡くなってから何年目 |
| 一周忌 | 満1年 | 2年目 |
| 三回忌 | 満2年 | 3年目 |
| 七回忌 | 満6年 | 7年目 |
| 十三回忌 | 満12年 | 13年目 |
| 十七回忌 | 満16年 | 17年目 |
| 二十三回忌 | 満22年 | 23年目 |
| 二十七回忌 | 満26年 | 27年目 |
| 三十三回忌 | 満32年 | 33年目 |
| 五十回忌 | 満49年 | 50年目 |
主な年忌法要の意味
どの年忌法要でも故人を偲ぶ気持ちは変わりませんが、規模や意味合いは異なります。特に亡くなってから日の浅い一周忌や三回忌は、親族だけでなく親しかった友人や知人にも声をかける方が望ましいでしょう。なお、年忌法要の考え方は地域や家庭・宗派によっても違いがあるため注意が必要です。
重要な法要である一周忌と三回忌
一周忌と三回忌は、年忌法要の中でも重要視されています。一周忌は喪が明けると同時に、残された方々も気持ちを切り替えて新しいステップに進む節目のタイミングです。そのため参列者も遺族や親族に加えて、故人と親しかった友人、知人を含むことが多いでしょう。
三回忌は一周忌と並んで重視される法要です。規模や参加者の範囲は一周忌とあまり変えずに行います。このため、年忌法要を別の故人とまとめて執り行う併修(合斎)も三回忌までは避けたほうがよいでしょう。
七回忌以降は規模を縮小することが多い
七回忌以降の年忌法要は、参加者の範囲を狭めたり会食をなくしたりして、規模を小さくすることが一般的です。親族が遠方にいて招待が難しい場合など、地元の親族のみで内々に執り行うこともあるでしょう。最近では法要そのものを行わないケースもあります。
しかし、地方に住む親族には法要を開いて欲しいと考える方もいるかもしれません。法要を取りやめる場合は独断で判断するのではなく、親族や葬儀のプロに相談し、双方が納得できる形を目指しましょう。
法要は何回忌まですればいい?
最後の法要を「弔い上げ」と呼びますが、弔い上げとする時期は明確に決まっていません。以下では弔い上げの意味と一般的なタイミングについて解説します。弔い上げの意味を知り、各家庭にあった方法を選びましょう。
弔い上げとは?
弔い上げは最後に行う年忌法要です。場所によっては「問い上げ」「揚げ斎(あげとき)」とも呼びます。仏教では、三十三回忌や五十回忌を迎えるころには、どんな方も無罪放免となり極楽浄土へ行けるという教えがあることも、弔い上げをする理由です。
また、亡くなってから年数が経つと、生前の人柄を知る方もだんだんと少なくなります。「故人を偲ぶ」という本来の意味も薄れるかもしれません。このことから、個人としての法要は一定の年数で止め、以降は先祖と共に故人を祭ります。
三十三回忌が一般的
一般的には三十三回忌をもって弔い上げとします。これは亡くなって約30年経つとだいたい世代が一巡するためです。以降の五十回忌・百回忌を行うこともありますが、これらは「長く家が続いたことへのお祝い」の意味が強くなる傾向にあります。
また、弔い上げの時期は地域や宗派によって違いがあるのも特徴です。近年では遺族の高年齢化などから十七回忌を弔い上げとするケースも増えました。伝統あるしきたりを大切にしつつも、弔い上げの時期は遺族や親族に合ったタイミングで決めましょう。
宗派や宗教による年忌法要の違い
仏教に限らず、神道・キリスト教にとっても命日は意味のある日です。ここでは、仏教の各宗派における年忌法要の考え方や、神道・キリスト教で年忌法要に当たる儀式について解説します。それぞれの違いを知り、宗教・宗派に合った方法で故人と向き合いましょう。
仏教の場合
原則どの宗派でも一周忌から十七回忌までは変わりません。それ以降は規模を縮小するか、法要自体を行わないこともあるでしょう。なお、十七回忌以降は宗派や地域ごとに判断が分かれます。
例えば真言宗や臨済宗では二十三回忌・二十七回忌をまとめて二十五回忌とする寺院もあります。ただし、同じ宗派であっても地域による違いもあるため、迷った際は菩提寺の僧侶や地元の親族に尋ねましょう。
神道の場合
神道で法事に相当する儀式は「霊祭(れいさい)、御霊祭(ごれいさい、みたままつり)」です。中でも年ごとに行う儀式を「式年祭(しきねんさい)」と呼びます。
式年祭では亡くなった翌年の祥月命日に一年祭を行い、年を重ねるごとに二年祭、三年祭と続けます。三年祭の次は五年祭、その次は十年祭となり、以降は十年ごとに五十年祭まで執り行うことが一般的です。
キリスト教の場合
仏教の法要に当たるものとして、カトリックでは「追悼ミサ」、プロテスタントでは「昇天記念日」があります。
カトリックでは亡くなった日から決められた日数で追悼ミサを行い、1年目の命日以降は各家庭で追悼ミサのタイミングを決める方式です。プロテスタントでは、亡くなってから1ヵ月、1年、3年といった区切りの昇天記念日に記念集会を行います。
供養する日は他にもある
供養は毎日の気持ちが大切ですが、法事・法要のようにある区切りに合わせて行うこともあります。中陰法要や、お盆は代表的な供養のタイミングです。以下では中陰法要とお盆の基礎知識や、手厚く供養を行う理由について解説します。
中陰法要
中陰は亡くなってから49日間(7週間)のことです。中陰の期間中は亡くなった方の霊がまだ現世に残って裁きを待っているため、追善供養を通じて故人の冥福を祈ります。数え方は地域によって差がありますが、命日から7日ごとの忌日(きじつ)に合わせて、初七日法要や四十九日法要といった中陰法要を営むのが一般的です。
初七日法要が葬儀と一緒に行われるなど、現在は中陰法要をすべてこなすことは珍しくなりました。しかし中陰の終わりである四十九日には納骨や忌明けがあるため、この日は今でも重視されています。
お盆
お盆は元々「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれ、先祖や亡くなった方の霊がこの世に帰ってくる大切な行事です。戻ってきた霊を迎え火で迎え、期間中は特に丁重に供養をします。地域や風習によって方法や時期が異なるため、お盆の供養の際は地元や親族の意見を伺いましょう。
亡くなった方が四十九日を過ぎて初めて迎えるお盆は「新盆・初盆(はつぼん、ういぼん)」と呼ばれ、お盆の中でも重要な意味を持ちます。無地の白提灯を軒先や仏壇に飾るなど、亡くなってから初めてこの世に戻ってくる故人のために特別な供養を意識しましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
回忌とは亡くなった方の祥月命日に執り行う大切な法要です。親族や故人の友人と共に、亡き方を偲びましょう。回忌法要を営む起源や時期は考え方によってさまざまです。困ったときは寺院や親族に連絡を取ることをおすすめしますが、遠方に住んでいるなどの理由で気軽に相談ができない方もいるでしょう。
回忌法要に際してお悩みの方はぜひ「小さなお葬式」へご相談ください。小さなお葬式では24時間365日、葬儀のプロへの電話相談が可能です。法事・法要以外にも、葬儀・法要全般に関する悩みや疑問を承っております。ささいなことでもかまいませんので、どうぞお気軽にお問い合わせください。


包む香典の金額は、故人・遺族との関係の深さ、年齢や社会的な立場で異なります。ホゥ。