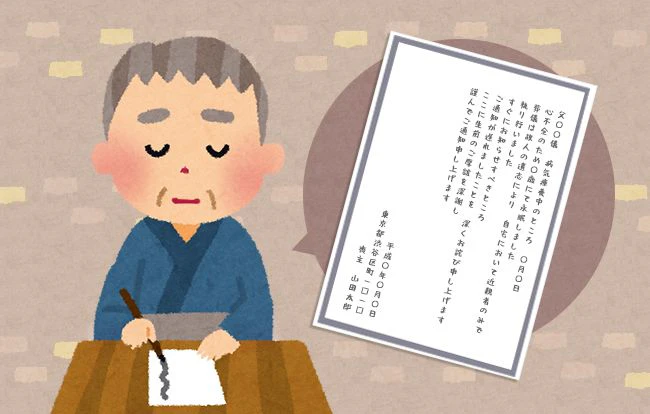家族が病院で死亡した場合、葬儀を執り行うまでに終わらせなければならない手続きがあります。この記事では、死亡から遺体の搬送までの流れや遺族がお葬式までに行うこと、死亡後の手続きについて詳しく解説します。よくある質問と回答も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
<この記事の要点>
・病院で死亡すると、速やかに自宅や斎場などの安置所に遺体を搬送する
・遺体を搬送する際には「死亡診断書」が必要になる
・年金や健康保険関係など、各種名義変更や民間の保険関係などの手続きも必要になる
こんな人におすすめ
病院で死亡した場合の手続きについて知りたい方
死亡からお葬式までの流れを知りたい方
訃報の際の連絡事項について知りたい方
病院で死亡した場合|搬送までの流れ
病院で死亡すると、所定の手続きが終わり次第、自宅や斎場などの安置所に遺体を搬送する必要があります。病院では霊安室のスペースが限られており、長時間の利用ができないためです。
医師による死亡確認がされたあと、臨終・死亡が告知されます。ここからは、死亡告知後に病院外へ遺体を搬送する際の流れを紹介します。
<関連記事>
臨終に立ち会うときの心構えとその後の準備
「末期の水」の儀式
「末期の水(まつごのみず)」とは、故人の口元に水を含ませる儀式のことです。この儀式は、お釈迦様が入滅(亡くなること)する際に口の渇きを訴えて、鬼神が水を捧げたエピソードに由来するといわれています。
ただし、亡くなるとすぐに成仏するという教えの浄土真宗では末期の水を行いません。門徒であれば、事前に病院のスタッフに伝えておくといいでしょう。
体を清める清拭
清拭(せいしき)は故人の体を拭き清めてあげる死後のお世話の一つです。昔はたらいにお湯を入れて入浴させる「湯灌(ゆかん)」が行われることが基本でしたが、近年ではガーゼにアルコールを含ませて全身を拭いてあげる清拭が主流になっています。
清拭や湯灌には現世での苦しみを洗い清める意味があります。また、きれいな状態で死後の世界に送り出してあげる宗教儀式の側面もあります。
身繕いと着替え
体を拭き清めたあとは、遺体に脱脂綿を詰めて身繕いをします。遺体に傷があれば処置を施し、遺体の内部にたまっている老廃物を出させて口や鼻・肛門などに脱脂綿を詰めます。
身繕いが完了したら死装束に着替えさせます。死装束の定番は白装束でしたが、近年ではスーツや着慣れた服を着せるケースも増えています。清拭や身繕いは硬直が出始める前の死後2時間以内に終わらせるのがベストです。死後硬直が始まると遺体の体勢を変えにくくなり、スムーズに儀式が進まない可能性があります。
外見を整える死化粧
死化粧は故人の外見を整え、顔から苦しみを取り除いて安らかな表情で送り出してあげるために行います。男女によって内容に差がありますが、髪を整えて爪を切り、軽く化粧を施すのが共通の流れです。
男性の場合はヒゲを剃り、女性は口紅やファンデーションを私用します。痩せて頬がくぼんでいる場合は、口の中に脱脂綿を詰めて元気だったころの表情に近づけることもあります。生前に愛用していた化粧道具や化粧品がある場合は、それらを使って死化粧をしてもよいかもしれません。
身内への連絡
死亡した事実を故人の身内に知らせる必要があります。訃報を伝える相手は、故人の配偶者・同居人・両親・子どもなど関係が深い方たちです。3親等以内の親戚には知らせたほうがよいでしょう。親戚以外にも、付き合いの深い友人などには訃報を伝えるようにします。
関係が近い方の場合、訃報の連絡は深夜でも問題ありません。電話でしっかりと状況を伝えましょう。友人・知人程度の相手には、時間帯によってはメールで知らせて改めて電話連絡をすることもあります。
葬儀社に遺体搬送を依頼する
遺体の処置が終わったら、次は搬送の手配をします。葬儀社に連絡をして、移動用の寝台車を手配しましょう。
この時点で葬儀社が決まっていなければ、病院に紹介してもらうことも可能です。しかし、病院提携の葬儀社は他の葬儀社に比べて費用が高額になる傾向があります。そのため、前もって葬儀社を決めておくと安心です。
斎場に搬送する場合は、葬儀が始まるまで安置室に遺体を預けることになります。安置室の利用料が発生するかどうか葬儀社に確認しておきましょう。
自宅に搬送する場合は、棺を安置するスペースを確保できるのか、火葬まで遺体の状態を保てる環境があるのかなど、考慮すべきポイントがあります。
死亡診断書の受け取り
病院外に遺体を搬送する際は、死亡診断書が必要です。病院では担当医が死亡診断書を発行します。紛失した場合は再発行できますが、有料になるので大切に保管しましょう。
死亡診断書は、自治体の役場で死亡届を提出する際に必要です。死亡届は亡くなってから7日以内に提出する必要があります。死亡届を提出すると「火葬許可証」が発行されて、葬儀を執り行えるようになります。
退院手続き
搬送の手続きを済ませたら、搬送車が病院に到着するまでの間に退院手続きを済ませておきましょう。病院側で手続きを進めてくれるので、用意された書類に必要事項を記入します。医療費や入院費の支払いは後日になることが一般的ですが、対応は病院によって異なるのでしっかりと確認しておきましょう。
退院手続きが終わったら、搬送車に遺体を載せて安置所に移動します。故人が入院していた場合は、病室の荷物もまとめておきましょう。
病院で死亡した後に遺族がお葬式までに行うこと
病院から遺体が搬送された後、遺族は何をすればよいのでしょうか。ここでは、遺体の安置が終わったあと、お葬式までに準備すべきことを紹介します。
遺体の安置と枕飾りの用意
斎場あるいは自宅に遺体が搬送されたら、頭を北向きにして布団に安置しましょう。遺体の状態を保つために、ドライアイスを置きます。葬儀社のスタッフが、腹部、首の下、腕と胴の間などに置いてくれるでしょう。
枕元には「枕飾り」として、白木の台の上に、香炉・ろうそく立て・しきみをさした花立て、線香立て、枕飯、枕団子などを置きます。置くものは宗派によって異なりますが、葬儀社が飾ってくれることが一般的です。
喪主・世話役を選ぶ
家族で話し合って、葬儀の代表者となる喪主も決めましょう。葬儀がスムーズに執り行われるように、喪主をサポートする世話役を立てることもあります。世話役は、血縁者でなくても問題ないので、親族や友人、知人の中から信頼できる人を選びましょう。
お葬式の形式・日程を決める
次に、喪主・葬儀会社・僧侶などの宗教者と打ち合わせをして、お葬式の形式・日程を決めます。火葬場の空き状況によっては、希望に添えないこともある点に注意が必要です。
通夜・お葬式の日程を参列者に連絡する
お葬式の形式や日程が決まったら、できるだけ早めに、親族、友人、知人、仕事関係者、町内会関係者などの参列者に連絡しましょう。遺族中心の家族葬の場合には、参列してもらいたい人にだけ葬儀の詳細を伝えます。
連絡する際は、用件を手短に伝えましょう。連絡する内容は、以下のとおりです。
・故人との関係性
・故人の氏名
・死亡日時
・通夜・葬儀の日程
・斎場の住所
・電話番号 など
電話で訃報を伝える際の例文は以下のとおりです。
「〇〇の長男〇〇でございます。本日〇時、父が息を引き取りました。通夜を〇日〇時に△△で、葬儀を〇日〇時に△△で行いますので、取り急ぎご連絡申し上げます」
火葬・埋葬許可証を受け取る
火葬や埋葬をするためには、市区町村長に許可をもらわなければなりません。管轄の市区町村に申請書を提出後、火葬許可証が交付されます。葬儀が終わったら火葬場の担当者に提出しましょう。なお「死後24時間以内は火葬してはならない」と法律で定められています。
正式名称ではありませんが、火葬後に火葬済の印が押された火葬許可証が通称「埋葬許可証」と呼ばれています。
遺影を選ぶ
祭壇に飾る遺影用の写真を用意しましょう。自然な笑顔で、生前のその人らしさが伝わる写真を選ぶのがおすすめです。集合写真であっても合成が可能です。
納棺を行う
納棺は、故人の身なりを整えて、遺体を棺へ納める儀式です。僧侶立ち会いのもと、枕元でお経(枕経)をあげてもらう場合もあります。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
病院で死亡した後に遺族が行う主な手続き
病院で死亡すると、遺族はいくつかの手続きをする必要があります。漏れのないようにひとつひとつ確実に進めていきましょう。主な手続きは次のとおりです。
・死亡届の提出
自治体に死亡届を提出します。死亡届は、死亡を知った日から7日以内に届け出る必要があります。死亡届を提出すると、火葬・埋葬許可証を申請できます。
・年金の受給停止手続き
故人が年金を受給していた場合には、年金事務所で手続きを行う必要があります。国民年金は死亡した日から14日以内、厚生年金と共済年金は死亡日から10日以内が期限です。
・健康保険証・介護保険証・運転免許証・パスポートの返却
健康保険証や介護保険証は、保険組合や自治体に返却しなければなりません。また、運転免許証は警察署や運転免許センターに、パスポートは旅券事務所に返却しましょう。
・故人名義の契約の解約
故人名義で公共料金などを契約している場合は、解約するか名義変更を行う必要があります。また、故人名義のクレジットカードやサブスプリクションサービスなども忘れずに解約しましょう。
・高額療養費の払い戻し申請
高額療養費制度とは、1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた金額が、あとから健康保険より払い戻される制度です。病院の領収書と共に申請しましょう。 
病院で死亡した場合|葬儀の準備
身近な方が亡くなると、葬儀の準備や遺言書の確認など、やるべきことがたくさんあります。死亡後はどうしても忙しくなるため、亡くなる前に準備をしておくのがおすすめです。ここからは、死亡前にやっておくべきことを4つ紹介します。
葬儀場の確認や生前予約
「亡くなる前から葬儀の準備をするなんて縁起でもない」と考える方もいるかもしれません。しかし、時間をかけて準備しておくことで、後悔のない葬儀を行えるという考え方もあります。
一般的に、葬儀の具体的な内容に関する打ち合わせは死亡後に行います。スムーズに葬儀を進めるには、事前見積もりの取り寄せや生前契約などがおすすめです。
しかし、生前から葬儀の準備を行うことに抵抗を感じる方がいる場合は配慮が必要です。その場合は、資料や見積もり書を葬儀社のものとわからないように届けてもらいましょう。多くの葬儀社では、家族や本人に気づかれないように送ってほしい旨を伝えれば対応してくれます。
遺言書の準備
死は突然訪れることもあります。突然亡くなってしまった場合に備えて、遺言書を作成しておくと安心です。遺言書には法的な拘束力が発生するため、死亡後の相続で家族が揉めないように準備しておきましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。それぞれの遺言書には方式が定められており、規定の方式に則って作成しなければ法的な効力が失効してしまうので注意が必要です。
特に「自筆証書遺言」は一部を除いて自筆で文章を作成して自分で封をするため、定められた様式から外れていても気がつかないこともあります。トラブルを防ぐためにも、内容の確認をしっかりと行うことが大切です。
生前の預金引出
死亡後、故人の預金は簡単に引き出せなくなります。家族と相談をして預金を引き出しておくと、葬儀の費用を賄えるかもしれません。金融機関は名義人が亡くなったことを知ると預金口座を凍結するため、以降は口座の運用に制限がかかります。
以前は遺産分割が済むまでは、亡くなった方の預金は相続人であっても単独では引き出すことができませんでした。しかし、2019年7月に相続法が改正されて、単独の相続人でも引き出せるようになりました。
ただし、引き出せる金額は法定相続分の3分の1までです。またひとつの金融機関の引き出し上限は150万円までといった制限が設けられており、預金のすべてを自由に扱えるわけではありません。預金引出は、生前にしておくのがベストです。
遺影写真の撮影
事前に遺影写真を用意したい場合は、生前に遺影写真撮影をしておきましょう。遺影用に写真を準備していない場合は遺影に適した写真を探して提出しますが、遺影に使える写真がすぐに見つからないこともあるでしょう。
近年は終活ブームが後押しとなって、生前に遺影写真を撮影する方が増えています。終活セミナーでは、遺影写真の撮影会を行っていることもあるようです。故人を偲ぶために重要な遺影写真の素材は早めに用意しておきましょう。
病院での死亡|よくある質問
ここからは、病院で死亡した場合に、よく寄せられる質問にお答えします。病院から紹介された葬儀社は断ってもよいのか、お世話になった病院へのお礼はどうすればよいのか、自宅への安置が難しい場合、菩提寺がない場合など、それぞれのケースへの対処法を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
病院から紹介された葬儀社は断ってもよい?
病院から葬儀社を紹介されることもあります。ただし、葬儀社は自分で選ぶものなので、紹介された葬儀社を断っても問題ありません。
また、遺体を自宅などに搬送したい場合、搬送のみを葬儀社に依頼することもできます。
お世話になった病院へのお礼はどうする?
お世話になった病院にお礼を渡したい方もいるかもしれませんが、ほとんどの病院ではお礼を辞退しています。以前は、退院時にお礼を渡すことは珍しくありませんでしたが、近年では患者や遺族からのお礼の品は受けとらない病院が増えています。
どうしても気持ちを示したい場合は、なるべく病院側が受け取りやすい品を贈りましょう。高級なものは避けて、長期保存ができて大人数で分けられる「個包装の菓子」などが無難です。
自宅への安置が難しい場合の対処法は?
スペースや環境などの問題により自宅に遺体を安置できない場合は、他の安置場所を選ぶ必要があります。
主な安置場所として、葬儀社が運営する安置施設があります。斎場内にあるため、葬儀の際に移動する必要がないというメリットがありますが、付き添いができないケースもあるので確認が必要です。
また、民間の安置施設も利用できます。ただし、冷蔵設備があるかどうかは施設によって異なります。冷房設備がない場合は、長期間の安置はできないでしょう。
菩提寺がない場合はどうする?
菩提寺がある場合は、そのお寺の僧侶に葬儀を執り行ってもらいます。菩提寺がない場合や、調べてもわからない場合には、葬儀社に宗教や宗派を伝えれば、希望に添ったお寺や僧侶を紹介してもらえるでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
家族が病院で死亡したら、清拭や遺体の処置をしてもらいます。並行して、身内への連絡や搬送の手配などをしましょう。その後お葬式の準備を進めますが、死亡届の手続きなど遺族が行う手続きも忘れないようにしましょう。
病院で死亡した場合の流れや、葬儀についてわからないことがある方は「小さなお葬式」にお気軽にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



遺言者の意思や希望を書面に反映し、公文書として承認された遺言書が「公正証書遺言」です。ホゥ。