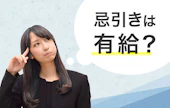親や兄弟、配偶者が亡くなった場合、忌引き休暇は原則取ることができるように規定が作られている会社がほとんどです。しかしながら、叔父・叔母という3親等に含まれる親族が亡くなったケースを忌引き休暇の取得対象にしているかは勤めている会社によって違います。
今回は、叔父・叔母が亡くなった場合の忌引き休暇の取得方法や、忌引き休暇を取得したいという旨の連絡方法などについて解説します。
<この記事の要点>
・叔父や叔母が亡くなった際の忌引き休暇の日数は1日であることが一般的
・忌引き休暇の規定は企業によって異なるため、就業規則を確認しておく
・忌引き休暇制度がない場合は有給休暇を使用する
こんな人におすすめ
叔父・叔母に不幸があった場合の忌引きマナーについて気になる方
忌引き休暇明けまでの流れについて知りたい方
忌引き連絡をする際の例文を調べている方
忌引きの日数は就業規則によって決まっている?
忌引き休暇は、福利厚生に関わる制度の一部としてそれぞれの会社の就業規則に基づいて決められているものです。つまり、忌引き休暇の日数は各会社によって異なるものなので、忌引き休暇の申請をする前に自分が勤めている会社の就業規則を今一度確認しておくことが重要になってきます。
忌引きの日数は企業によって異なる
忌引き休暇は、「故人を偲び、喪に服すための期間」のための休業期間です。しかし、法律で厳密に取り決めがなされているものではないため、各々で自分が勤めている会社の就業規則に則って忌引き休暇を取得することになります。
忌引き日数も各企業の就業規則に定められたものに即して取得する形になるので、「忌引き日数は一律○日」といった決まりはありません。中には、忌引き休暇そのものが無い企業もあるので注意が必要です。
叔父・叔母が亡くなった場合は忌引きの日数は「1日」
忌引き休暇として取得可能な日数は、故人と自分との関係性によるところが大きいと言えます。実の親や配偶者といった身近な人の場合は5日間前後休暇を取得することができますが、3親等以上離れている場合は忌引き休暇を取得できてもせいぜい1日といったところになります。
ちなみに、叔父・叔母は3親等に含まれるので、忌引き休暇を取得できたとしても1日のみの休暇となります。ただし、叔父・叔母の葬儀が遠方で執り行われる場合はプラス1~2日休暇の延長が認められる場合があるので、早めに上司に相談することをおすすめします。
忌引き日数の目安|血縁関係別一覧表
| 血縁関係 | 忌引き休暇取得可能日数(目安) |
| 配偶者 | 10日 |
| 両親 | 7日 |
| 実子 | 5日 |
| 孫 | 1日 |
| 祖父母 | 1日 |
| 兄弟 | 1日 |
| 叔父・叔母 | 1日 |
| 高祖父母 | 1日 |
| 甥姪及び配偶者の両親 | 3日 |
実の両親が亡くなった場合の忌引き休暇は7日間が一般的です。しかし自身が喪主である場合、忌引き休暇取得可能日数は10日となります。
ただし、これはあくまでも目安の日数なので、確実な忌引き休暇取得可能日数は勤め先の企業の就業規則を参照するようにしましょう。
法律上「忌引き」は規定されていない
「喪に服す期間」である忌引きは、法律上で定義されているものではありません。つまり、忌引き休暇の有無もそれぞれの会社の規定に任せられているため「必ず定められていなくてはいけない休暇」というものでもないのです。
多くの企業は、福利厚生の一部として忌引き休暇(特別有給休暇)を設けていますが、中には有給ではなく無給で忌引き休暇の取得を認めている会社もあります。
忌引き休暇の在り方は一律ではないので、「前の会社ではこうだったから」という安易な判断をするのはあまりおすすめできません。時間に余裕があるときに自分が勤めている企業の就業規則を一度確認しておくことをおすすめします。
忌引き取得の流れ
予期せぬ訃報で平常心が掻き乱されることもありますが、会社に忌引き連絡を入れることを怠ってはいけません。忌引き連絡もただ連絡すればいいというものではないので、社会人としてのマナーを忘れずに、テキパキと伝達事項を正確に伝えるようにしましょう。
場合によっては取引先にも一方入れる必要が出てくるかもしれないので、業務の伝達もれ、引き継ぎもれなどがないよう気をつける必要があります。
就業規則を確認し忌引き日数を決定する
忌引き休暇を取得する上で大切になってくるのが、休暇の日数です。どのぐらいの期間休む必要があるのかを明確にした上で、会社の就業規則と照らし合わせながら決めなくてはいけません。このとき「だいたい5日間ほど」といった曖昧な申請をすることはできません。
葬儀の日程と葬儀が執り行われる場所や、そこが遠方か否かを明らかにし、会社の就業規則で定められている忌引き日数の範疇を逸脱しない日数を申請するようにしましょう。
上司に忌引きを取得したいと報告する
訃報が入ったらまず自分の上司に連絡を入れ、忌引き休暇取得の必要性があることを伝えましょう。その際に必要となるのが、故人と自分との関係、葬儀の日程、葬儀が執り行われる場所の情報です。
これらを明らかにした上で、何日間の忌引き休暇が必要なのかを伝えるようにしましょう。葬儀場所が遠方で、忌引き休暇を通常よりも1日長く欲しい場合は、この連絡の際に上司に相談を持ちかけてみましょう。
また、忌引き休暇の申請は必ず口頭で行うようにし、メールのみで済ませてしまうことのないようにしましょう。口頭で伝えることが多い場合は、後ほど確認の意も含めてメールや文書で葬儀の日程や忌引き休暇取得希望日などを送るようにすると安心です。
同僚や上司に業務の引き継ぎを行う
会社に勤務している以上、自分だけしか関わっていない仕事というのはそれほど多くありません。自分の受け持っている仕事と同僚の受け持っている仕事がリンクしていたり、クライアントとの連携で仕事をしていたりする場合もあるでしょう。いずれの場合も、組織の一員が数日間休むことで業務に支障が出ることがありえます。
自分が休んだ場合、同僚や上司の誰かが自分の仕事を担ってくれるということを念頭に入れた上で、速やかに業務の引き継ぎ連絡をしなくてはいけません。少しでも他人の負担を減らすために、それまで自分がまとめてきた仕事をわかりやすくファイリングしたり、カテゴライズしたりしましょう。整頓してから次の人に仕事を委ねるようにすると親切です。
他社の人間と仕事を連携させて行っている場合は、そのクライアントにも忌引き休暇の旨を伝える必要があることを忘れてはいけません。仕事の急な連絡を受けられるよう、念のために個人のメールアドレスや連絡先を渡しておくとお互いに安心です。
忌引きを取得するための申請書を提出する
上司に口頭で忌引き休暇を取得したい意向を伝えたのちは、総務課やそれに準ずる部署に忌引き休暇を取得するための申請書を提出することが多いです。忌引き休暇の申請書は会社ごとにフォーマットが既に用意されていることが多いので、その書類に必要事項を記入して提出すれば良いでしょう。
書類に必ず書かなくてはいけない事項は、「自分と故人との関係性」、「葬儀が執り行われる場所」、「葬儀、通夜、告別式などの日程」、「自分が喪主を務めるか否か」です。詳しく決まっていない場合は決まり次第連絡を入れる旨を伝えておきましょう。
忌引き休暇を取得する
忌引き休暇は、まず訃報が入って忌引き休暇が必要であるという判断がなされた時点で上司に口頭で申請します。そこで忌引き休暇の日数をあらかじめ相談して決めるようにすると後々面倒がありません。その後、手順に従って忌引き休暇の申請書を提出すれば、忌引き休暇の取得が可能となります。
忌引き休暇が急に必要になったからといって、メールのみで忌引き休暇の申請をすると申請として認められず、休んだ期間は無給とみなされることもあり得るので気をつけましょう。
また、会社によって忌引き休暇開始日が異なることがあるので、あらかじめ開始日が故人の亡くなった日なのか通夜の日なのかなどを確認しておくと安心です。
証明書を提出する
忌引き休暇を特別有給休暇と定めているところでは、本当に忌引き休暇を取得する必要があったのか否かを精査するための書類を提出させる場合があります。その書類とは、「死亡診断書」、「火葬許可証」、「会葬礼状」、「訃報」といったものになります。
しかし、家族葬の場合は、身内だけで執り行うため会葬礼状を用意しないことがほとんどで、会社に提出できる書類が全くないということもあり得ます。その場合は、葬儀社に頼んで会社用の証明書(訃報)を作成してもらうことになるので、早めに葬儀社に一報を入れて証明書を作成してもらうようにしましょう。
香典返しや手土産と共にお礼を伝える
叔父・叔母などの3親等は香典や弔電、供花の対象にはなりませんが、万が一香典や弔電などを貰った場合は、忌引き休暇復帰後にしっかりとお礼をしなくてはいけません。
香典を貰っていない場合でも、自分が急に休んでしまった期間、一生懸命に自分の抜けた穴をフォローしてくれた同僚や上司に感謝の意を伝え、今日からまた社の一員として頑張りますという旨をしっかり伝えるようにすることが大切です。
手土産はみんなで分けられるもので、日持ちするものを選びましょう。小袋に分けられた、箱入りの菓子折りなどがおすすめです。特に遠方に葬儀に出掛けた方は、その地の銘菓を用意していくと喜ばれるでしょう。
忌引きを取得する際の連絡に使える例文
急な訃報で慌ててしまい、忌引き連絡の際に大事な連絡事項をうっかり言い損ねてしまうというミスは起こり得ます。しかし、一度連絡した後に、また「先ほど言いそびれてしまったのですが」と再度連絡を入れることは相手の混乱も引き起こしかねません。
そういった事態にならないように、忌引き取得連絡を入れる際には伝えるべきことを事前にメモしておきましょう。以下の例文をフォーマットとして使うことで伝達もれを防ぐことができるはずです。
電話で忌引きの取得を打診する場合
○○課の○○(自分の名前)ですが、○○様、お疲れ様です。急なことで恐縮なのですが、私の○○(関係性)が○月○日に永眠いたしました。葬儀は○月○日に○○(場所)で執り行われる予定です。つきましては、○月○日から○日間忌引きを頂きたいのですが……
メールで忌引きの取得を打診する場合
(件名:忌引き休暇の取得について)
○○課の○○様
お疲れ様です。
私事で大変恐縮なのですが、○月○日に私の○○(関係性)が永眠いたしました。取り急ぎここにお知らせいたします。
つきましては、忌引き休暇の取得をお願いしたく、ここに届け出いたします。
期間:令和○月○日~令和○月○日
内容:通夜○月○日、葬儀○月○日、告別式○月○日(場所○○)
葬儀準備、及び片づけのため
忌引き休暇中のご連絡は、携帯(カッコ内に番号を明記する)まで頂けますと助かります。
お手数おかけいたしますが、何卒宜しくお願いいたします。
○○課○○(名前)
叔父・叔母の葬儀で忌引きを使えなかったらどうするか
忌引き休暇は法律で定められているものではありません。したがって、勤めている会社によっては、3親等に当たる親族の葬儀に対する忌引き休暇の取得を認めていないことも少なからずあります。
それでも親族の葬儀には出席し、しっかりとお別れの挨拶をしたいと考える人は多いでしょう。忌引き休暇を取得できなかった場合、どのように葬儀や通夜に参列すれば良いかをまとめました。
方法①:有給を使って必要な日数分の休みを取る
会社の規則によっては、3親等以上の忌引き休暇取得が認められない場合があります。その際には有給休暇を使って必要な日数分の休みを取り、葬儀や通夜、告別式に参列するようにします。
仮に、忌引き休暇が認められていても1日しかもらえなかった場合、有給休暇も併用して自分が必要だと考える日数分の休暇を取得することも可能です。
忌引き休暇が認められない場合や無給でしか休暇が認められない場合は、思い切って有給休暇を申請して、時間に余裕を持って葬儀に臨むようにすると良いでしょう。
方法②:通夜だけ参列する
有給があまり残っていないといった理由で取得が難しい場合や、今の仕事の関係上どうしても休みを取るのが難しいという場合は、通夜だけに参列して故人との別れを済ませるという方法があります。
しかし、遠方での葬儀の場合はこれが難しいので、やはり有給を取って故人との別れをしっかり済ませられるようにすることをおすすめします。万が一残業や急な仕事で通夜に参列できなくなりそうな場合は、上司に相談してみましょう。
方法③:半休を使って出棺だけ見送る
会議や残業、クライアントとの打ち合わせなどで、夜に通夜や告別式に参列することが難しい場合もあるでしょう。夜はどうしても社外に出ることが難しいという場合は、上司に相談の上、半休を取って出棺だけ見送るというのも一つの手です。
叔父・叔母は両親や兄弟ほど近しい間柄ではないかもしれませんが、比較的近しい関係の親族であることに変わりはありません。人によっては親に代わって育ててもらったということもあるでしょう。
親族との別れは、やはりしっかり葬儀に参列して行うことに越したことはないでしょう。そのため、忌引き休暇が取得できない場合でも、どこかの儀に顔を出して別れをしっかり済ませるようにしたいところです。
方法④:葬儀後に弔問する
叔父・叔母が亡くなったとき、海外にいてどうしても葬儀に参列できないという場合も考えられます。その際は日本に帰国後に故人宅を弔問し、そこでしっかりとお別れの挨拶をするのが望ましいです。
海外にいなくとも、仕事の関係で昼夜問わず会社から出ることができず、通夜にも告別式にも参列できないという場合もあり得ます。その場合もまた、仕事が一段落したところで故人を弔問し、お別れをしっかり済ませるようにするのが望ましいと言えます。
仮に葬儀や告別式に参列できなかったとしても、焦らず遺族に後日弔問する旨を伝えるようにしましょう。
そもそも忌引き制度とは何のためにあるのか
忌引き休暇は、特別有給休暇や慶弔休暇などと呼ばれることもありますが、世間的に「喪に服すために取得が認められている休暇」と認識されています。
人の死は予期せぬときに訪れるものですが、人が亡くなってから葬儀の準備などが始まるので、様々な準備が故人の死後にスタートします。故人の死を受け入れ気持ちの整理をしつつ、葬儀の準備を進めるには当然時間が必要です。忌引き休暇は、いわばその準備のための時間を設けるための期間なのです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
両親や兄弟が亡くなった場合に忌引き休暇を取得するのはそれほど難しいことではないでしょう。しかし、3親等に当たる叔父・叔母の場合は、忌引き休暇そのものを適用してもらえる可能性が低くなることもあるので注意が必要です。
また、忌引き休暇は法律ではなく各企業の社内規定によって定められているものなので、各々が自分の勤め先の社内規定を確認して、忌引き休暇取得についての知識を改めて知っておくことが大切になってきます。
人の死はいつ訪れるか全く予想がつかないものなので、時間のあるときに忌引き休暇について調べ、万が一忌引き休暇を使う事態になった際に落ち着いて対処できるように準備しておくと良いでしょう。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



直葬とは、通夜式や告別式などの式をはぶき、火葬のみを行う葬儀のことです。ホゥ。