「位牌(いはい)」は故人の戒名や法名の書かれた木牌のことで、故人の魂が宿った大切なものです。
この記事では、位牌についてよくある疑問や質問をQ&A形式でご紹介します。
<この記事の要点>
・位牌は故人の魂が宿る大切なもので、開眼供養をすることで位牌としての役割を持つ
・位牌は絶対に作る必要があるわけではないが、遺族の心の拠り所となるため、よく検討する
・本位牌は四十九日までに用意するのが一般的
こんな人におすすめ
位牌とは何か知りたい方
位牌を作るべきかお悩みの方
位牌の処分をお考えの方
Q1.位牌とは何ですか?
位牌とは、故人の戒名や法名が書かれた木牌(ぼくはい)のことです。位牌は故人そのものといえる大事な物です。
位牌を作ったあとは、まず始めに開眼供養(かいげんくよう)を行います。これを行うことで、はじめて位牌としての役割を持つとされます。
開眼供養は、代々お世話になっている菩提寺(ぼだいじ)に依頼し、位牌を作成することが決まったら早めに相談しておきましょう。
Q2.位牌の相場は?
位牌の値段は種類や加工のしかた、品質によって異なり、ほとんどは5万円以内で購入できます。
「小さなお仏壇」では位牌を取り扱っており、送料無料・戒名の彫刻料も含んで21,800円(税込23,980円)で販売しております。詳しくはこちらのページをご覧ください。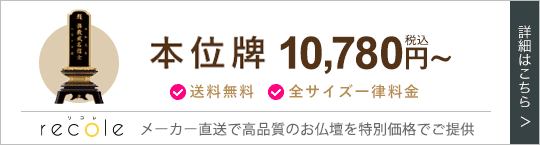
Q3.古い位牌を処分するにはどうすればいいですか?
位牌を処分する場合は、菩提寺に持って行ってお焚き上げ(おたきあげ)をしてもらいます。菩提寺がなければ、近くのお寺に相談します。
お焚き上げの前には、位牌から魂を抜くための供養(閉眼供養)をしてもらいましょう。新しい位牌に切り替える場合には、元の位牌の閉眼供養と共に、新しい位牌への開眼供養を行います。
Q4.位牌がたくさんあるのですが、ひとつにまとめることはできますか?
先祖の位牌が増えてくると、仏壇内に置けなくなることもあります。この場合、位牌をひとつにまとめる方法があります。「○○家先祖代々之霊位」というようにまとめた位牌を作るか、もしくは回出位牌(くりだしいはい)または、繰出位牌とよばれる位牌を利用します。
回出位牌とは、戒名を記す札板が10枚程度入るようになっている箱状の位牌です。
Q5.位牌にはどんな種類がありますか?選ぶ基準は?
まず、葬儀から四十九日まで用いる仮の位牌である「白木位牌」があります。これは全国共通で使用されます。その後の本位牌には、主に3つの種類があります。
■塗位牌
漆を塗り重ね、ところどころに金の装飾が施されている位牌です。
■唐木位牌
黒檀や紫檀などの硬度の高い木を用い、木目を残した位牌です。
■回出位牌(くりだしいはい)
見た目は塗位牌や唐木位牌のようで上部が箱型になっています。その中に札板を複数納めることができ、先祖代々の位牌をまとめる役割をもちます。
基本的に宗派ごとに指定された位牌というものはないため、仏壇やお部屋に合ったデザインのものを選べば問題ありません。
Q6.位牌のサイズがいくつかありますが、何を基準に選べばよいですか?
位牌のサイズは「寸」で表され、一寸は約3cmです。0.5寸刻みでだいたい4~5寸程度のサイズの中から選びます。次のことを考慮してサイズを選択します。
・ご先祖の位牌サイズより小さくする(大きな功績があるなどの場合は例外あり)
・ご先祖以外の位牌があればサイズをそろえる
・仏壇の大きさを考えてサイズを決める
Q7.位牌をネット通販で購入する際の注意点はありますか?
位牌をネット通販で購入すると、店舗がない分コストを抑えられているため安く購入することができます。
注意点としては、あまりに値段が安いのものだと位牌の木が変形しやすいなど、品質面での心配があります。事前にそのような場合の対応方法を確認しておくと良いでしょう。注文方法は、位牌の種類を選択してネットでフォーム入力をするか、用紙を印刷してFAXや郵送で原稿を送ります。
「小さなお葬式」でも、お位牌のネット注文を承っています。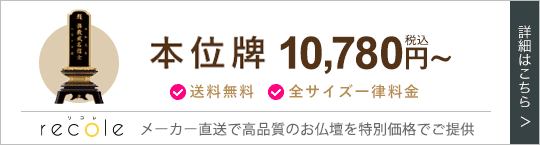
Q8.戒名がなくても位牌は作れますか?
最近は無宗教で葬儀を行うことも増えているため、戒名がない方もいます。そういった場合であっても、問題なく位牌を作ることができます。戒名がない場合は本名の後に「霊位」「位」などと付けることで、戒名と同じように扱うことができます。
例)葬儀太郎霊位、葬儀太郎位
小さなお葬式では、戒名をお持ちでない方に向けて、戒名をお授けするサービスがございます。詳しくは下記のページを参考にご覧ください。
参考:小さなお葬式のてらくる 戒名授与
Q9.位牌は必ず作る必要がありますか?浄土真宗の場合は?
位牌は、実は本人がいらないと考えるのであれば必要ありません。ただし、位牌はご遺族の心の拠り所となるものであり、気持ちの支えになる役割があり、位牌を作らなかったことで、供養の仕方がわからない、きちんと供養ができていない気がする、といった意見もありますのでよく検討しましょう。
また、浄土真宗では位牌ではなく過去帳を仏壇に飾ります。
Q10.本位牌はいつまでに作るべきですか?
本位牌は、四十九日までに用意するのが一般的です。これは、四十九日を過ぎると故人の霊は仏のもとに向かうとされているからで、四十九日のタイミングで魂を移すための位牌を用意するのです。位牌を注文してから手元に届くまでに1~2週間ほどかかるので、早めに手配をしましょう。
もし四十九日までに位牌を用意できない場合、納骨時や百か日法要などの区切りに合わせて作るとよいでしょう。
四十九日法要について、詳しい記事がありますので参考にしてみてください。
Q11.位牌を複数作っても問題はありませんか?
複数の位牌を作りそれぞれに持つことは可能です。「位牌分け」と呼ばれるもので、一部の地域では習慣的におこなわれているほか、どの地域でも希望される方にはお寺で対応していただけるようです。四十九日法要に仮位牌から本位牌へと魂が移されるタイミングで、複数作ることになります。
Q12.手彫りと機械彫りがあると聞きましたがどう違いますか?
手彫りや機械彫りというのは、位牌に文字を彫る方法のことを指します。手彫りは職人が自らの手で彫る方法、機械彫りは機械が均一に彫る方法です。手彫りは、その職人によって出来栄えが変わります。上手・下手も当然あるため、見本をよく見て選ばなければいけません。
機械彫りにはそういった差はなく、全て均一に彫られます。字体の種類はいくつかあるため、気に入ったものを選ぶことはできます。現在はほとんど機械彫りで行われていて、手彫りの位牌はあまり見られなくなっています。
Q13.神道にも位牌はありますか?
神道にも、仏教の位牌に当たる霊璽(れいじ)というものがあり、見た目は白木位牌のようなシンプルなつくりをしています。仏教では四十九日に位牌の開眼供養を行いますが、神道では通夜祭の前に遷霊祭というものを行い、故人の魂を霊璽に移します。
Q14.位牌に刻字される項目は何ですか?
位牌には戒名・梵字・命日・俗名・享年の5つの項目が刻字されます。それぞれの詳細は以下です。
・戒名:故人が浄土にて仏の弟子になったことを表す名前
梵字:生前の宗派をあらわす印
命日:故人が亡くなった日付
俗名:故人の本名
享年:故人が亡くなった年齢
基本的にはこの5つの項目が書かれますが、梵字は位牌の種類や生前の宗派によっては省かれることもあります。どの宗教にも属さない場合も、梵字は省いて戒名だけが刻まれます。
また、宗派によって5つの項目を位牌の表に刻むのか、裏に刻むのかも変わります。注文時に宗派について伝えておきましょう。
Q15.直葬の場合は位牌を作る必要はありますか?
人が他界したときは通夜→告別式→火葬という流れが一般的でしたが、最近では通夜と告別式を行わないケースも増えています。その場合は他界→火葬の直葬になりますが、必ずしも位牌を用意する必要はありません。
直葬だけど位牌を用意したいという場合は、葬儀社から白木位牌を購入しましょう。故人が何らかの宗派に属していた場合は、菩提寺に行って戒名をもらってから位牌の注文をします。戒名の有無は自由なので、それも併せて親族内で話し合って決めると良いでしょう。
位牌は故人の名前や年齢などが刻まれたものです。位牌があることで故人のことを忘れず、時には家族内で故人との思い出を話すこともあります。親族との繋がりを強めるものでもあるため、用意するかどうかをしっかり話し合って決めると良いでしょう。
Q16.本位牌は絶対に必要ですか?
前述した直葬の場合は位牌を用意しないケースもありますが、葬儀で白木位牌を用意したのであれば本位牌も用意しましょう。
白木位牌とは葬儀で使用するもので、いわば仮の位牌です。葬儀の際に仮の位牌に故人の魂を宿し、四十九日のときにお経を読んでもらうことで魂を本位牌に移します。仮の位牌のままで済ませてしまうと遺族としても心苦しく思うこともあるかもしれません。
白木位牌は葬儀までに、本位牌は四十九日までに用意しておきましょう。注文してから納品まで時間がかかることもありますので、なるべく早めに注文を済ませておくと安心です。
Q17.本位牌に移した後、仮位牌はどのように処分すれば良いですか?
仮位牌から本位牌に故人の魂が移された後は、仮位牌は通常のごみとして処分可能です。白木位牌は木材で作られているため、自治体の分別ルールに従って処分しましょう。
故人の葬儀のとき、個人の魂は仮の位牌である白木位牌に宿ります。そのままずっと仮位牌に宿るわけではなく、四十九日のときに僧侶にお経を読んでもらうことで、仮位牌から本位牌へと魂が移されます。本位牌へと移れば、仮位牌をずっと残しておく必要はありません。
前述したように仮位牌は通常のごみとして処分できますが、俗名や戒名が記されているため捨てにくいと感じる人も多いでしょう。その場合は寺院でお焚き上げをしてもらうことがおすすめです。
Q18.位牌がないと菩提寺で納骨をさせてもらえませんか?
菩提寺が浄土真宗であれば用意しなくてもいいのですが、それ以外の宗派であれば四十九日までに本位牌を用意しておきましょう。納骨の際には位牌を持参し、遺骨を納骨堂に納めたら自宅の仏壇に位牌を置いておきます。
浄土真宗の場合は位牌を必要としません。浄土真宗では死去後は誰もが仏になれて成仏できるという考えから、成仏を祈る位牌は必要ないという考えのためです。
自宅に仏壇がない場合は、菩提寺に位牌を置けるかを聞いてみましょう。お寺によっては位牌堂という位牌専用の建物を設けているところや、納骨堂に位牌を置けるところもあります。
Q19.位牌を祀る場所はどこですか?
位牌を祀るのは仏壇の2段目です。仏壇は多くのタイプが3段になっています。上から1段目には宗派の中心的な仏像である本尊を、2段目には位牌を、3段目にお供物を置きます。
仏壇には線香を立てるための香炉や供花も置きます。4段以上あるなら、供花や香炉は4段目以上に配置しましょう。手を合わせるときに使うおりんは、一番下の段に配置してください。
仏壇は正面右側が上座です。位牌が複数ある場合は、上座から先祖の順に配置しておきましょう。
Q20.位牌をお手入れするにはどうすれば良いですか?
位牌はできればお手入れなしでそのまま置いておきましょう。位牌は刻字する黒い部分を枠で囲ってあり、枠には金箔や金粉が施されています。お手入れをしようとすると金箔や金粉が剥がれしまう恐れがあります。
位牌の台座に関しても同様で、台座にも金箔などが使われていることから剥がれてしまうことがあります。金箔や金粉の下は黒くなっているため、所々が剥がれてしまうとまだら模様の不格好な状態になってしまいます。
水拭きはおすすめできません。ほこりがついているときは柔らかい毛のブラシで優しく取りましょう。手で持つときは手に金箔が付着するかもしれませんので、柔らかい手袋をつけて優しく持ちます。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
位牌にまつわる疑問は多くの人が抱えています。特に初めて位牌を用意するとなれば、いつまでに用意すればいいのか、どこに注文すればいいのかなど疑問がいくつも出てくるでしょう。
位牌を仏壇に祀ることで故人を忘れることなく、長く供養ができるのではないでしょうか。位牌を用意しなかったことで供養の仕方がわからないと悩む人もいます。後悔しないように、故人の魂が宿る位牌を用意しておいてはいかがでしょうか。
位牌に関する疑問以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


湯灌は故人の体を洗って清める儀式のことです。ホゥ。


































