故人の通夜や葬式を終えて、火葬を行ったあとは遺骨を骨壺に納めるのが一般的です。この骨壺をお墓に納める儀式のことを「納骨」といいます。
突然の不幸であわただしく葬儀が行われると、「遺骨を納めるお墓がまだない」「まだ骨壺を手元に残しておきたい」と悩んでしまう方もいるでしょう。
納骨は、いつまでにどのように行うのがよいのでしょうか。この記事では、納骨に適した時期や納骨式の流れ、費用、お供え物、納骨以外の供養方法などを解説します。
<この記事の要点>
・納骨の時期は定められておらず、四十九日法要や一周忌などのタイミングが一般的
・納骨方法と日程を検討し、納骨先の寺院へ連絡を行い、火葬許可証を用意する
・納骨しない場合は、手元供養や散骨などの供養方法がある
こんな人におすすめ
納骨の時期はいつが一般的かを知りたい方
納骨の流れを知りたい方
納骨のお供えものについて知りたい方
納骨はいつまでに行うのが一般的か
さまざまな事情により遺骨が手元にある場合、このまま納骨せずにいてもよいのだろうかと悩んでしまう方もいるかもしれません。ここからは、納骨の期限や一般的な納骨の時期について解説します。
納骨の時期にきまりはない
いつまでに納骨をしなければならないという、法律などで定められた期限はありません。葬儀が一段落した後には「四十九日」や「百箇日法要」「一周忌」「三回忌」などさまざまな法事があり、遺族が集まる機会が何度かあります。
親族や周りの人などから「一周忌までに納骨をするべき」と言われることもあるかもしれません。しかし、納骨には期限がないので、慌てて納骨する必要はありません。家族で十分に話し合って気持ちの整理がついたタイミングで納骨すればよいでしょう。
四十九日
四十九日は、仏教において「故人が極楽浄土に行けるかどうかが決定する日」とされており、遺族が集まって「故人が極楽へ行けるように」と願いを込めて供養をする日です。
故人が現世から死後の世界へ向かう日であると考えられていることから、遺骨をお墓へ納める日としては最適だといえるでしょう。
法事のなかでも四十九日は、納骨を行うことがもっとも多い日といわれています。とはいえ、まだお墓の準備ができていない場合は納骨ができないので、その後の法要のタイミングで納骨を行います。
百箇日法要
百箇日法要とは、故人が亡くなった100日後に行われる法要のことです。大切な人が亡くなると、悲しみに暮れる毎日を過ごすことになりますが、死後100日が経った日に「悲しみは消えずとも、区切りをつけていつもの生活に戻ろう」という意味を込めて行うのが百箇日法要です。
故人の死から約3か月で、この頃にはお墓の準備ができている方も多いことから、百箇日法要のタイミングで納骨を行う方もいます。
一周忌
一周忌法要は、近親者が喪に服すことへ区切りをつけるタイミングです。喪中の間はお正月のお祝いや結婚式などの祭事を慎むことが一般的ですが、一周忌を迎えると喪に服す期間は終わり、心新たに生活をスタートさせます。
これまで遺骨が手元から離れることに抵抗のあった人も、一周忌を迎え少し心の整理をすることができたら、この時期に納骨に踏み出すのもよいでしょう。
三回忌
納骨をする時期にきまりはありませんが、三回忌は納骨を終わらせる目安の時期であると考えられています。
故人が亡くなってから遺族が集まる法要も三回忌で一区切りつくということや、あまり長い間納骨をしないと親族が心配をしてしまうことも考えられるため、可能であれば三回忌までに納骨を執り行うようにしましょう。
新盆
四十九日法要が終わり、忌明け後に初めて迎えるお盆である「新盆(初盆)」も、納骨のタイミングのひとつです。
新盆には親族や友人を招いて盛大に法要を行うことが多いため、法要と同時に納骨をすれば、たくさんの方とともに供養できるでしょう。ただし、忌明け前にお盆を迎える場合、新盆は翌年になることに注意が必要です。
納骨の準備
納骨の時期がきまったら、納骨式を行うための準備をします。納骨するためのお墓を用意したり、納骨式を行うために寺院に連絡をしたりする必要があります。ここからは、納骨式に必要な準備について紹介します。
納骨方法を検討する
先祖代々続いているお墓に納骨する場合を除き、納骨先がきまっていない場合は納骨方法を最初に考えましょう。
近年では「お墓を継承する人がいない」「お墓を建てると高額になる」などの理由で、永代供養や樹木葬など遺族の負担が少ない納骨方法を検討する方が増えています。
お墓を一から準備する場合は、墓地選びやお墓のデザインや大きさの決定、契約など、墓石が完成するまで2か月から3か月ほどかかるため、早めに準備を始めることをおすすめします。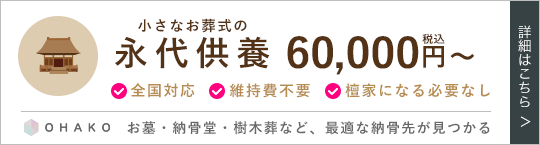
お寺に納骨したい旨を伝える
納骨先がきまったら、納骨式の詳細についてお寺に相談します。納骨の希望時期をきめて、大体の費用を調べておくと話をスムーズに進めることができます。納骨式を法要と一緒に行いたい場合は、その旨も伝えるようにしましょう。
納骨の時期を決定する
納骨先がきまったら、納骨の時期も決定しましょう。一般的には、三回忌までのいずれかの法要のタイミングで納骨式も一緒に執り行います。
どのタイミングで行うのかは、遺族同士で話し合ってきめましょう。土日は混雑が予想されるため、週末を希望する場合は早めにお寺の都合を確認しておきましょう。
埋葬許可証(火葬執行証明済の火葬許可証)を準備する
納骨をする際は、「火葬許可証」という許可証が必要です。火葬許可証がないと納骨ができないため、紛失しないようにしましょう。
多くのインターネット上の情報や、葬儀の手順を解説する書籍の中で「火葬許可証に火葬済の印が押されたものが埋葬許可証になる」と記されていますが、正確には、火葬許可証が埋葬許可証に変化することはありません。
「火葬執行証明済の火葬許可証」は納骨の際、お墓を管理している霊園や寺院に渡します。
参列者や当日の流れをきめる
納骨式の具体的な内容がきまったら、最後に参列者を決定しましょう。親族や関係者のうち、誰へ声をかけるのかを相談します。
また、当日の集合時間や納骨式および法要の流れや会食場所について、施主をはじめとした遺族の代表者の間で相談をして、お寺にも伝えておきましょう。
参加者に納骨式の詳細を伝える
納骨式の詳細がきまった後は、参列を依頼する親族や関係者へ案内状を出します。
遠くから足を運んでくれる参列者もいるので、納骨式の詳細や会食の有無などの流れをあらかじめ伝えておくと親切です。
納骨式当日の流れ
納骨式はどのような流れで進行するのでしょうか。ここからは、納骨式の一般的な流れを紹介します。地域や宗派によっても異なりますので、事前に菩提寺に確認しておきましょう。
挨拶・読経
まず、納骨式の施主、もしくは遺族代表が、参列者に対してお礼の挨拶をします。参列してもらったことへの感謝の気持ちに加えて、遺族の近況報告なども織り交ぜます。
納骨式終了後に、会食の席も設けている場合には、このタイミングで案内しましょう。続いて、納骨の前に僧侶が読経をします。
納骨・読経
読経終了後に、お墓を開けて遺骨を納めます。納骨室の中に骨壷を入れることが多いですが、地域によっては骨壷から遺骨を取り出して納骨袋に入れ直す場合もあります。
納骨が終わった後は、僧侶が「納骨経」と呼ばれる2度目の読経を行い、故人の供養を行います。
焼香・会食
納骨が終わったあとは、僧侶の指示に従って焼香を始めましょう。まず施主が行い、次に遺族、親族、知人と続きます。四十九日や百箇日など、法要と同時に納骨式を執り行う場合は、すべての儀式の終了後に会食をするのが一般的です。
納骨にかかる費用
納骨にはまとまった費用が必要になるので、あらかじめ何にどの程度かかるのかを把握しておくと安心です。ここからは、納骨そのものにかかる基本的な費用、納骨式にかかる費用、その他の費用について解説します。
納骨にかかる基本的な費用
納骨の際は墓石を開閉する必要があるので、石材店に依頼することが一般的です。相場は1万5,000円~3万円程度でしょう。また、すでにあるお墓に納骨する場合は、戒名・俗名・没年などを彫刻する費用が、3万円~5万円程度かかります。その他に塔婆を建てるのであれば、2,000円~5,000円程度かかるでしょう。
納骨式にかかる費用
納骨式では、菩提寺の僧侶に読経をしてもらいます。お布施の目安は、3万円~5万円程度です。菩提寺で行うのであれば「お車代」は必要ありませんが、別の場所に来てもらう場合には1万円程度を包みましょう。
また、僧侶が会食に参加しない場合は「お膳料」として5,000円~1万円程度を渡します。ただし、地域や宗派によっても異なりますので、周囲の人に相談するのがおすすめです。
その他の費用
霊園などで納骨式を行う場合は、法要部屋を使用するのが一般的です。使用料として1万円~3万円程度かかるでしょう。また、会食の費用は、参加者1人あたり3,000円~5,000円程度が相場です。
納骨のお供え物について
納骨式では祭壇に花を飾りますが、これは施主が用意するのが一般的です。ここからは、祭壇に飾る生花の選び方やお供え物の選び方を紹介します。
納骨式の生花に関する注意点
納骨式では祭壇に生花を飾りますが、縁起の悪い花を選ばないように注意が必要です。
たとえば、椿は花ごと落ちて散ります。これが首が落ちるように見えることから、武士の間で縁起が悪いとされていたという歴史があります。また、藤は垂れ下がっているため、家の運を下げてしまうと考えられています。このように、縁起がよくないとされている葬儀に不向きの花は選ばないようにしましょう。
花以外のお供え物の選び方
花以外にお供え物が必要かどうかについては、地域や宗派などによって異なります。日本でよく取り入れられている仏教のお供え物には、食べ物や飲み物、心を浄化する香りもの(線香など)、故人がいる場所を明るく灯すロウソクなどがあります。
お供え物は、その後遺族が使い消費できる「消えもの」がよいとされています。その他にも、故人の趣味に関係するものや好きだったものなどをお供えしてもよいでしょう。
納骨以外の供養方法
気持ちの整理がつかず、納骨せずに遺骨を手元に置いておきたいと考える方もいるかもしれません。ここからは、納骨以外の供養方法について紹介します。
手元供養
気持ちの整理がつかなかったり、お墓を準備できなかったりする場合は、遺骨を自宅に置いて供養する「手元供養」という方法があります。
故人に自分のそばにいてほしいと考える方には、遺骨の一部だけを手元に置いておく方法がおすすめです。
室内に置いても違和感のないミニ骨壷や、遺骨を収納できるペンダントなど、さまざまな手元供養品が販売されています。
散骨
火葬後に遺骨を粉骨して、海や山に撒く供養方法が「散骨」です。法律上の規制はありませんが、地域ごとに条例を定めている場合もあるので注意が必要です。
海洋散骨には、専門業者から船をチャーターする方法や、他の人と一緒に船に乗り合う方法、業者に全てを委託する方法など、さまざまな種類があります。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。※2024年4月 自社調べ
まとめ
いつまでに納骨をしなければならないという、法律などで定められた期限はありません。家族で十分に話し合い、気持ちの整理がついたタイミングで納骨をしましょう。一般的には三回忌が納骨を終わらせる目安の時期とされています。
気持ちの整理がつかず、納骨せずに遺骨を手元に置いておきたい場合は、手元供養や散骨など、納骨以外の供養方法も選べます。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



「お悔やみ申し上げます」は通夜や葬儀の定型句なので、宗派を気にせず使えます。ホゥ。


































