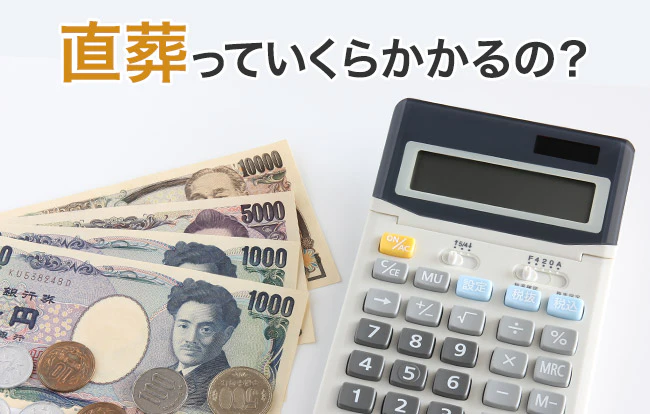「葬儀の費用は高い」と思ったことはありませんか。また葬儀は通夜と告別式があり、故人に縁のある多くの参列者がいて、終了後には料理がふるまわれるものだと思うこともあるでしょう。
葬儀には様々な常識があります。しかしそれは日本特有のものであり、他の国では行われていないこともあります。そのせいか、日本の葬儀は基本的に高めの値段設定です。
この記事では日本の葬儀が高い理由や、葬儀の費用を低減する方法を解説しています。ぜひ最後までご覧ください。
<この記事の要点>
・日本の葬儀費用が高い理由は、会場費や祭壇にかかる費用が高く、戒名代やお布施が必要となるため
・葬儀費用を抑えるには、葬儀会社を検討したり、葬儀プランを見直したりするとよい
・葬儀費用の負担を軽減するには、葬祭扶助制度や年金制度を利用するとよい
こんな人におすすめ
日本の葬儀費用が高い理由を知りたい方
日本の葬儀費用の内訳を知りたい方
葬儀費用を安く抑える方法を知りたい方
日本の葬儀費用は世界一高いといわれている【平均127万円】
日本の葬儀費用は諸外国と比べて高いといわれています。小さなお葬式が行った調査では、葬儀にかかる費用の全国平均は約127万円※という結果になりました。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)
葬儀にかかる費用を意識されることは少ないと思いますが、実際に必要な金額を見ると「高い」と感じられるのではないでしょうか。
地域によって葬儀費用の差があるのか、気になる方もいらっしゃると思います。比較のために諸外国の葬儀費用を例に出すと以下の通りです。
アメリカ:80万円
イギリス:86万円
どうして日本だけがこれ程までに高額になってしまうのでしょうか。日本の葬儀費用の内訳は以下のとおりです。
・会場代
・運搬費や人件費
・棺や祭壇の費用
・戒名代やお布施
・香典返しや食事代
この中で日本独自の風習として、戒名をつけたりお布施を渡したりする習慣があります。当然ですが、戒名やお布施は有料です。海外ではこれらの文化がないため、日本の葬儀は宗教関係に多額の費用がかかっているといえます。
日本の葬儀費用が高い理由
こちらでは、日本の葬儀が高い理由を5つ挙げています。どの項目を取り上げても、当たり前のように行われている葬儀の常識です。
しかしながら、日本では常識であっても諸外国の葬儀では行われていないこともあります。それぞれの内容を理解することで、これまで何の疑問もなく受け入れてきた葬儀費用についての見方が変わってくるでしょう。
1. 一般葬が多い
日本ではその名の通り「一般葬」という形式にて、多くの葬儀が執り行われています。一般葬では通夜と告別式の2日間に渡って葬儀が行われます。また、参列者を親族に限定せずに、会社関係者や友人などにも参列していただくケースが多いです。参列者が多くなれば、相対的に葬儀に必要な費用も大きくなります。
小さなお葬式が行った調査では、一般葬にかかる費用総額の全国平均は約191万円※1という結果になりました。(※1対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)
一方で、通夜のない一日葬の葬儀自体の平均費用は約45万円※2です。(※2対象期間:2021年2月~2022年2月 2022年3月 自社調べ)一般葬の平均費用と比較すると、約150万円の価格差があります。
<関連記事>
【第1回調査】一般葬にかかる費用相場(全国編)
【第1回調査】家族葬にかかる費用相場(全国編)
【第1回調査】直葬にかかる費用相場(全国編)
一日葬の費用はいくら?相場や内訳を徹底解説!
2. 会場代・祭壇が高い
日本の葬儀は、斎場で行われることが一般的です。会場代がかかるとともに、祭壇を使用するのにも費用がかかります。特に祭壇は安くても30万円以上するなど、葬儀費用を増大させる要因のひとつです。
【斎場費用の料金相場】
| 斎場の種類 | 利用料 |
| 公営斎場 | 2万円~15万円 |
| 民間斎場 | 10万円~30万円 |
| 寺院斎場 | 10万円~30万円 |
斎場の費用は民間の斎場を利用するか、公営の斎場を利用するかで大きく変わります。民間斎場は利用料が安いものの「希望者が多く予約が取りにくい」「駅から離れているなど立地が良くないことが多い」などのデメリットもあるのが特徴です。
【祭壇費用の相場】
| 祭壇の種類 | レンタル価格 |
| 白木祭壇 | 30万円~120万円 |
| 花祭壇 | 30万円~80万円 |
| キリスト教祭壇 | 30万円~80万円 |
レンタル価格は、祭壇のみならず、人件費等の諸経費が含まれた費用です。祭壇を手配する葬儀社の運搬費や、事務作業をする従業員の経費も含まれています。
3. 戒名代・お布施代がかかる
日本で葬儀というと仏教の形式で行われることがほとんどです。通夜と告別式を行った後に火葬を行うのが仏教式の葬儀ですが、他にも大きな特徴があります。僧侶に戒名をつけていただいたり、読経していただいたりする儀式があることです。
戒名とは「死後に僧侶からいただく名前」で、戒名がつくことによって仏の世界に入ることができると言われています。
戒名や読経のお礼として渡すお布施も、日本の葬儀費用が高額になる理由の一つです。一般的な葬儀にかかるお布施・寺院手配に関するお金の全国平均は約26万円※です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)
4. 飲食費がかかる
通夜が終わった後の「通夜ぶるまい」と火葬後の「精進落とし」といったように、葬儀には飲食費がかかります。これも日本特有の文化です。海外でも葬儀後に参列者同士が食事に行って故人を供養する文化はありますが、葬儀を主催する遺族が食事の手配をするわけではありません。
一般的な葬儀にかかる飲食費の全国平均は約16万円※です。(※対象期間:2021年2月~2022年5月 2022年5月 自社調べ)飲食費もまた日本の葬儀費用が高額になる理由のひとつになっています。
5. 葬儀プランのオプションが多い
基本の葬儀プランの費用の他に、葬儀社の方から追加オプションやアップグレードの提案を受けることがあります。例えば以下のとおりです。
花祭壇
料理
返礼品
メイク
棺・骨壷
故人を弔うための費用を出し惜しみすることに、後ろめたさを感じてしまうこともあるでしょう。その結果、必要ではないオプションをつけてしまうことがあります。こういった事情も、葬儀が高額になってしまう一因となっています。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
葬儀の費用を安く抑える3つの方法
ここでは、葬儀の費用を安く抑える具体的な方法を解説しています。葬儀を執り行う経験を何度もしている方は、あまりいないでしょう。つまり、葬儀に関する知識や経験が豊富な人というのは珍しいと考えられます。
だからこそ、葬儀の費用を抑えるための知識を確認して、必要以上に葬儀費用が高額にならないようにしてみてください。
1. 葬儀会社を比較検討する
日本には数多くの葬儀会社があり、しっかりと比較検討することで費用を安く抑えられます。
葬儀を執り行う機会は、人生においてそう何度もあるものではありません。そのため「知人に紹介された会社」や「広告が目に止まった会社」など、あまり比較検討せずに選んでしまうこともあるでしょう。
今はインターネット上でも、多くの葬儀に関する情報を確認できます。どんな葬儀にしたいのか、基準を持って葬儀会社を選んでいきましょう。
2. 葬儀プランを見直す
葬儀プランは葬儀全体の費用に直結している要素です。安い葬儀プランを選択すれば、葬儀費用は大幅に下がります。
葬儀の費用を決定するポイントは以下の3つです。
・参列者の数
・通夜の有無
・告別式の有無
通夜も告別式も行い参列者が多いのは「一般葬」で、葬儀費用が最も高くなります。反対に、通夜も告別式も行わず、参列者も親族に限られる「直葬」が、費用が最も安くなる葬儀形式です。
当然、費用だけが葬儀形式を決定する要素ではありません。故人の年齢や交友関係、生前の意向や遺族の意見から総合的に判断して、葬儀プランを決定していくことが重要です。
3. 見積りの内訳をよく確認する
葬儀の費用が必要以上に高額になることを避けるには、見積書の精査が欠かせません。とはいえ、葬儀の準備は非常に慌ただしいため、中々見積りを精査している余裕はないでしょう。
しかしながら、基本料金に含まれていると思った内容が、後日追加費用で請求されるということもありえます。見積りに関する疑問点や不明点は担当者によく確認して、納得したうえで発注するようにしましょう。
葬儀費用の負担を低減する方法
葬儀自体の費用を下げる方法の他にも、葬儀を執り行う遺族の負担を低減させる方法があります。ここで紹介するのは3つの方法です。
使うために条件がある方法や、一時の支払額を抑えられても、トータルの支払額が増加してしまう手法もあります。また活用自体のリスクはないものの、事前の意思決定が必要な方法もあります。正しい知識を身につけて、ご自身の状況に最適な方法を取ってください。
1. 葬祭扶助制度を利用する
葬祭扶助制度とは、経済的な理由で葬儀を行うことができない方のために、自治体が費用を援助してくれる制度です。「生活保護葬」と呼ばれることもあります。
受給金額の基準は以下のとおりです。
| 大人 | 子供 |
| 20万6,000円以内 | 16万4,800円以内 |
遺族が最低限度の生活が維持できないケースだと、葬祭扶助を受けられます。その他に適用されるのは、故人に身寄りがなく民生委員の方などが葬儀を手配するケースです。
支給される金額には限りがあり、最低限の葬儀費用のみです。通夜や告別式を行うことはできません。執り行う葬儀形式は「直葬」のみ利用できます。
<関連記事>
生活保護受給者の葬儀とは?葬儀内容や葬祭扶助の申請方法
2. 年金制度を活用する
故人が生前に年金を受け取っていた場合、受給者の他界により受給する権利がなくなったことを申請する必要があります。その後に手続きを行うことで、遺族年金を受給することが可能です。
遺族基礎年金受給額=81万6,000円に子供一人あたり以下の金額が加算された額
| 第1子・第2子 | 23万4,800円 |
| 第3子以降 | 7万8,300円 |
※令和6年4月からの年金額。昭和31年4月2日以後生まれの方は上記の金額に、昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円 + 子の加算額となります
参考:厚生労働省
※受給期間は子供(健常者の場合)が18歳を迎える年度の3月31日を経過するまで
受給するためには、必要書類を用意したうえで年金事務所へ申請する必要があります。自身がどのような年金を受給することができるか確認して、受給漏れのないようにしましょう。
<関連記事>
遺族年金の手続き方法は?受給条件や期限も紹介します
3. ローンを利用する
葬儀費用は葬儀社によって異なるものの、葬儀後1週間以内と規定されている場合がほとんどです。葬儀は突然訪れるものであり、事前に費用を準備しているケースは少ないでしょう。
そこで葬儀用のローンを利用するという方法があります。葬儀社の担当者に相談するか、事前にローンが利用できる葬儀社を調べてから依頼する方法もあるでしょう。
ただしローンを組むには事前審査があり、分割手数料を負担しなければならないことも十分留意していただく必要があります。
「小さなお葬式」は、クレジットカードでの分割払いや、ローンでの分割払いにも対応しています。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
葬儀は高いものだと思いこんでいた方にも「葬儀費用を低減する方法」をご理解いただけたかと思います。葬儀はお金がかかってしまうものなので、無理なく負担できる形式を選択してみてください。
葬儀を執り行う機会は突然訪れるものです。葬儀の経験が豊富な方というのはなかなかいらっしゃらないでしょう。小さなお葬式には日々お客様のサポートをしている、総勢60名のコールスタッフがおります。
葬儀の費用を抑えて故人に最適な葬儀を行いたい方は、ぜひとも小さなお葬式にご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。



お通夜とは、家族や友人たちが集まり、故人と最後の夜を過ごす儀式のことです。ホゥ。