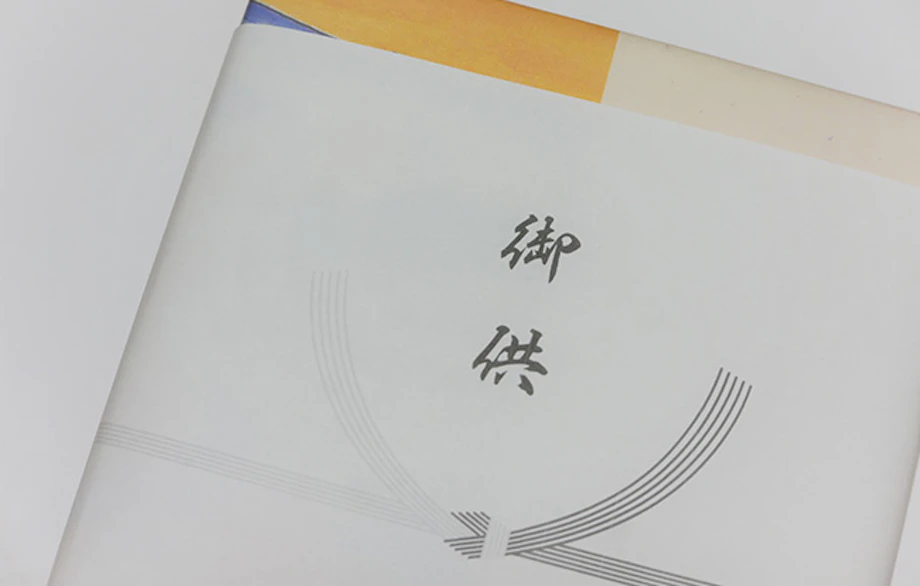不幸は突然訪れます。亡くなった知らせを聞いても、遠くに住んでいたり都合がつかなかったりして通夜や葬儀に参列できない方もいるかもしれません。
ご自身の気持ちを伝える方法のひとつに、贈り物を贈る方法があります。ただ経験がない方の場合、何を贈り物として選べば良いのか分からず悩んでしまう方もいるのではないでしょうか。
お悔やみの贈り物の選び方や渡し方について知識を身に付けておけば、故人や遺族に気持ち良く受け取ってもらいやすくなります。そこでこの記事では、お悔やみの贈り物の基本知識を解説します。
<この記事の要点>
・お悔やみの贈り物として香典、供花、供物などがあげられる
・葬儀に参列ができない場合、香典は現金書留で送るのがマナー
・お供え物を渡す際は場所を取らないサイズで日持ちする果物や乾物などを選ぶのがよい
こんな人におすすめ
お悔やみの贈り物に悩んでいる人
贈り物の渡し方のマナーを知りたい人
お悔やみの贈り物は何を選ぶ?
故人を亡くし悲しみに暮れる遺族へのお悔やみの贈り物として、メジャーなものに、香典、供花、供物があります。
さまざまな事情により通夜や葬儀に参列できない場合、気持ちを伝える手段として贈り物を贈ることが一般的です。ここでは、お悔やみの贈り物に何を選ぶのがベストなのか見ていきましょう。
葬儀の贈り物とは
訃報を聞き通夜や葬儀に参列できない場合、多くの方がお悔やみの贈り物の手配を始めます。
葬儀後は遺族も法要の手配などで忙しくなりがちですので、葬儀前や当日に贈るのもよいでしょう。また遠方ですぐの手配が難しい場合は、弔問時などに合わせて後日贈る方法もあります。
しかし、故人が信仰する宗教や宗派によって、選ぶべき不祝儀袋や贈れる花の種類も変わるため、宗教宗派の確認が必要です。
弔問する際には遺族は大切な方を亡くしたばかりであることも考えて長時間滞在することは避け、お悔やみの気持ちを伝え贈り物を渡したら短時間で帰るようにします。
香典
お線香の「香」という字を使用する香典は、文字通りでお線香代として供えるお金です。通夜や葬儀に参列する場合、持参時は地味な色の袱紗(ふくさ)に入れて受付で渡したり喪主に渡したりします。
参列ができない場合は、現金書留で送るのがマナーです。不祝儀袋の厚みを抑えるために、あらかじめ水引が印刷されたものを選ぶとよいでしょう。手順を以下にまとめました。
1. 現金を不祝儀袋に入れてから、定形外サイズとなる現金書留用の封筒に入れる
2. 郵便局の窓口で手続きを済ませる
香典の相場は、生前の故人との関係性や香典を贈る方の年齢によって変わります。以下に相場の一覧をまとめました。
| 両親 | 3万円~10万円 |
| 兄弟姉妹 | 3万円~5万円 |
| 祖父母 | 1万円~5万円 |
| 叔父叔母 | 5,000円~3万円 |
| 友人や知人(家族含む) | 5,000円~1万円 |
供花
供花の読みは、「きょうか」または「くげ」です。贈る場合は、葬儀後から忌明けとされる四十九日法要までに贈りましょう。法要前日や当日でも開始前までに手配を済ませていれば、会場を飾る役割にもなるため迷惑をかけることはありません。ただし、宗教や宗派によって忌明けの日数は異なるため確認が必要です。
花についてですが祭壇に飾ると目立つような派手な花は避け、日持ちしやすいものを選びましょう。故人が大好きだった花があれば、そちらも入れると喜ばれるかもしれません。花は四十九日法要まで、自宅など遺骨を安置しておく場所に供えられます。
一般的なアレンジメントの相場は5,000円~1万円です。相場以上のものを贈ってしまうと、遺族も素直に受け取れなくなるため、注意しましょう。
不慣れな方は花屋さんや葬儀社に相談するのがベストです。ふさわしいものを用意してくれますので、マナー違反になるような事態を招く心配もありません。
供物
供物は「くもつ」と読みます。一般的には、弔問客が祭壇に供える品物のことをいいます。日本人の多くが信仰する仏教を例にすると、焼き菓子、果物、ろうそく、進物用線香が定番です。相場ですが供物を持参する場合は3,000円前後、後日郵送する場合は5,000円前後となっています。
弔問先に到着したら、基本的には玄関先で遺族に品物を渡して帰りましょう。また供物を持参する場合は、香典を渡さなくてよいとされています。
宗教によっては、お悔やみの贈り物の中に供物がない場合もあるため、弔問前に確認したほうがよいでしょう。このことを知らずに供物を持参してしまうと、遺族に迷惑をかけてしまうかもしれません。
葬儀のお返しに贈る物
葬儀を執り行うにあたり、遺族はさまざまな方からお悔やみの贈り物を受け取ります。「香典返し」という言葉がありますが、これは参列者からいただいた香典に対して遺族がお返しを贈る際に使用する言葉です。
供物を受け取った場合もお返しをします。ここでは、葬儀のお返しとして遺族は贈り物に何を選べばよいのかを見ていきましょう。
食品や日用品
香典返しの定番は、「消えもの」といわれる食品や日用品です。消えものが選ばれやすい理由には、故人を偲んでくれたことに対する感謝の気持ちと共に、「不祝儀がそのまま残ってしまわないように」という意味があります。
定番な品物は、お茶、乾物(海苔など)、焼き菓子、線香、ろうそくです。最近は受け取った人が選んで楽しめるということで、カタログギフトを選択する方も増えています。価格帯別に選べるため、多めに香典をいただいたり供物も一緒にいただいたりした場合などにも対応しやすいと評判です。
贈り物の相場
香典返しを贈る場合の相場は、香典や供物などいただいた金額に対して半額が基本となります。また香典には遺族を援助するという意味もあるため、金銭面で厳しい場合は4分の1でもよいでしょう。いただいた香典の金額が相場よりも高い場合は、3分の1の金額でお返しすることもあります。
ただし相場は地域や家庭の考え方によって差が出やすいため、香典返しを含めたマナーに自信がない場合は周囲の年長者に相談するとよいでしょう。
葬儀以外で贈り物を贈るタイミング
遺族へ贈り物を贈るベストなタイミングは、葬儀以外にも複数回存在します。故人を偲び、思い出に浸る時間は故人が喜ぶことはいうまでもありませんが、悲しみの気持ちでいっぱいの遺族や深い親交があった知人らにとってもかけがえのない時間だといえるでしょう。ここでは、どのようなタイミングで贈り物を贈るのがベストなのか解説します。
初七日と四十九日法要
仏教の場合は故人が亡くなった日から数えて7日目は初七日であり、この日は死後の世界を決める大切な日です。
また49日目は四十九日法要を執り行う日であり、無事に故人が極楽浄土に行けるかどうか決断が下されます。遺族らは故人が無事に極楽浄土に行けることを願いながら、追善供養を執り行うことが一般的です。
また追善供養をしなくとも、浄土真宗のように初めから行き先が決まっている場合もあります。初七日と四十九日法要は、故人が亡くなってから節目となる大切なものです。
そのため、親戚や故人と親交の深かった方に声を掛けて法要を執り行うのが一般的となっています。このときに贈り物を贈ると遺族から大変喜ばれます。
お盆
日本ではお盆に合わせて故郷に帰省する習慣があり、滞在する中でお墓参りに親や親戚と一緒に行くという方も多いのではないでしょうか。お盆は故人の魂が供養されているお墓に戻ってくる日と考えられているため、この世に迎えるための迎え盆とあの世に無事に帰れるようにサポートする送り盆をする家庭も多くあります。
故人がこの世に戻ってきているお盆に何か贈り物をするのもよいでしょう。親戚で集まった際には、故人との思い出話をして故人を偲ぶことが大切です。
お彼岸
お彼岸とは、先祖を供養する日本独自の伝統行事をいいます。この期間は仏教でいうあの世とこの世の距離が近くなると考えられており、お墓参りに行ったり故人をしのんだりすることで有名です。年2回3月と9月にあるもので、それぞれ春分の日と秋分の日が中日となります。
遺族や親戚も故人を偲ぶことが多い期間のため、このタイミングで贈り物を渡すのもよいでしょう。
あわせて読みたい
命日
命日には、祥月命日(しょうつきめいにち)と月命日(つきめいにち)があります。祥月命日とは「故人が亡くなった日」で年に1回しかありません。祥月命日には親戚や知人を呼んで法要を執り行う家庭も多いため、贈り物を渡す場合はこの日に贈るとよいでしょう。
また月命日は故人が亡くなった日にちをいいます。例えば3日に亡くなったのであれば、月命日は3日です。月命日ごとに法要を執り行う家庭は少ないとされています。
葬儀以外の日の贈り物の選び方
葬儀が終われば遺族は一段落できそうなものですが、実は法要の日程を組んだり故人が亡くなったことで手続きに追われたりと忙しい日々を送る場合が大半です。
葬儀に参列できなかったからということで、弔問して贈り物を渡したい場合は事前に遺族へ連絡しておくとよいでしょう。
贈り物を贈る際は、日持ちするかどうかを軸に品物を選ぶことが大切です。日持ちが良くて故人が好きだったものを選ぶと、あの人のことを考えて選んでくれたのねと遺族も嬉しい気持ちになるでしょう。
好きなものが分からない場合は、果物や花がおすすめです。たくさんの方が故人の家に弔問することを考えて、傷みやすいものや、かさばりやすいものは選ばないようにしましょう。
お悔やみとして贈り物を渡す際のマナー
遺族に贈り物を渡す際は、素直に受け取ってもらえるように最低限のマナーを知った上で渡すように心がけます。
例えば品物にのしがなかったり、あっても慶事用ののしだったりすると受け取った遺族もマナーを知らない人なのね、と呆れてしまうかもしれません。お悔やみの贈り物を渡す際のマナーを知って、遺族に喜んでもらえるものを贈りましょう。
のし紙のマナー
遺族に贈り物を渡す際は、のし紙をかけるのがマナーです。のし紙には、慶事用と弔事用があります。慶事用は蝶々結びで紅白、弔事用は結び切りで黒白と全く見た目が異なる点を知っておきましょう。お悔やみの贈り物は弔事用ののし紙を使用します。
次にのし紙のかけ方です。かけ方には、贈り物を持参するときに主に使う「外のし」と郵送するときに主に使う「内のし」があります。
「外のし」とは包装紙の上からかけるもので、「内のし」とは品物の箱の上に直接かけて上から包装紙で包むものです。持参するか郵送するかを決め、ふさわしいのし紙のかけ方で贈り物を贈りましょう。
お供え物を渡す際のマナー
遺族へお供え物を渡す際はマナーを守った上で品物を渡します。まずお供え物を選ぶのですが、場所を取らないくらいのサイズで日持ちする果物や乾物などを選ぶのがベストです。
お供え物にかけるのし紙は結び切りで黒白、表書きは「御供」「御供物」とします。お供え物の相場は、5,000円~1万円くらいがちょうどよいとされています。
葬儀の際に渡すことになりますので、渡す場合は受付の方に「御霊前にお供えください」と言って渡します。
香典を渡す際のマナー
お悔やみの贈り物として香典を渡す際は、不祝儀袋に入れ地味な色の袱紗(ふくさ)に入れて葬儀が執り行われる場所まで持って行きましょう。斎場の場合は受付に渡す際はお悔やみの言葉を述べて袱紗から不祝儀袋を取り出し、相手側に向けて渡します。
仏教の葬儀では、香典に使用する不祝儀袋の水引は結び切りの黒白、表書きは「御霊前」「御香典」とするのが一般的です。ただし浄土真宗の場合は「御仏前」と書きましょう。香典の相場は親戚で1万円~3万円、知人・友人で5,000円~1万円です。年齢や故人との関係性によって、適切な金額は異なります。
葬儀におすすめの喜ばれる贈り物
葬儀の際に渡す贈り物にはタブーとされているものがいくつかあります。
例えば、殺生に関する肉や魚、慶事に使用する鰹節や昆布などがあります。ここからは、故人や遺族から喜ばれやすい贈り物を確認しましょう。
お菓子類
贈り物の王道はお菓子類です。焼き菓子や砂糖菓子などが定番となっています。日持ちしやすく場所を取らない上に、遺族や親戚などが集まったときに食べられることから人気です。
焼き菓子であれば万人受けしやすいマドレーヌやバウムクーヘン、砂糖菓子であれば昔ながらの落雁(らくがん)や羊羹(ようかん)が喜ばれるでしょう。
お茶やコーヒー
お茶やコーヒーは消え物としてお菓子と同じくらい定番の品物です。故人はお供えした飲み物を飲むとされているため、飲み物は故人の好みを重視して選ぶとよいでしょう。
またサイズに関してですが、仏壇に供えるのに困るようなサイズは避けます。350mlや500mlサイズの飲みものを選べば、遺族が仏壇にお供えする際に苦労しないでしょう。
ろうそくや線香
お参りするときにろうそくや線香は必需品です。頻度は仏壇を管理する家庭の状況によりますが、毎日お参りするとなれば使用頻度は高くなります。
ろうそくや線香は同じものを使い続けるのも良いのですが、贈り物として選ぶ場合は珍しいデザインや香りに注目して選ぶと喜ばれるかもしれません。
職人がこだわって作っているろうそくやリラックスできる香りが漂う線香などもありますので、選ぶ際は参考にするとよいでしょう。
フルーツ・ジュース・そうめんなど食べ物
日持ちすることを重視して贈り物を贈りたい場合は、果汁が少ない丸いフルーツや保管に困らないジュースがおすすめです。他に食べ物を贈りたい場合は、そうめんや冷や麦を選ぶとよいでしょう。
故人がこの世からあの世に戻るときにお供え物を持って帰る際は、背中に品物を担ぐと考えられています。その際に品物を縛る目的で麺類が必要と考えられているため、故人も麺類を贈れば喜んでくれるでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
故人や遺族にとってお悔やみの贈り物をもらえることは嬉しいことではありますが、マナーを守らなければ相手を不愉快にさせてしまうかもしれません。
不幸は突然訪れるものですので、その時が来ても慌てなくて済むように事前に葬儀社へ葬儀について相談しておくとよいでしょう。
小さなお葬式であれば、遺族の思いを形にした葬儀を提案できます。悲しい気持ちを抱えながらの葬儀は大変ではありますが、葬儀の前後に弊社スタッフがしっかりと遺族に寄り添ってサポートしますので安心してください。葬儀について詳しく知りたい方は、小さなお葬式へ連絡いただければ幸いです。


遺言書には、誰の遺言かを明確にするために署名が必要です。ホゥ。