「次の法事はいつか」「法事は何回忌までするものなのか」など、法事についてよく分からずお困りではないでしょうか。
ひと昔前までは、身近にいる父母、親族や近所の年長者から法事のやり方、回数など自然と教え伝えられてきたものです。しかし、近所同士の交流が減り、核家族化が進む昨今において、法事について教えてもらう機会は滅多にないのが実状です。
本記事をお読みいただくことで、法事の種類や回数、弔い上げについてお解りいただけます。ぜひ最後までご覧ください。
<この記事の要点>
・法事には逝去後7日ごとに49日まで行われる忌日法要と、一周忌以降の祥月命日に行われる年忌法要がある
・一般的に三十三回忌または五十回忌の法要で弔い上げとするケースが多い
・法事の準備には日時や場所の決定、僧侶の手配、参列者への案内、供物や供花などがある
こんな人におすすめ
次の法事がいつなのか気になる方
弔いあげをお考えの方
法事の種類について知りたい方
法事の目的や種類をチェック
全国各地で法事が営まれているのですが、何のために執り行うのかご存知の方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。
法事にも長い時をかけて伝わってきた仏教の知恵が詰まっています。出席する意味や目的を理解して、法事に臨むと自分の気持ちもまた違ってくるものです。
まずは法事の意義など基本的知識、法事の種類について確認していきましょう。
法事の必要性
法事の目的は宗派ごとに捉え方が若干異なりますが、亡くなられた方があの世でより良い処遇を受けられるように、悟りを開き浄土の世界に行けるように祈ることです。
仏教の多数の宗派において、故人は死後7日ごとに生前の言動に関する審査を受け、49日目に生まれ変わる世界が決まるとされています。
49日以降は法要ごとに阿閃如来など仏様のご加護を頂き、改めて生前の言動や死後における修行の様子が裁定され、悟りを開き浄土に行くための教えを受けることができるという考え方です。
また、本来は故人を想って行う法事ですが、最近は故人を縁として家族親族が親交を深める場としても意味を有する風潮もあります。
法事と法要は違うもの?
法事と法要は似ている言葉ですが、意味合いは異なります。「法事」は僧侶の読経と法話に会食を含めた一連の行事のことです。対して、「法要」は僧侶の読経と法話のみを意味します。
法要は「仏様の教えの主たる部分」という意味があり、仏教に基づく儀式全般を指します。故人や先祖の供養だけではなく、仏前の結婚式や寺院の住職就任式も法要の一種です。
法事の種類1 忌日法要
逝去後7日ごとに49日まで行われる法要と逝去後100日目の法要のことを「忌日法要」と言います。忌日法要の読み方は「きにちほうよう」または「きじつほうよう」です。初七日法要、四十九日法要が代表的な忌日法要として挙げられます。
なお、忌日法要の該当日は、逝去日を含めて日数をカウントし決まります。たとえば1月1日が逝去日であれば初七日法要は1月7日です。
法事の種類2 年忌法要
年忌法要は一周忌以降、定められた年の故人の祥月命日に執り行う法要です。祥月命日とは、一周忌以降の故人が逝去した月日と同じ月日のことを指します。年忌法要には、三回忌、七回忌などが代表的です。
諸説ありますが、インド地域で発祥した仏教においては四十九日までの法要しかなかったと言われています。後に中国で儒教の影響により加わったのが百箇日、一周忌、三回忌、そして日本で神道の影響を受けて加わったのが、七回忌以降の法要と考えられています。
法事の種類3 その他の法要
忌日および年忌以外の法要もあります。たとえば、春と秋の彼岸会、夏のお盆、お盆と同時期に実施されることの多い施餓鬼(せがき)です。お盆に限っては、故人が初めて迎えるお盆を「新盆(にいぼん)」や「初盆(ういぼん)」と言います。
そのほか、仏壇や位牌購入した際の魂入れの法要、お墓に遺骨を納める際の納骨法要など状況に応じて寺院にお願いする法要もあります。
| 法要名 |
行う時期 (逝去日からの日数・ 年数) |
特記事項 |
| 初七日法要 | 7日目 | 葬儀告別式当日に営むことが多くなっている |
| ニ七日法要 | 14日目 |
省略されることが多い 霊前にお供えをして線香を手向けるのみで 家族だけで対応することも多い |
| 三七日法要 | 21日目 | |
| 四七日法要 | 28日目 | |
| 五七日法要 | 35日目 | |
| 六七日法要 | 42日目 | |
|
七七日法要 または 四十九日法要 |
49日目 |
親族も呼び比較的盛大に営むこと傾向が強い |
| 百箇日法要 | 100日目 |
省略することも多く、実施する場合は 僧侶を呼び家族のみで行うことが多数 |
| 一周忌法要 | 1年目 | 親族も呼び比較的盛大に営むことが多い |
| 三回忌法要 | 2年目 |
家族と親交の深い親族を中心に営むことが多い |
| 七回忌法要 | 6年目 | |
| 十三回忌法要 | 12年目 | |
| 十七回忌法要 | 16年目 | |
| 二十三回忌法要 | 22年目 | |
| 二十七回忌法要 | 26年目 | |
| 三十三回忌法要 | 32年目 | |
| 三十七回忌法要 | 36年目 | |
| 五十回忌法要 | 49年目 |
上記の一覧のなかで、百箇日(ひゃっかにち)法要までが忌日法要、一周忌法要以降が年忌法要に該当します。
一周忌が逝去日から1年後で、三回忌が2年後となることに困惑される方が多いようです。一周忌は年が一周したことを意味しています。
三回忌は逝去日を1回目、その1年後が2回目、2年後を3回目としてカウントし、3回目の祥月命日と考えると分かりやすいでしょう。
年忌法要はいつまで実施するもの?
一覧表でもご覧いただいたように、法要は長期に渡って続いていきます。宗派や寺院の開祖など、なかには百回忌、三百回忌を越えるような法要が続いている方も見られますが、一般的には年忌法要をいつまで実施するのでしょうか。
地域差もありますので一概に申し上げるのは難しいところですが、ここでは一般的な年忌法要の終了について説明します。
弔い上げのタイミング
弔い上げとは、故人に対する個別の供養を終了することです。弔い上げ以降は、故人として供養されるのではなく、他のご先祖様と一緒に供養されていくことになります。
弔い上げのタイミングに明確な決まりはありませんが、一般的には、三十三回忌または五十回忌の法要をもって弔い上げとするケースが多く見られます。
ただし、弔い上げのタイミングは地域の慣習、寺院の方針や意向に大きく左右されますので、実際に弔い上げの法要をいつとするかは、寺院に相談すると良いでしょう。
宗派による弔い上げの時期
真言宗、天台宗、曹洞宗では三十三回忌を弔い上げとすることが多い傾向にあるようですが、特に宗派ごとにはっきりとした決まりはありません。
浄土真宗でも三十三回忌とするケースが多いようですが、弔い上げという考え方自体が浄土真宗にはないとおっしゃる住職もいます。
宗派による違いよりも、前述のとおり地域性や寺院の方針や意向によって弔い上げの時期が変化しますので注意を要します。
回によって異なる規模
法事では、何回忌なのかによって集まる人数の規模が変わります。法事の中で、家族に加え広く親族をお招きし比較的大きな規模で行われるのは、初七日、四十九日、一周忌、三回忌の各法要です。
一般的には一周忌以降、家族と近しい親族のみとなるなど、段々と規模が小さくなっていく傾向が強く、特に七回忌以降は家族のみで行う場合が多くなります。
弔い上げを早く行いたい場合
子供がいない場合など、家やお墓のことを引き継ぐ方がおらず、自分自身も高齢であるため三十三回忌や五十回忌を待たずに弔い上げをして、お墓も仏壇も整理しておきたいという方がいらっしゃるかもしれません。
実際に家庭の事情により、十三回忌や二十三回忌のタイミングで弔い上げをする場合もあります。もし、前倒しの弔い上げを希望するのであれば、菩提寺に相談が必要です。
菩提寺をお持ちでない方につきましては、小さなお葬式にご相談ください。ご事情に合わせて適切なご助言やお手伝いをさせていただきます。
法事までにするべき準備とは
長い年月をかけて様々な法事が存在するわけですが、準備するべき事柄は概ね全て同じです。法事を執り行うには、どのような準備が必要となるのでしょうか。法事を行うべき日にちが間近に迫ってきてから、慌てるのは避けたいものです。
ここでは法事までに準備するべき主なポイントをお伝えします。
寺院への依頼
法事を実施する日時や場所の相談を含めて、該当日の1ヶ月~2ヶ月くらい前を目安にして寺院に法事の依頼を行います。お盆やお彼岸シーズン、年末年始近辺は寺院の予定が立て込む可能性が高いので、特に早めに依頼することが重要です。寺院に連絡する際には、会食の参加の有無、交通手段、御布施を渡すタイミングについても確認しておくことをおすすめいたします。
お寺とお付き合いのある方
菩提寺(ぼだいじ)とは、先祖代々のお墓のあるお寺のことです。菩提寺がある場合には、菩提寺に連絡をして、読経の依頼を行いましょう。
お寺とお付き合いが無い方
菩提寺が無い場合には、知人縁故からお寺を紹介してもらう方法や、葬儀の際にお世話になったお寺に相談する方法があります。
その他最近では、インターネット上でお坊さん手配サービスを利用される方も増えています。
自宅はもちろん、手配したお坊さんのお寺での法要も行えるので、菩提寺がない方には便利です。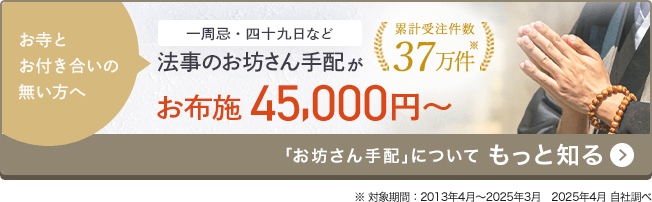
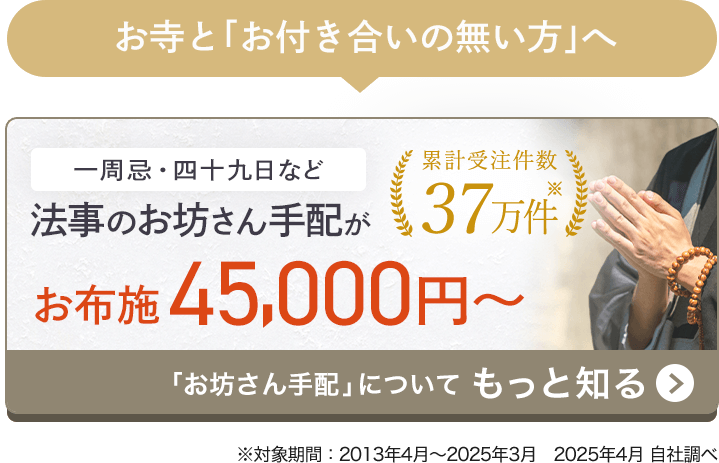
お寺の都合によっては希望日に添えない場合もあるため、1ヵ月~2週間前を目安に寺院手配の予約をすることをお勧めします。
会場の予約をする
法要会場、食事会場の予約も必須です。ただし、法事会場でそのまま食事ができるようであれば、法事会場とは別に食事会場を押さえる必要はありません。
参加者に高齢者が多い場合、会場は椅子席のほうが喜ばれるようです。寺院や霊園併設の法事会館は、お盆やお彼岸の時期に予約が混み合いますので、余裕を持って行動することをおすすめします。
料理・返礼品・供花を手配する
注文数が確定するのは法事の日を迎える直前になるかもしれませんが、料理や返礼品の内容は早めに業者と打ち合わせを行い決めておくことも必要です。供花も誰が出すのか取りまとめて、生花店や葬儀社に依頼をかけておきます。料理や返礼品の用意の仕方は、地域差がありますので、寺院、葬儀社、料理業者、返礼品業者などに確認をしながら手配を進めていきましょう。
案内状の手配と送付
ごく近しい親族であれば、電話やメールで案内を済ませることもありますが、普段あまりお付き合いのない親族に対しては、案内状を送付するほうが丁寧です。案内状は料理業者や返礼品業者が、作成から送付の代行サービスを提供していることが多いので、状況に応じて依頼するとよいでしょう。
案内状は、遅くとも法事実施日の1ヶ月前までに相手の手元に届くよう手配することが適切です。
仏教以外の宗教でも法事はするの?
日本では仏式による葬儀が多くを占めますが、神道やキリスト教で葬儀を行う方もいらっしゃいます。神道やキリスト教は、仏教とは異なる死生観です。神道やキリスト教には、葬儀を終えたあとに仏教の法事に相当するような故人に対する行事があるのでしょうか。
ここでは仏教以外の宗教として、神道とキリスト教について見ていきましょう。
神道の場合
神道には、法事に相当する行事として「霊祭(れいさい)」があります。神道では、亡くなられた方は家や子孫を守る神になるという考え方です。霊祭では、無事に神になれることを願い、自分達をお守りくださいますようにと祈ります。
霊祭には、たとえば逝去後50日目の五十日祭、逝去後100日目の百日祭、そのあとは一年祭、三年祭、五年祭、十年祭と続き、その後は十年ごとに営まれる式年祭などがあります。神道において一般的に弔い上げとされるのは、五十年祭です。
キリスト教の場合
キリスト教にはカトリックやプロテスタントなどの教派があり、死の捉え方にも違いがあります。しかし、キリスト教では総じて、死は神の元に召される祝福すべきことという考え方です。
法事に相当する行事には「追悼ミサ」や「記念集会」があります。逝去後1ヶ月、1年後は実施されるケースが多い傾向にありますが、追悼ミサや記念集会を行うタイミングは地域や教会によって様々です。
実はキリスト教では、もともと葬儀後の行事が存在しませんでした。しかし、日本に伝来してから各地の慣習に合わせるようにして、葬儀後に追悼ミサや記念集会が実施されるようになったと言われています。
法事参列時の適切な服装マナー
多くの方にとっては頻繁に参列するものではありませんし、法事参列時の服装に不安をお持ちの方も散見されます。
法事の施主側の立場であっても、招かれる立場であっても、場の雰囲気を壊さない適切な服装で参加することは大切です。いずれの立場であっても基本的に服装マナーは同様となります。
法事参列時の服装についても確認しておきましょう。
基本は喪服スタイル
法事の参列に適切な装いは、男女とも喪服です。男性であれば、礼服やフォーマルスーツと呼ばれるような黒いスーツに、白ワイシャツ、黒ネクタイ、黒靴下、黒革の紐靴を着用します。
女性は礼服やフォーマルウェアと呼ばれるようなアンサンブル、ワンピース、スーツのいずれかに、黒のインナーまたはブラウス、黒のストッキング、黒のパンプスとなります。
喪服を着ないケースもある
回忌法要が進み、七回忌や十三回忌を過ぎる頃から、喪服から平服寄りの装いになることもあります。平服と言いましても普段着ということではなく、黒系や濃紺の色合いで男性はスーツ、女性はアンサンブルなどの着用が適切です。
なお、自宅に僧侶をお呼びし家族のみで執り行う場合には、三回忌などもっと早い時期に平服寄りの服装が着用される場合もあります。
法事に持参するもの
念珠(数珠)は必須のアイテムではありませんが、持参した方が丁寧な印象を与えます。法事でも参加者は香典を持参することが一般的慣習です。香典は、袱紗に包んで持参することが本来の作法となりますので、所有していなければ用意しておくと良いでしょう。
そのほか、法要に合わせてお墓参りをするのであれば、虫よけスプレーや日焼け止めもあるとより安心です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
法事は故人があちらの世界で厚遇を受けられるように、悟りを開き浄土の世界に行くことができるように祈りを込めて行うものです。
法要は故人の忌日法要、年忌法要と長期に渡って続いていきます。その他にもお盆やお彼岸なども年中行事も大切な法要です。
法事は一般的に三十三回忌または五十回忌をもって弔い上げとするケースが多く見られます。
法事も葬儀同様に準備や寺院の対応などすべきことが多々あり、判断に迷うこともあるかもしれません。小さなお葬式では、法事に関するご相談も承っております。早い時期での弔い上げをお考えの方や、寺院手配サービスにご興味をお持ちの方など遠慮なくご連絡ください。
また法事・法要以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へぜひご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


人が亡くなった後に行う死後処置と、死化粧などをまとめて「エンゼルケア」と呼びます。ホゥ。



































