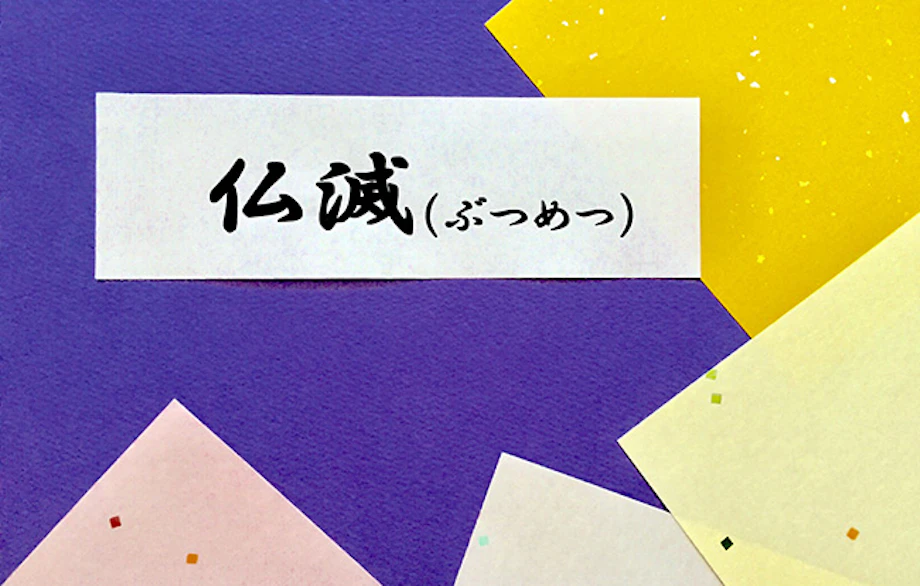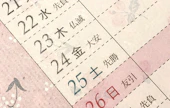法事・法要は、故人の遺族や友人にとって大切なものです。亡くなった方の魂を供養するためにも、正しく理解しておくのがよいでしょう。特に施主として法事の日程を組むときに、「いつ行うか」は悩ましい部分です。
仏滅といった六曜を基準にして日程を決めるべきか迷う方もいらっしゃるでしょう。今回は、法事と六曜の基本的な知識について説明します。
<この記事の要点>
・法事とは本来葬儀のあとに執り行われる仏教行事全般を指す
・六曜とは「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」の六つで構成されている
・六曜に合わせて法事の日程を組む必要はないが、参列者の希望も考えて決める
こんな人におすすめ
法事の日程調整にお困りの方
法事と六曜の関係性について知りたい方
主な法事の種類を知りたい方
法事とは
仏教では、亡くなった方の冥福を祈り、定期的に供養を行うことが通例となっています。法事と聞くと、僧侶を招きお経を読んでいただくものというイメージをお持ちの方も多いでしょう。
実際、お寺や自宅で僧侶にお経を読んでもらい、焼香、会食といった流れで進むことが多いです。しかし、「法事」というのは本来葬儀のあとに執り行われる仏教行事全般を指します。
そのため、一周忌やお盆、お彼岸というように法事と一口にいってもそこにはさまざまな仏教行事が含まれています。
法要との違い
法事と聞くと、法要を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。この二つにはどのような違いがあるのか、整理しておきましょう。
法要とは、逝去された方の冥福を祈るための供養行事のことを指します。一方法事は、法要と「お斎(おとき)」と呼ばれる会食を含む行事のことをいいます。また、昨今では法事のことを「追善法要」と呼ぶことが多いでしょう。
法要の種類
仏教では、亡くなってから数えて7週間、四十九日間を「中陰(中有)」といいます。中陰の間、故人の魂はあの世とこの世をさまよっていると考えられており、無事成仏できることを願い供養するのがならわしとなっています。
関西地方では、四十九日目を中陰が終わる「満中陰」としています。いわゆる「忌明け」です。この日は、忌明けのための宴を開き、納骨を行います。
ここからは、法要にはどのような種類があるか見ていきましょう。大きく分けると、7日ごとに行う「忌日法要」と年単位で行う「年忌法要」があります。
| 忌日法要 | 中陰 | 初七日 | 死後七日目 |
| 二七日 | 死後十四日目 | ||
| 三七日 | |||
| 四七日 | |||
| 五七日 | |||
| 六七日 | |||
| 満中陰 | 七七日 | 四十九日 | |
| 百箇日 | |||
| 年忌法要 | 一周忌 | 死後満1年 | |
| 三周忌 | 死後満2年 | ||
| 七回忌 | |||
| 十三回忌 | |||
| 十七回忌 | |||
| 二十三回忌 | |||
| 二十七回忌 | |||
| 三十三回忌 | この日を弔い上げとすることが多い | ||
| 三十七回忌 | |||
| 五十回忌 |
初七日
故人が亡くなった日から数えて7日目に行われる法要です。忌日法要は7日毎に行われますが、これは中国の儒教「十王信仰」の影響があるといわれています。
十王信仰では、7日ごとに死者の罪を裁く裁判が開かれると考えられており、四十九日には、7回目の審判を受け生まれ変わるとされています。
五十七日
故人が他界された日から35日目に行う法要を、五十七日法要といいます。閻魔大王の審判を受ける日とされており、四十九日と同じくらい重要視されている忌日です。
四十九日
四十九日は、特に重要な忌日と位置づけられており、閻魔大王からの審判がくだる日とされています。遺族は故人の成仏を祈って、法要を行います。合わせて納骨や仏壇に仏様の魂を入れる、開眼法要を行うことも多いです。
百箇日
百箇日法要は、卒哭忌(そっこくき)とも呼ばれており、命日から数えて100日目に行われます。自宅で行うことが多い法要でもあります。また、最近では百箇日を省略して一周忌法要を行うケースも増えています。
一周忌
死亡した翌年の同月同日(祥月命日)に営む法要を、一周忌法要といいます。喪中は一周忌までの間のことを指すため、一周忌をもって喪が明けるということになります。
三回忌
三回忌法要は、死後満2年目に行う法要です。「三」という数字がついているため、つい3年目と勘違いしてしまうことも多いため、注意しましょう。
三十三回忌
三十三回忌を迎えると、「弔い上げ」をするケースが多いです。しかし、宗派や土地柄によっても異なるため、僧侶や親戚に確認しておくとよいでしょう。
初盆
四十九日後に迎えるお盆のことを「初盆」といい、親戚や友人を招待して盛大に行うことが通例となっています。四十九日を迎える前にお盆が来た場合は、翌年に初盆の行事を行うことになります。
法事はいつ行うのがよい?
先述したように、法事・法要はさまざまな種類があり、定期的に行うものになります。しかし、「仕事で忙しくて同月同日の参加は難しい」「祥月命日だと参列者を招待できない」という方も多いでしょう。
原則として、法事は命日に行うことが望ましいですが、参列者やお寺のスケジュールによっては、別の日に変えても問題はありません。しかし、この場合は必ず「命日より前」にすることを忘れないようにしましょう。
では、具体的にどのような日がよいのでしょうか。近年では、参列者が参加しやすいよう、土日といった週末に法事を行うことが多いようです。
一方で「仏滅に法事を執り行っても大丈夫?」「赤口は凶と聞くけれど、法事を行ってもいいのだろうか」と法事を行う日の「六曜」を気にされる方もいるでしょう。
六曜というのは、カレンダーでよく見かける「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」のことです。日本人にもなじみ深く、結婚式の日取りや建物の着工日を六曜で決めるという方も少なくありません。
ここからは、六曜とは何であるのか、また法事は六曜で決めた方がよいのかどうかについて解説していきます。
六曜とは
そもそも六曜とは何なのでしょうか。歴史をさかのぼっていくと、その起源は中国にあるといわれています。
しかし、いつ誰が作り出したのかは不明です。六曜は鎌倉時代に日本に伝わったとされており、本格的なブームとなるのは江戸時代に入ってからになります。
日本に伝来してから、六曜の名称は少しずつ変化しており、現在目にする形で定着したのは江戸後期といわれています。
六曜は「六」という数字が表すように、「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」の六つで構成されています。順番もこの通りに巡っていきます。旧暦の毎月1日にはどの六曜が入るか決められており、その日を基準に割り当てられていきます。
| 1月・7月 | 先勝 |
| 2月・8月 | 友引 |
| 3月・9月 | 先負 |
| 4月・10月 | 仏滅 |
| 5月・11月 | 大安 |
| 6月・12月 | 赤口 |
新暦ではこのルールが適用されていないため、順番が不規則になっています。
法事は仏滅に行ってもよい?
仏滅は六曜の「大凶日」といわれています。本来は「物滅」という文字で、「空回りして何事もうまくいかない」という意味が込められました。
最終的に、仏の功徳も意味をなさないという解釈が生まれ、「仏」の字があてられたといわれています。結婚式といったお祝い事を挙げる方も少ない傾向があります。
「仏」と「滅」という言葉のイメージから、仏教との関連があるように思える仏滅ですが、実際のところ特別何か関係があるというわけではありません。これは仏滅を含めた六曜すべてがそうです。そのため、無理に六曜に合わせて法事の日程を組む必要はないでしょう。
しかし、参列される方の中には「六曜を考えて法事の日程を決めてほしい」「大安に法事を営むのはちょっと…」という方もいらっしゃると思います。
こういった気持ちの面は法事においてとても重要なポイントになります。法事は、遺族はもちろん招待する親族や友人にとって故人を偲ぶ大切な時間です。
可能な限り故人を弔う日は、よい日を選びたいと思う気持ちは、ごく自然なものだと思います。特に日本人は縁起を担ぐことを重視する方も多いため、法事の日程は参列される方の希望も考えて決めることをおすすめします。
仏滅以外の六曜の意味
六曜と仏教の間には特に関係はないとはいうものの、吉日・凶日はいつなのか知りたいという方もいらっしゃると思います。ここでは、仏滅以外の六曜について簡単に紹介します。
先勝(せんしょう)
「先んずれば即ち勝つ」という意味から、やることは早めに済ませた方がよいとされる日です。午前と午後で吉凶がわかれており、午前は吉・午後は凶となっています。
友引(ともびき)
「友が冥土に引きつけられる」という言い伝えから、多くの地域でこの日に葬儀を行うことは好ましくないとされています。
そのため、地域によっては葬儀場がクローズしていることもあり、法事の日程を決める際には注意が必要です。友引自体には、勝負の決着がつかない日という意味があります。
先負(せんぷ)
文字通り「先んずれば即ち負ける」といった意味を持っており、急な用事はなるべく避けた方がよい日とされています。午前は凶・午後は吉ともいわれています。
大安(たいあん)
大安は、六曜をあまり知らないという方でも一度は耳にしたことがある日ではないでしょうか。大安は六曜で一番の「吉日」とされており、何をやってもよい方向に進む日といわれています。大凶日とされる仏滅とは異なり、この日に挙式するという方も多いです。
赤口(しゃっこう)
正午の前後、午前11時頃から午後1時頃までの間以外が凶とされる日です。赤口の「赤」が火や刃物を連想させるということで、仏滅と同様お祝い事で避けられる日でもあります。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
法事は、命日に行うことが望ましいとされていますが、仕事や家庭の事情で難しい場合も多いでしょう。その場合は別の日でも大丈夫です。
ただし、必ず命日よりも前の日で調整するようにしましょう。また、仏滅といった六曜は仏教とは関係がないため、特段気にする必要はありません。ただし、気にされる方もいるので、法事の日程は、参列者の気持ちも考慮して決めましょう。
法事の日程以外にも、気になることやお困りのことがあれば、小さなお葬式にお気軽にご相談ください。小さなお葬式では24時間365日専門のスタッフがお客様をサポートいたします。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


初七日とは故人の命日から7日目に行われる法要のことです。ホゥ。