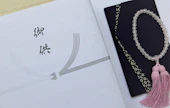故人が旅立った日から2年目の命日が三回忌です。一周忌を終えた時には、三回忌はまだ先だと感じるものですが、実のところ一周忌の翌年にはもう三回忌を迎えます。まだ先だと思い込んでいて、準備が全くできていないこともよくある話です。
今回の記事では、法要の流れを踏まえた上で、三回忌に必要となる準備について解説します。事前に準備を進めやすくするために三回忌の法事の流れも確認しておきましょう。
<この記事の要点>
・三回忌の法要は施主の挨拶、読経、焼香、施主挨拶、会食の順で進行する
・三回忌法要の会食の金額は1人当たり5,000円程度が一般的
・三回忌でもお布施を用意する必要があり、約1万円~5万円が目安
こんな人におすすめ
三回忌法要の流れを知りたい方
三回忌法要に必要な準備を知りたい方
三回忌法要の参列者の準備物を知りたい方
三回忌の流れについて
三回忌の準備を行うにあたって、まず当日の流れを確認しましょう。基本的には下記の順序となります。
1.【法要会場】施主挨拶
2.【法要会場】住職による読経
3.【法要会場】焼香
4.【法要会場】施主挨拶
5. 移動
6.【会食会場】施主挨拶
7.【会食会場】会食
三回忌における一連の流れを把握した上で、それぞれに必要な準備を行っていくようにしましょう。
日程を決める
三回忌の準備を行う上で、初めに決めるのが法要の日程です。三回忌は、故人が亡くなってから満3年だと勘違いしやすいですが、正しくは満2年となります。
日程は、できるだけ参列者が集まりやすい日を選ぶように配慮することが大切です。一般的には、忌日前の休日を三回忌法要にあてるパターンが多いでしょう。遠方から訪れる参列者がいる場合には、移動方法や宿泊についても考慮して日取りを決める必要があります。
また、菩提寺がある場合は、住職と相談しましょう。特に、土日は他の法要が入っている場合が多いため、早めに相談することが大切です。
会場を決める
日程が決まれば、続いて会場の手配をする必要があります。菩提寺や自宅で行う場合は、日程を決める際に会場についても住職と相談ができるでしょう。斎場の場合は、専門の担当者と相談しながら準備を進められるため安心です。
また、多くの場合、法要の後に会食を設けます。そのため、法要会場と同時に会食会場を決めることも忘れてはなりません。忘新年会シーズンや新年度などは会場が混み合うことが予想されます。希望の日程に会場を予約するためにも、三回忌の準備は早めに行うことが大切です。
三回忌に必要な事前準備
日程と会場を決めた後は、参列者への連絡や会食の手配など、細かい準備が始まります。三回忌では意外とたくさんの準備が必要となるため、ひとつでも漏れてしまうと当日に慌てかねません。必要事項をチェックしながら準備すれば、三回忌をスムーズに行うことができるでしょう。
参列者への案内状
三回忌は、四十九日や一周忌と並んで重要とされる法要です。葬儀ほどではないにしろ、親族はもとより故人と親しかった人も招くことがあります。そのため、招待する方に漏れがないようにしっかりとリストアップしておきましょう。
その上で、三回忌のお知らせと日時・会場などを記載した案内状を送ります。返事をしやすくするために、可能であれば、往復はがきで知らせると丁寧です。招く人がさほど多くない場合や、関係性によっては電話でお知らせしても構いません。
会食手配
法要の準備に追われていると、つい滞りがちになるのが会食の手配です。ある程度参列者の人数が把握できたら、会食会場に報告するようにしましょう。大勢での食事になるため、できるだけ早めに伝えておくことが大切です。
また、人数を伝える際には、間取りについても確認する必要があります。年配の方が参列される場合は、一階にある部屋で行うほうが安心です。
菩提寺や自宅で会食を行う場合は、仕出し料理店へ依頼する必要があるでしょう。予算については、一般的に1人当たり5,000円程度といわれています。
送迎バスの手配
三回忌法要の会場と会食会場に距離がある場合、公共交通機関で移動するのもひとつの手段ですが、自家用車か送迎バスで移動することが多いでしょう。
特に、法要の会食ではお酒を飲むケースが多いため、送迎バスを手配しなければなりません。斎場で法要を行う場合は、斎場の送迎バスを手配するのが一般的です。
しかし、菩提寺や自宅で法要をする場合は、バス会社や会食会場となる飲食店に送迎バスを手配する必要があります。会場の手配と同様に、シーズンによっては予約が取れない可能性もあるため、早めに準備をしておくことが大切です。
お布施の準備
葬儀や一周忌と同様に、三回忌でもお布施を用意する必要があります。三回忌のお布施は、おおよそ1万円~5万円が目安の額です。しかし、お寺や地域によって異なるため、不安な場合は菩提寺や斎場に問い合わせることをおすすめします。
また、僧侶を自宅や斎場にお招きした場合には、お布施だけではなくお車代を準備しましょう。お車代は5,000円程度が一般的です。さらに、僧侶が都合により会食に同席できない場合もあります。そうした場合は御膳料として5,000円~1万円程度用意しておきましょう。
お布施やお車代を準備し忘れて、当日焦ることがないように、前日までにきちんと確認しておくことが大切です。
お供え物の準備
三回忌ではお供えの準備も必要となります。仏式の場合、祭壇を飾るためのろうそくや線香、お花の準備は欠かせません。
菩提寺での法要であれば、お寺側で用意されるケースもありますが、施主側もお供えするのがマナーです。自宅を会場とする際には、忘れずに準備するように心がけましょう。
また、参列者がお供え物としてお花や線香を持参する場合もあります。果物やお菓子、日持ちのする佃煮など、故人が好きだったものを供えるのもよいでしょう。ただし、殺生をイメージさせる生ものは法要のお供えとしては避ける必要があります。
返礼品の準備
三回忌法要において参列者からお供えや香典をいただいたら、返礼品が必要となります。返礼品のマナーは、基本的には葬儀や一周忌と同じです。しかし、掛け紙の水引の色は三回忌以降から青白か黄白も使用できます。
また、引き出物の金額としては、いただいた金額に対して1/3~半額程度が一般的です。3,000~5,000円程度の品物を準備しておくとよいでしょう。
香典辞退の場合でも返礼品を用意することもあります。これは、参列に感謝する意味合いの贈り物と捉えておきましょう。
挨拶の準備
三回忌の施主の役目として欠かせないのが挨拶です。施主は、法要を円滑に進めるための司会進行役という一面もあります。そのため、前日までに挨拶の内容をまとめておくと、当日にスムーズに進行できるでしょう。
とはいえ、三回忌の挨拶はできるだけ手短に行うのがポイントで、一周忌と比べると和やかな雰囲気で話すといった特徴があります。そのため、あまり気負う必要はありませんが、いざ本番となったときに慌てないためにも事前の準備が大切です。
三回忌当日の注意点
三回忌の準備を万全に行っていても、当日になってうっかり忘れ物をする場合もあります。また、仏事におけるマナーがわからず、服装や持ち物などに迷うこともあるでしょう。三回忌当日になって困らないように、前もって当日に必要なものをリストアップしておくと安心です。
三回忌当日の持ち物
前日までしっかり準備していたのに、当日必要なものを忘れてしまっては意味がありません。三回忌当日に必要なものは次の通りです。忘れないようにひとつにまとめておくとよいでしょう。
・お布施、お車代、御膳料
・袱紗(ふくさ)
・お供え物(仏花・線香・ろうそくなど)
・遺影
・位牌
・数珠
・白いハンカチ
・ティッシュ
・黒いバッグ
・返礼品
返礼品については、参列者が会場を後にする際に渡すのが一般的です。会食に出席しない方がいる場合も踏まえて、渡す場所やタイミングについて打ち合わせをしておくようにしましょう。
三回忌当日の服装
三回忌は比較的和やかな法要となりますが、大切な法要には変わりありません。そのため、施主側は喪服を着用するのが一般的です。格としては準喪服です。
靴下やストッキング、靴も黒色のものを準備しておきましょう。また、結婚指輪以外の装飾品は外しておくのがマナーです。女性の場合、露出の多い服装も避ける必要があります。
子どもは、学生服を着るのが無難ですが、制服がない場合は黒や濃紺など派手ではない色での装いでまとめましょう。
三回忌において参列者が準備するもの
三回忌は前もってお知らせが届くのが一般的です。そのため、参列者も事前に持ち物を準備できます。特に、服や小物などは前日に用意すると足りないものが出てくる可能性があるため、早めに確認しておくことが大切です。
当日になって慌てないように、参列者も必要なものをリストアップしておくことをおすすめします。
参列者の服装
葬儀や一周忌は、参列者も喪服を着て参加するのが一般的です。しかし、三回忌になると参列者は平服でもよい場合があります。法事での平服とは、黒や紺などトーンの低い色の服です。また、女性の履物は3センチ~6センチのヒールが低めのパンプスを選ぶことをおすすめします。
加えて、寒い時期は上着にも注意が必要です。殺生をイメージさせる本革や毛皮のコートは、三回忌だけではなく仏事全般において避けたほうがよいでしょう。
施主側同様、結婚指輪以外のアクセサリー類は控えましょう。また、仏事のマナーとしてマニキュアも避けるようにしましょう。
参列者の持ち物
参列者が三回忌に出向く際に、準備しておくべき持ち物は下記の通りです。早めに準備して、忘れ物がないように心がけましょう。
・お供え物:フルーツやお菓子、生花などを準備します。生物はマナー違反となるので注意しましょう。
・香典:関係性によって異なりますが、香典は1万円~5万円程度といわれています。不祝儀袋に包むようにしましょう。
・袱紗(ふくさ):御香典を包む際に使用します。弔事用の色は紺や紫といった寒色系です。
・数珠:宗派によって異なりますが、略式数珠を持っておくとどの仏式法要でも使えるのでおすすめです。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
三回忌は、葬儀や一周忌よりも決まりごとに縛られないのが一般的です。とはいえ、仏事には変わりなく、準備するものもたくさんあります。
特に施主を担う方は、参列者への案内から会食まで細やかな手配が必要となるため、早い段階でお寺や斎場に相談をして準備をしておくことが大切です。
法事・法要に関するお困りごとや葬儀全般に関する疑問がある場合は、「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


亡くなった方や仏に向けて、香を焚いて拝む行為を焼香(しょうこう)といいます。ホゥ。