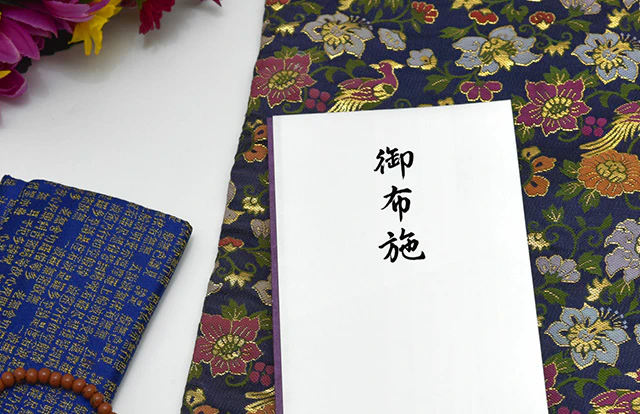命日から四十九日までの間、7日ごとに実施される法要を「中陰法要(ちゅういんほうよう)」と呼びます。法要では読経が不可欠ですが、お布施は必要になるのでしょうか。この記事では、中陰法要のお布施について解説します。
<この記事の要点>
・準備は日時・場所を決めて、僧侶や参列者の都合を確認し、お布施を用意する
・お布施の目安は3万円~5万円で、お寺以外で法要を行う場合はお車代も包む
・お布施は直接手渡しせず、切手盆に載せて渡すのがマナー
こんな人におすすめ
中陰法要とは何かを知りたい方
中陰法要の準備を知りたい方
中陰法要のお布施の目安や渡し方を知りたい方
中陰法要とは?
中陰法要とは、逝去した方の命日から7日ごとに実施される仏教の法要のことを指します。
逝去した方は「命日から四十九日間はこの世を彷徨う」とされています。この四十九日間を、現世にも来世にもいない中間的な期間として「中陰」と呼びます。中陰の間は7日ごとによい来世になるか否かの判断が下されるので、中陰法要を営みその判断がよいものになることを願います。
中陰の意味
中陰とは、逝去した日から四十九日までの期間を指し「中有(ちゅうう)」とも呼ばれます。逝去した方の魂は、中陰の間に六道(ろくどう)と呼ばれる世界をさまようといわれています。7日ごとに十王(じゅうおう)の裁きを受け、六道である「天道」「人間道」「修羅道」「畜生道」「餓鬼道」「地獄道」のいずれかに行先がきまります。
中陰法要は、逝去した方が極楽浄土へ行けることを願って行われる法要です。生前に悪行を犯していても、遺族が祈りを捧げることでその徳を故人が受けられると考えられています。
満中陰の意味
満中陰(まんちゅういん)は「命日から四十九日が経過して忌が明けた」という意味を持ちます。「忌明け(きあけ)」「尽中陰(じんちゅういん)」と呼ばれることもあります。
命日から数えて四十九日目が満中陰となり、故人の魂の行き先がきまります。満中陰は忌日の中でももっとも重要な日とされているため、親族一同が集まり盛大に法要を行うことも多くあります。
満中陰と満中陰志の違い
満中陰志(まんちゅういんし)とは、葬儀でいただく香典に対するお返しを意味する言葉です。忌明けを意味する満中陰とはまったくの別物なので、混同しないようにしましょう。
満中陰志は、主に関西地域で香典返しの同義として使用されています。中国地方、四国地方、九州地方の一部地域では「茶の子」と呼ばれることもあります。
満中陰志を渡す際は、忌明けや葬儀法要が無事終了したことを報告し、香典をいただいたことに対する感謝の意を述べましょう。
中陰法要の準備
中陰法要を行う際は、事前準備が大切です。準備物も多いため、事前に内容を把握しておかないと直前に慌ててしまうかもしれません。ここからは中陰法要の準備について解説します。
日程を決定する
はじめに、法要を行う日にちを決めます。満中陰(四十九日)よりも前倒しで行うことは可能ですが、先送りにしてはいけないとされている点に注意しましょう
会場を決定する
次に、法要を実施する会場をきめましょう。自宅や寺院で法要を行い、会食は別の場所で行うこともあります。
会食の料理を準備する
会食の場を設けるのであれば、料理の手配をしましょう。仕出し弁当を手配したり、近くにある料亭を予約したりするのが一般的です。あらかじめ出席者の数がわかっていれば参考にして予約するとよいでしょう。
お寺へ連絡する
お世話になっている菩提寺があれば、連絡して読経の依頼をします。菩提寺がない場合は、葬儀社に連絡して僧侶を紹介してもらいましょう。また、インターネットで僧侶を手配できるサービスもあるので、菩提寺がない方にはおすすめです。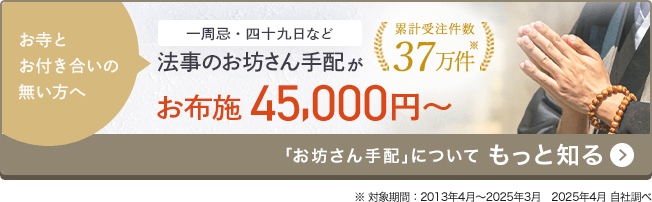
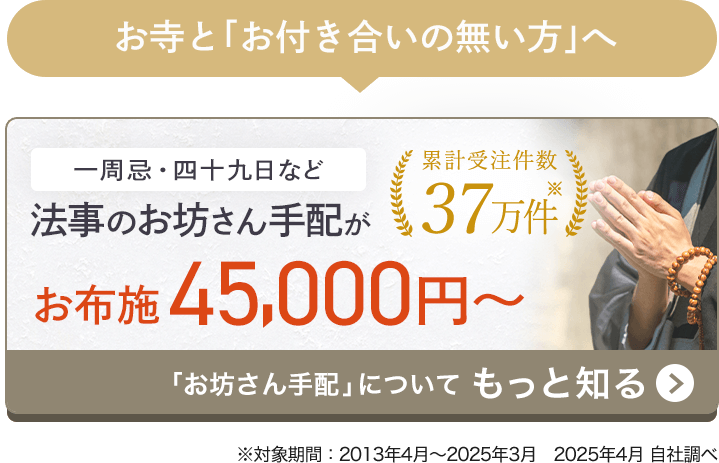
案内状を出す
招待する方がきまったら、法要の案内状を送りましょう。案内状は往復はがきを使用すると、返信用はがきを投函するだけで返信ができるので便利です。
出席人数を把握するためにも、案内状は早めに出しましょう。親族のみを招待する場合は電話連絡でも問題はありません。
お布施を準備する
僧侶に出席してもらう場合は、お布施も忘れずに用意しましょう。中陰法要のお布施の目安については、次の項目で解説します。
中陰法要のお布施の目安は?
中陰法要の場合は、僧侶に渡すお布施の金額は3万円~5万円が目安といわれています。お布施の金額に悩む場合は、親族などお布施を渡した経験がある方に相談することをおすすめします。お寺ではない場所で法要を実施する際は、お車代も包みましょう。
出席者が香典を渡す場合は、1万円~2万円が目安となります。
お布施の渡し方
お布施には表書きの書き方や渡し方にルールがあります。適当に渡してしまうとマナーに反するため注意が必要です。ここからは、お布施の渡し方について解説します。
表書き
お金は無地の袋に入れるのが一般的ですが、袋の中央上部には表書きを書く必要があります。表書きは「お布施」、あるいは「御布施」と記載しましょう。
表書きは自身で書いたものを使用しても、印刷された袋を使ってもどちらでも問題はありません。表書きを書いたら、その下に氏名、裏には包んだ金額や住所を記載しましょう。
また、お車代の表書きは「御車代」、食事代には「御膳料」と記入します。包むお札は、新札ではなく使い古したお札を使用します。
お盆に乗せて渡す
僧侶にお布施を渡す際は、手渡しではなく切手盆など小さなお盆に乗せて渡すのがマナーとされています。
お布施は渡す直前に袱紗(ふくさ)から取り出し、僧侶から氏名が読める向きで渡します。なお、小さなお盆がない場合は、袱紗の上にお布施を乗せて渡しても問題ありません。
お車代やお食事代も用意している場合は、お布施と同じタイミングで渡しましょう。
渡すタイミング
お布施を渡すタイミングは、法要前でも後でも問題ありません。法要前であれば読経が始まる前に、法要後であれば法要がすべて終わった時点で渡すとよいでしょう。
渡すときの挨拶
お布施を渡す際は、一言挨拶を添えて渡すのがマナーです。法要が始まる前に渡す場合は読経を実施してもらうことへの感謝を伝え、法要が終わった後に渡す場合は無事に終えられたことへの感謝を述べるとよいでしょう。
挨拶を交わす際は、不幸を連想させるような「忌み言葉」は使わないように注意が必要です。
中陰法要でお布施以外に必要なお金
中陰法要では、お布施以外にも以下のようなお金が必要になります。
・御膳料
僧侶が何らかの事情で法要後の会食に出席されない場合に、料理の代わりとして渡します。5,000円~1万円程度を目安に包みましょう。
・開眼供養のお布施
四十九日後に新たにお墓を建てる場合は、開眼供養(かいげんくよう)が必要になります。開眼供養とは、新しくお墓や仏壇を購入した際に行う供養のことです。僧侶を招いて読経をしてもらい、魂を込める法要です。金額は、1万円~5万円程度を目安に包みましょう。
・納骨式のお布施
納骨式は納骨をする際に行われる儀式で、僧侶に読経をしてもらいます。法要のお布施とは別に納骨式でもお布施が必要になります。目安は、3万円~5万円程度です。
中陰法要の種類
中陰法要は「忌日法要」とも呼ばれ、逝去した日から経過している日数によって忌日法要の呼び名が変化します。ここからは、中陰法要の種類について解説します。
初七日(しょなのか)
逝去した方は、命日から7日後に三途の川のそばに到着するといわれています。このタイミングで初七日法要を行い、現世から祈りを捧げることで無事に向こう岸まで辿り着けると考えられています。
法要会場に制限はなく、仏壇のある自宅でも、お世話になっているお寺でも問題ありません。出席者は、僧侶が読経をしている間に焼香をあげます。
なお、昨今では親族が離れて暮らしていることも多いため、葬儀の日に初七日を実施する「 繰り上げ法要 」を行うことも珍しくありません。
二七日~四七日
逝去した日から2週間~4週間までの1週ごとに実施される法要を「二七日(ふたなのか)」「三七日(みなのか・さんしちにち)」「四七日(よなのか・ししちにち)」と呼びます。これらの法要はそれぞれ以下のような意味や役割を持っています。
・二七日
逝去した日から2週間が経った日に行われる法要です。「初江王(しょごうおう)」という王が、故人が生前に犯した盗みについての審判を行うとされています。現世から供養やお祈りをすることで故人の罪が軽くなり、よい旅立ちができると考えられています。
お供え物は、線香やロウソク、お菓子などの消耗品がよいとされています。使用するとなくなることから「不幸を続かせない」という意味が込められています。
・三七日
逝去した日から3週間が経った日に実施される法要です。宋帝王(そうたいおう)が故人の生前の不貞についての審判を行う日とされています。三七日は僧侶や親族のみで営むことが多く、比較的小規模な法要になります。
ただし、近年では生活様式の多様化に伴い、三七日を省く家庭も増加傾向にあります。
・四七日
逝去した日から4週間が経った日に行われる法要です。四七日では、普賢菩薩(ふげんぼさつ)によって生前に犯した言葉の罪についての判決が下されるとされています。
三七日と同様に、僧侶や親族のみで営まれることが一般的です。また、二七日と同様に、判決がよりよいものになるように現世から祈りを捧げましょう。
五七日~七七日
逝去した日から5週間~7週間までの1週ごとに行われる法要は「五七日(いつなのか・ごしちにち)」「六七日(むなのか・ろくしちにち)」「七七日(なななのか・しちしちにち)」と呼ばれます。それぞれ順番に解説します。
・五七日
逝去した日から5週間後に実施される法要です。故人は地蔵菩薩(閻魔大王)から生前に犯したすべての罪を目視されると考えられています。また、ここまでの審判をもとに故人がどの世界(六道)に進むのかがきまる日とされています。現世から供養している親族の姿も目に映るとされているので、中陰の中でも重要な法要です。
また、五七日を忌明けとして、忌明けの法要を行う家庭もあります。
・六七日
逝去した日から6週間が経った日に行われる法要です。弥勒菩薩(みろくぼさつ)によって、過去に犯した罪について裁かれるとされています。この際に故人は「来世では正しい行いをしなさい」と命じられます。
・七七日
逝去した日から7週間経った日に実施される法要です。「四十九日」とも呼ばれ、これまでに受けた裁定の結果に基づき、次に生まれ変わるときの対象がきまるとされています。
この日は、逝去した方と親交のあった方々を招いてともに冥福をお祈りするのが一般的です。
百か日
逝去した日から100日が経った日に行われる法要です。「声を上げ泣き叫ぶ(哭)ことを卒業する」という意味が込められていることから「卒哭忌(そっこくき)」とも呼ばれます。
七七日を忌明けとする家庭が多いため、百か日は実施されなかったり、存在が知られていなかったりするでしょう。悲しみに区切りをつける法要として執り行い、招待する方は僧侶や親族のみであることが多いでしょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
中陰法要とは、逝去した日から四十九日までの間、7日ごとに実施される法要を指します。
中陰法要では僧侶に読経をしてもらうので、お布施を渡す必要があります。食事の場を設けたり、お寺以外の場所で法要を行ったりする場合は、御膳料やお車代が別途必要になります。
中陰法要に初めて参加する方やお布施を初めて渡す方などは、戸惑うことも多いでしょう。法要について疑問をお持ちの方は、小さなお葬式へお気軽にご相談ください。専門知識が豊富なスタッフが、法要やお布施について、丁寧にアドバイスをいたします。
法要以外にも、お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


東京や一部の地域では7月、ほかの地域では8月にお盆を迎えることが多いようです。ホゥ。