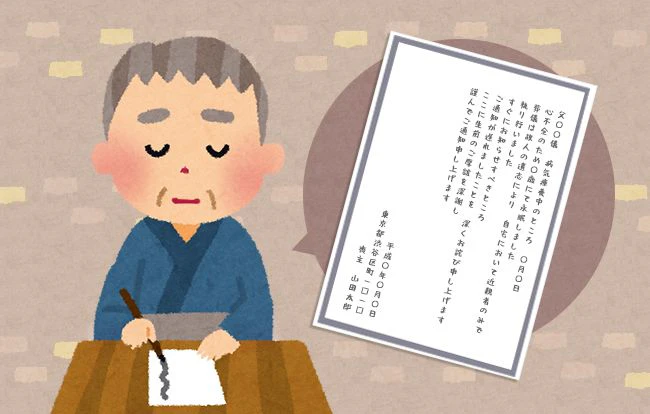家族が亡くなると、遺族の方はさまざまな手続きに追われます。葬儀の準備や役所への届出、親族や知人への連絡といったすぐにでもやらなければならないことが山のようにある中、冷静に手続きを進めるのは難しいと考える方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、家族が亡くなったら、いつまでにどのような手続きが必要かについてご紹介します。記事を読めば、葬儀や手続きに関する基本を押さえられるので、いざというときに慌てずに済みます。ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・病院で亡くなった場合は、死亡診断書を受け取ってから遺体を安置先へ搬送する
・葬儀や火葬を行うには、死亡届・火葬許可申請書などが必要
・相続関係の手続きは3か月~4か月以内に行う
こんな人におすすめ
家族が亡くなったらすぐに行うべきことを知りたい方
葬儀や法要の主な流れについて知りたい方
相続関係の手続きの主な流れについて知りたい方
亡くなったらすぐにおこなうべきこととは?
家族が亡くなったら、その当日から早速やらなければならない準備や手続きがあります。葬儀の準備はもちろん、役所の手続きも期限が短いものが多く、ひとつひとつ漏れのないよう計画的に進めることが必要です。ここでは、亡くなったあとに行うべきことについて見ていきましょう。
病院で亡くなった場合
亡くなる方の8割ほどは病院で最後のときを迎えるといわれています。医師により死亡が確認されると、死亡宣告が行われます。その後、死亡診断書を医師が用意し、看護師やスタッフの方が丁寧に遺体の処置をしてくれます。
遺族の方は故人の安置先を決めて、病院から遺体を搬送しましょう。病院にもよりますが、なるべく早めに病院から出るようにいわれることが多いようです。
自宅で亡くなった場合
自宅で亡くなった場合、療養中の病気が原因ならかかりつけの医師に連絡して死亡の確認をしてもらうとともに、死亡診断書を作成してもらいます。
一方、療養中の病気以外が原因の場合には、救急車か警察を呼びます。その際、警察が来るまでは遺体に触れてはいけません。警察は死因を明らかにするために検視を行い、事件性がなければ行政解剖、事件性があれば司法解剖をした後に、死体検案書を発行します。時間がかかることが多いので、いつ発行されるか尋ねておくと、葬儀の日程調整に役立つでしょう。
葬儀の前に確認しておくべきポイント
一般的には亡くなった翌日にお通夜、その次の日に葬儀や告別式と火葬を行います。最近は火葬場の事情で葬儀まで間が空くことも多くなっていますが、いずれにせよ葬儀の準備にあてられる時間はあまりありません。葬儀までに何をしなければならないのか、事前にしっかりと確認しておきましょう。
遺言書があるか
葬儀を行う前に遺言書の有無を確認しましょう。遺言書には故人の意志が記載されているので、葬儀についても何か書かれている可能性があります。
ただし、遺言書は家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければならないと法律で定められています。
生前、遺言書を預かった方でも勝手に読んではいけません。家庭裁判所で遺言書を開封することを「検認」といいますが、遺言書が本物かどうか、書き換えられていないかを確かめるためにも検認は必要です。
エンディングノートがあるか
故人が意志を残す手段として、エンディングノートというものもあります。遺言書とエンディングノートの違いは、法的効力があるかないかです。遺言書には法的効力がありますが、エンディングノートにはありません。法的効力のないエンディングノートは書式が自由で、また検認も必要ないので内容をすぐに確認できます。
遺言書よりも手軽に書けることもあり、最近ではエンディングノートを残す方が増えています。故人の希望を叶えてあげたいなら、エンディングノートが残されているかどうか確認しましょう。
小さなお葬式で葬儀場をさがす
葬儀や法要の主な流れ
葬儀の前には日取りや場所を決めたり呼ぶ方へ連絡したりとやることが多く、身内だけですべて準備するのは難しいといえます。
まずは親切で信頼できる葬儀社を選んで相談しましょう。また、法要を行う場合も葬儀と同様にさまざまな準備が必要になります。ここでは、葬儀や法要の流れについて解説します。
身内や親族に連絡
家族が亡くなったとき、または危篤状態のときは身内や親族に連絡しましょう。迅速かつ確実に伝える必要があるので、基本的には電話で連絡します。
特に、親族や故人と親しかった方には電話での連絡がおすすめです。また、遠方の方は移動する時間が必要なので早めに連絡します。それ以外の方に対しては、手紙や死亡広告といった手段を臨機応変に利用しましょう。
また、連絡の順番は以下の通りです。
1.家族や親族
2. 故人の友人や知人、会社関係者
3.遺族の関係者
4.近所の方や町内会、自治会
葬儀社と打ち合わせ
葬儀社は早めに手配しましょう。病院には遺体を安置しておけないので、葬儀社と相談して安置場所を自宅にするか葬儀社にするか決めなければなりません。また、お通夜や葬儀の日程や場所についても早急に打ち合わせが必要です。
特に、両親や身内が亡くなったときはやらなければならない手続きが多いため、丁寧で親切に対応してくれる信頼できる葬儀社を選びましょう。そうすることで、トラブルを未然に防げます。
<関連記事>
初めての葬儀依頼で失敗しない!喪主として知っておきたい葬儀社の選び方
葬儀を行う
一般的な葬儀にするか、家族葬や直葬、密葬といった形にするか、亡くなった方の意志を尊重して家族で話し合って決めます。仏式で葬儀を行う場合、宗派によって作法が異なるので、どの宗派で行うのか葬儀社に伝えましょう。
近年は身内だけで行う家族葬が増えています。ほかにも、後日お別れ会や本葬を行う場合に身内のみで弔う密葬、お通夜や告別式を行わない直葬など、故人の希望で小さなお葬式をする方が多くなっています。葬儀の規模や参列いただく人数をしっかりと把握して、葬儀社と打ち合わせしましょう。
初七日や四十九日などの法要を行う
葬儀に続いて、初七日の法要を行います。初七日法要は、故人がきちんとあの世にいけるようにお祈りをする大切な法要のひとつです。
しかし、葬儀の数日後に再び集まるのは難しいため、近年は葬儀の際に初七日の法要をあわせて行うケースが増えています。火葬前に繰り込み初七日を行いたい場合には、忘れずに葬儀社に伝えましょう。
次は四十九日の法要です。四十九日とは仏教の考え方で「極楽浄土に行けるか否かの判決が下される日」のことをいいます。四十九日までは故人を偲びながら過ごしましょう。毎日お線香をお供えして、祭壇の前にいる時間を作るとよいでしょう。
<関連記事>
葬儀当日に法要を行う、繰り上げ法要って何?
葬儀でかかる平均費用
一般的な葬儀にかかる費用は200万円程度といわれています。内訳は葬儀一式の費用が約120万円、お寺や僧侶に渡す謝礼金が50万円程度、弔問客にふるまう接待飲食費用が30万円程度です。香典返しや手伝ってくれた方への謝礼は含まれていないので、実際にはさらに費用がかかります。
一方、直葬は火葬だけを行うシンプルな葬儀なので、式場を借りたり弔問客をもてなしたりする必要がなく費用を大幅に下げられます。料金相場は20万円~30万円程度です。しかし、納骨できない可能性があり、葬儀を簡略化したデメリットもあるので注意しましょう。
手続きの主な流れ
遺族の方は葬儀の準備だけでなく、さまざまな手続きをする必要があります。たとえば、死亡届や火葬許可申請書を役所に提出しなければ、遺体を火葬できません。
それ以外にも期限付きの手続きが多く存在し、遺族の方が書類の記入や提出を行います。申請を忘れるともらえるはずのお金がもらえない場合もあるので、手続きは忘れずに行いましょう。ここでは、具体的な手続きの内容についてご紹介します。
死亡診断書はコピーしておく
家族が亡くなると、医師から「死亡診断書」が渡されます。死亡診断書は死亡届と一体になった一枚の用紙で、左側半分が死亡届、右側半分が死亡診断書になっています。
死亡診断書は年金の手続きや埋葬料を請求する際に必要なので、3枚~5枚程度コピーして手元に置いておくとよいでしょう。死亡届と一緒に死亡診断書も役所に提出してしまうと、戻ってこないので注意しましょう。
死亡届や火葬許可申請書は速やかに提出
家族が亡くなったら、死亡届と火葬許可申請書を速やかに役所に提出しましょう。二つの書類を提出すると、火葬許可証が発行されます。死亡届の提出期限は亡くなった日から7日以内ですが、火葬許可証がなければ火葬できないため、できるだけ早めに提出しましょう。
死亡届の受付窓口は24時間あいていますが、夜間は火葬許可証の発行を行わない役所もあります。ただし、ほとんどの場合、死亡届は葬儀社が代行して提出してくれます。
期限付きで速やかに手続きが必要なもの
遺族が行う手続きは期限付きのものが多く、しかも期限が短いものもあるので、早めに手続きしましょう。主な手続きと期限は次のとおりです。特に、埋葬料や遺族年金は手続きをしないと受け取れません。
・健康保険証の返却:4日以内
・年金受給廃止手続き:国民年金14日以内、厚生年金10日以内
・世帯主変更届け:14日以内
・埋葬料などの請求:2年以内
・生命保険の保険金:3年以内
・遺族年金の受給:5年以内
期限はないが早めに手続きするべきもの
特に期限はないものの、早めに手続きをしたほうがよいものをご紹介します。期限が決まっていないとつい後回しにしてしまいがちですが、年会費のような費用がかかるものもあるので、できるだけ早めに解約したほうがお得です。
・パスポートや運転免許証の返還
・水道、ガスなどの解約
・会員証の解約・返還
・クレジットカードの解約
相続関係の手続きの主な流れ
相続の手続きは亡くなった日から10か月後までに行います。ただし、相続放棄や準確定申告はそれより前に手続きする必要があります。また、相続人も決めなくてはなりません。ここでは、相続関係の手続きについて詳しく見ていきましょう。
相続放棄をする場合は3か月以内に行う
相続放棄とは、亡くなった方の財産の相続の権利を放棄することです。特に、故人が多くの負債を残した場合は相続放棄の手続きをしないと負債まで背負うことになります。相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内に行います。限られた時間の中、必要書類を揃えて裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。
相続を放棄すると、ほかの方に相続人の権利が移ります。相続人全員が相続放棄を希望する場合には、それぞれが相続放棄の手続きをしなければなりません。
準確定申告は4か月以内に行う
準確定申告とは、相続人が亡くなった方の納税を行う手続きのことで、亡くなった日から4か月以内に行います。
ただし、すべての人にとって必要な手続きではありません。給与所得のほかに事業所得や不動産所得があるなど、仮に生きていても確定申告が必要な方は準確定申告をしましょう。また、高額の医療費を支払っていた場合には申告により還付を受けられることもあります。
相続人を早めに確認しておく
誰が相続人になるか決めなければ、相続放棄の手続きや準確定申告ができません。法定相続人を確認するには、戸籍の取得が必要です。また、遺言書に相続について書かれている可能性もあるので、遺言書が残されている場合はしっかりと内容を確認しましょう。
法定相続人の範囲ですが、故人の配偶者はどのような場合でも法定相続人になります。配偶者以外の法定相続人については、以下のように相続順位が定められています。
第1順位 子供(直系卑属)
第2順位 親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹
<関連記事>
親が亡くなったらするべき相続手続きまとめ!手続きの期限にも注意
小さなお葬式で葬儀場をさがす
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
家族が亡くなったとき、遺族がやらなければならない手続きは思っている以上にたくさんあります。亡くなってから慌てていると、間に合わないかもしれません。
役所での手続きに関しては遺族が自らやるべきことが多いですが、葬儀については信頼できる葬儀社に任せることが可能です。経験豊富なスタッフが葬儀の準備をしっかりとサポートします。
近年は大々的な葬儀は行わず、家族葬や直葬を選択する方も増えています。葬儀の準備や手続きについて困ったことがあれば、ぜひ「小さなお葬式」へご相談ください。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。


よくある質問
亡くなったら忌引き休暇はどれくらい取ればいい?
喪主は誰が務めればいいの?
亡くなったときは誰に連絡すればいい?
亡くなった人の借金はどうなるの?
喪中のときに避けるべきこととは?

御仏前は「仏となった故人の前に供えるもの」という意味です。ホゥ。