喪中はがきを受け取ったことや送ったことがある方は多いでしょう。喪中は年賀状を出さない、新しい年を祝わないなど、日本では一般的になっている風習です。喪中に比べれば馴染みはありませんが、関連する言葉で忌中という言葉もあります。
この記事では、「喪中」や「忌中」について、詳しく解説します。
<この記事の要点>
・喪中は約1年間の喪に服す期間で、忌中は四十九日を過ぎるまでの期間を指す
・仏教の忌中は四十九日法要までの期間を指すが、浄土真宗には忌中や喪中の概念はない
・慶事のお誘いを受けた場合、喪中期間中は出席を控えるのがマナー
こんな人におすすめ
喪中と忌中の違いを知りたい方
喪中や忌中に慶事のお誘いを受けた方
宗教ごとの喪中や忌中の概念について知りたい方
喪中とは
喪中はがきを受け取るなど、言葉は聞いたことがあるが喪中の意味を理解できていない、という方もいるのではないでしょうか。喪中の意味を知ることで正しいマナー等を身に着けることができます。ここでは、喪中についてご紹介します。
喪中の意味
喪中とは、亡くなった故人を追悼するため、遺族や関係者が自らの行動を慎むと同時に、近い人を亡くした悲しみから立ち直るための期間のことです。儒教の考え方に基づく風習で、古くは奈良時代の養老律令にも規定されていました。
喪中の期間
喪中の期間は、徳川幕府5代目将軍 徳川綱吉の時代に制定された服忌令という、家族や近親者が亡くなった際の喪に服す期間について定めた法律を基に決められています。この服忌令は昭和22年に廃止されているため、現在は喪中について法律で定められているわけではありません。
服忌令は「喪に服す」期間と「穢れを忌む」期間に分かれていて、現在一般的となっている喪中の期間は「喪に服す」期間の定めを参考にしています。
喪中の期間は、故人が亡くなった日から1年間が喪に服す目安とされていますが、故人との続柄や住んでいる地域、風習によって変わります。以下に一例をご紹介します。
故人の配偶者・父母:12ヶ月~13ヶ月
故人の子供:3ヶ月~12ヶ月
故人の祖父母、兄弟姉妹:3ヶ月~6ヶ月
喪に服す間柄とは
基本的には故人から見て2親等までの親族が喪に服す間柄とされています。しかし、血縁で見れば3親等以上離れている場合でも、故人との関係性が深ければ喪中となる場合もあります。なお、親等で表すのは血族と姻族で、配偶者に関しては親等で表すことはないため、注意が必要です。3親等までにあたる親族は以下の通りです。
1親等:故人の両親と子供、配偶者の父母
2親等:故人と配偶者の祖父母、兄弟姉妹とその配偶者、孫とその配偶者
3親等:故人と配偶者の曽祖父母、曽孫、叔父叔母(伯父伯母)、甥や姪
喪中に控えるべきこと
喪中は、結婚式への参列といったお祝いごとや派手なレジャーへの参加は控えるべきとされています。
また、年始のお祝いは控えましょう。喪中のために新年の挨拶を控えることを、喪中はがき(年賀欠礼状)を出して知らせます。もし喪中はがきを出さなかった人から年賀状が来た場合は、「寒中見舞い」として返すといいでしょう。寒中見舞いは松の内が明けてから立春までの間に出します。
子供たちに渡すお年玉も「新年のお祝い」という意味合いがあるため、控えた方がいいでしょう。しかし、子供たちが楽しみにしているイベントでもあるため、ポチ袋に入れて「お小遣い」や「文具代」「図書代」という書き方で渡すケースも多いです。
正月飾りなども行いません。元々、正月飾りは「一年間を無事に過ごせたことに感謝し、また歳神様を迎える」ために飾るものです。身内が亡くなっている以上、「一年間を無事に過ごせた」ことにはならないため飾ることはNGです。
喪中でもしていいこと
喪中でも他の葬儀への参加や節分行事への参加は問題ないとされています。
また、年末の風習である年越しそばは食べても問題はないとされています。年越しそばは、「長いものを食べることで健康と長寿を願う」、「一年間の厄を切り落とす」という意味であり、新年を迎えるお祝いではないためです。ただし、お祝いを連想させる紅白の具材などを入れるのは避ける必要があります。
そして、鏡餅は福をもたらす神様にお供えするもので、「不幸が訪れた家にまた福をもたらしてもらいたい」との願いを込める意味で喪中であっても飾るケースもあります。
お歳暮・お中元の送付も、自分が喪中、または送付先が喪中であっても問題ないとされています。そもそもお歳暮は、年の暮れに一年間お世話になった方々への感謝の気持ちを贈り物にして表す慣習であり、お中元も夏の暑い時期に暑中見舞いと合わせて半年間お世話になった感謝の気持ちを表す慣習です。
ただし、お歳暮もお中元も故人宛に送らないこと、水引のない無地のかけ紙または短冊を選ぶこと、添える手紙の文章に「祝いの言葉」を使わないこと、の3点に注意しましょう。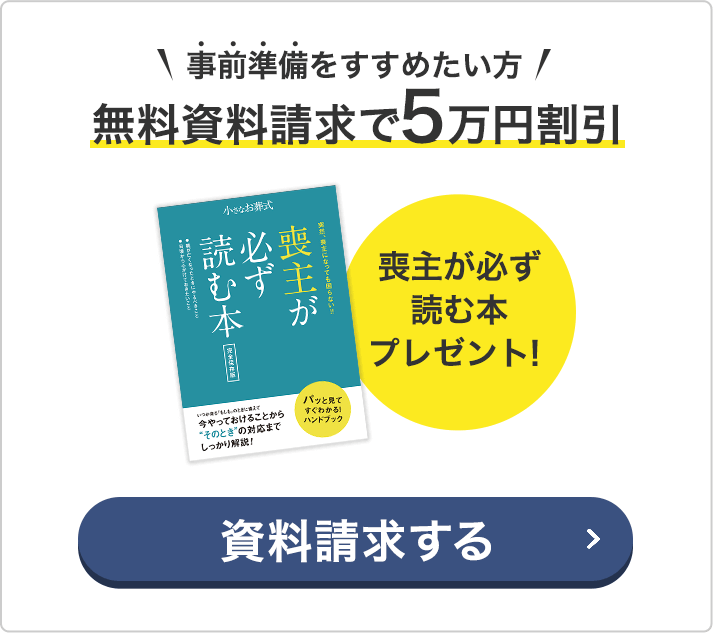
忌中とは
この章では忌中についてご紹介します。喪中同様、言葉の意味や正しいマナーを知らない場合、失礼が生じてしまうかもしれません。ぜひ以下の内容をご参考にしてみてください。
忌中の意味
忌中とは、死による穢れを他人に移さないよう外部との接触を避けて身を慎む期間です。元々は神道の考え方であり、神道と仏教の概念がまとまり、神仏習合の一つの名残として今に受け継がれています。
かつて、忌中の間は喪服を着て、家の門戸を閉めて完全に外部との接触を絶っていました。また、お酒を飲んだり肉や魚を食べたりすることもせず、精進料理を食べて過ごしていました。
しかし、現代において完全に外部との接触を断って暮らすことは難しいため、普段通り職場や学校へ行き、食生活も普段通りとすることが一般的です。
忌中の期間
忌中の期間は、一般的には故人が亡くなった日から四十九日を過ぎるまでの期間です。忌中の期間は、喪中と同様に服忌令における「穢れを忌む」期間の定めに従っています。故人との関係での忌中の期間は以下の通りです。
配偶者・父母・子供:50日
祖父母・孫・兄弟姉妹・配偶者の父母:30日
曽祖父母・曽孫・おじおば・甥姪・子供の配偶者:10日
なお、神道では同居している人が亡くなった場合、血縁の濃さに関係なく忌中の期間は50日となります。
忌中の際に気を付けること
自宅に仏壇がある場合は、仏壇の扉を閉じておきましょう。また、自宅に神棚がある際には、忌中の間「神棚封じ」をする必要があります。これは、神様を死の穢れから遠ざけるために神棚にお札や半紙を貼ることで、忌明けするまでは神棚にお参りをしないようにします。
忌中に控えるべきこと
忌中の際は、結婚式の主催や参列、家の新築や改築などのお祝いごとは避けましょう。パーティーや宴会、忘年会や新年会なども、どうしても出席しなければならない場合を除き、基本的には出席を控えます。
子供の七五三も忌中に行うことは避けましょう。七五三の時期でなくても七五三祈願をしてくれる神社は多く、衣装も貸衣装屋やスタジオなどで借りられるため時期をずらすのがおすすめです。時期に関して周囲に気にする人がいる場合は、一年遅らせて喪中が明けてからという選択肢もあります。
また、忌中の間は神社への参拝も控えましょう。「神社の鳥居をくぐってはいけない」といわれますが、これは「神社の鳥居をくぐらなければ忌中でもお参りしても構わない」という意味ではなく、神社に立ち入ることはしてはならいという意味です。
ただし、忌中の間に参拝してはいけないのは神社のみで、お寺へのお参りはしてもよいとされています。喪中の場合にはお歳暮やお中元を送ってもよいとされていますが、忌中の場合は控えましょう。
忌明け後にするべきこと
葬儀やお通夜の際にいただいた香典に対し、香典返しを行います。地域によっては会葬礼状とともに葬儀やお通夜の当日に香典返しをする場合もあり、この場合は忌明け後に香典返しをする必要はありません。
ただし、四十九日の法事の際にいただいたお供えや香典に対しては忌明け返しと呼ぶお返しをする必要があります。
また、故人が亡くなった際に行った神棚封じを解き、お参りを行いましょう。同じく、閉じてあった仏壇の扉も開けます。
忌引きとの違い
忌引きは、一般的には身近な人が亡くなったときに取得する休暇のことを指します。喪主は葬儀を執り行うため、喪主でない場合は葬儀へ参列するための休暇です。
一般的な会社では福利厚生の一部として慶弔休暇や特別休暇として設けられていることが多いですが、法律上で必ず設けなければいけないものではないため、会社によっては制度自体が存在しない場合もあります。
忌引き休暇の日数も会社によって異なりますが、一般的には配偶者が亡くなった場合は10日間、父母の場合は7日間、子供の場合は5日間、兄弟姉妹や祖父母の場合は3日間となっていることが多いです。
宗教による違い
ここでは、日本における一般的な宗教として、神道、仏教、キリスト教の3つの宗教における忌中の扱いの違いをご紹介します。
神道における忌中・喪中
神道では、「死は穢れたもの」であるという考え方があります。「穢れ」は「気枯れ」とも表記され、死そのものが穢れているというよりは死によってもたらされる、遺された人の気が滅入ってしまう状態を穢れとしているのではないか、という説もあります。
神道において、忌中は50日間です。人は亡くなってから50日間は霊として存在し、五十日祭をすることで家庭を守る守護神になるという考え方が基になっています。
元々は五十日祭の翌日に行われていた、「清祓いの儀」を行う前までを忌中としていましたが、現在は清祓いの儀を五十日祭の当日に一緒に行うのが一般的となっています。清祓いの儀とは忌明けを象徴する儀式で、故人が亡くなった段階で神棚に貼った白紙を剥がす儀礼です。
仏教における忌中・喪中
仏教では、「死」は「生の苦しみから解放され、別の世界へと生まれ変わるための通過点」と位置づけられています。神道とは異なり死を穢れたものとしては扱いません。
仏教において、忌中は49日目の法要までの期間のことです。故人が生まれ変わるためには7日ごとに生前の行いについての裁判を受ける必要があり、その最後の裁判が49日目であるとされていることに由来します。
そして、遺族らは故人が無事に生まれ変わることを願い、善き行いである追善供養として、本来7日ごとに49日目まで、法要を行います。なお、現在は初七日法要と四十九日法要だけを行うことが増えています。
ただし、仏教の中でも浄土真宗は例外で忌中や喪中の概念はないとされています。浄土真宗では亡くなった人は生前の行いに関係なく、すぐに仏様になると考えられているためです。
魂がさまようことも穢れを現世に残すこともないとされていて、「忌」という考え方自体がありません。
キリスト教における忌中・喪中
キリスト教も、浄土真宗と同様にもともと「忌」という考え方はありませんでした。キリスト教では、「人は死ぬと神様によって天国へと導かれる。遺された人たちも同じように死後天国へ行くため、後々再会できる」という考え方であるためです。
したがって、死はひと時の別れであり、また再会できるために死を悼む期間も必要ないとされているのです。
しかし、日本では風習としての忌中、喪中の考え方が受け入れられており、プロテスタントの場合は亡くなってから1ヶ月後の召天記念日、カトリックでは亡くなってから30日目の追悼ミサまでを忌中としています。
仏教における忌中・喪中
仏教では、「死」は「生の苦しみから解放され、別の世界へと生まれ変わるための通過点」と位置づけられています。神道とは異なり死を穢れたものとしては扱いません。
仏教において、忌中は49日目の法要までの期間のことです。故人が生まれ変わるためには7日ごとに生前の行いについての裁判を受ける必要があり、その最後の裁判が49日目であるとされていることに由来します。
そして、遺族らは故人が無事に生まれ変わることを願い、善き行いである追善供養として、本来7日ごとに49日目まで、法要を行います。なお、現在は初七日法要と四十九日法要だけを行うことが増えています。
ただし、仏教の中でも浄土真宗は例外で忌中や喪中の概念はないとされています。浄土真宗では亡くなった人は生前の行いに関係なく、すぐに仏様になると考えられているためです。
魂がさまようことも穢れを現世に残すこともないとされていて、「忌」という考え方自体がありません。
キリスト教における忌中・喪中
キリスト教も、浄土真宗と同様にもともと「忌」という考え方はありませんでした。キリスト教では、「人は死ぬと神様によって天国へと導かれる。遺された人たちも同じように死後天国へ行くため、後々再会できる」という考え方であるためです。
したがって、死はひと時の別れであり、また再会できるために死を悼む期間も必要ないとされているのです。
しかし、日本では風習としての忌中、喪中の考え方が受け入れられており、プロテスタントの場合は亡くなってから1ヶ月後の召天記念日、カトリックでは亡くなってから30日目の追悼ミサまでを忌中としています。
慶事のお誘いを受けた際の注意点
喪中の最中に結婚式などの慶事のお誘いを受けた際にはどうすればよいでしょうか。基本的には、喪中の際には出席を控えるのがマナーです。なお、忌中の間に招待を受けて欠席の連絡をする際の理由には、直接的に喪中や忌中とは書かず、ぼかした表現を使うようにしましょう。
しかし、近年では忌中でなく喪中であれば出席してもいいという傾向が生まれています。ここでは、喪中に慶事のお誘いを受けた場合の対応方法について解説します
相手方や自分の身内に意見を聞く
近年では、身を慎む喪中の習慣も緩やかになってきており、個人や家族の状況を踏まえて出欠席を決めることも増えているようです。
忌明け後に招待された場合は、まずは喪中であることを相手方に伝え、相手方のご家族の意向を確認しましょう。特に、結婚式の場合は他の参列者への配慮も重要です。
故人への自分の気持ちの整理ができていて、心からお祝いするために参列したくとも、他の参列者、特に主催者の親族などに気にする人がいる場合、主催者へ迷惑がかかる可能性があります。
主催者の親族など、他の参列者に気にする人がいないことを確認することはトラブルを減らすためにも重要です。また、自分の家族などにも意見を聞き、さまざまな立場の方の意見を取り入れたうえで判断するのがよいでしょう。
故人や遺族の思いを尊重する
近年、喪中であっても遺族にとってとても大切なイベントや行事であれば、「故人も許してくださる」として柔軟に考えることが増えてきています。しかし、遺族がよくても周囲が喪中であることを気にするケースも少なくありません。したがって、周囲を不快にすることがないよう、故人の意向を尊重したうえでマナーを守ることが大切です。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
最近では、喪中であっても故人が生前楽しみにしていたお祝いなどでは「故人のために」「供養として」などと柔軟に考えることも増え、昔ほど厳密に過ごすことも少なくなりました。
喪中や忌中の期間を過ごすにあたって何よりも大切なのは、亡くなった方を偲ぶこと、そして遺された遺族が悲しみに暮れるばかりでなく、よりよい日々を過ごしていくことです。
四十九日法要などの節目の法要は遺族の気持ちを整理するためにも役立ちます。忌中や喪中における過ごし方もその一つのため、年配の方と若い方とでは考え方が違いも生じます。そういった場合には、目上の方々に失礼のないようマナーに配慮しながら過ごしましょう。
お葬式を出す際、ご遺族の方々は慣れない急な別れで不安に苛まれていることと存じます。「小さなお葬式」ではその不安に寄り添えるよう、誠心誠意ご葬儀の対応をさせていただきます。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートしますので、ぜひご相談ください。


自身が亡くなったときのために、エンディングノートを書いておくのもおすすめです。ホゥ。

































