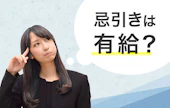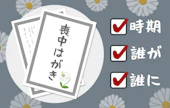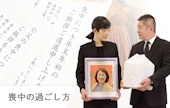親族が亡くなった時、どこまでの続柄なら喪中として考えるべきか、その判断はなかなか難しいものです。
喪中の際には控えるべきこともありますので、その範囲については知っておくとよいでしょう。故人との続柄によっても変わりますが、一体どこまでが喪中となり、どこからが喪中とならないのでしょうか。
この記事では、喪中として判断するべき続柄の範囲と期間の違い、喪中に控えたほうがよいことについてお伝えします。
<この記事の要点>
・一般的に2親等までが喪中になる
・喪中期間は、両親の場合12~13ヵ月が一般的
・喪中期間には正月のお祝いや、結婚式への出席などは控えた方がよい
こんな人におすすめ
喪中の範囲が知りたい人
忌引き休暇について知りたい人
喪中の過ごし方について知りたい人
続柄によって変わること
故人との続柄によって、喪中の範囲やその期間が変わります。自分を基準とした0親等から3親等までを表にまとめました。
| 親等 | 自分との関係 |
| 0親等 | 夫、妻 |
| 1親等 | 父母、配偶者の父母、子供(何人目かに関わらず) |
| 2親等 |
(自分の)兄弟・姉妹、兄弟・姉妹の配偶者、祖父母、孫 (配偶者の)兄弟・姉妹、兄弟・姉妹の配偶者、祖父母 |
| 3親等 |
(自分の)曾祖父母、伯叔父母、伯叔父母の配偶者、甥、姪 (配偶者の)曾祖父母、伯叔父母、伯叔父母の配偶者 |
一般的には2親等までが喪中になるとされ、3親等からは喪中としないことが多いようです。
ただし、3親等以降は喪に服してはいけないというわけではなく、故人との縁が深い場合には、親等に関わらず喪に服してもよいとされています。
そもそも親等とは
親等という言葉を聞いたことがあるかと思います。親等とは法的な単位のひとつです。具体的に言うと親族との関係が近いのか遠いのかを表すものです。そして多くの職場はこの親族関係の遠近をもとに、忌引き休暇が何日取れるのかを決めています。
数が小さいほど近い親族関係を表しています。例えば1親等にあてはまるのは父母や子どもです。もう一つ大きい数字の2親等になると、祖父母や孫、兄弟姉妹が当てはまります。おじ・おばは3親等になります。
また親族には直系と傍系という分類があります。直系の親族には父母や祖父母、子や孫などがあてはまります。そして傍系とは、兄弟姉妹、おじ・おば、甥・姪、いとこなどのように直系から枝分かれした系統に対しての呼称です。
また、配偶者の兄弟姉妹、おじ・おば、甥・姪、いとこ、伯叔祖父母(大おじ・大おば)なども傍系にあてはまります。
忌引き休暇が認められるのは何親等まで?
忌引きとして認定されるどうかは亡くなった方と何親等離れているのかによって異なります。ただし、どの関係まで認めてもらえるかは勤務先によって違うものです。忌引きは労働基準法などの法律で決められているものではなく、企業がそれぞれに定めているものだからです。
一般的には3親等まで認定されることが多いですが、同じ親等でも直系の親族の場合のみとなり、傍系の親族だと認めてもらえないケースもあるようです。3親等で傍系にあたる親族とは、例えば配偶者の甥や姪などがあてはまります。
4親等以上離れている方でも、親しくしていた親戚であればせめて葬儀には参列したいケースもあるでしょう。その場合、年次有給休暇をとるなどして休めないかどうか勤務先と交渉してみましょう。
忌引き休暇の日数の目安は?
忌引きで休んでもいい日数を計算するために、故人とご自身がどのような関係なのかと聞かれることがあります。故人と親族としての関係が近いか遠いかによって、何日間休めるのかを規定している職場が多いからです。
1親等の場合は5~10日間、2親等なら3日間、3親等なら1日というように、近しい親族ほど日数が多いパターンが一般的です。休んでもいい日数は特に共通のルールが決まっているわけではなく、各企業が独自に決めています。
このため、同じ1親等でも配偶者なら10日間、父母なら7日間、子どもなら5日間などと細かく分けている職場もあれば、1親等、2親等までしか忌引き休暇を受け付けてもらえないというパターンもあります。
忌引き休暇を取る際のマナー
忌引き休暇は突然取るケースも多いので、勤め先を休んでしまう際に、上司や同僚などへの負担を最小限にするために確認しておかなければならない事柄がいくつかあります。また、忌引き休暇を取得する際には、必要な情報の伝え漏れがないようにすることが重要です。
初めて忌引きで勤め先を休む場合は、どのように申し出たらいいのかわからないこともあるでしょう。以下では、スムーズに忌引きをとるために伝えるべきポイントや確認したい注意点を紹介します。なるべく周囲に迷惑をかけないように心がけるのがポイントです。
なるべく電話で連絡をする
忌引き休暇が必要になったことがわかったときに勤め先にいたのであれば、直属の上司にまず口頭でその旨を伝えましょう。その後は指示に従って必要な手続きをします。迷うのは、自宅や病院など職場外にいるときに、勤め先に忌引き休暇を取りたい旨を伝えたいケースです。
勤め先以外の場所にいた場合、上司や担当者が今忙しいのかどうか、電話に出られる状態なのかどうかがわからず迷ってしまうことがあります。この場合でもできる限り電話をかけて連絡をするようにしましょう。
急に休みを取るときには業務の引継ぎなど急ぎで伝達や指示を出す必要がある事柄や、何日休んでもいいのかといった確認しておくべき内容もあります。よほどの事情がない限りは電話をかけ、事前に情報をまとめて伝え漏れのないように心がけましょう。
また、大切なのは突然休みを取ってしまうことで、自分が職場に迷惑をかけてしまうことに対する謝罪や感謝を伝えることです。急な休みをいただいて申し訳ないという旨は、メールよりも電話によって口頭で言ったほうが心からの気持ちが伝わりやすいと言えるでしょう。
必要事項はきちんと伝える
必要事項はきちんと伝えるようにしましょう。勤め先によっては誰の弔事で休むのかなど、忌引きを申請する理由を伝えることを義務付けているケースもあります。状況によって休むことのできる日数が変わったり、会社として葬儀への参列や弔電の必要性などを検討する必要があったりするからです。
特に、故人とはどのような関係なのか・通夜や葬儀の日時・葬儀を執り行う場所の3点については忘れないようにしましょう。家族葬などで親族以外の参列を遠慮する際は先に伝えてください。
また、自分が留守の間に担当している業務をどのように扱うのかをきちんと引継ぎ、業務が滞ってしまわないように意識します。大まかな流れや急ぎの案件のみ電話で簡潔に伝え、細かい点については上司や関係者に後ほどメールで送りましょう。
忌引き日数の確認をしておく
忌引きの日数は一般的な基準が存在するといえども、勤め先によって多少は異なるものです。何日間休んでもいいのかということをきちんと確認するようにしましょう。以前に忌引きで休んだことがあっても、就業規則の更新によって規定が変わっている可能性もあるので注意してください。
またチェックしておいてほしい事柄は他にもあります。それは、休みを申し出るのに必要な書類や情報は何なのかということです。勤め先によっては弔事が終了してからでもいいので内容を書面で提出してくださいといわれるケースもあります。
この書面には、誰の弔事なのか、ご自身から見た関係、場所はどこでおこなわれたのかなどを記入する必要がある場合があります。会葬礼状などを持っていくパターンもあるでしょう。後で慌てないようにするためにも何が必要なのか事前に確認しておくと安心です。
喪中の期間
喪中の期間についても続柄が関わってきます。
喪中に関する取り決めには、明治時代に定められた太政官布告があります。これは昭和22年に撤廃されてはいますが、現在の喪中の基準にもなっています。
この布告による喪中の範囲は次の通りです。
▼ 明治時代の喪中の期間
| 続柄 | 喪中期間 |
| 父母、夫 | 13ヵ月 |
| 義父母、祖父母(父方)、夫の父母 | 150日 |
| 妻、子供、兄弟姉妹、祖父母(母方)、伯叔父母、曾祖父母 | 90日 |
| 養子 | 30日 |
ただし、この時代は男尊女卑が激しく、女性側の喪の期間が短く設定されています。このままでは今の時代に合わないため、現在は次のような基準となっています。
▼ 現在の喪中の期間
| 続柄 | 喪中期間 |
| 父母、義父母 | 12~13ヵ月 |
| 子供 | 3~12ヵ月 |
| 祖父母 | 3~6ヵ月 |
| 兄弟姉妹 | 1~6ヵ月 |
| 曾祖父母、伯叔父母 | 喪中としない |
これらは一般的な認識ではありますが、同居・別居など付き合いの程度によっても変わるため、あくまでも参考程度のものです。
悲しみの大きさによって期間は変わります。
喪中に控えるべきこと
喪中には控えたほうがよい行事があります。
正月のお祝い
喪中に正月が訪れる場合、お祝いはしないのが一般的です。年賀状も正月のお祝いのひとつであるため控えます。
その際には年賀欠礼状、いわゆる喪中はがきを出します。年賀欠礼状という名前の通り、新年の挨拶を欠くことを知らせるためのものです。
喪中の場合は事前に知らせましょう
喪中はがきは「喪中であるため、新年の挨拶は控えさせていただく」という旨を事前に知らせる役割があります。
送る時期は11月から12月15日までに相手に届くように投函する必要があります。それ以降の場合は、年賀状と行き違う可能性があるので、1月8日~2月4日の間に送る「寒中見舞い」として喪中の旨を伝えるのがよいでしょう。
寒中見舞いは、年賀状の返事が遅くなった場合によく使用されますが、年賀状をもらったお返事としても送られています。
結婚式など祝い事への出席
正月のお祝いと同じく控えるべきとされています。
しかし、忌明け(四十九日)を迎えていればいいという意見も多く、周囲と相談して決めるのが良いでしょう。
喪中でも許されるもの
喪中でも参加が許されているものをみていきましょう。
寺への初詣
喪中でも問題なく初詣をすることができます。これは、寺と神社の死に対する考え方の違いからきています。
神社は死を穢(けが)れと捉えますが、寺はそういった考えがないのです。神社の場合でも、五十日祭が済んで忌明けを迎えていれば、初詣をしてもよいと言われています。
ただし、神社はその地域によっても考え方が違うこともあります。
お中元・お歳暮
喪中であってもお中元やお歳暮を送ることができます。相手が喪中の場合も特に問題はありません。お中元やお歳暮は、感謝の気持ちを伝えるために送るものであるため、お祝いにはあたりません。
ただし、この場合でも四十九日を過ぎてから送るようにし、紅白の熨斗も使わないようにしましょう。
暑中見舞い・残暑見舞い
自身が喪中であっても残暑見舞いや暑中見舞いは送っても大丈夫です。また、こちらから喪中の方に対して送っても問題ありません。残暑見舞いも暑中見舞いもお祝いのために送るものではありません。喪に服していることが特に送ってはいけない理由にはあてはまらないのです。
ただし、四十九日の間は忙しかったり、気持ちの整理がついていなかったりということも考えられます。無理にやり取りしようと考えなくてもいいでしょう。この期間に暑中見舞いや残暑見舞いがとどいたとしても、自分自身が落ち着いてからの返信で大丈夫です。
返信が遅くなった場合には、それに対するお詫びと慌ただしくしていた旨を書き添えたうえで、近況をお知らせするといいでしょう。相手の方に気遣かわせないようにして、さらに自分の現在のことを知らせることで安心してもらえるようにしましょう。
「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中
「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。
喪主を務めるのが初めてという方に役立つ情報が満載です。いざというときの事前準備にぜひご活用ください。
\こんな内容が丸わかり/
・病院から危篤の連絡がきたときの対応方法
・親族が亡くなったときにやるべきこと
・葬儀でのあいさつ文例など
資料請求で葬儀が5万円割引
「小さなお葬式」では、お電話・WEBから資料請求をいただくことで、葬儀を割引価格で行うことができます。お客様に、安価ながらも満足できるお葬式を心を込めてお届けいたします。

※一部式場ではプラン料金以外に式場利用料等が発生します。
無料資料請求で割引を受ける
「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす
小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上※の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。(※2024年4月 自社調べ)
まとめ
故人との関係が深かった場合、死後は悲しみに暮れるものです。そのために喪という期間が設けられていて、故人を偲ぶことができるようになっています。
喪中の期間は正確に定められているわけではなく、一般的な認識はあるものの、大切なのは自分の気持ちです。判断に迷ったときは、この記事を参考にしてください。
また喪中に関する疑問以外にも、葬儀全般に関する悩みや疑問があれば「小さなお葬式」へご相談ください。知識豊富な専門スタッフが24時間365日サポートします。


よくある質問
喪中とはなんのこと?
喪中の期間に決まりはあるの?
喪中に控えるべきことは?
喪中でもおこなっていいことはあるの?
喪中の範囲はどこまで?
忌引き休暇が認められるのは何親等まで?
忌引き休暇の目安や取得時のマナーはあるの?
遺言書には、誰の遺言かを明確にするために署名が必要です。ホゥ。